母親の「過保護」はホルモンの問題?
夫婦で、子育ての方針に違いを感じた瞬間はありますか?
ママと専門家をつなげるプラットフォーム企業・株式会社ベビーカレンダー(本社:東京都渋谷区)の調査では、子育ての方針の違いに悩む女性の多さが明らかにされています。裏を返せば、子育て方針の違いに悩む男性も同じだけ多いと考えられます。
その子育て方針の食い違いには当然、過保護・過干渉の問題を含む子どもへの接し方も入ってくるはずです。この問題、どうしたらいいのでしょう。

「あくまでも今回は、パートナー側が妻の子育てを過保護・過干渉だと感じている状況を想定しますが、女性が過保護になってしまいがちな背景には、オキシトシンと呼ばれるホルモンの影響があります。
オキシトシンとは『愛情ホルモン』『きずなホルモン』とも呼ばれ、子どもを守りたいという感情や、不安や心配感の増大を引き起こします。
要するに、過保護の傾向が母親に見られがちな背景にはホルモンの影響がある、生物学的な影響があると理屈で理解していただきたいです。
さらに『女性には母性本能が備わっている』だとか『女性こそが子どもに深く愛情を注ぐべき』といった、偏った思い込みが社会の根底にはいまだに存在します。
その世の中の空気が、過剰な保護を生み出す原因となっていると、心理学者の河合隼雄さんも著書『母性社会、日本の病理』(岩波書店)で指摘しています。
言い換えると、自分こそがわが子を守らなければいけないという責任感を男性以上に背負わされてしまう傾向が母親にはあるのです。
ホルモンの影響が大前提にあり、母性社会という病理が世の中の根底にあり、結果として、父親やパートナーにとって『過保護・過干渉』に思えるような行動を母親がとっている、そういう風に理解できれば、ロジックを好む男性パートナーなどは納得できるのではないでしょうか。
少なくとも、頭ごなしに妻を否定せずに済むようになると思います」(沢野さん)
取材後に調べてみると、海外の論文でも「Maternal Overprotection(母親の過保護)」という言葉が研究対象になっています。子育てにおいては一般に、母親(女性)のほうが過干渉・過保護になりやすい傾向があるとも言われ、男性側には逆に、子どもには自立を求め、少しくらい厳しい場面があってしかるべきだと考えがちな傾向があるのだとか。
沢野さんいわく、オキシトシンは男性にも分泌されるそうですが、出産や授乳時に大量に分泌されるホルモンのため、その分泌量の違いが存在するそう。
その違いを知らないがゆえに、「干渉しすぎだ」「甘やかしすぎだ」という自分の考えや主張を男親の側が強要し、一方でパートナー(主に女性)の側にも自分なりの正義があるため、喧嘩になってしまうのですね。
「放っておけ」と言ってみたところで逆効果
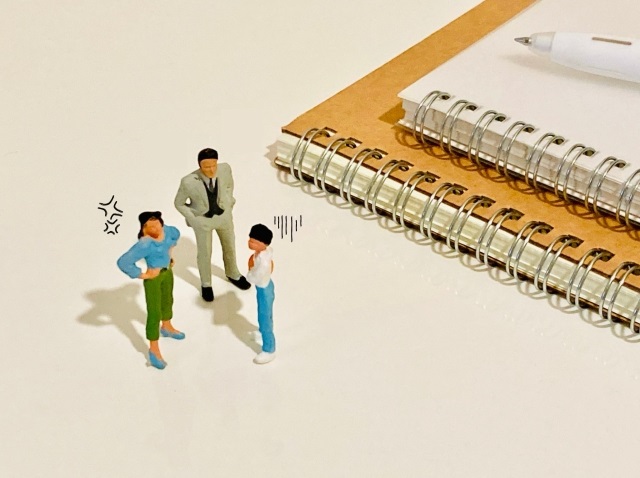
理屈に納得できたところで今度は、実際に「過干渉」「過保護」にも思える行動を目にした時、男親の側はどのようにアプローチすればいいのでしょう。
そもそも論として、過干渉や過保護はどうして、子どもの成長に悪影響をもたらす危険性があるのでしょうか。
「過保護の親を上手に描写するたとえとして、ヘリコプターペアレントとカーリングペアレントという言葉があります。
ヘリコプターのように子どもの上空をずっと飛んでいて、子どもに問題が起きるとすぐに降下し、手を出してしまう親をヘリコプターペアレントと呼びます。
一方で、カーリングのストーンの進む先の氷をブラシで熱心にこすって、あらゆる障害を取り払って道を整備するように、子どもの行く先に存在するリスクを全て取り除こうとする親をカーリングペアレントと言います。
結果的に、どちらも、失敗や挫折のチャンス、葛藤する機会を子どもから奪います。悩みや失敗を経験できない子どもは、心理的にも人間的にも自立できません。その意味で、過保護・過干渉には問題が多いのですね。
しかし、子どもの失敗や挫折を過度に恐れて、男親から見れば『過保護』のような状態になっている母親に『放っておけ』と言ってみたところで逆効果です。
かなりの自制心が求められるとは十分に分かった上であえて言いますが、セルフコントロールを男親の側が率先して発揮し、過剰反応しているパートナーの気持ちをまずは理解してあげてください。相手を理解せず、自分の思いだけを相手に理解してもらおうと思っても難しいです。
繰り返しますが、過保護になりがちなメカニズムが母親の側にはあります。子どもに対して過保護・過干渉になって当然だというスタンスで寄り添ってあげてください。表面的だとか、しらじらしいとか思われても構いません」(沢野さん)

とはいえ、沢野さんも認めるように、男親側からすれば看過できない「過保護・過干渉」を目撃した瞬間に相手の気持ちに寄り添えとは、なかなか高度なミッションではないでしょうか。
「おっしゃるとおり、たいていの場合、現場で文句を言ってしまい、喧嘩になるパターンが多いです。しかも、パートナーの過保護が気になる瞬間は、たいてい忙しく切羽詰まった状況です。
それを分かった上でもなお、建設的な態度で、穏便に接するようにセルフコントロールを発揮してくださいと男性の側にはお伝えしたいです。
『なんで俺だけが気を遣わなければいけないの?』
と多くの方が思うかもしれません。夫婦関係では特に、甘えが出て我慢ができなくなってしまいがちです。配慮のない言葉をずけずけと言ってしまい、喧嘩になるパターンも多いはずです。
だから、余計に難しいというのであれば、自分の幸せと子どもの幸せをあらためて見つめ直してみてはいかがでしょうか。豊かな夫婦関係・家族関係は仕事以上に重要です。
1938年に開始され、約80年間にわたり、724人の男性を追跡した「ハーバード成人発達研究(Harvard Study of Adult Development)」でも、人の幸せを左右する最大の要素は、仕事でもなくお金でもなく身近な人との良好な関係だと明らかにされています。
仕事の場面で、上司や取引先に対して建設的な態度ができるのであれば、仕事で培ったセルフコントロール術を家庭内で発揮してみてはいかがでしょうか。
その上で、子どもが寝た後など、双方が冷静に話せるタイミングを探して『ところでさ』と切り出し、相手の気持ちに寄り添った上で、ご自身の意見を聞いてもらってください」(沢野さん)
過干渉・過保護の問題が本当にあるとすれば子どもの未来にもかかわってきます。
冷静に話し合えるタイミングで、子どもが大事という気持ちを共有し、子どもにはこう育ってほしいという理想の未来像を語り合えば、おのずから状況は改善されていくのではないかと沢野さんも語ります。
沢野さんによれば、家事、育児などの負担が極度に偏っている状況があると、余裕を失った側の人間が、子どもと接する場面で過剰な反応を示すケースもあると言います。
冷静に話し合えるタイミングで、家事や育児の負担が相手の側に集中していないか、その点も語り合ってみるといいかもしれません。
過保護を自覚し自己嫌悪に陥る女性も

他にも、過保護・過干渉の問題について沢野さんは付言しておきたい話があると言います。
「私にも子どもがいて、大学生になった下の子をいまだに手取り足取り世話している妻に、過保護・過干渉のような印象を受ける瞬間も正直あります。
その意味で、男性として共感できるテーマではあるのですが、男性側から見て『過保護・過干渉』に見える行動も、女性の側からすれば、ある種の理想のために頑張っている行動です。その行動を貫くために時には、無理している場面もあると私は考えます。
さらには、その自分の行動を顧みて妻自身がいちばん反省している可能性すらあるのです。
子どもを愛するがゆえに『過保護・過干渉』に見えてしまう女性の行動を攻撃するような行動は避けたいですし、この記事そのものが、女性を傷つける内容になってほしくないと願います」(沢野さん)
セントラル警備保障株式会社(本社:東京都新宿区)の意識調査によると「子どもへの過干渉」を自覚し、自己嫌悪に陥る女性はなんと、3人に1人の割合で存在するとされています。
ホルモンの影響で抑えがたい愛情を感じ、社会的な圧力も重なって、自分が守らなければと過剰に接しながらも、時には行き過ぎてしまう自分の行動を最も反省している人間が、実は母親本人かもしれないという話。
以上のファクトやメカニズムを踏まえ、子どもの未来や自分の幸せを目標に、お互いのセルフコントロールを発揮して、共感から話し合いを始めてみてはいかがでしょうか。
お話を伺ったのは

note|夫婦の悩み相談カウンセラー 沢野まもる
こちらの記事もおすすめ

取材・文/坂本正敬
【参考】
・パパの子育てに関するアンケート – ベビーカレンダー
・ 子育て・見守りに関する調査 – セントラル警備保障株式会社
・ Maternal Anxiety and Physiological Reactivity as Mechanisms to Explain Overprotective Primiparous Parenting Behaviors – National Library of Medicine





