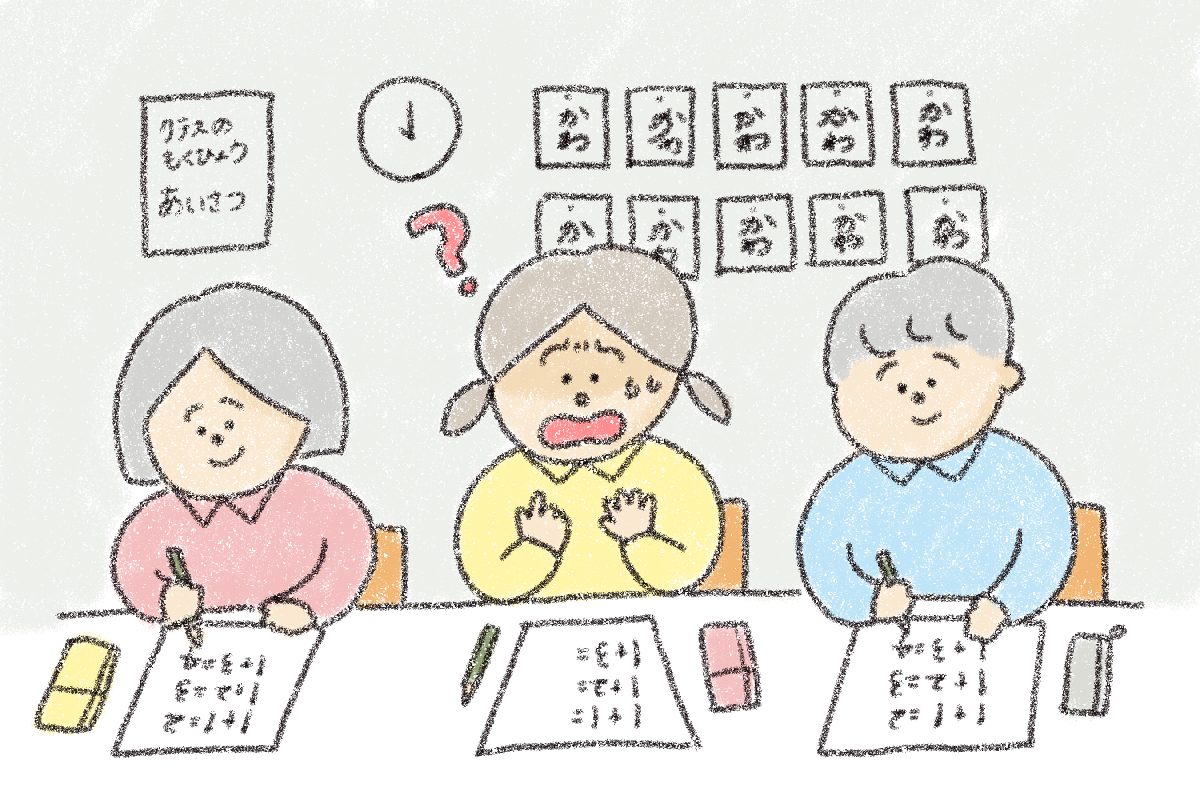目次
算数障害って、どんな特性があるの?
算数障害とは、学習障害(LD)の一種で、ディスカリキュアと呼ばれることもあります。
具体的な特性として、数の大小や量の多少がわからなかったり、足し算や引き算、かけ算、割り算ができなかったり、図形に関しては、例えば円を四等分するといったことができなかったりします。
算数障害の原因ははっきりわかってはいませんが、特に計算は、複数の数字を一時的に記憶しながら頭の中で作業するため、短期記憶を司るワーキングメモリーの処理能力が大きく関与していると言われています。
学習障害のうち、以前からよく知られている読字障害(ディスレクシア)や、書字障害(ディスグラフィア)とちがい、算数障害はまだあまり知られていません。けれども、出現率は5〜7%で1クラスに2人程度はいると言われており、決して珍しくはないのです。
本田すのうさんが、数への違和感を自覚したのは、小学1年生の算数の授業が始まってからでした。
1年生で自覚した「自分は他の子と違って算数ができない」
――ご自身が算数障害だと気づかれたのは、いつぐらいだったのでしょうか?
学習障害についてまだ情報がない時代でした。だから、算数障害ということばや概念を知ったのは成人してからのことです。でも、自分が他の子に比べて算数ができないと気づいたのは、小学1年生のときでした。幼稚園の頃までは、数を数えてもせいぜい5本指におさまる程度ですし、特に困った記憶がないのですが、小学校にあがって算数の授業が始まってしばらくしてから、「自分は他の子と違って算数ができない」ということを自覚しました。実は読んだり書いたりといった国語の領域はよくできていたので、算数に限って他の子と同じようにできないことに、とても悔しい思いをしたことを憶えています。
算数の授業も最初の頃は、みんなが指を使って計算しており、それが当たり前でした。けれども、他の子は徐々に頭の中で計算できるようになっていったのに、私はいつまでも指を使わないと計算ができず、それが恥ずかしくて、ノートに点を書いて数えるようになりました。繰り上がりの計算もそうやって数えていたんです。
例えば、17+5を計算するのは、17のうちの10は「○」、1の単位は「・」で表し、
「○」を一つと 「・」7つ、そして「・」を5つ書いて、それを「ジュウ、ジュウイチ、ジュウニ……、ニジュウニ」と唱えながら数え、ようやく答えを出します。
算数ができないことで、他の教科にもマイナスの影響が出始めた
けれども扱う数が大きくなると、こうした計算もできなくなり、そのうち、繰り上がり計算の際に、自分が計算の最中に数が覚えられないことに気づくようになりました。繰り上がった数を覚えておこうとすると、1の位の数を忘れてしまい、1の位の数を覚えておこうとすると、繰り上がった数を忘れてしまうのです。
社会や理科といった教科と違い、算数は小学1年生でやる内容が理解できなければ、2年生の内容は理解できません。私にとって算数の授業は、苦痛な時間でしかありませんでした。しかも、数の概念が理解できないことや計算ができないせいで、他の教科でもわからないことが出てきてしまって……。

――他の教科で困ったことはありませんでしたか?
まず、理科は実験などが始まると、L(リットル)やmL(ミリリットル)dL(デシリットル)といった単位が登場し、量の計算がわからなくなりました。例えば、1Lと1000mLが同じだと言われても、同じであると理解しているつもりでも、頭の中のイメージでは1Lと1000mLが全然別のものになってしまいます。1Lは少なく、1000mLは多い。
うまく言えないのですが、私の頭の中では、象は大きくてアリは小さいのです。ですから象1頭とアリ1匹が、同じ1を表していると思えないんです。
母親が危機感を感じて高学年で家庭教師がついたけど…
社会だと年号が出てきても、794年と710年のどっちが古いかがわかりません。1092年も1192年も1992年なども、ほぼ同じ数字に感じます。2000年に近い方が最近だとわかりますが、それがどれなのか、パッと見ただけでは今でもピンときません。数さえ出てこなければ、他の教科は理解できるのですが……。数が絡むと途端にわからなくなります。
あまり勉強について厳しい家庭ではありませんでしたが、母親も私の算数のできなさを何とかしなければと思ったのでしょうね。小学校の高学年になって家庭教師がつきました。
家庭教師の先生は、「どこがわからないの?」と私に尋ねます。けれども私は、どこがわからないかがわからないといった状態です。「どこがわからない」以前に、足し算の時点でつまずいているわけです。だけどそれが恥ずかしくて口に出せない。黙ってうつむいているうちに涙がこぼれます。先生は教えようもなく困ったでしょうね。1か月ほどで来なくなってしまいました。
国語と英語の成績は抜群だった中・高校時代。でも、算数から数学になってますます苦手意識が増幅
「どこがわからないの?」と問われることに答えられるぐらいなら、困らなかったに違いないのです。小学校の高学年の頃には、「みんながわかることが自分だけわからない」ということで屈辱感に打ちのめされ、自己肯定感が落ちまくっていました。わからないことが辛く悔しいのは、もしかしたら得意なことがあったからこそ余計にそう感じたのかもしれません。もともと他の教科に関しては、積極的に授業中に手を挙げて答えるような子どもでした。小さい頃から本が大好きで国語の成績はよかったですし、英語は学年一位を取るほど得意でした。
中学に入って算数が数学になると、ますます授業はチンプンカンプン。なので、高校は数学ができないままでも合格できる学校を選びました。「なんで私がこんな低レベルの高校に行かなきゃならないんだ」と、自分では不本意な選択でしたね。ちなみに兄と姉はどの教科もよくできる優等生で、私の高校よりずっと偏差値の高い高校に通っていました。そのことも、自分が劣等生だという意識を持つ要因だったかもしれません。
――子どもの頃、授業以外で算数障害のために困ったことはありましたか?
そうですね、デジタル時計で時間は読めるようになっても、時間の見通しがつかなくて困ることはありましたね。それは大人になってからも続きました。
デジタル時計は、例えば、20分後がいつ何分になるのかを理解するまでに時間がかかります。そういう意味ではアナログ時計の方が、イメージがつきやすいかもしれませんが、それに気づいたのは10代も後半になってから。それまではアナログの時計は苦手でした。時計の針の4が20分を表すことが覚えられないのです。考えてみたら、私の実家にはやたらと時計がありましたね。アナログとデジタルと両方ある部屋とか。もしかしたら、私のためだったかもしれないですね。
物の値段感がわからずに、高額な焼きいもを友達にふるまって母親から平手打ち

あと、困った出来事というか、今でも忘れられないのが焼きいも事件です。
小学5年生の頃、友達と遊ぶ際に、よくお菓子の交換会をしていたんです。小遣いで買えるようなチョコや駄菓子を交換していたのですが、冬休みのある日、遊んでいるときに焼きいも屋さんが通りかかったんですよ。当時、焼きいもは1本800円以上。その頃の小遣いは1か月500円でしたから、手持ちの小遣いでは当然足りなくて。いったん家に戻り、とっておいたお年玉の5000円で、友達の分まで支払ったんです。焼きいもはホクホク甘くて美味しくて、みんな喜んでくれたので「買ってよかったなあ」って思ったんですよね。
ところが帰宅してその話を母親にしたら、ものすごく怒られて平手打ちまでされてしまい……。でも、そのとき、なんで怒られたのかがよくわかっていませんでした。10円のチョコや駄菓子と、800円の焼きいもの金額の違いに気づいていなかったんですね。何がいけないのかわからないまま成長して、母親が怒った意味がわかったのは、自分がアルバイトでお金を稼ぐようになってからでした。
――物の値段の安い・高いというのがわからなかったのですね
生活体験を重ねて物の価値が実感できるようになった
放課後、時給710円のアルバイトを週に3回やっていたのですが、5000円稼ぐのに2日以上かかります。あるとき、またしても焼きいも屋さんの車が目の前を通りかかり、子どもの頃に焼きいもを買って平手打ちされたことを思い出したんですね。今度は自分で稼いだお金だから「誰にも文句は言われない」と考えたんですよ。車に駆け寄り「1本下さい!」と言ったときに「900円ね」と返されて、「高い!」って思ったんです。小学生の自分は「高い」ということがわからなかったけど、自分でそのお金を得るために働くようになって、ようやく「高い」という感覚に。お金の大小といったものを実感した瞬間でした。
小学生からPCになじんで計算はソフトでできるように。高校時代は個性的な級友のおかげで劣等感も薄れました
――その後、日常生活でほかにどんな困り事がありましたか?
実は小学校の頃からパソコン部に所属していたのです。当時、Windows95か98が出たばかりで「シムシティ」というゲームに夢中になりました。また、パソコン部でタイピングゲームもしていました。英語を習っていたので、ローマ字入力でタイピングするとすごく速くキーボードが打てることに感動しましたね。
エクセルやパワポを本格的に使い始めたのは高校生以降ですが、どちらも遊び感覚でどんどんできるようになっていったと記憶しています。
算数ができなくても自分の強みを見つけていけばいいと思えるように
――小学生からパソコン部だったのは意外ですね。パソコンスキルが算数障害をカバーできたということですか?
自分の中では、パソコンと算数は結びついてはいないのです。でも、何よりもよかったのは、高校に入ってから自分が算数障害であることへの劣等感が薄れたことでしょうか。高校の同級生たちは、得意不得意の凸凹が大きい人ばかり。勉強ができなくても自分の好きなことに秀でている人たちが数多くいて、とにかく個性派集団でした。たとえ算数ができなくても、それが気にならなくなっていったんです。自分の強みを見つければいいんだって思えるようになって。その後の生きやすさに繋がっていったと思います。
さらに社会人になってからは、極端に困ることは減りました。スマホが普及したので、日常的に必要な計算はスマホの電卓をつかえばよいですし。仕事上、算数障害で困ることはありませんでした。
パソコンさえできれば、事務の仕事も困ることはありませんでしたし。ICTをうまく使いこなせば、今の世の中、算数障害でもそれほど問題ないのではと思います。
社会人となり、母となり、算数障害で困ったこととは…。後編はこちら

取材・構成/仲尾匡代 イラスト/MAI TANAKA
教えてくれたのは

小学1年生から算数の理解が困難になり、算数のどこがわからないのかがわからない状態が続く。成人してからそれが「算数障害」という特性であることを認識。2024年、SNSでの登録で、ロボットでないことを証明するための数字の問題でつまづいたことをきっかけに、「算数障害」の理解を促すために電子書籍『算数障害の人が見ている世界』をAmazon Kindleで刊行。文章を書くのが好きで、「算数障害」について以外にも、SNSなどで日々発信をつづけている。算数障害の当事者の観点から内容構成に協力をした『たのしい!算数のおはなし』(山本良和・監修/高橋書店)が2025年4月に刊行された。小学生2人と3歳の子どもがいる3児の母。