目次
通常学級に在籍する「困り感」のある子どもたちが自立活動を学ぶために通う教室が「通級」

学習や学校生活で困り感をもっている比較的軽度の障害のある子どもが、基本的には通常の学級に在籍し、一部の授業を抜けたり、放課後の時間を使ったりして、学級とは別の「通級指導教室」で自立活動を学ぶ制度が「通級」です。平成30年度から、小・中学校に加えて、高校でも通級指導が制度化されました。「特別支援学級」とは別の制度です。
対象となる障害
対象となる障害は、言語障害・自閉症・情緒障害・弱視・難聴・肢体不自由・身体虚弱者・LD(学習障害)・ADHD(注意欠陥多動性障害)。知的障害は対象になっていません。
通級の形態
「通級指導教室」は、
①自校通級(通っている学校に設置されている通級指導教室)
②他校通級(地域のほかの学校の通級指導教室に通う)
があります。
また、通級指導教室担当教員が勤務する学校以外の学校に訪問して通級を実施する
③「巡回指導」もあります。
③は、子どもにすれば、自分の学校で通級を受けることができるので「自校通級」と言えるかもしれません。設置されている学校によって、「コミュニケーションルーム」「〇〇教室」などのように教室に呼称を設けている場合が多いようです。
通級で学ぶ授業時間数と内容
小・中学校では、週1~8時間程度、高校では、年間7単位までを標準にしています。国語や算数などの教科や科目の勉強ではなく、その子の抱えている障害が原因で生じている学習や生活の困難さを改善するための「自立活動」を学びます。指導に当たるのは、それぞれ小・中・高校の教員免許をもった教諭です。
通級を利用したいと思ったらどうすればいい?

利用するためには手続きが必要です。申請手順や申請書類は自治体によって異なりますが、窓口は、通っている学校の特別支援教育コーディネーターやお住まいの市区町村の「就学支援相談窓口」「学校教育課」などになります。申請書類を提出の後、面談を経て、「通級指導」が必要と見なされれば決定され通知されます。
自治体によっては、申請書類に医師の診断書や発達検査の結果などが必要な場合もあります。発達検査や診断書は、費用や用意に時間がかかる場合がありますので注意が必要です。就学前から療育施設などに通っている場合は、その施設等で実施している療育内容が示されている計画を求められる場合もあるでしょう。
カリキュラムは子ども一人ひとりに合わせたものを作成。本人・保護者との情報共有が必須

「通級」では、子ども一人ひとりに合わせて、「個別の教育支援計画」と「個別の指導計画」を作成して指導します。
・個別の教育支援計画(教育と家庭、医療、福祉などの関係機関が連携・協力を図るために作成されるもの)
・個別の指導計画(子どもの実態に合わせた指導を行うために作成されるもの)
このうち、「個別の教育支援計画」は、作成する際に、本人、保護者(家庭)の意向を踏まえること、関係機関で情報共有することが法で定められています(平成30年8月 学校教育法施行規則の一部改正)。
放課後等デイサービス(福祉機関)等を利用している場合、必要に応じて「ケース会議」が持たれることがあります。決まった教科書や教材がない通級指導では、一人ひとりの子どもに合った課題や指導目標、指導内容、支援方法が記載される「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」がとても重要になります。
保護者は、学校、放課後等デイサービスをつなぐハブの役割を意識して
「ケース会議」をスムーズに行うために、保護者の方は「学校」と「放課後等デイサービス」(以下、放デイ)をつなぐハブの役割を、ぜひ、意識してください。先に情報共有が法で定められていると述べましたが、私は、教育現場である学校と、福祉を担う放デイの連携がまだまだ図れていないことを実感しています。
放デイの担当者から学校との「子どもの情報連携」をしたい旨、依頼があった場合は、保護者自身が情報連携を了解していることを、在籍する学級担任、通級の担任等に、あらかじめ伝えておきましょう。もちろん保護者から放デイの担当者に学校と連携したい旨を依頼しても構いません。保護者の心がけと行動でスムーズに「情報連携」「ケース会議」を持つことができます。
何よりも大切なのは子ども自身の意思
そして、通級を利用したり、2つの個別の計画を作成する際に、何よりも大切なのは、どんなことができるようになりたいのか、どんな夢をもっているのか、そして通級に行ってみたいのかなど「本人の意思」です。本人の年齢や性格、障害の状態等によっては、ケース会議に一緒に出席するということも考えられますね。
保護者も子どものために情報通になるべし~通級指導の教師向けガイドを活用~
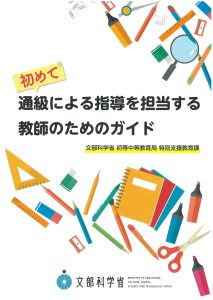
子どもには困り感を解消して、楽しく学校に行ってほしい。そのためには必要な情報を知っておきましょう。
文部科学省のHPから、「初めて通級による指導を担当する教師のためのガイド」をPDFでダウンロードできます。
文字通り、初めて「通級」の担任になった先生のための資料集ですが、年間の流れ、通級指導の利用フローや、子どものことを知るためのアドバイスなどが詳細にまとまっています。3章に16の実践例が掲載されており、具体的な事例に即した対応を知ることができます。
「実践例」の1では、「担当する子どもについて知るには、保護者との面談の前にどこから情報を集めればいいのだろう?子どものどんなところを見ればいいんだろう?」が取り上げられています。
子どもがどんなことに困っているのか、好きなことや得意なことは何なのか?子どもの日々の様子をしっかり見ることがポイントとなっていますが、これは、ケース会議に向けての保護者の心得にも通じるところです。
何より、このガイドの存在を保護者が知っていることを学校側が認識することで、保護者の真剣さが伝わります。
利用希望者の増加に応えるべく、教師の配置を確保。2027年度から「通級」は定数化します
文部科学省の発表によれば、令和5年度時点で、「通級」による指導を受けている児童・生徒は全体で20万人に上っています。阿部大臣から発達障害の特性がある子どもとその保護者に向けて発信されたメッセージは、以下のような主旨でした。
・学校では、困難さのある子どもたちへの支援を用意しています。
・「困難さを改善していきたい」「通級による指導に興味がある」「お子さんに合う支援について知りたい」といった場合は、ぜひ学校の教員や教育委員会にご相談ください。
そして、メッセージでは「通級の充実に取り組んでいる」ことにも言及されています。年々、右肩上がりで通級の利用者は増えていますが、利用したくともできない子どもたちがたくさんいるのが現状です。新規利用者を優先するために、進級すると「通級」を継続できなくなったという事例も多々あるようです。
「通級」は、子ども13人に指導教師1人の体制に

利用希望の需要に応えられない大きな要因は「通級の指導教員」の不足ですが、実は、「通級」制度は、2027年度から子ども13人にひとりの教師を配置する「定数化」に移行します。
全国の公立小中学校等に配置される教職員の数は、総数として算出される「基礎定数」と、「いじめ対応」などの政策目的に応じて措置される「加配定数」を合わせた総数になります。従来、「通級の指導教員」は加配措置の対象となっていました。これが、法律により、2017年から10年かけて、13人に1人が措置される「基礎定数」として新設されることになったのです。
「希望する人誰もが受けられるようにする」というのが「通級」制度の大切なポイントです。利用したくてもできない、いわば待機状態の子どもたちの数が、「定数化」によって少しでも緩和されることを期待したいですね。今こそ、教育(学校)と家庭と福祉(放デイ)が手を携えて、困り感を抱えている子どもたちが安心して過ごせる場としての学校、そして「通級」への理解を深めてほしいと思います。
「合理的配慮」についてのこちらの記事もおすすめ

記事監修

取材・構成/Hugkum編集部





