目次
赤ちゃんは成長に伴って感情も豊かになっていきます
体の成長と同様に、人間の感情も少しずつ育っていくものです。
生まれたばかりの赤ちゃんが持っている感情は、「快い」「不快・苦痛」「興味」の3種類といわれています。
その後、周りの人との関わりなどを通して、生後6カ月頃までには「喜び」「悲しみ」「怒り」「怖れ」「嫌悪」「驚き」の6種類が備わってきます。
1歳半頃から「自分」という存在に気づくことで、さまざまな感情が芽生えます

そして、1歳半頃にはっきりと芽生えてくるのが「自己意識」です。
自己意識とは、周りのものや人と自分自身を区別できるようになる力のこと。「自分が他人からどう見られているか」などを意識するようになるため、「恥ずかしい」「うらやましい」といった感情も抱くようになります。
また、友だちが転んだ様子などを見て「痛そうだな」「かわいそうに」などと共感を覚える場面も出てきます。
さらに2歳半ぐらいになると、「よい・悪い」という観点も持つようになります。自分のしたことがよいことなのか、悪いことなのかを考えるようになり、周りの人にどう思われるかということにも敏感になります。
たとえば、「トイレで用を足せること=かっこいい(よい)」と感じるため、成功すると「やった!」と誇らしくなる。反対に、「おもらしをすること=かっこ悪い(悪い)」ため、失敗したときには恥ずかしさを覚えるわけです。
また、友だちのものをこわしてしまったような場合、自分のしたことが「相手にとって悪い」ということを感じ取り、罪悪感や反省などの感情も生じるようになります。
乳幼児期は「イメージする」力が伸びるとき
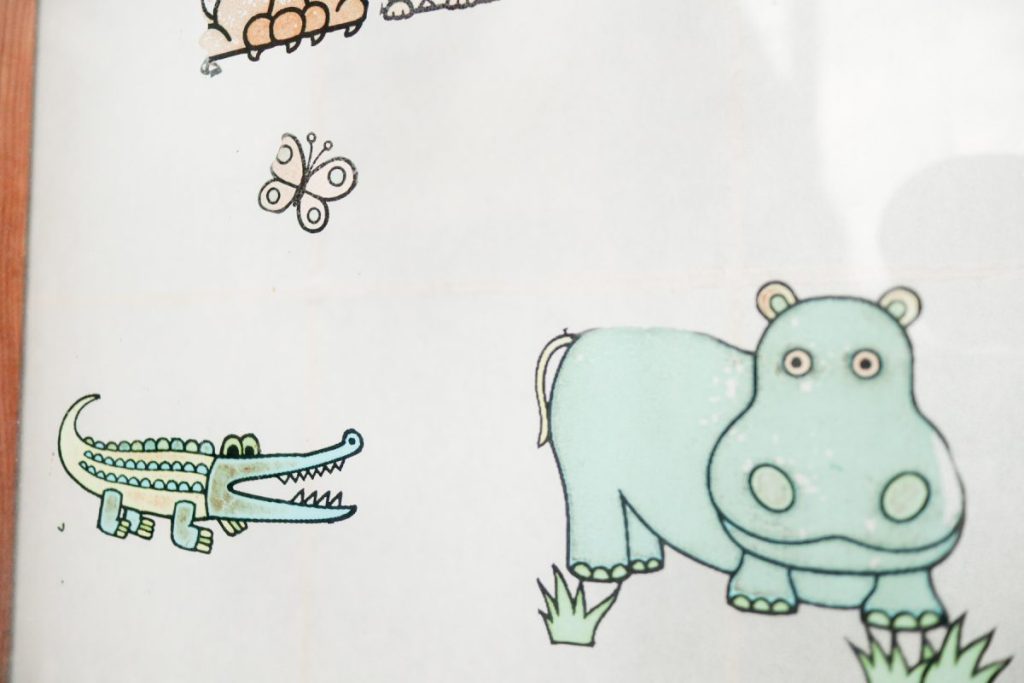
言葉でのコミュニケーションがまだ難しい時期、赤ちゃんの感情は、表情や行動から読み取ることになります。落ち着いていれば「快い」、泣いたり不機嫌になったりしていれば「不快・苦痛」。では、「興味」はどのように現れるのでしょう?
赤ちゃんの気持ちは視線に表れる
もっとも大きな手がかりになるのが、視線です。子どもは、興味を覚えたものをより長く見つめる傾向があります。このことは科学的に証明されており、乳児の心理等を調査する際の指標のひとつとしても使われています。
子どもの好みや心の動きを知るためにも、日頃から子どもの視線の先に注意を向けることを心がけてみませんか?
五感を使うことがイメージする力につながる
赤ちゃんは、自分の感覚を使ったり周りのものに働きかけたりしながら、自分を取り巻く世界を認識しています。そして、徐々にそこにないものをイメージする力も身につけていきます。
たとえば、バナナを耳に当てて電話ごっこをするのは、電話のイメージをバナナに重ねることができるからです。
こうした力は、言葉を獲得していくために欠かせないものです。言葉の意味やイメージの広がりを捉える力は、実際に言葉を使うようになる前から少しずつ育っています。こうした力を伸ばすためには、生活の中で五感をフルに使うことが大切です。
夢中になって遊んでいるときに、赤ちゃんの脳は活性化しています

大人は「頭を使う=勉強」と考えがちですが、赤ちゃんにとっては、「頭を使うこと=五感を使うこと」。そしてもっとも頭を使うのが、夢中になって遊んでいるときです。
興味のあるものと向き合っているとき、子どもは五感を総動員し、その情報をもとにしてさまざまなことを考えます。自発的な遊びこそ、主体的で深い学びにつながるものなのです。
遊びに没頭している子どもの頭の中はまるで科学者
ひとり遊びに夢中になっているときの子どもは、「孤独な科学者」にたとえられます。
たとえば積み木を高く積み上げたい場合、子どもはまず「仮説」を立てます。積み木を見たり触れたりした経験から、「これの上にあれをのせればうまくいくはずだ」などと考えるわけです。そして、「仮説」に従って積み木を積んでみる。つまり「実験」をするわけです。
実験が成功すれば達成感が得られ、もっと遊んでみたくなるでしょう。ただし、実験が失敗することもあります。すると子どもは「それなら、こっちをのせたらどうだろう?」と仮説を立て直し、再び実験に挑みます。
自分で考えて実行し、興味の対象を深く探求していく。まさに科学者と同じ頭の使い方が、遊びの中で自然に生じるのです。
五感を使う遊びをたくさん経験することがコミュニケーションの土台に

「孤独な科学者」としての遊びで大切なのは、成功・達成することではなく、経験することです。
自分が思う高さまで積み木を積むことができなくても、遊びが失敗したことにはなりません。仮説を立て、実験する過程にこそ意味があるからです。
情報をキャッチする力、分析して考える力、想像して考えを広げる力……。コミュニケーションの土台となるこうした力は、赤ちゃんの頃に頭(=五感)を使う経験をしっかり積むことによって伸びていくのです。
スマホは親と一緒に楽しむツールとして使うことがおすすめ
五感の使い方の偏りにつながりがちなのが、スマートフォンなどで動画を見ることです。
視覚と聴覚にはたくさんの刺激が入ってきますが、「嗅ぐ」「味わう」「触れる」という刺激は不足してしまいます。
また、動画は自動的に流れるので子どもは受け身になり、「自分で刺激を探して発見する」という経験にもつながりません。子どもが五感を存分に働かせる機会を奪わないためにも、動画などは親と一緒に楽しむツールとして使うのがおすすめです。
内容に応じて「○○のマネをしてみようか?」といった言葉かけをするなどして、「見る」「聞く」以外にも楽しみ方を広げる工夫をしてみましょう。
注射で子どもが泣きだした。泣き止ませるにはどうしたらいい?

子どもが泣き出したとき、状況によっては「早く泣き止ませなくては」とおやつを与えたりすることがあります。おいしいお菓子をもらえば、子どもは機嫌を直すかもしれません。でも、それは一時的なもの。
乱れた感情をケアするためには、共感を示すことが必要です。まず、何かがイヤで泣き出した子どもの気持ちにいったん寄り添い、「うん、イヤだよね」と同じ気持ちを体験します。その後で「でも、大丈夫!」と感情を立て直せるような声がけをするのが理想です。
子どもの感情に寄り添うことで気持ちは伝わります
子どもの感情の変化を知るために、初めての予防接種を受ける親子の様子を観察した実験があります。
ほとんどの子どもは、場の雰囲気などに反応して注射をする前に泣き出します。その際の親の反応を次の3タイプに分類し、子どもの様子を観察しました。
A:お菓子などを与えて「大丈夫!」と励ます
B:子どもと一緒におろおろする
C:子どもと同じように悲しそうな表情になった後、「大丈夫!」と励ます
子どもがいちばん早く泣き止んだのは、親がCタイプの場合でした。
相手の表情やしぐさをまねすることを「ミラーリング」と言い、相手に感情移入することで自然に起こります。
赤ちゃんは、親が自分と同じような表情を見せることで「気持ちをわかってもらえた」と感じます。そして、受け止めてもらえた安心感から、気持ちを素早く立て直すことができるのです。
赤ちゃんとのコミュニケーションには、言葉以外の部分が深く関わっています。言葉だけに頼らず、身体全体で、とりわけ視線や表情を通して、感情を込めて働きかけることをおすすめします。
こちらの記事もおすすめ

記事監修

取材・構成/野口久美子 写真/山本彩乃





