目次
小学校受験のきっかけは大きく3つ! 中学受験からシフトする新規層が増加中
まず、小学校受験は下記の3つのようなきっかけで検討されるご家庭が都内を中心に多いんだとか。
(1) 保護者のどちらか片方、もしくは両方が私立小出身者で子どもも同じような環境で育てたいと考えている家庭。
(2) 先輩、後輩、同僚などが私立小出身者、または、子どもを私立小に通わせているなど、自分自身は小学校受験はしていないが、周囲からの情報に触れ、その豊かな初等教育環境を与えたいと考えている家庭。
(3) 中学受験の過熱ぶりに疑問を持つ中で、附属小学校の存在に気づいた家庭。上の子の中学受験を経験して、もう中学受験は避けたいと考える家庭も。
狼侍さんはX(旧Twitter)で4年前から小学校受験を発信していますが、フォロワー数の激増ぶりは、(2)や(3)に該当する教育熱心で情報収集する親層が増えていることに関係していると話します。
倍率の高い中学受験よりも小学校受験の方がお得?
中学受験というと、御三家などハイレベルな学校に目がいきがちですが、実際のボリュームゾーンは偏差値50台の層です。その層の中学校を検討するご家庭が附属小学校への選択肢にも目を向けるようになり、小学校受験の認知がどんどん広がっていると思います。
例えば、きょうだいで上のお子さんの中学受験でとても苦労したケースがあります。ハードな受験勉強で苦労した中学受験よりも、附属小学校に入れてしまった方が楽なのではないか、と興味を持つ保護者の方も増えていると感じます(狼侍さん)

ひと昔前まで小学校受験情報は、その世界にしっかり足を踏み入れなければ全く情報にリーチできなかったものの、今は検索すれば学校HPや体験者のSNSなどで得ることができます。私立小を調べるきっかけを得た親がさらに「どんなものだろう」と一歩先の情報が取れる時代になったことで、昨今小学校受験がじわりと増えている要因につながっているそうです。
学校選びは家庭との相性。わが家の子育て方針とマッチした学校を探そう
小学校受験の入り口に立ったならば、「志望校を絞り込む」ことが先になります。その後に、その学校に合った塾(教室と言います)探しとなります。まずは大まかな志望校群を決めましょう。
詳細は拙著『小学校受験は戦略が9割』に譲りますが、その方法として、「なぜ小学校受験をさせたいのか?」など、夫婦の教育観を話し合い、男女共学・別学、出願倍率、卒業後の進路などいくつかの「志望校選びの切り口」を組み合わせて5校程度をピックアップし、仮の志望順位を付けます。その上で、志望校に合ったメインの教室を決めます。
さらに並行して、実際に説明会や見学に行って知識を得てください、と狼侍さん。
はじめて小学校受験を検討するときには、早稲田大学や慶應義塾大学の附属校、白百合学園、聖心女子学院など誰もが聞いたことがあるような知名度の高い学校へ目がいきがちです。でも、大切なのは学校の知名度ではなく、ご家庭に合った初等教育を選ぶこと。まずは学校の説明会、運動会などのイベント、複数の学校による合同説明会などで学校の公式情報に触れ、知識を深めることをおすすめします(狼侍さん)
そして、教室や志望校は、下の図のようにPDCA(計画、実行、検証、改善)サイクルを意識して、違和感がないか、常に現状を検証しながら進めましょう。

わが子にどう育ってほしいのか、親が責任と覚悟を持つことが大事
学校や先生、生徒の雰囲気や地理的要因、宗教、男女共学か別学かなど絞り込みにはさまざまな要素があります。子どもが小学校6年、あるいはその先の附属中・高含めて12年間を過ごす場としての判断基準や視点は親にしかない、と狼侍さんは話します。
小学校受験をはじめる子どもの年齢は3~4歳だと言われていますが、6年後、12年後まで長期の目線を持って子どもが自分で判断できる視点はまだ持っていないと思います。「学校の遊び場が楽しそうだった」「一緒に過ごした先生が好きだった」そういった子どもの直感的な要素は相性という意味では大切なものですが、それよりもわが子にどう育ってほしいのか、どんな教育を受けてほしいのか、親自身が責任と覚悟を持つ必要があります(狼侍さん)
教育方針を固めてみるとわが子の将来や人生が見えてくる
一口に、わが家の教育方針、と言っても、小学校受験を念頭に置きはじめる3歳くらいでは、子どもが成人するまでどんな教育を受けさせようかなんて、まだまだ先のことだと、あまり具体的なイメージを描いていない家庭も多いかもしれません。
夫婦の意見や価値観をすり合わせることは小学校入試の副産物
狼侍さんによれば、小学校受験はいわば就職試験の面接のようなもので、「この会社に入ったらどんなことができるか、したいか」などと同様に、大事な小学校時代を過ごす場所として、子どもやその両親、家庭としての姿や価値観を面接試験でお互いの相性を見ているんだそう。
夫婦の別々の価値観は、時にはぶつかり合ったり、本心をさらけ出したり、子どもの教育方針をすり合わせる作業は労力がいるものの、小学校受験というライフイベントに際して固まった「わが家の教育方針」は、受験の副産物、家庭内のプラスなイベントになるのです。

また、小学校の合否は別にしても、小学校に入る前に立てた教育方針について仮説をたてて行動したり、検証や改善を通して修正したり。PDCAをまわすことでその後の子どもの成長を長い目で見通せば、有益な「わが家の教育方針の土台」が出来上がるというわけです。

教育方針が固まれば日常生活にも活かせる土台ができる
基本となる教育方針が固まり、その後も検証し続けPDCAをまわすことは、小学校受験を見送って中学受験にシフトしたり、はたまた高校受験にシフトしたりなど、わが子の進路選択のターニングポイントの指針にもなるのだそう。教育方針が決まれば、おのずとそれは、日常生活の習慣や年中行事、遊びの取り入れ方や旅行・レジャーのときにも、その一家の教育指針としてブレない柱になるのです。
「どの学校か」よりも、最も大事なのは、「どんな12歳になってほしいか」
いざ、小学校受験の世界に足を踏み入れ、情報収集や説明会、お教室など、深掘りしはじめてから、現実に直面し、小学校受験をやめる家庭もあまた見てきた、という狼侍さん。
知名度や周囲の評価で私立小の世界に過大に憧れたり、体験で行った教室でわが子が優秀とのせられたり。「なんで私立小がいいのか?」と立ち止まって考え、前述のわが家の教育方針と外れて大切なことをおざなりにしていないか考えることも重要だそうです。
「せっかく…なのに」は、親が絶対に、言ってはいけない言葉
そんなときに、「『せっかく…したのに』という言葉、考えは、親が一番切り捨てなければならないものですね」と狼侍さん。小学校受験でなく中学受験もあるし、小学校受験で入学しても中学や高校の進路変更で内部進学しないかもしれない。PDCAをまわす中で、新たな仮説を子どもが見つけたら、自立心が見事に伸びたんだな、とその成長を喜んであげて、応援するのが親の役目。間違っても「せっかく…したのに」「もったいない」的な言葉を子どもに向けるのは避けるべき。
受験というと、勝ち負けにクローズアップしがちですが、それよりも子育てに向き合ういい機会ができたと捉えてみると良いと思います。だんだんと『どこでもいいから私立に行きたい』『有名なところだったらどこでも構わない』となってしまうことが往々にしてありますが、自分たちが何を大切にしたいのかは忘れてはならないポイントではないでしょうか(狼侍さん)

どんな12歳になっていてほしいか、という視点を持つことで、あくまでも小学校6年間を過ごす環境として、わが子やわが家とのマッチングを考え、進路選択をすることが最適解なんだとか。
共働きでも小学校受験にチャレンジできる
私立小学校というと、お迎えのルールや平日の行事があって共働きの家庭だと縁のない世界なのでは…と思うかもしれませんが、実はそんなこともないと狼侍さんは話します。
学校側の仕組みも昔とはちがい、大きく変わってきています。学童などのアフタースクールを併設している学校や、お弁当サービスを導入している学校もあります。これまでそういったサービスを利用していなかった伝統的な女子校など含めて、導入する学校が増えてきています。
世の中的にも共働きの家庭は増えていますから、シッターさんや学童などのサポートを活用する傾向は広がってきていると感じます(狼侍さん)
小学校受験の勉強のノウハウは全ての家庭の役に立つ
たとえ子どもの受験を小学校入学で考えなくても、小学校受験対策としての学びは、全ての家庭の知育に役立つと断言する狼侍さん。
もともと、狼侍さんは、おむつ替えなどタスク的な部分での育児は担っていたものの、クリエイティブ系の子どもとの遊び、自由遊び、が苦手だったとか。季節の行事で果物狩りがあったり、キャンプでは火はどうしてつくのか構造を説明したり、生き物に触れたり、魚も淡水魚か海水魚かの違いを調べてみたり、どんな絵本を読み聞かせるといいのかだったり。

小学校受験の必要性に駆られていっていた子どもとの遊びが、ふだんの親子の会話、語彙力を高めるような知育につながったのだとか。受験をしない家庭でも子どもと目一杯遊びたくても方法論が見つからず困っている親御さんには、小学校受験用のテキストや参考書などが大いに役立つというわけです。「うちは小学校受験はしないし、関係ないか…」ではなく、一度手に取ってみてはいかが? 今まで思いつかなかった遊びや、お子さんの興味の広げ方のヒントを見つけられるはず。
わが子の進路、人生の選択肢は無限! 子どもと向き合うかけがえのない時間は宝物
小学校受験をするか否か、希望した小学校にご縁をいただけるのかどうか、選んだ道がわが子に本当に合っていたのか…。わが子の人生の選択肢は、無限にある、と狼侍さん。ご自身のお子さんの受験経験が、親自身の成長につながり、今こうして情報を発信することになったことからも、親として子どもの長きにわたる教育プランや教育方針、さまざまな選択肢を考え、わが子と真剣に向き合うかけがえのない時間になったと話します。
小学校受験で培った「親力」や「家庭力」は、子どもの将来、ずっと先まで役立つものなのかもしれません。
著書をチェック
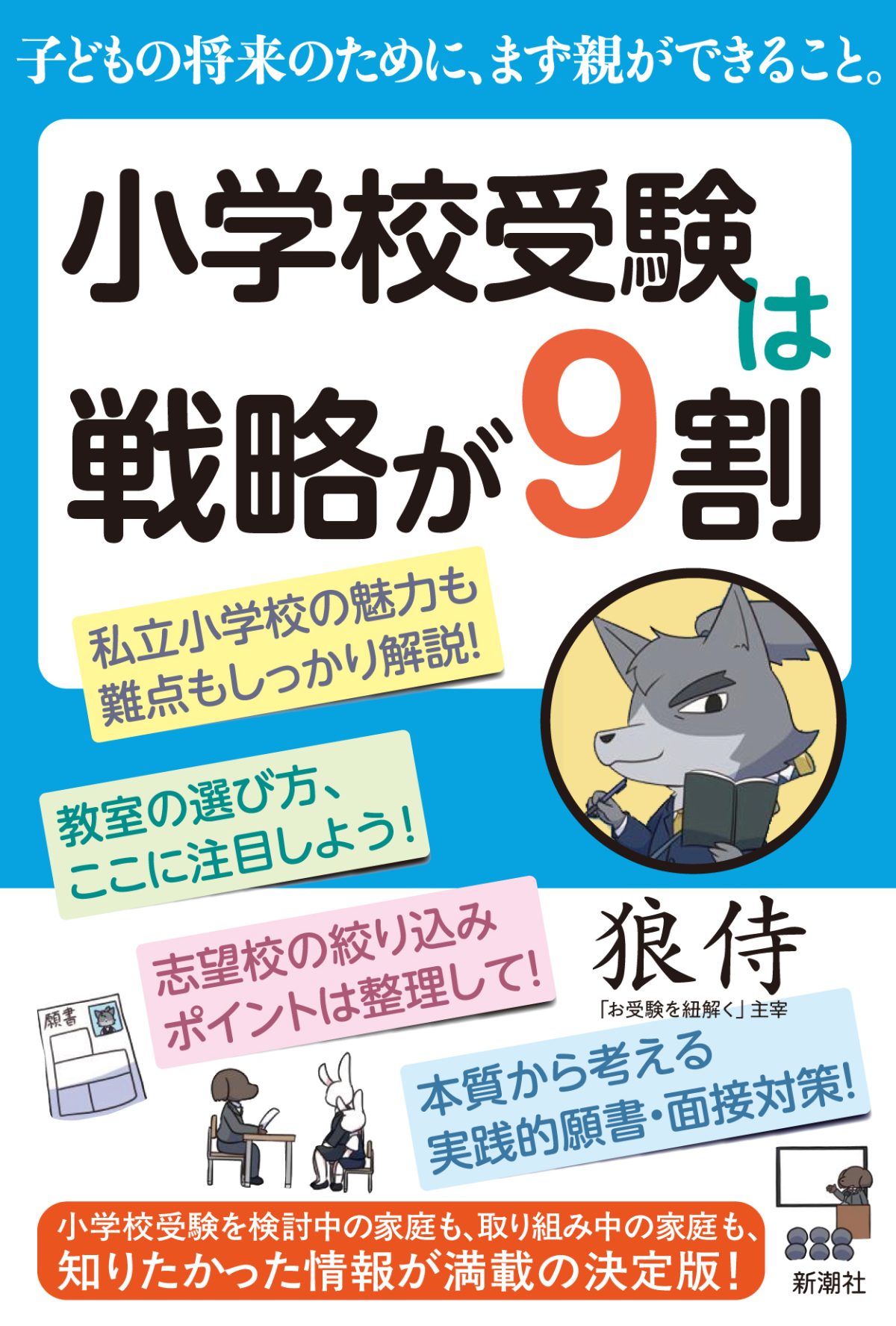
小学校受験の本質は、各家庭に合った初等教育を見つけること。私立小学校の魅力や、志望校と教室選びの決め手、縁故の役割、願書や面接の実践的な対策など、お受験解説の第一人者である著者が独自の分析をもとに、どう挑むべきか、その戦略を徹底解説。検討中の家庭も取り組み中の家庭も、知りたかった情報が満載の決定版!
お話を伺ったのは

私立一貫校に通う二児の父親であり、自身のお子さんの幼稚園・小学校受験の経験と、多数の取材に基づいた独自の分析を基に、X(旧Twitter)、note、Instagramを中心に、「お受験」の構造や対策について、小学校受験に関する情報を発信。経験者としてのリアルな声とデータに基づいた分析で、ヴェールに包まれた小学校受験の世界を解き明かす情報発信者として注目されている。
著書に『小学校受験は戦略が9割』(新潮社)。
取材・文/羽生田由香





