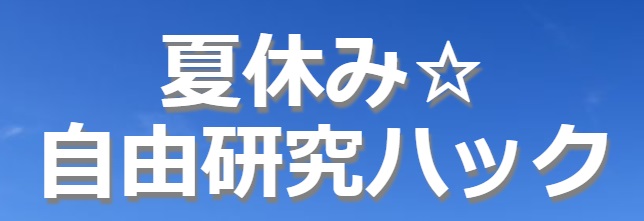目次
自由研究に卵を使って実験してみよう!
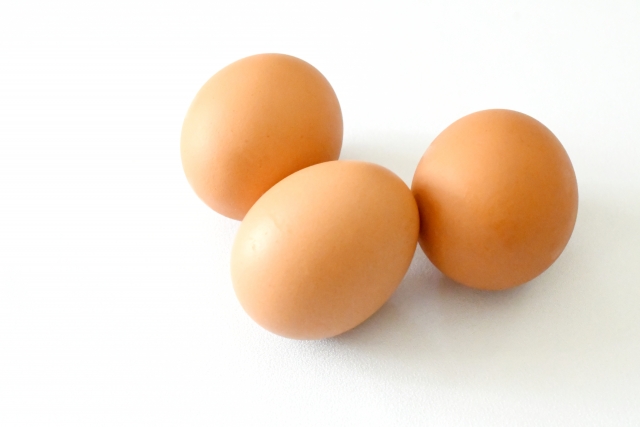
毎日食べている子も多い卵は、とても身近な食材です。そんな卵は、実験材料にぴったり。さまざまな食べた方があるように、起こる反応もさまざまだからです。キッチンを使った実験もあるので、料理に興味を持つ子もいつかもしれません。
【1】お酢を使ってスケルトン卵
劇的な変化が面白く、ぜひ時間のある夏休みにこそ試したいのが、お酢を使った実験。硬い卵がぶよぶよになるのを実感できる簡単で楽しい実験です。

用意するもの
- ・卵2個(1個は比較用なので、冷蔵に入れておきましょう)、穀物酢500ml程度
- ・口の広いガラス瓶
- ・キッチンペーパー
- ・輪ゴム
- ・箸
- ・黒い画用紙
実験の考察
お酢につけると卵がどんな変化を起こすか。殻の成分と、お酢の成分との化学反応がポイントになるのでは?
実験方法
手順①
卵は水でよく洗い、ガラス瓶は洗剤できれいにあらいます。汚れがついていると、実験がうまくいきにくくなるので、よく洗うこと。洗ったらガラス瓶に卵を入れ、卵がかぶるまでお酢を注ぎます。
手順②
卵から泡が出てくるのを確認します。ほこりが入らないようキッチンペーパーなどでふたをして、冷蔵庫または冷暗所に2日ほどおいておきます。(この際に密閉はしないこと)
手順③
- 殻が溶けて、薄い皮だけになったらスケルトン卵のできあがり! 殻が残っていたら、水でやさしく洗うときれいに落ちます。
実験のポイント
この実験のポイントをまとめます。
ポイント①
お酢にはカルシウムを溶かす力があります。卵の殻は「炭酸カルシウム」というものでできているので、お酢につけると殻が溶けます。
ポイント②
殻が溶けてもなぜ卵が割れなかったかというと、殻の内側には薄い膜があり、これはお酢には溶けないので残るから。 この膜は、ゆで卵の殻をむくときについている、薄い白い皮です。
ポイント③
お酢につけた卵は通常より大きくなります。それは浸透圧の関係で、お酢が卵の中に入ってくるので、元の大きさよりも少し大きくなることに。通常の卵と比べてみましょう。
ポイント④
スケルトン状態になった卵は、ぷよぷよして弾力があります。壊れない程度に押してみましょう。また、電気の光の通し方について調べても面白そう。
実験の注意点
注意点①
- スケルトン卵の内部は基本的に害はありませんが、温度によっては菌が発生することがあるので、口に入れるのは避けましょう。手についたものも洗い流しましょう。
- また、お酢についても風味が変わるので使用は避けましょう。
注意点②
容器には必ずガラス製を使いましょう。
実験のまとめ方
まずは基本のスケルトン卵の作り方の紹介。なぜ、作ってみたか、どんな変化が起きそうか、自分なりの言葉で導入にしましょう。
その後、実際に作ってみた経過を写真で押さえ時系列で紹介。なぜ、スケルトンになったのかなどを図鑑等で調べてみんながわかるように説明しましょう。
- また、ほかのものでも同様の変化があるのか調べてみると、さらに幅のある自由研究になります。ほかの酸性成分でも同じことができそう。つまり、サイダーや柑橘系の飲料、またハイターやサンポールなどの酸性洗剤で調べるのも面白いですね。洗剤を扱う際には、手につかないようにゴム手袋をするなど注意しましょう。
【2】ゆで卵の固さ調べ
日々何気なく食べているゆで卵。おいしい固さになっているけれども、それってママ・パパがちょうどいい固さにゆでてくれているから。夏休みは、自分でどのくらいのゆで時間なら好みのゆで具合になるのか調べてみましょう。

用意するもの
- ・卵4つ
- ・塩小さじ1杯
- ・鍋、おたま、時計、ボウル、まな板、包丁、油性ペン
実験の考察
ゆでる時間によって半熟卵〜固ゆで卵になるまでに変わるはず。
実験方法
手順①
それぞれの卵に、油性ペンで5、8、10、15とゆで時間を書きます。
手順②
鍋に卵を入れて卵がかぶるくらいの水、塩小さじ1杯を入れて中火にかけます。(中火=鍋底に火が当たるくらい)
手順③
沸騰したら弱火にして、タイマーで時間をはかり始めます。5分・8分・10分・15分たったらそれぞれの卵をおたまで取り出します。取り出した卵は氷水を張ったボウルに入れ、よく冷ましたら殻をむきます。
手順④
それぞれの卵を真ん中で切ってみて、ゆで具合を比べ、写真を撮りましょう。
実験のポイント
ポイント①
この実験のポイントは、卵の性質を調べるものです。
卵の黄身は70℃で完全に固まり始めます。それよりも時間が短いとそのぶん卵の中まで熱が伝わらず、温度が上昇しなくなるんですね。
ポイント②
100均でも売っているエッグタイマーを使って、同じような結果になるか調べるのも面白いですね。
実験の注意点
注意点
高温のお湯を使うので、必ず大人と一緒に実験しましょう。特にゆで卵を取り出す際には注意が必要。
実験のまとめ方
自分がいつも食べている固さは何分ゆでだったかを示しながら、他の固さのものを食べた感想や、固ゆでならタルタルソースに、半熟ならラーメンになど食べ方もまとめてみると楽しい実験だったことが伝わりますね。
【3】カラフルゆで卵
日本でもイースターにホームパーティをするなど、特に子どもの間では根付いてきていますよね。今回は、殻ではなくカラーゆで卵を作ります。ほんとに? と思う人もきっと多いですよ。
用意するもの
・殻をむいたゆで卵 5個
・カレー粉
・バジルペースト
・ナス漬物汁
・漬物赤カブ汁
・キャベツの千切り
実験の考察
すべて食べることのできる自然の素材ですが、どこまで卵の色が変わるのかを調査。どのくらいの色味になりそうかも予想するといいですね。
実験方法
手順①
コップにそれぞれの液を作ります。カレーやバジルペーストなど、なるべく濃い色になるまで溶かしましょう。
手順②
むいたゆで卵をそれぞれの色のコップに全体がかぶるようにつけます。ムラにならないように、たまに割り箸などで混ぜるようにします。
実験のポイント
ポイント①
カレー粉など、色の濃いものは早めに染まるので、時間を短く区切ってチェック。それ以外は一晩かかる場合もあるかも。
ポイント②
人工の赤色や青色の食紅もあり、染まりやすいので、合わせてチェックしてもいいかもしれません。また、他の色味のもので試してみるのもおすすめ。例えば、たくあんの汁や、きゅうりのキュウちゃんなど…。スーパーで探してみるのも面白いですね。
実験のまとめ方
最初に可愛くアレンジしたカラフル卵を、アイキャッチとして入れるのがおすすめです。なんで? とみんなの興味を引けるはずです。まずは基本の色味で紹介。その後にほかの色でチャレンジしたものも紹介してみましょう。他の子から新たなアイディアが出てくるかもしれないですね。
【4】温泉卵の作り方実験
温泉卵は、普通のゆで卵と違い、温度管理が難しいもの。今回は、ちょうどいい具合の温泉卵をつくるべく実験をしてみましょう。

用意するもの
新鮮な卵3個、60℃、75℃、90℃のお湯、温度計
実験の考察
温泉卵は熱湯でゆでるのではなく、白身が固まらないようにお湯につけて作るもの。黄身は程よく柔らかな固さ、白身は固まらない、程よい温度を探ります。
実験方法
手順①
それぞれのお湯に卵がかぶるくらいつけます。それぞれ30分つけることでどのくらいの硬さの温泉卵になるかチェック。
手順②
実験結果を記録するために、それぞれの温度でどんな温泉卵ができたか撮影しましょう。
実験のポイント
黄身と白身がどのくらい固まっていたか、自分で食べて好みのものを記録しておくのもいいかもしれないですね。
実験の注意点
温泉卵を作るには、お湯の温度を一定に保つ必要があります。温度計で温度を測りながら、卵をお湯につけましょう。時間が長いと固まりすぎるので注意が必要。
実験のまとめ方
旅館でよく出てくる温泉卵が家で食べられたらと思ったなどのきっかけを導入に。それぞれのお湯につけている写真は、温度計の目盛りがよく見えるように写真で押さえましょう。ゆるすぎる卵ができた場合には、さらに時間を延ばして作ってみるなどの工夫をするのもおすすめです。
【5】白身と黄身の逆転ゆで卵の実験
普通、卵と言えば外側が白、中身が黄色が基本ですよね。それが逆転したら?! 新しい発想の実験にみんなクギづけになるはず。
用意するもの
・テープ
・ストッキング
実験の考察
事前に卵に細工をしておくのか、それともゆで上がった卵に何かをするのか…想定がしにくいですよね。まずは実験をしてみることにしましょう。
実験方法
手順①
卵が割れるのを防ぐため、殻がついたままの卵を、テープで十字になるように巻きます。
手順②
ストッキングなど伸縮性の高い袋状の布に入れて、卵の両端を輪ゴムで留めます。
手順③
手でストッキングの両端を持ったら、ぐるぐると卵を高速回転させます。ある程度回したら、腕を横に引くとグルグルと自動で回りますよ。ブチッと音がするまで回します。
手順④
鍋に熱湯を沸かし、箸などで転がしながら弱火で10分間ほどゆでます。
手順⑤
火を止めて、余熱で5分。その後、氷水で5分冷やします。
殻をむくと、黄身返し卵が完成!
実験のポイント
ポイントは、生の卵を高速回転させると、卵の中の卵黄膜が破れ、黄身が割れます。割れたかどうかは懐中電灯で照らして確認できます。黄身が割れると光を当てても透けないので、卵が暗く見えます。
実験の注意点
ブチっと鳴ってからも回しすぎてしまうと、黄身と白身が完全に混ざった、全部が薄く黄色っぽいゆで卵になってしまうので、しっかり音を聞くようにしましょう。
実験のまとめ方
逆転ゆで卵と言われてもなかなか想像がしにくいもの。先の導入部分で完成形の写真を紹介しましょう。その後、タネあかしをするように、実験の手順をまとめます。最後に、なぜ逆転したかの現象を書いて完成です。
【6】フッ素を使った実験
卵の殻はカルシウムでできているので、人間の歯と同じ構造をしています。そこで興味をそそられるのが、歯と卵の相関性がわかる実験です。
用意するもの
- ・卵
- ・お酢
- ・油性マジック
- ・フッ素入りの歯磨き粉
- ・歯ブラシ
- ・コップ
- ・スプーン
実験の考察
歯にいいとされているフッ素。実際に、歯にどんな変化をもたらすのかを、同じ構造の卵の殻で証明したい。
実験方法
手順①
油性マジックでそれぞれの卵にフッ素を塗る場所がわかるように線を引きます。同時に「フッ素あり」「フッ素なし」と書くと分かりやすいです。
手順②
線を引いたところに合わせて、歯ブラシで卵にフッ素入り歯磨き粉を塗ります。3分間置いて乾燥させてから歯磨き粉を水で洗い流します。
手順③
卵が浸かるくらいのコップに、気泡が出始めるくらいまでお酢を入れます。
手順④
フッ素を塗っていない方は、お酢の酸で殻が溶けていきます。フッ素を塗っている方は酸から守られていて溶けません。
実験のポイント
歯磨きの大切さを子どもにわかりやすく伝えることもできる実験ですね。なるべくフッ素がしっかり入った歯磨き粉を選ぶのがコツですが、いつも子どもが使っているものであれば親近感がわきますよね。
実験のまとめ方
フッ素の実験というよりも、歯にフッ素がいいのはなぜ? という切り口での紹介の方が、子どもは気になるかと思います。それぞれの実験がよくわかるように、時間ごとに溶け方を撮っておきましょう。最後には、なぜフッ素がカルシウムを守るのかの化学反応を、図鑑などで調べてまとめられるといいですね。
【7】スケルトン卵で浸透圧の実験
冒頭でご紹介したスケルトン卵をいくつか作うと、高学年向けの実験を行うこともできます。

用意するもの
・スケルトン卵3個
・水
・しょうゆ
・減塩しょうゆ、
実験の考察
スケルトン卵を作った際に、実際に卵よりも大きくなったが、その後、その大きさを変えることができるのかどうか。
手順①
スケルトン卵を水につけてみます。すると、水よりも卵の中の方が濃度が濃いので、水が卵の膜を超えて卵の中へと流れ込み、卵はどんどん大きくなります。
手順②
もう1つの卵はしょうゆにつけてみます。卵の中の水分よりもしょうゆの方が濃度が濃いので、卵の中の水分が抜けていきます。このため卵は小さくなっていきます。
手順③
水、しょうゆ、減塩しょうゆの3つでスケルトン卵を1日程度つけておき卵の大きさを比べてみましょう。しょうゆのほかにも、砂糖水や食塩水、ジュースや塩分のあるソースなどでも実験可能です。
実験のポイント
水分は濃度が薄い方から濃い方へ移る性質があります。この水分が移動する力を浸透圧といいます。始める前に卵の重さを測っておいて、卵の重さや大きさがどのように変化したかを記録すると良いでしょう。
実験のまとめ方
簡単にスケルトン卵の作り方を紹介。その後、大きくなった卵を戻すには? さらに大きくするには? という疑問点を書き出します。そこで浸透圧について紹介。実際に実験で試してみます。
【8】塩水で卵を浮かせる実験
「水に卵を入れると沈むのに、塩を入れると浮く?」そんな不思議を親子で楽しみながら確認できる実験です。物の浮き沈みと水の密度の関係を、目で見て実感できます。
用意するもの
・生卵(殻つき)
・水(常温でOK)
・塩(食塩)
・透明なコップや容器(卵が沈む深さのもの)
・スプーンや泡立て器(かき混ぜ用)
・メモ用紙とペン(記録に使う)
・写真を撮るためのスマホやカメラ(ビフォーアフター用)
実験の考察
水に塩を加えると、水の密度が高くなります。そのため卵の重さより塩水の浮力の方が上回り、卵が浮いてくるというしくみです。「水に浮くもの/沈むもの」の違いは、実は水の性質にもよることがわかります。
実験方法
手順①
透明なコップに水を入れ、生卵を静かに入れてみましょう。卵は沈みます。
手順②
卵を一度取り出し、水に塩を少しずつ入れてかき混ぜます。最初は少量からスタート。
手順③
生卵を再び入れて、浮いてくるまで塩の量を調整します。何グラムで浮いたか記録しましょう。
手順④
塩水を濃くするほど卵がどんどん上に浮かんできます。濃度と浮き方の変化を観察しましょう。
実験のポイント
塩の分量によって浮き方が変わるので、メモや写真で記録を残すと自由研究らしくなります。水と塩の割合を変えて何度か試すことで、より興味深い結果になります。塩水は濃度に限界があるため、濃すぎて溶けなくなったときの様子も観察ポイントに。
実験のまとめ方
なぜ水に卵が浮くのか? の理由を、水の密度や浮力の図解とセットでまとめるとわかりやすくなります。塩をどのくらい入れたら卵が浮いたかの比較表などをつくると、説得力もアップ。最後に「普段の生活で同じ原理が使われているものは?」など調べてまとめるのもおすすめです。
【9】卵焼きの実験
「ふわふわ? しっとり? 焼き方や材料でどう変わる?」卵焼きは身近な料理ですが、加熱方法や混ぜ方、材料を少し変えるだけで驚くほど食感が変わります。今回は数パターンの卵焼きを作り比べながら、食感や見た目の違いを観察してみましょう。おいしく楽しく学べる、食育にもつながる実験です。
用意するもの
・卵(3~4個)
・牛乳/だし/砂糖/塩などの調味料
・フライパン(できれば四角い卵焼き用)
・菜箸/ヘラ/ボウル
・計量スプーン
・計量カップ
・記録用ノート/ペン
・カメラ(工程や完成品の記録用)
実験の考察
卵は熱を加えると固まる性質があり、混ぜ方や加える水分の量、焼く温度によって固まり方や空気の入り方が変化します。これが「ふわふわ」や「しっとり」などの食感の違いにつながります。科学的には、タンパク質の変性や水分量・空気の含有が関係しています。
実験方法
手順①
卵焼きの条件を3つに分けて用意する。
例・何も加えない卵だけ(基本型) ・牛乳を加えて焼く(ふわふわ型) ・だし+砂糖を加えて焼く(甘くてしっとり型)
手順②
それぞれの卵液をよくかき混ぜ、同じサイズ・時間で焼きます(弱火でじっくりがおすすめ)。
手順③
焼き上がったら、見た目、厚み、色、食感などを比べます。断面や切り口の写真を撮ると比較しやすくなります。
手順④
試食して、味の違い、柔らかさや弾力などを感じながら記録します。家族の感想を聞いてみるのも楽しいです。
実験のポイント
火加減や材料が同じでも、混ぜ方や焼き方で食感は変わります。違いを感じたポイントを「どうしてそうなるのか?」と考えることで、料理に潜む科学が見えてきます。卵に空気を含ませるとふくらみやすくなります。牛乳は水分と脂質が多いため柔らかく、だしはうま味と水分でしっとり仕上がる傾向があります。
実験のまとめ方
それぞれの卵焼きを比較した表をつくるとわかりやすくなります(条件/見た目/触感/味の評価など)。なぜそうなったのかを調べて、卵の成分や調理化学(タンパク質変性)に関する情報を図鑑やインターネットで調べてみましょう。身近な食材だからこそ、理解が深まるきっかけになりますよ。
卵の実験は手軽で身近なのがいいところ
さまざまな卵の実験を見てきましたが、どれも家にある身近な材料でできるのがポイントですよね。難しいテーマのものも少ないので、小学生が取り組む自由研究にぴったり。ぜひ楽しみながら実験してみてくださいね。
あなたにはこの記事もおすすめ
文/松川麗 構成/HugKum編集部