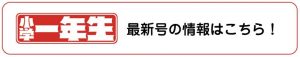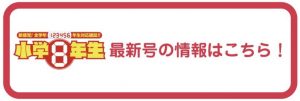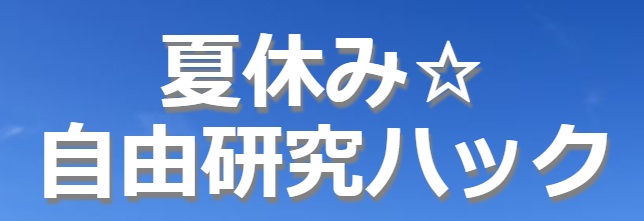※この記事は、小学館の学年誌『小学一年生』『小学8年生』の協力の下、HugKum内特設サイト「夏休み★自由研究ハック」にて配信された記事をもとに再構成しています。
目次
6年生の自由研究テーマの選び方
小学校6年生にとっては、小学校最後の自由研究になるでしょう。そんな6年生の自由研究のテーマはどんな風に選んだらいいでしょうか?

自由研究の目的
そもそも自由研究とはなぜ行われるのか知っておきたいところ。小学校での学びには、子どもが先生から習いながら新しいことを習得していく勉強と、自分で決めた課題を深めていく学びと2種類があります。夏休みのような長期休暇では、自由研究を通して、後者の研究的な学びを行ってほしいという意図があります。
子どもの「好きなこと」から探す
自由研究のテーマを選ぶ方法のひとつが、子どもの好きなことから探す方法。「電車が好き」「サッカーが好き」「昆虫が好き」など、子どもが興味を持っている分野を掘り下げていくと、興味を持って取り組めるようになるはずです。
日常の「ついで」を記録にまとめる
「家族で祖父母の家に遊びに行った」「プールに友だちと出かけた」といったシーンで、そのときの内容を写真やメモで記録して、日記などに残してもいいでしょう。またスーパーに買い物に行ったときに、どんな食材がいくらで売られていたかまとめて分析するといった研究など、日常のなにげないシーンからヒントを得られることもできます。
子どもの「やってみたい!」をきっかけにする
そのほか、子どもが「やってみたい!」と思ったことがあれば、それをきっかけにチャレンジするのも〇。学校から禁止されていなければ、市販の工作キットなどを活用してもいいですし、小さなことでも子どものやる気を大切にするといいでしょう。
実験の自由研究アイデア
理科の実験のように楽しめる、6年生におすすめの自由研究のアイデアをご紹介します。
ろ過実験
活性炭を使って、泥水をろ過する実験です。私たちが普段使っている水がどんな風に処理されているのか、水の大切さを知ることができる自由研究です。
■材料
- ・350mlの空のペットボトル2本
- ・砂
- ・小石
- ・活性炭
- ・カット綿
- ・カッター
- ・ビニールテープ
- ・ガーゼ
- ・輪ゴム
- ・泥水
■作り方
①ペットボトルは、1個は上部を、もう1個は下部をカッターで切りとります。切り口は危なくないように、テープで保護します。
②ペットボトルの注ぎ口に、ガーゼをかぶせて輪ゴムでとめます。
③②のペットボトルの中身を、小石→カット綿→活性炭→カット綿→砂の順で詰めます。活性炭は小石の1.5倍くらいにします。
④③を受け皿となるペットボトルに重ねます。
⑤④の上から泥水を流します。出てくる水の様子を観察しましょう。
色水づくり
ムラサキキャベツの色水に、酢や石けん水などの身近なアイテムを加えて、どんな風に色水が変わるか観察して楽しむテーマです。
■材料
・ムラサキキャベツ
・鍋
・透明なコップ6個
・酢
・サイダー
・石けん水
・重曹
・塩
■作り方
①鍋に水と数枚ちぎったムラサキキャベツを入れてゆでます。
②①を冷まして、6個のコップに均等に入れます。
③5個のコップに、それぞれ酢・サイダー・石けん水・重曹・塩を入れます。何も入れないコップの色と、入れたものでどんな変化があるか観察します。
『小学8年生』2019年8・9月号
実験指導/山田ふしぎ 構成/桧貝卓哉 撮影/岡本好明 モデル/岡村圭将 デザイン/堀中亜理+ベイブリッジ・スタジオ
ペットボトルで野菜の栽培

ペットボトルで野菜を栽培することができます。お料理に使った野菜の根っこの部分を育ててみましょう。
■材料
・小松菜や豆苗など根つきの野菜
・ペットボトル
■作り方
①ペットボトルをカットします。
②小松菜や豆苗を、水を入れたペットボトルに挿します。水の量は、小松菜の根をカットした面に触れるくらいにします。豆苗の場合はお豆に触れない程度の高さまで水を入れましょう。
工作の自由研究アイデア
物づくりが好きな子や、手が器用な子には、工作の自由研究もいいですね。
スライム砂時計

スライムでできた砂時計です。スライムも手づくりできますよ。
■材料
・ホウ砂(薬局で売っています)20g
・水 200cc
・液体洗濯のり(PVAと表示されているもの) 100cc
*PVAとは、ポリビニルアルコールのこと。化学のりと表示されているものもあります。
・お湯(50~60℃くらい) 100cc
・食紅(あれば) 少々
・ペットボトル 2個
・ボウル
・割り箸
・じょうご
・ビニールテープ
■作り方
①ペットボトルに水とホウ砂を入れ、ふたをしてよく振ります。下に溶け残りがたまり、上澄み部分が飽和水溶液です。
②ボウルにお湯と液体洗濯のりを入れて、割り箸で混ぜます。よく混ざったら食紅少々を入れて(食紅を水少々に溶かしてから入れてもOK)、ダマがなくなるまでよく混ぜます。
③②に、①のホウ砂飽和水溶液20ccを入れて、素早く割り箸で混ぜたら、スライムの完成です。
④③のスライムに、少しの水を加えて、割り箸でよく混ぜます。
⑤ペットボトル1個に、じょうごを使って④を流し入れます。
⑥もう1個のペットボトルと⑤の口どうしを合わせて、ビニールテープをしっかり巻いたら、完成です。
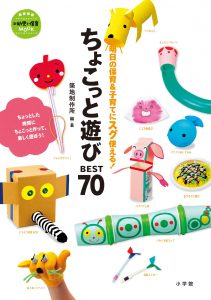
築地制作所
造形作家(佐々木伸、立花愛子、とりごえ こうじ)と、フリーの編集者(青木智子、神崎典子、木村里恵子)による制作ユニット。「造形と子どもの遊び」をテーマに書籍、雑誌、イベント、テレビなど媒体を問わず活動を展開中。著書に『5回で折れる! 遊べる折り紙』(PHP研究所)などがある。
ガリレオ温度計
温度の異なる4個のガラスビンを作る「ガリレオ温度計」。中に入っている水の温度によって、ビンの浮き方がどう変わるか、自分の目で確かめることができます。
■材料
・ペットボトル(1.5リットル、丸いもの)
・小さなガラスビン4個(ふたがしっかり閉まるもの)
・ビーズ
・大きめのボウル(バケツでも可)
・温度計
・水
・お湯
・氷
■作り方
①ボウルに水を入れ、温度をはかります。
②ガラスビン1個に、ビーズを半分くらい入れ、ふたを閉めます。
③①に②を入れ、ボウルの真ん中より少し上くらいに浮かぶよう、②のビーズの量を調整します。
④ボウルの水を少し捨てて、氷を加え水の温度を①より3度くらい低くします。別のガラスビンで②と③の作業を繰り返します。
⑤ボウルにお湯を入れ、①より3度くらい高い温度にします。ガラスビン3個目で同じ作業を繰り返します。
⑥ボウルにさらにお湯を加えて、温度を①より6度くらい高くします。ガラスビン4個目で同じ作業を繰り返します。
⑦最後にペットボトルに水を入れ、そこに4個のガラスビンを入れます。中の温度が異なる、4個のガラスビンの浮かび方の変化を観察します。
プラネタリウム

自宅をプラネタリウムにできる工作のアイデア。ライトをつければ、暗くした部屋に星空が光ります。
■材料
深型のアルミ皿 1個
LEDライト(100円ショップなどで購入できます) 1個
油性マジック
画鋲やきりなど、穴をあける道具
■作り方
①深型のアルミ皿は、外側を油性マジックで黒く塗り、しっかり乾かします。
②画鋲やきりなどを使って、①に穴を開けます。底の部分や側面にも、大小の大きさの異なる穴を開けましょう。
③LEDライトに、②をかぶせてできあがり。
観察の自由研究アイデア
モノや生物などが変化する様子をじっくり観察する自由研究は、こちらです。
表面張力の実験

コップの水があふれそうになっても、あふれないのは「表面張力」が働いているから。この様子をじっくり観察するテーマです。
■材料
- ・グラス
- ・ビー玉
- ・水
■作り方
①グラスにぎりぎりまで水を入れます。
②①のグラスにビー玉を一個ずつ入れ、水が盛り上がっていく様子を観察します。
③②の様子を横から写真に撮って観察します。
④水がこぼれるまでこれを繰り返し、ビー玉をいくつ入れられたか記録をつけます。
ペットボトルでマヨネーズ作り

水分と油分は分離するものですが、マヨネーズ作りでは卵黄をプラスすることで乳化剤の役割となってうまくまとまります。その様子を、マヨネーズ作りの体験を通して観察しましょう。
■材料
- ・油(キャノーラ油など) 150cc
・酢 大さじ1
・卵黄 1個
・塩 小さじ1/4 - ・ペットボトル(炭酸飲料用)
- ・じょうご
■作り方
①じょうごを使って、くずした卵黄をペットボトルにれ、酢と塩を加えます。
②ふたをしめたら、3分ほど振って混ぜます。
③150ccの油を5回に分けて入れます。油を加えるたびにペットボトルをよく振って混ぜます。
④5回目の油を入れて振ったらマヨネーズのできあがり。
甘いトマトの見分け方

プチトマトの甘さを調べる実験です。
■材料
プチトマト
砂糖
水
ペットボトル(1Lのもの)
カッター
■作り方
【1】ペットボトルのラベルを取り、上部をカッターでカットする。
【2】【1】のペットボトルに水をいっぱい入れ、プチトマトを加える。砂糖を少しずつ入れて混ぜ、トマトの浮き具合を観察する。
調べ物の自由研究アイデア
夏休みのように時間がたっぷりあるときは、じっくりとひとつのことを調べるのに最適。ぜひ子どもが興味を持つテーマを見つけてみましょう。
世界の主食調べ
日本ではお米が主食ですが、国により違うもの。そんな世界の主食について調べ、気候や地域、文化などの背景についても掘り下げてみるといいでしょう。
■材料
・ノート
・図鑑 など
■作り方
①世界各地で食べられている主食を調べます。
②なぜそれが主食になったのか、図鑑や本などで調べます。
③気候や生活習慣などの背景を分析します。
④世界地図に調べた内容を書き込みまとめます。
空気の汚れを調べる
場所によって空気の汚れ具合がどのくらい違うのか、両面テープを貼って調べる内容です。
■材料
・両面テープ
■作り方
①空気がきれいな場所(公園、木が多い場所など)と、汚いと思われる場所、さらに自宅などの場所を決めます。
②①で選んだ場所に両面テープを貼ります。低い位置だと土ぼこりがつきやすいため、高さ1m以上の場所に貼りましょう。両面テープの外側のテープもはがします。
③ 1週間程度、そのままにします。
④両面テープをはがし、ついた汚れを比べてみます。
⑤それぞれの違いをノートなどにまとめます。
都道府県境調べ
47都道府県の県堺はどんな風になっているのか、調べてみるテーマです。地図をじっくり見て観察する力や創造力が育まれそうです。
■材料
・日本地図
■作り方
①日本地図で都道府県境を調べます。
②山の上、川など、県境がどこにあることが多いか、どんな特徴があるか調べていき、ノートなどにまとめます。
読書感想文のテーマ
自由研究で定番の読書感想文。6年生ならこんなテーマの本を選んでみてはいかがでしょう?
ふしぎ駄菓子屋 銭天堂(偕成社)
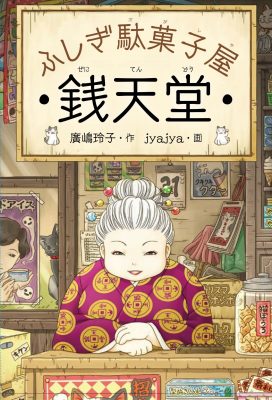
願い事を持った幸運な人だけがたどりつけるという、女主人紅子が営むふしぎな駄菓子屋さんのお話。「小学生がえらぶ!こどもの本総選挙」9位にランクインした人気の1冊です。
宿題ひきうけ株式会社新版
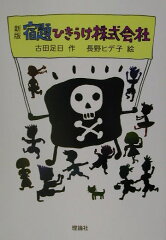
お金をもらってかわりに宿題をやってあげる“宿題ひきうけ株式会社”ができたという物語。なぜ勉強するのか、なぜ学校に行くのか、子どもなりに考えるきっかけになると評判の本です。
小説 名探偵コナン
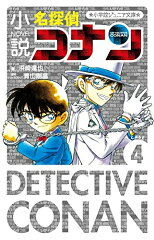
アニメでおなじみの名探偵コナンの小説版。アニメや映画で親しんでいる題材だけに、本が苦手な子どもでも読み進めやすい本です。アニメよりも細かい描写を追うことで、子どもの創造力が膨らんでいくはずです。
1日でできる自由研究アイデア
取り掛かってその日のうちに完成する、時短の自由研究を紹介します。
三色の焼きそば作り

紫キャベツの赤色はアントシアニンというリトマス試験紙に含まれる物質と同じです。そのため麺に含まれるかん水のアルカリ性にアントシアニンが反応、緑色に変わります。実験の後は、おいしくいただけるのもいいですね。
■材料
・焼きそばの麺
・紫キャベツ
・塩コショウ
・ソース
・カレー粉
■作り方
①紫キャベツを焼きそばの具に使い、刻んで麺と一緒に炒めます。すると不思議なことに、黄色かった麺の色がみるみる緑色に。
②次に新しい麺を紫キャベツとカレー粉と一緒に炒めましょう。今度は麺の色が赤く変わります。カレー粉の酸性にアントシアニンが反応したことがわかります。
③写真をとり、記録をして自由研究を仕上げましょう。
海の生物の研究

干潮時の水位が下がったときに現れる岩場は、潮が引く際に凹部に水がたまり、「タイドプール」と呼ばれる潮だまりができます。その時間を調べてから行くのがおすすめです。
■材料
・カメラ
・ノート
・筆記用具
・小さな水槽
・虫眼鏡(観察用)
■作り方
①海に行き、生き物を探して観察します。
②写真をとり、しばらく観察して気づいたことを記録します。観察が終わったらもといた場所にそっと放しましょう。
③帰宅してから、写真を貼ったりスケッチしたりしてまとめます。記憶が新しいその日のうちにするのがおすすめです。

高学年女子に人気の自由研究アイデア
ここでは高学年の女子に人気の自由研究アイデアを紹介します。
白い花をカラフルに

白いカーネーションを使って、食紅などで色をつける実験です。茎の導管を通って、花びらに色素が届いて色が変わる様子を自分の目で確認できるテーマです。
■材料
- ・白いカーネーションやバラ、菊など
- ・食紅2色以上
- ・コップ2個
- ・割り箸
■作り方
①コップに食紅を濃いめに溶かします。色の違うコップを2個用意します。
②花の茎を2本に割いて、1本ずつコップに入れます。
③割り箸で花を挟むように固定して、倒れないようにします。
④しばらくしてから、花の色がどう変化したか
リボンで作るミニバッグ

リボンを交互に通すだけで、おしゃれなバッグが完成! お好みの色のリボンを用意して、とっておきの1個を作ってみてくださいね。手芸感覚なので、制作過程も楽しめます。
■材料
・お菓子の空き箱
・リボン
・フエルト
・カッター
・はさみ
・接着剤
■作り方
①バッグの土台となるお菓子の箱を用意し、側面にリボンを巻きます。端だけ接着剤を付け、内側に折って貼ります。
②底面のリボンにも、交互にリボンを通していきます。端は内側に折って、箱に接着します。
③縦のリボンに1本おきに裏側へくぐらせ、横の段のリボンを通します。端は、他のリボンの下に差し、接着剤でとめます。
④③と互い違いになるように、次の段のリボンも横から通して、これを繰り返します。
⑤箱のサイズに合わせて、フェルトでふたを作ります。バッグの前になる部分に切りこみを入れて、リボンを交互に差しこみ、端は折り返して接着剤でとめます。
⑥⑤のふたの端3㎝を箱の背面に貼り、肩かけ用のリボンを付けたら、できあがり。
『小学8年生』2019年8-9月号
石けんをレンジでチンする

石けんをレンジでチンすると、膨らんでいきます。その様子と変化をじっくり観察するテーマです。
■材料
- ・固形石けん(小さめにカットしておく)
- ・電子レンジ
- ・耐熱皿
■作り方
①耐熱皿に小さく切った固形石けんを置きます。
②電子レンジに入れて加熱します。
③数十秒ごとに区切りながら、熱で石けんが膨らむ様子を観察します。
※電子レンジの取り扱いに気を付けてください
6年生の知識・経験をさらに大きく
小学校6年生になると、学校で学んだ知識やさまざまな経験を通して、ものごとを探究したり調べたりする力が育っているでしょう。夏休みの自由研究では、ぜひそれらの力を伸ばせるテーマを選んでみてはいかがですか?
<協力誌>
1925年創刊の児童学習雑誌『小学一年生』。コンセプトは「未来をつくる“好き”を育む」。毎号、各界の第一線で活躍する有識者・クリエイターとともに、子どもたち各々が自身の無限の可能性を伸ばす誌面作りを心掛けています。時代に即した上質な知育学習記事・付録を掲載し、HugKumの監修もつとめています。
『小学8年生』は上のような自由研究アイデアのほか、すべての小学生の好奇心と創造性を伸ばす付録・学習コンテンツ・読み物が満載の新しい学習雑誌です。
夏休みの自由研究
↓↓テーマ探しなら…ここをクリック↓↓
文・構成/HugKum編集部