目次
算数の問題の種類に合わせて関わり方を変える
算数の問題には、計算や図形、単位や割合、比や速さなど様々な問題があります。この記事では「問題の種類」を、計算ドリルにあるような「基本的な問題を繰り返し解くことで身につく」訓練的な要素の問題と、パズルや文章題といった「試行錯誤をしてじっくり解くことで身につく」思考系の問題の二つに分けて考えたいと思います。大迫ちあき先生は「この2種類の問題には決定的な関わり方の違いがある」と話します。

関わり方の違いとなるキーワードは「時間」
単純な訓練のような算数の問題と、思考力を働かせる問題の関わり方の決定的な違いとなるキーワードは『時間』だそう。「単純な訓練のような算数の問題は時間を区切り、思考力を働かせる問題は時間を決めずに好きなだけ取り組む。これに尽きます」と大迫先生は言います。
基礎知識問題は「時間」を区切ってゲームのように解く!
単純な訓練のような算数の問題は筋トレのようなものなので時間を決めて毎日やる。ただし長い時間はやりません。楽しさの演出として『間違い直し含めて今日は〇分でできたね』『昨日より早くできたね』『競争しようか』と、ゲームようにやれるといいですね。基本問題は受験をする・しないにかかわらず短い時間で集中することが大事になります
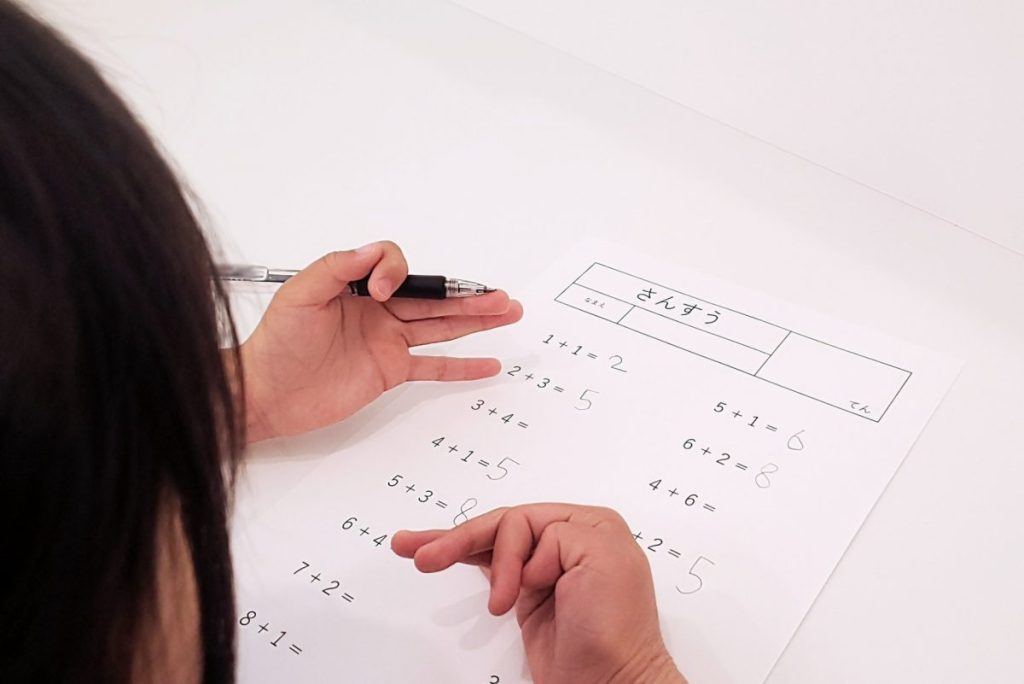
【おすすめの基礎学習の進め方①】
算数ドリルなど、学力の下支えとなる基礎学習は脳の筋トレのようなもの。
時間を決めて進め、間違い直しで確認できるところまでをスピーディに。
親子で競争するなどゲーム性があると楽しめます。
訓練のような単純な問題は時間をかけすぎると「飽きてイヤになる」と大迫先生。小学校の宿題によく出る算数ドリルはほぼこの基礎問題にあたります。短い時間に集中して正答率を上げることが目的なので、間違い直しも時間に含めることも大事なポイントです。

【おすすめの基礎学習の進め方②】
「やり始めから見直しまで、今日は何分でできるかな」「お母さんも一緒に同じ問題解くよ!」など、基礎学習のゲームは工夫のしどころ。
子どもが勝つよう仕向けてあげましょう!
思考系の問題はとことん考えさせて、考え方を整理できそうなヒントを出す
一方、思考力を働かせる問題を「好きなだけ時間をかけて解く」場合、子どもに任せて放っておくということではないようです。そのコツについて大迫先生は「思考問題は『考え方が自分なりに整理できるかどうか』と、『自分で解けた達成感を感じられるかどうか』が関わり方のカギ」と話します。
思考系の問題にはパズルのような図形問題や文章題などがあります。このときに子どもが頭の中で行っているのが『試行錯誤』や『トライ&エラー』。好きなだけじっくり考えさせて、もしわからない場合は、『どこまで考えが進んでいるのか』を見てあげてほしいのです

【おすすめの思考系学習の進め方】
思考を使う問題は「考えている最中はじっくり時間を与えて」「考えが煮詰まっている場合は次の思考に進めるようなヒントを」が基本。
自分で考えを進めて解いて、解けたときの達成感を大切に。
じっくり考えているときは子どもに集中させて、わからなそうなら程よいところで声をかける――タイミングを合わせるのは難しい気がしますが、そこは子どもの様子を見ている親自身が判断することになります。「果たして自分はうまくかかわれるのだろうか」と心配になる方もいるかもしれません。
正しい関わり方だけに気を取られるより、失敗する姿を見せよう
「間違った声かけや関わり方をすると子どもに悪い」「正解だけを知って、そのまま子どもに伝えたい」ということは親ならだれでも思うもの。そう思う背景には親が受けてきた教育と今の子どもが受けている教育の違いや、「失敗してはいけない」「よその子どもと比べてうちの子はどうなのか」といった心配があるからです。

「なるべく正しい方法で関わりたい」「間違った関わり方をしたくない」と思われるかもしれませんが、実は親が失敗したり試行錯誤をしたりする姿を子どもに見せてあげることも大切です。思考問題は試して失敗して、また挑戦しながら最後に自分で解けた達成感を得るまでがセットなんです。なんとかなるという気持ちがあれば、あれこれ試すことができますし、問題にぶつかっていく力を持つことができます。失敗をしていい空気を作るために親の失敗をする姿を見せたほうがいいですね
子どもをよく観察して「間違ってもいいからここだと思うタイミングで声をかけてみるうちに、ちょうどいいタイミングが分かるようになる」そう信じてやってみるとよさそうです。

【子どもを責めたり、答えを横取りしたりするのはやめて】
パズル、文章題問題などはとことん時間をかけて考えることで思考力がはぐくまれます。
「まだできてないの?」「こうやったらできるでしょ」といった責めたり答えを横取りしたりするのはNG
思考が進む関わり方に必要な「問いの技術」
「どこまで考えているのか」を探る声かけとは
では、思考問題を前にどこまで考えが進んでるかを探るとき、具体的にはにどんな声かけをするといいのでしょう。例えば以下のようなものがあります。
「もしかして今考えが止まってる?」
「どこまで考えが進んだの?」
「ここの式は合ってるね。こっちの情報を使って考えたらどうだろう」など
次の手段がひらめく「選択」の問いかけ
次に、「ここら辺までは進んでいるんだ」と分かったら思考の整理できるようなヒントを与えてみましょう。
例えば『次はこれとこっちとどっちの情報を使うと思う?』『次は何の式を使えばいいかな。足し算とかけ算、どっちだと思う?』など選択制にすると子どもは考えやすいようです。5W1H(なぜ、なに、だれが、どこで、いつ、どのように)を使って聞いてみるのもおすすめですし、そもそも問題の意味が分かっているかどうかを確認するために一緒に問題文を読むとどこで思考が止まっているのかも見えてきます。重要なのは考えの道筋を子ども自身が見つけるようにヒントを出すことと、『自分で解けた!』という成功体験や達成感を子ども自身が味わうことの二つですね
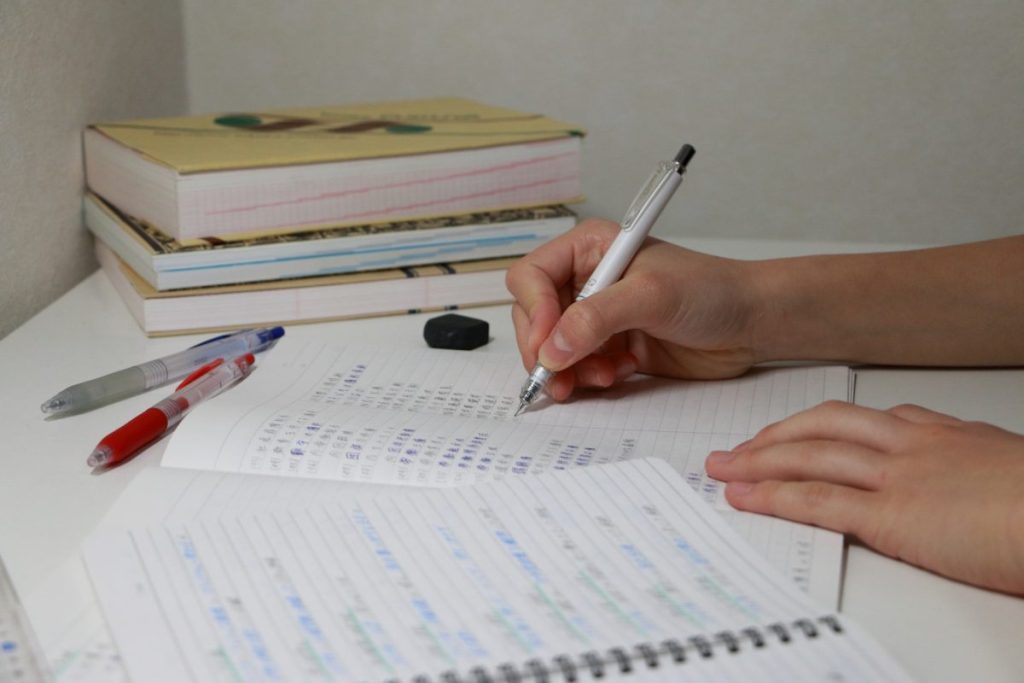
学年が上がると複雑になり、様々な知識を使うことが増えてきます。次の手立てとなるヒントが分からないときは一緒に問題文を読んだり与えられている条件を確認してみるといいですね。
自分で考えた達成感を味わえるとベスト
考えの手立てを自分が見つけられるようなサポートや、達成感を味わうときは一緒に喜ぶことを繰り返すと、思考問題を頑張って解くことが気持ちいいし、楽しいものとして子どもの心に刻まれます。
子どもの様子をよく見て観察眼を磨こう
「考えてやりなさい」と言われたところで、子どもはどう考えたらいいのかわかりません。間違っているところを指摘したり責めたりすると考えることも嫌になってしまいます。
大迫先生はこう強調します。
考える道筋を示しながら、子どもが自分で道筋を作れるようになって、結果的に自分で解けた喜びを味わうことができれば、算数を解くときの楽しさや自己肯定感が育つし、勉強に対して前向きな気持ちになれる。この循環を今一度考えながら、子どもの観察を続けてほしいと思います

子どもの様子を観察してみて!
解けたときのうれしそうな表情や、わからなくて悩んでいるときのつぶやきなど、キャッチしようと思えば自然と目に留まるようになります。問題のタイプやお子さんの様子を観察しながら、親御さんが適切だと思う声かけをトライしてみてくださいね!
算数力が伸びる声かけ術はこちらをチェック

文・構成/HugKum編集部
記事監修






