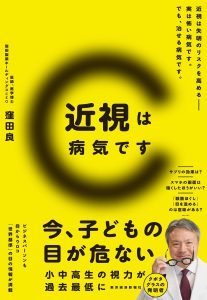目次
近年近視の子どもは増え続けている
現在、「小学6年生の2人に1人が近視」の時代と言われています。文科省による調査の結果、裸眼で視力が1.0に満たない小学生は37.8%、中学生は61.2%、高校生になるとさらに増えて71.6%もいて、近年近視の子どもは増え続けているのだそう。
とは言え「ゲームやタブレットをやめさせるのは難しい」「親が近視だから、子どもが近視になるのも仕方がない」と、あきらめているママやパパも多いのではないでしょうか。
しかし、近視は抑制できるということを眼科医の窪田 良先生はご著書『近視は病気です』で書かれています。そして近視は特別難しいことをしなくても抑制できるんだそう。私たちが思い込んでいた情報を一新する近視の最新事情は必見です。
近視が進行するとなにが問題なの?
世界的に見ても急増している近視。日本では屈折異常として、身体的特徴のひとつとしてとらえられていますが、米国科学技術医学アカデミーが、

軽い近視であれば近くが見やすい目であるので、現代人のライフスタイルに合った環境適用とも言えますが、実は近視の影響で、失明につながる眼疾患のリスクが高まることもわかってきました。よって、たかが近視と思わず、予防治療としたほうがいいというのが主たる考えです。
窪田先生に質問!「近視は我が子に遺伝する?」に驚きの回答が!
ここからは窪田先生が昨今の近視事情についてQ&A形式で答えました。
Q.母親の私も、父親の夫も近視。近視は我が子に遺伝しますか?
A:×
窪田先生:実は必ずしも遺伝するとは言えず、環境要因が大きいとされています。
遺伝的要素も見つかっているので、間違いなくあるんですが、それはあくまでなりやすい目、なりにくい目ということ。きちんとした環境においてあげれば、なりやすい目であっても抑制することができると、最近わかってきています。
そして抑制のためには外遊びが非常に効果があると言われています。外で太陽を浴びて遠くを見ることで、発症を抑えられたり、進行を送らせることができるのです。

その理由は、太陽の光が目に入ることで網膜にドーパミン産生をうながし、近視抑制が働くとされるため。太陽光は窓ガラスなどのフィルターを通してしまうと、波長が変化してしまい近視抑制の効果が失われます。屋外で太陽光を浴びましょう。
知り合いの眼科医は、子どもがゲームをやるときは屋内でなく、ベランダに出てやらせるようにしているそうです。
Q.眼を悪くしないために遠くを見なさい!というのはほんと?
A:〇
窪田先生:人間の目は本来、遠くを見るようにできています。近視発症の環境要因は
- 近目作業の連続(手元にピントが合って眼軸長が伸びる)
- 屋外活動の減少(太陽光を浴びていない)
とされています。
屋外に出ることで太陽光を浴びられて、自然に遠くを見るので近視抑制ができるのです。それ以外の時間をどんなに室内で過ごそうが“1日2時間、外で遠くを見るだけ”で、室内にいた十数時間分の目への悪影響を打ち消してもらえるのです。
アフリカには視力がいい方が多く、近視も10%以下しかいません。それは、このような環境で子どもの頃から生活しているためなのです。
Q.国を挙げて近視抑制に取り組み、実際に成果を出した国(地域)がある。
A:〇
窪田先生:台湾、香港、シンガポール、中国では2010年代から取り組んでいます。台湾では、
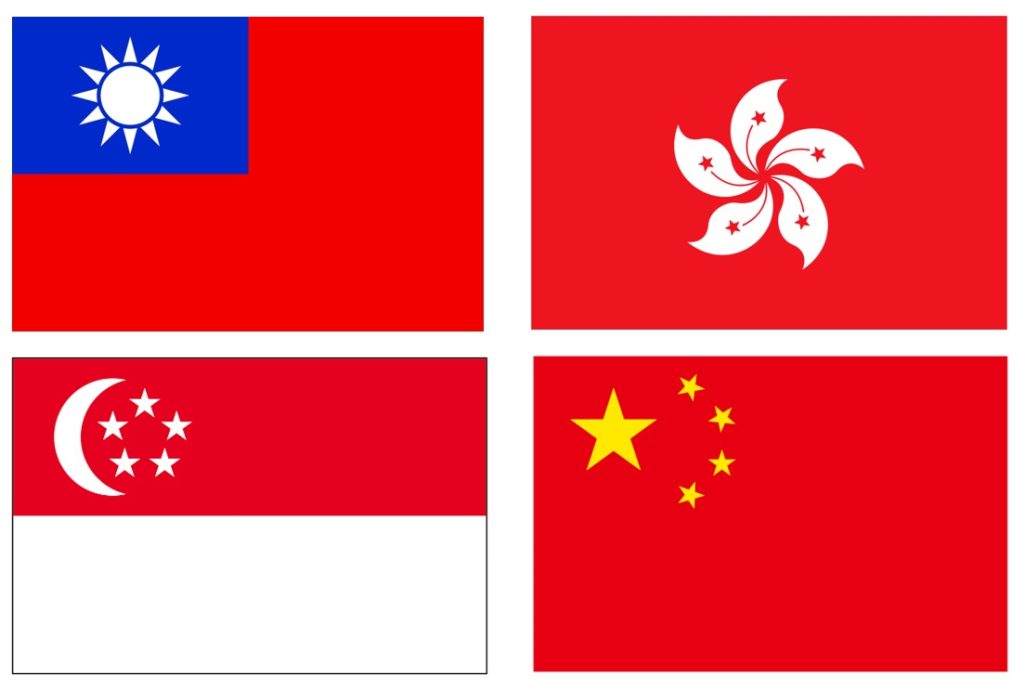
Q.一度低下してしまった視力の回復は難しい?
A:〇
窪田先生:今のところは、一度伸びてしまった目の奥行の長さ(眼軸長)は、元に戻すことが難しいので予防がとても重要です。現在、近視抑制眼鏡の研究・開発に取り組んでいるところです。
スマホやタブレットの普及によって近視が増えているわけではない!
ここまでの窪田先生からの答えを受けて、高濱正伸先生(はなまる学習会代表)が気になることをどんどん質問します。
高濱先生:遠くを見るのは星をずっと見るのでもいいんですか?
窪田先生:一般的には日中それなりの強度の光のもと、外で遠くを見ることが重要で、網膜全体に像が写っているのがいいとされています。
高濱先生:男の子たちがよく公園でゲームをしているのを見ますが、家でやるよりはいいんですか?
窪田先生:そうですね。室内よりはいいと思います。
高濱先生:そう考えると、長野県で育った人と新宿区で育った人では視力の差はあるんですか?
窪田先生:それはそうですね。日本の地域差ではあまり言われませんが、中国では農村部と都市部では圧倒的に違いが出ます。どれくらい外で過ごすかによって違います。
高濱先生:では登校も電車に乗って、ずっと室内にいるような都会の子どもほど意識的に外に出たほうがいいですね。
窪田先生:猛暑の夏は大変ですが、日陰でも十分効果がありますので、日陰にいて遠くを見るようにするといいと思います。よく暗い中で本を読んじゃダメですよとか、近くでテレビを見ちゃダメですよって言うと思いますが、実は外で遠くを見ることを促すほうがはるかに効果があります。
そもそも暗いところで本を読むことや近くでテレビを見ることが近視進行に影響するというのは、まったくエビデンスがないんです。
高濱先生:例えばサッカー部に入って、外で運動しているのも意味がありますか?
窪田先生:ものすごく意味がありますね。欧米諸国では屋外スポーツが盛んなので、東南アジア諸国ほど近視が多くないと言われていますね。

高濱先生:スマホやゲームは影響しないんでしょうか?
窪田先生:そうですね。スマホやタブレットの普及によって近視が増えているとは言われていません。室内で漫画を読もうが本を読もうが、ぼーっとしていようが、室内にいること自体がダメなことなのです。
高濱先生:そうなると国として、近視対策に取り組むことははっきりしているように思いますね。
窪田先生:対策は年齢が小さければ小さいほど効果があります。小学校・中学校までに目の対策をきちっとしてあげれば、いい目を作ることができると考えます。
視聴者からの質問への回答も役立つ情報がずらり
今回の対談をオンラインで視聴した視聴者や、事前に寄せられた質問にも回答してくださいました。
Q.電車や車などの車内で本を読んだりPCを見るのは、揺れがあるのでよくないと判断しているのですが、光を意識するほうが大切ですか?
窪田先生:揺れがよくないと言われているわけではないです。それよりも外に出て、光を意識するほうがいいと思いますね。
Q.スマホやゲームを外でやると反射が目に悪いのではないかと思いますが。影響はありますか?
窪田先生:見づらいという意味では疲れはあると思いますが、お子さんは疲れを感じたりしないこともありますし、近視予防の観点からすると外でやることはメリットのほうが大きいです。
Q.夕方の太陽の光でも効果がありますか?
窪田先生:太陽が沈む前でしたら効果があります。研究レベルでは30代くらいまでの方に近視抑制の効果があると言われています。
Q.1日2時間というのは継続して2時間でしょうか?トータルで2時間でしょうか。
窪田先生:今のところ、最低15分刻みでトータル2時間でも意味があると言われています。ある日1時間だったら翌日3時間、あるいは週末にハイキングなどで5、6時間、外で過ごしても十分効果があると言われています。
Q.LEDライトが目に悪いと聞いたことがありますが本当でしょうか。
窪田先生:目に悪いというのは言われていません。
Q.眼がどのように成長していくのか教えてください。
窪田先生:基本的に生まれたときは遠視で、成長過程を通じて正視になり、ちょうどいいところで止まらない場合、近視になるというのが流れです。近視になってしまうとブレーキが効かず、どんどん悪化してしまう方もいて、なるべく近視の発症を遅らせることが大切です。
また歳を重ねると遠近調節をするレンズである水晶体が少しずつ硬くなり、動かなくなってしまうと老眼。硬くなるだけでなくにごってしまうのが白内障です。例えるなら卵の白身をゆでる際、少しずつ硬くなって最後に白くなるのをイメージするとわかりやすいかと思います。
近視が強ければ強いほど、この水晶体の硬化や白濁化がはやく進むと言われているので、近視を抑制していくのは重要です。
Q.夏に外に長時間いる場合、サングラスはつけたほうがいいでしょうか?
窪田先生:子どもの成長の過程においてはサングラスはつけないほうがいいです。あらゆる波長の光が目に入るほうがいいので、せっかく外にいるのですからサングラスをかける必要はありません。スキー場など極端に紫外線が強い状況のときはつけるのがいいと思います。
Q.子どもが眼鏡をかけたがらないのですが、どのような声掛けが効果的ですか?
窪田先生:眼鏡をかけることがどれだけ重要か、論理的に説明してあげること。説得力のある専門の先生に直接伝えていただくのもいいと思います。
小さいお子さんだったら、「眼鏡が似合ってるね、素敵だね」と褒めて抵抗を減らしてあげるのも重要かなと思います。
Q.眼鏡は常につけるべきですか? 眼鏡がなくても見えるときは外すべきですか?
窪田先生:眼鏡をずっとかけている状態のほうが、度の弱い眼鏡をかけたりするよりも近視の進行を抑制することが報告されています。適正矯正の眼鏡をずっとかけていることが一番いいと考えられています。
近くを見る際は眼鏡をかけつつも、ときには目を休めるがいいと思います。

Q.レーシックについてはどうお考えですか?
窪田先生:レーシックが出た当初よりも技術も洗練されて安全になってきています。ただ手術ができる面・できない面がありますし、術後のドライアイなどの合併症の可能性もゼロではないので、リスクとベネフィットをセカンドオピニオンも含めて医師に相談したうえで選択いただけたらと思います。
ただ、レーシックで視力が回復しても、
また、近視抑制薬のアトロピン点眼、オルソケラトロジー治療を子どもに選ぶ際は、目の中に医薬品やレンズを入れることに抵抗がないか、もたらされる一部の副作用が気になるかならないか、使ってみないとわからないこともあるので、まずは近視の専門医に相談されて、どれがお子さんや親御さんに合うのかを決めるのがいいと思います。
自分の知識を過信せず、最新の情報にアップデートを!
今回お話を聞き、今まで「近視は遺伝する」「スマホ、タブレットは視力に悪い」などが思い込みであったと知り、本当に驚きました。こんな風に情報が時代とともに覆されているケースがいくつもあり、最新の情報にアップデートすることが重要だと感じます。
また、先生によると治療方法も進化しており、悩んだら専門医に相談するのもおすすめとのこと。まずは室内で過ごす時間が多い子どもの近視抑制のため、外遊びの時間を増やしてみようと考えさせられた対談でした。
眼科医・窪田良先生
こちらの記事もおすすめ

文・構成/長南真理恵