目次
合奏や合唱が学校の大イベントの日本。個性より「和」を重んじる風潮
――日本では、自分の意見を口に出すより「人に合わせているほうが安心」という人が多い気がします。なぜそうなってしまうのでしょうか。
日本では、空気を読むことが長く大切にされてきたんですね。個人の意見を強く主張すると場の空気が乱れる、誰かを傷つける、だから周囲の人の気持ちを推しはかり、忖度するようになってしまいます。
それに、日本では保育園、幼稚園の頃から運動会で同じ演技に取り組むとか、合奏や合唱が大事なイベントであるとか、「和」を重んじることが多いですよね。海外からは「それこそが日本人の力」と称賛されているのですが、諸刃の剣でもあります。和を大事にするあまりに個性を否定することになったり、自分の意見を言うのが苦手になったり。
特に、学校教育の中でこうした「和」を重んじる機会が多いので、自分を前に出す機会が失われがちなんです。
日本では自分の意見を言わないほうがうまくいく……
――竹内さんご自身は、小さい頃に海外から日本に戻ってきて、自分の意見をはっきり伝えたら周囲から浮いてしまい、人前であまり話せなくなった、という経験をお持ちですね。
幼い頃、父の転勤でニュージーランドに住み、ブリティッシュスクールに通っていました。帰国し、日本の小学校に通い始めて一番ショックだったのは、みんなが発言しないことでした。
「なんで手をあげないんだろう?」と思いながら、自分は何度も何度も手を上げるのですが、何度も上げるから余計に指してもらえず「痛い子」のようになって。日本の学校では「意見を言うことはあまりいいことではないんだ」と子どもながらに悟りました。

私が海外で通っていた学校では、自分の意見を言うことが大事、自己主張することこそが授業に出る児童の務めという感じでしたし、人の意見を「なるほど!」と称え、自分は「こう思うよ」と意見の違いをおもしろがるっていう雰囲気でした。
日本では、短い授業時間の中で正解を出そうとし、最大公約数の意見を一生懸命に探すようになってしまいがち。すると、人と違う意見を言いにくくなるんですよね。今の子たちは、私が子どもの頃よりもっと自分の意見を言わないんじゃないでしょうか。みんなと違う意見を言って、SNSの仲間からハズされたくないでしょう?
でも、自分の思いや意見を言語化したらもっとラクになるんじゃないかなと思うんです。「実は……」と話してみたら「わかる!」となるのではないかなと思うんですよ。
子どもに意見を求めてすぐ返ってこないのはよくあること
――子どもがプレゼンができるようになるには、まず家庭内でしっかりと自分の意見を言えることから始めるといいように思います。どんな会話がいいでしょうか?
何かの話題について「ねえ、どう思う?」「あなたは賛成?」など、質問して働きかけるのは大正解です。
でも、急かさないでください。質問してその場ですぐ意見を返せる子はそんなにたくさんいません。2日後、10日後、何年か後に答えを言うこともありますよ。
うちの末っ子が小学校1年生の頃のことです。私がオンラインで社外の方と打合せをしていたのを脇で聞いていて、そのときは何も言わなかったのですが、3カ月後くらいにようやく言語化して、「ママがミーティングしていた人、なんであんなこと言ったんだろう」って。ですから、質問をしたら待ってあげる姿勢は大事です。

正解を求めない。親の意見は押し付けない
――家族との会話も論理的なほうがいいのでしょうか。
家族ですから、あまり堅苦しくなく、自分が思ったことを言えるほうがいいですよ。親は「こうしなさい」と命令口調だったり、「こうじゃなきゃ」みたいに絶対的な基準になりがちですが、それだと子どもは本心を言いにくく、だんだん言わなくなります。正解を求めないことが大原則です。
まずは子どもの意見をおもしろがる、否定しなくていい。あまりに一般的な基準からずれていたら「そこまでしたらこういう困ることが起きない?」と、笑顔で問いかけると良いです。「それはダメ」じゃなくてね。子どもって多面的に見られないので、不思議なことを言うことが多いですよね。受け取る側がニコニコしていたら「ああ、そうか」と素直に受け取れます。
ただ、子どもでも「端的に言語化する」力は必要です。「お夕飯に何食べたい?」と聞いた時「ええと何にしようかな、今日は給食があれだったから、同じのはいやだな、ええとスパゲッティがいいかな、そうじゃなくて……」となって結論が出ないと、こちらは料理が作れません。その場でパッと言えるようになれるといいですよね。
私はプレゼンの授業で「エレベーターピッチカード」というものを使うことがあります。ビジネスの現場では、エレベーターに乗り合わせた少しの時間など、ちょっとした機会をとらえて言語化して相手に伝えることが大事、と教えられますよね。
そこで、子ども対象のワークショップで、「エレベーターで会いたい人にバッタリ会ったときを想定して、その人や自分が降りる前に言いたいことを伝えなければいけない」という状況をあえてつくるのです。パッと答える練習をするために、カードを渡した子どもにすぐに答えてもらいます。練習するうちに、だんだん早く結論を出せるようになりますよ。
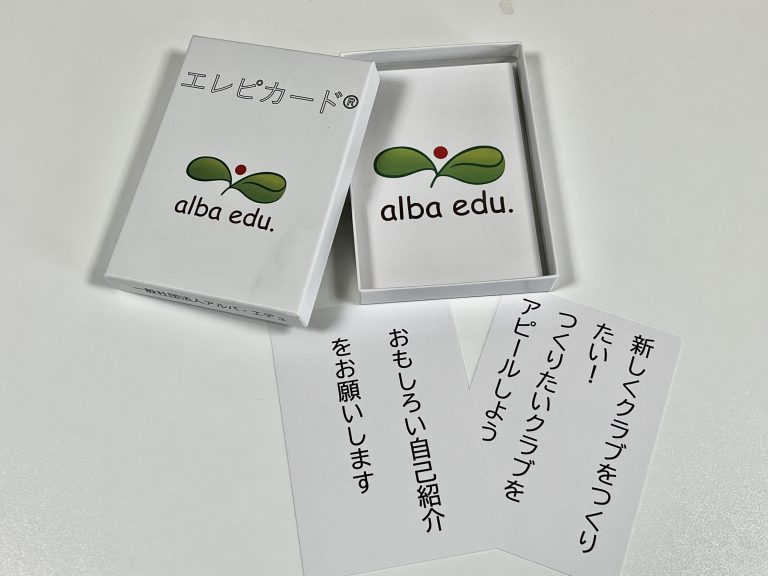
子どもの言葉を聴くとき、親は脳を活性化して対応したい
――親のほうも、きちんと話し、聴いてあげられる自分でいないといけませんね……。
そう、子どもが自分の意見を言える環境を作るには、親のほうも脳を活性化させて、子どもの意見を前向きに「さあ、受け止めますよ! 楽しくリアクションしますよ」という雰囲気を出すことが大事ですよね。
ただ、いつもいつも、親は子どもの言うことにテンションを上げて楽しく聴いてあげる余裕があるかというと、難しい。大人だって疲れているときはあるし、いつも「いい親」であり続けることなんてできない、私もそうです。
毎日やらなくても、おでかけしたときの電車の中とか、お互いの気分のいいときにやってもいいですし。あのとき楽しく話したよね、という記憶が残ればいいなぁと思いますね。

大きな声ではっきり言う。身振り手振りもプレゼンには重要
――保育園や学校で意見を言う場合、自分の意見が相手に伝わり、かつケンカにならないようにする工夫などはありますか?
日本の場合は、ひとりの子だけプレゼン力があると、その子がクラスで「出る杭」になって浮いてしまうことがあります。ですから私は公教育でも私立の学校でも、クラス全員に対してワークショップを行います。するとクラス内の心理的安全性が高まって「何を言っても安心だ」となり、全員のプレゼン力が伸びていきます。
1対1で意見を言うときもみんなの前で言うときも、問いかけの口調や表情、身振りも大事です。同じ意見でも、厳しい顔や無表情で言うより、口角を上げて笑顔で話したほうが伝わりやすいですよね。楽しそうに身振りをしながら言うのもポイントです。まずは大人のほうが子どもに話すときにやってあげるとわかりやすいでしょう。
また、学校でも家庭でも意外と教育されないのが「はっきりと聞こえる声でしゃべること」。特に学校で発表をするときなどはうわずっていたり、声が小さかったり弱かったりすると信憑性が低く聞こえてしまいます。これは、大人も同様です。特に、何か相手にマイナスの効果になることをきちんと意見するときには、しっかりした声を作ることが大事です。詳しくは私の本を参考にしてください。
発声練習
口を「いーっ」と発声するときのように横長に伸びた形にして、しっかり奥歯をかみ合わせたら、歯の間から息を「スーッ、スーッ」と強く吐き出します。これは、喉の奥にある声帯を鍛える動きで、プロサッカー選手も、遠くにいるチームメイトに大きな声で指示を出せるように取り入れているトレーニングです。
「スーッ、スーッ」と息を強く吐き出す 『話す力で未来をつくる ~プレゼンアドバイザーが伝える 子どもの思考力 判断力 表現力を伸ばすチャレンジ~ 』より引用
また、音楽と一緒で、序奏があって盛り上がりがあって、クライマックスがあって終了がある、のような話し方ができるといいですね。子どもの言葉は短いですから、「もう少しながーくゆっくりお話してみて」「しゃべるときも文章になるかなって意識するといいよ」みたいに言ってあげるといいんじゃないでしょうか。
常識の枠を超えた子どもの発想力とプレゼン力を称えよう!
――竹内さんがこれまで聴いてきたお子さんたちの意見で、「これはイイ!」と記憶に残るものはありますか?
私は、常識の枠を超えた意見が好きなんです。枠にとらわれないで自分の発想を豊かに表現するものが印象に残ります。
以前プレゼン大会の審査員をしたとき、私がすごいと思ったのが「課金のゲームがどれだけよくないか」をテーマにした小学校6年生のプレゼン。お金の大切さを実感するために「ブロッコリーを栽培してみた」というのです。
しかし、栽培がうまくいかず商品にならなくて、見かねた大人が15円で買ってくれたという話なんですが。「こんなに苦労して15円しかもらえなかったのに、1回の課金が100円って、使いすぎだと実感した」という主張でした。大人では考えもつかないですよね。正論だけを繰り返すより、こんなふうに自分らしい体験で語れるところがおもしろいと思いました。
生成AIでさまざまなことができる近未来では、AIの学習を飛び越えた発想や尽きない情熱こそが人間に残された力ではないかと思うのです。子どもたちの枠にとらわれない発想力と体験を、楽しくおもしろく語れるプレゼン力を、大人は大事にしてあげたいですね。
『話す力で未来をつくる ~プレゼンアドバイザーが伝える 子どもの思考力 判断力 表現力を伸ばすチャレンジ~ 』
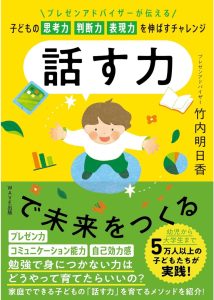
著/竹内明日香( WAVE出版)
Amazonでチェック≫
お話を聞いたのは?

取材・文/三輪泉






