お話を聞いた佐藤義竹先生は、筑波大学附属大塚特別支援学校教諭。東京都文京区教育委員会・特別支援教育外部専門委員も務めていらっしゃいます。社会性や自尊感情を育む教材の開発や著書も多数。近著に『自信を育てる 発達障害の子のためのできる道具』(小学館)。
目次
特別支援学校ってどんなところ?
-まずは改めて、特別支援学校はどんな学校なのかを教えてください。
特別支援学校は、障害がある子どもに対して、小学校、中学校または高等学校に準ずる教育を行うとともに、障害による困りごとを克服し、自立をめざすために必要なことを学ぶ学校です。
1学級あたりの人数も、通常の学級は40人(小学校は35人)以下とされていますが、特別支援学校は6人(高等部は8人、重度重複学級は3人)以下となっており、少人数で手厚く見ることができます。
また、通常の学級や特別支援学級とは違い、教員が必ず特別支援教育の専門資格を持っているのも、特別支援学校だけの特徴です。
-佐藤先生の学校は、特別支援学校の中でも特殊な国立の特別支援学校ですが、都立や県立などの特別支援学校との違いはどのようなところでしょうか?
国立の特別支援学校は、本校のような研究活動をしている学校も多いですが、基本的には学校で学ぶ目的は都立や県立の特別支援学校と同じです。
ただ、スクールバスが運行しているかなど、学校によって細かな違いがあります。
-たしかに、スクールバスがあることは大きなメリットですよね。
息子を通わせていて思うのは、帰りも、都立の特別支援学校だと地域の放課後等デイサービスが学校まで迎えに来てくれたりもするので、楽ですね。
そうですね、国立や私立の特別支援学校だと、通学範囲がとても広いので、登下校の移動に伴う負担感や安全面の確保なども大切になります。本校の場合、登下校は保護者責任での対応をお願いしています。
入学を控えたお子さんの親御さんへ、進学前に知っておいてほしいこと
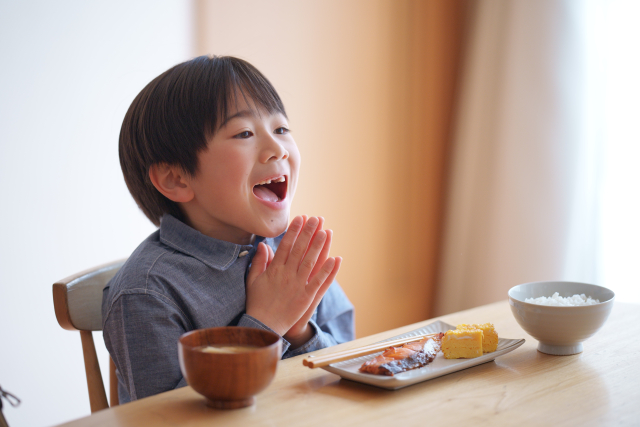
-特別支援学校入学前に、子どもと家庭で準備できることはありますか?
私からは、次の2つのことをお願いしたいと思っています。
1つは、生活リズムを整えること。
就学後は、登校から下校まで時間割に沿って集団生活を送ることになります。
お子さんが安定した生活リズムの中で過ごせるように、大まかでもいいので、「〇時には布団に入る」など、生活リズムを整えることは可能な範囲でお願いしたいと思っています。
もう1つは、あいさつなどのコミュニケーションを積み重ねること。
他者との関わりの基礎として、「おはよう」「ありがとう」などの挨拶をする機会を家庭でも積み重ねてほしいと思います。
単純に「おはよう」と言われて「おはよう」と返せることが目的ではなく、相手の働きかけを聞き、受け取るといったことが、大切な関わりの基礎となります。
-うちの息子は発語がないのですが、それでも、ぺこっとおじぎをしてあいさつしてくれます。こういう動作は、特別支援学校でしっかり定着したなと思います。
そうなんです、言葉で話さなくても、動作でも「あいさつ」はできますからね。
あとは、食事や排泄の自立を気にする親御さんもいますが、特別支援学校ではそういったことは「日常生活の指導」として指導や支援を行いますから、安心して下さい。
-子どもの特性などについて知っておいてほしいことを、まとめて先生に渡したりした方がいいのかな、ということも気になります。
それについては、そこまでがんばらなくてもいいと思います。学校の書式で作ってもらう支援シートもありますし、面談や入学後の連絡帳などのやりとりで、お子さんのことをいろいろと聞かせてもらえたらいいのかなと。
小人数制の特別支援学校。子ども同士のかかわりは?どんな授業をするのでしょう?

-私は息子の進学先を特別支援学校に決めるとき、「特別支援学校だと子ども同士の関わりが少なくならないかな?」と不安だったんです。どうしても、コミュニケーションが苦手な子どもたちが多く、人数も少ないですし、地域の学校に比べると、難しくなるのかなと。特別支援学校では、子ども同士の関わりがスムーズにできるようにどのような配慮をしていますか?
特別支援学校では1学級あたりの子どもの数が少ないですが、その分、一人ひとりに応じたきめ細やかな支援ができます。
大人が加減しながら介入していくので、子どもの数が少ないからといって、友だち同士の関わり合いが全くないわけではありません。
学級だけではなく、複数の学級や学年合同など、さまざまな集団での活動を通して、子ども同士がやりとりをできるよう、学習計画や教材教具、教師の支援など、さまざまな手だてに配慮しています。
そして、私は子ども同士のやりとりがすべてではないとも思うのです。
もちろん友だちとも関わりますが、支援学校では多様なやりとりがあるので、子どもが自分らしくいられる環境になっているのではないかと思います。
-たしかにそうですね、息子も重度の知的障害で発語もないですが、学校に仲の良いお友だちがいるようで、よくペアになって活動しているようです。学習のことなのですが、特別支援学校では子どもが授業内容を理解しやすくするためにどんな工夫をしているのでしょうか?
個人的には、「具体的」「反復的」「段階的」「体験的」な学びを提供できるように、授業を考えたいと思っています。
「具体的」は、子どもにとって身近で興味関心がある、具体的な題材を扱うこと。
「反復的」は、繰り返しの活動、経験の積み重ねを大切にすること。
「段階的」は、一人ひとりの実態把握をして、スモールステップで考えること。
「体験的」は、子どもが自分で動く、取り組むことができる学習内容であること。
これらを踏まえて、年間の計画をたて、スモールステップ的に学習内容を深めていくようにしています。
学校外のサポート機関との連携のキーパーソンは保護者

-学校と家庭、放課後等デイサービスなどの学校外のサポート機関との連携は、どうやってとったらいいのでしょうか?
個人情報の取扱いには注意しなければならないので、学校としては、外部関係機関とのやりとりは、保護者を介するようにしています。
そのため、保護者がハブになっていただき、学校と家庭、そして放課後等デイサービスなどの関係機関をつないでいただきたいと思っています。
学校から保護者に、他の機関での様子などをお聞きすることもあるかと思いますが、気になることがあった際には家庭から学校にお知らせいただけると助かります。
一人ひとりのニーズに合った「自己選択」「自己決定」につながる活動で子どもは成長します
-実際に特別支援学校に入学した子どもたちは、どのように成長していますか?
例えばあるお子さんに、「突然泣き叫ぶ、パニックになる」という行動が見られたとします。
特別支援学校では、その行動が「いつどのようなときに起こりやすいか」という実態把握と、それをもとにした分析を行います。
すると、授業終盤や、本人が困ったときに起こりやすいなどの傾向が分かるのです。
次に、授業であれば「予定」を示すようにし、伝え方も文字だけでなくイラストも使って視覚的に示すことができるようにします。
そうすることで、子どもも「あとどれくらい?」「あと何をするの?」を把握できるようになるのです。
さらに、本人が困ったときによく見せる表情やしぐさを整理し、泣き叫ぶ前に先生から声がけし、子どもの方から「教えてください」などの援助を求められるような状況を作っていきます。
そうすることで、安心して授業や活動にとりくむことができるようになっていくのです。
もちろんはじめからうまくいくとは限りませんが、その都度、支援の方針を振り返り、本人のニーズにあった内容にしていくようにしています。
-特別支援学校での指導によって、落ち着いてきたお子さんは多そうですよね。将来についてなのですが、特別支援学校に在籍しているお子さんは、将来の進路のためにどのようなことを準備したらよいでしょうか?またそのためのサポートは、学校ではしてくれていますか?
小学生ですと、まだ「将来」といっても漠然としていてイメージするのが難しいかもしれません。ですから、小学生のうちは、「自己選択」「自己決定」ができること、意思の表出ができることを大事にしています。選ぶことが難しい子が、だんだん自分で選ぶことができるようになる、それが進路へとつながっていくと思っています。
-たしかに、重い知的障害がある子だと、「好きなものを選ぶ」ということだけでもすごく難しいんですよね。うちの息子も、以前は「好きなもの選んで」と言っても何も選べなかったのですが、特別支援学校に行って、だんだん自分で選べるようになってきました。今ではお店に行ってたくさんの商品がある中から、好きなジュースを自らとってきます。
まさにそれですね、最初は2択から始めて、徐々に選択肢を増やし、子どもに選ばせていきます。「選ぶ」ということひとつとっても、とても大切なことです。
親も自分の生活を大事にしてほしい。親がゆったりと構えることでお子さんも安定します

-佐藤先生はこれまで、いろいろな保護者と関わってきたと思うのですが、特別支援教育に関してよく聞かれる不安や疑問と、それに対するアドバイスがあれば教えてください。
やはり、「同学年の友だちと関わる機会が少ないのではないか?」という不安をお聞きすることは多いです。
たしかに、通常の学級と比べれば、関わる相手の数は減少します。しかし、私は必ずしも「友だち100人つくらなければいけない」というわけではないと思うのです。
たくさんの友だちよりも、1人でも安心できる友だち、の方が大切ではないでしょうか。
多くの友だちがいることが、絶対ではないと思っています。
-障害がある子の保護者が子どもと一緒に成長するために大切なことは、何でしょうか?
私からは、2つのことを挙げたいと思います。1つは、保護者自身の生活環境も大事にしてほしいということ。
障害がある子を育てていると、どうしても子ども中心になってしまうこともあるかと思いますが、ご自身の生活を大事にしてほしいと思います。親御さんがゆったりかまえていた方が、子どもも安定します。
もう1つは、環境との相互作用で考えることです。「障害の社会モデル」とも言われますが、障害は個人の心身の機能の問題ではなく、社会や環境によって作られるものであるという考え方ですね。
子どもの気になる行動には原因やきっかけがあり、それは本人と環境とのミスマッチで起こっています。
子どもが安心して自分らしく活動できるように、「環境を調整する」という視点が大切です。
-子どもたちの自立やより深い学びを促すために、家庭でもできるサポートはどんなものがあるでしょうか?
やはり、自己選択、自己決定を促すことですね。受け身ではなく、自分から動けるようになると良いと思います。
-先ほどの進路の話にもあったことですね。我が家も、買い物に行ったときなど、息子には自分で好きなおやつやジュースなどを選んでくるように言っています。最後に、これから特別支援学校へ入学するお子さんがいる親御さんに対して、メッセージがあればお願いします。
特別支援学校では、「わかった」「できた」「やってみたい」の気持ちを大事にしています。障害があるお子さんを育てる中で、不安に思うことや、困りごともあるかもしれません。しかし、学校は家庭と力をあわせてお子さんの学び、育ちを支えていきたいと考えています。
連絡帳などを活用しながら、ぜひ前向きにコミュニケーションを図って、一人ひとりの学校生活を充実したものにしていきたいですね。
こちらの記事もおすすめ


取材・構成






