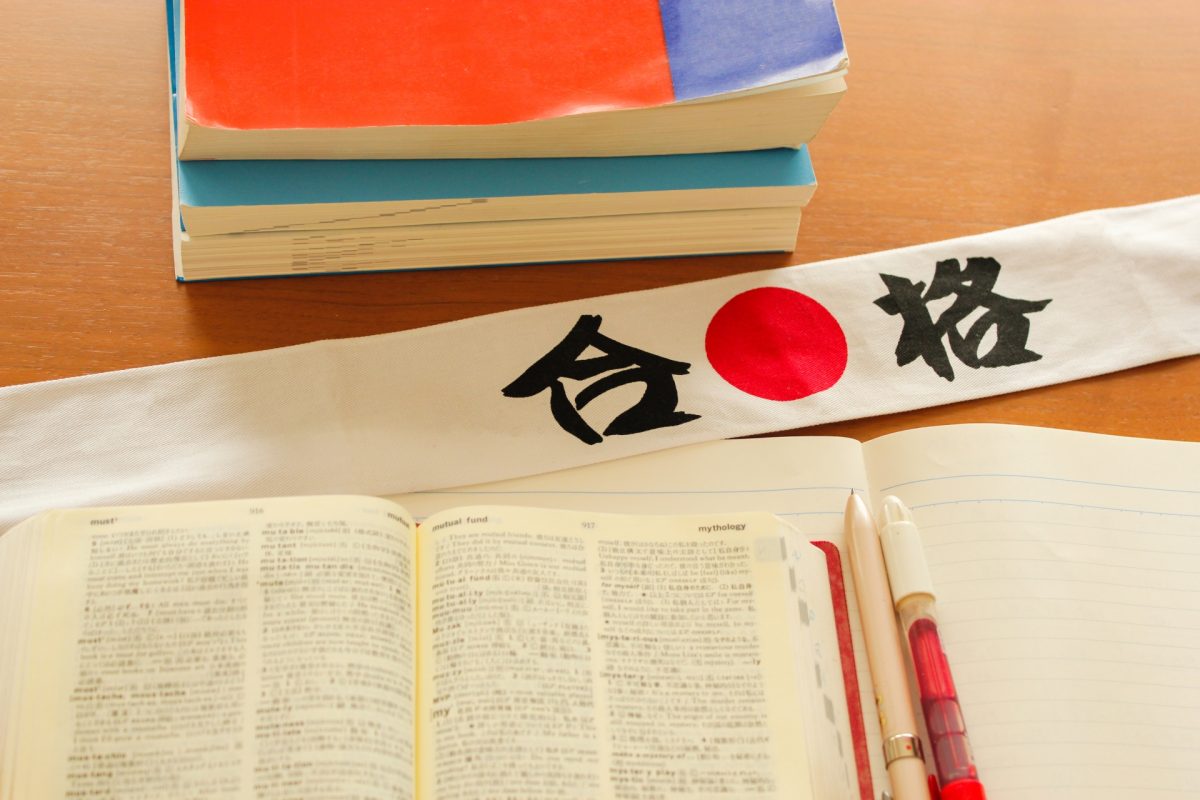2025年首都圏中学入試の傾向
受験者数の推移と出願動向
2025年の首都圏中学入試(東京・神奈川・千葉・埼玉)の受験者数は52,300人で、前年の52,400人とほぼ同じ。受験率は18.10%と高い水準を維持しています。1人あたりの出願校数は7.44校と、年々増加傾向にあります。
「開智」の人気上昇 出願者数の増加が顕著な茨城県と埼玉県
出願者数の増加が特に目立ったのは茨城県と埼玉県でした。「開智望中等教育学校」のある茨城県は前年比196.1%と最も高く、「開智所沢中等教育学校」や「開智中学・高等学校」のある埼玉県も121.1%と大きな伸びを見せました。東京都の出願率は103.5%、千葉県は99.3%とほぼ前年並みでしたが、神奈川県は97.9%とやや減少しました。
受験者数も埼玉・茨城で大幅増
受験者数の増加率でも、「開智」が県全体の受験者数を押し上げた影響が大きく、埼玉県は前年比119.6%、茨城県は190.3%と急上昇。東京都(101.6%)、千葉県(100.3%)、神奈川県(96.9%)を上回る結果となっています。特に開智所沢は前年比221.2%、開智は197.5%と、埼玉県の受験者増を牽引しました。
開智所沢の人気の背景
開智所沢の受験者が大幅に増えた背景には、入試システムの工夫があります。同校では今年から、複数回受験による加点制度を導入。複数回受験すれば合格への可能性が高まるため、昨年と比べて複数回受験する受験生が増加したのでしょう。
立地の良さも人気の要因の一つです。武蔵野線沿線に位置し、東京の多摩地区や神奈川県川崎地区などからも通いやすいため、東京からの受験者も昨年より増加しました。さらに、昨年は合格者・入学者を多く出したこともあり、今年の受験生にとって「合格をもらえる可能性が高い」という安心感があったことも志願者増加につながったと考えられます。
最難関校の受験が減少
2025年入試では、最難関校(首都圏模試偏差値71~78)の受験者数が減少する一方で、男子は偏差値61~70の受験者数が多い傾向が見られました。女子は偏差値41~50の学校への出願が増え、受験の選択肢が広がっている傾向がみられました。
2月4日、5日の受験増
これまで2月1日・2日の午前・午後すべてを受験するケースが多かったのに対し、2025年入試では、2月4日・5日の受験者が増加しました。Web出願は直前まで出願できるため、安全校の合格を確保した上でより高いレベルの学校に最後まで挑戦するというように、ゆとりのあるスケジュールでの受験が増えていると考えられます。
英語入試の拡大と多様化
英語(選択)入試を実施する学校は、2024年の98校から2025年には113校へと増加しました。英語資格型の入試も増えており、筆記型の受験者が全体の56%を占める一方で、英語資格型の受験者は36%となりました。グローバル教育を重視する私立中学校の増加を反映しており、今後も英語を重視した入試が拡大していく可能性があります。
共学校:ゆとりのあるスケジュールが主流

「受験しっぱなし」はもう古い?
かつては、1月の埼玉・千葉入試から始まって2月4日、5日の東京・神奈川入試まで、連日受験を続けるのが一般的でした。しかし、最近では「途中で休みを入れながら受験を進める」スタイルが定着しつつあります。2025年度入試で、1月10日(埼玉)、1月20日(千葉)、2月1日(東京・神奈川)の午前入試で受験者数が伸び悩んだのは、受験生が無理なく実力を発揮できるように、間に休息日を設けながら試験を受ける計画を立てる家庭が増えたためです。「とにかく受ける」から「効率よく受ける」へ。受験生や保護者の意識は、より戦略的になっています。
「子どもに合った学校を」。保護者の情報収集力もアップ
「とにかく上を目指す」よりも「子どもに合った学校を確実に選ぶ」傾向が続いています。多くの情報を集め、併願戦略を立てる保護者が増えており、塾の先生への質問の仕方も、「うちの子に合っている学校はどこですか?」から、「この学校はうちの子に合っているのか?」へと変わっているようです。
公立中高一貫校の志願者減少と適性検査型入試の低迷
2025年の公立中高一貫校の受験者数は過去最低となりました。公立中高一貫校に合格した生徒が私立中学へ進学するケースも増えています。探究型学習や国際教育、ICTを活用した授業など、特色ある教育を提供する私立中学が増えており、公立の適性検査型入試を回避し、より確実な進学先として私立を選ぶ家庭が増えているとみられます。
公立中高一貫校の人気低下に伴い、適性検査型入試も減少傾向にあります。今後、「公立・私立どちらも適性検査型で受験する」層は減り、一般的な私立型の受験を選択するケースが増加するかもしれません。
1月に決着 「早めに合格を確保したい」
受験生が早めに進学先を確保し、受験を終える傾向が強まっており、1月入試も注目です。2月本番に向けた力試しとしての側面も強く、多くの受験生が活用しているようすがうかがえます。
開智や開智所沢の受験者数急増で、1月入試の競争は激化。例年よりも合格ラインが上昇した学校が増えました。渋谷教育学園幕張や佐久長聖(長野県)などの人気校では、前年よりも若干受験者数が減少しましたが、合格者層のレベルは維持されており、依然として高い競争率を誇っています。
埼玉県の中学受験で受験者数No.1の栄東は、これまで1月10日・11日に実施していたA日程(難関大)を、1月10日を東大クラス、1月11日を難関大クラスと分けて実施したところ、1月10日の東大クラスの受験者数がやや減少したものの、受験者数は前年比160.3%と大きく増加しました。受験生や保護者の間では、「早めに合格を確保し、受験を終えたい」意識が強く、1月10日〜12日までに進学可能な学校を決めるケースが増えています。
男子校:難関校、伝統校が激戦化!
難関校の競争激化!慶應中等部・本郷・聖光学院
伝統的ならではの魅力が人気の慶應中等部で受験者数が増加しました。本郷も同様に合格者の偏差値帯が上がり、難関校としての存在感を増しています。
2月2日の聖光学院は、保護者や生徒の愛校心が強く、説明会ではPTAが主体となって学校の魅力を伝える点も特徴的です。
伝統校の魅力!明大中野・浅野・学習院の教育方針
明大中野は基礎学力を重視し、成績不振の生徒には部活動の制限を課すなど、厳格な教育方針を取っています。礼儀や時間管理、身だしなみにも厳しく、学校生活全般にわたってしっかりと指導する点は、保護者にとって安心感につながっています。
浅野は定員削減が行われたにもかかわらず、受験者数は依然として多く、高い人気を維持しています。試験の難易度は上がっており、補欠繰り上げ合格の調整も難航しているようです。学習院は、青山学院の試験日程変更の影響を受け、2日試験の競争率が高まりました。
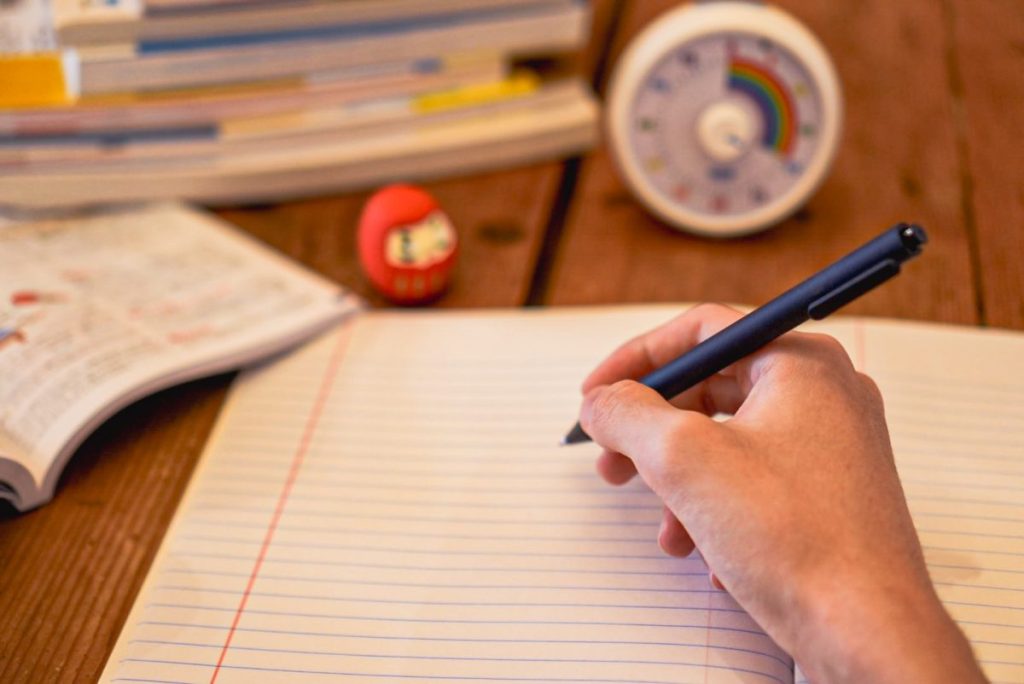
これからの注目校!逗子開成・日本学園
逗子開成では、主体性を育む教育を重視し、オリジナルの手帳を活用した学習管理が注目されています。最近の中学生は、授業のメモを取るのが苦手になっている傾向があり、保護者の間でも、こうした教育方針が評価されているようです。
日本学園は共学化の影響で、受験者層に変化が。今後、男子の募集枠が減るため、来年度以降はさらに難易度が上がるでしょう。学校改革が進む中で、今後の受験生の動向に注目が集まります。
女子校:志望校の選択は前日まで
志望校はギリギリまで悩む
ダブル出願をしておいて、1月の試験結果を見ながら直前まで受験戦略を練る家庭が増えています。東京だけでなく千葉や埼玉の1月入試を活用する動きも加速。背景には、女子の入試における安全志向の強まりが影響しているのでしょう。以前は11月以降に志望校を変えるのは珍しいのが一般的でしたが、今は直前まで調整するのが主流となっています。
午後入試の受験率増が止まらない
2月1日は受験生の約7割が午後入試を活用しました。今年は午後入試の開始時間を15時半や16時に遅らせる女子校も多く、受験生の負担が軽減。1日の試験結果を受けて2日の受験校を決めやすくなった点が保護者の安心材料となりました。「3日までに合格を決めたい」「4日、5日にはかからないようにしたい」という短期決戦志向も強まっており、早期に合格を確定させる動きが目立ちました。
実は横ばい。帰国生入試のリアル
帰国生入試の割合は増加しているように見えますが、実際にはほぼ横ばい。保護者からは「海外での学習環境と日本の入試のレベルにギャップがある」「入学後、受験科目のフォローが十分なのか不安」などの声が多いようです。帰国生入試は早期に合格を確定できるメリットがありますが、実際の入試難易度や学習準備などの情報がつかみにくい点が課題となっています。

高大連携が人気。2026年度は「サンデーショック」も
山脇学園と法政大学、跡見学園と東京農業大学など、多くの女子校が大学との提携を発表したことで大学進学を見据えた選択肢として人気が高まっています。
2026年度の中学受験では、9年ぶりに「サンデーショック」が発生し、キリスト教系の学校で試験日が変更されます。志望校によっては併願計画の見直しが必要になるでしょう。女子学院の志願者が急増しており、競争のさらなる激化が予想されます。
2025年度入試では、「開智」ブランドの人気上昇が受験者増に影響を与え、全体的にゆとりのある受験スケジュールを立てる受験生が増えてきました。男子校・女子校ともに、難関校で競争が激化しています。2026年度は「サンデーショック」の影響を受けるため、例年とは違った戦略が必要となるでしょう。
あなたにはこの記事もおすすめ

取材・文/黒澤真紀 協力/森上教育研究所