目次
9月1日は「防災の日」。 その由来や意味は

毎年ある「防災の日」。学校やオフィス、地域の施設などで防災訓練が行われたりするものですが、「防災の日」とはいつなのでしょうか?
「防災の日」は毎年9月1日
「防災の日」は毎年9月1日。日本は地形や地質などから、地震や台風、津波、豪雨などの災害が発生しやすい国で、これまでにもさまざまな災害に見舞われてきました。そのような災害による被害を少なくするために、「防災の日」が設けられました。また、「防災の日」は祝日ではありません。
9月1日から1週間は「防災週間」
また、9月1日の1日だけを「防災の日」とするのではなく、9月1日から1週間は「防災週間」とされ、この期間中には、市町村や行政と連携しながら、各地域でさまざまな防災関連の行事が行われます。
毎月や月違いで防災の日を設定している地域も
また、9月1日以外の「防災の日」もあります。例えば、阪神・淡路大震災が起きた1995年1月17日を忘れないために、毎年1月17日は「防災とボランティアの日」に定められ、1月15日から1月21日までは「防災とボランティア週間」となっています。また「防災用品点検の日」は、3月1日、6月1日、9月1日、12月1日の年4回あります。
さらに、地域ごとに過去の災害にちなんで独自に「防災の日」を設けているところもあり、次のようなものがあります。
・3月11日 いのちの日
・5月26日 県民防災の日(秋田県)
・6月12日 みやぎ県防災の日
・10月28日 岐阜県地震防災の日
・11月5日 津波防災の日
防災の日の由来、創設について
さまざまな「防災の日」があることがわかりましたが、全国的に展開されている最も大きなものが、9月1日の「防災の日」。この日がなぜ、「防災の日」に制定されたのでしょうか?
日本は、これまでにも数々の大災害に見舞われてきましたが、歴史上の大きな地震災害のひとつとして記憶されているのが、1923年9月1日に起きた関東大震災です。この震災を忘れず、災害に対する備えをしっかり行おうと、1960年、国は9月1日を「防災の日」として制定しました。また9月1日は、立春から数えて210日目の日で「二百二十日(にひゃくはつか)」と呼ばれる暦の日。この時期は台風が多く、災害が発生しやすいことも、防災の日に設定された理由のひとつといわれています。
子どもへの簡単な伝え方
さまざまな災害に備えるべく、子どもにも防災への意識をきちんと伝えておきたいですね。そのためにも、「防災の日」はいい機会のひとつとなるでしょう。
「防災の日」について、子どもには、「避難訓練を行ったり、防災グッズをそろえて、地震や台風などが起きたときに備える大切な日」であると伝えましょう。また、子どもは災害の怖さをあまり実感できないかもしれないので、防災に関するテーマの絵本などを一緒に読むのもいいかもしれません。
防災の日に保育園・幼稚園で行うこと

子どもが保育園や幼稚園にいるときに災害が起きたとしたら…。そんな万が一に備えて、保育園や幼稚園では「防災の日」にさまざまな行事や訓練が行われます。大事な子どもたちを守るために、親もどんな取り組みが行われるのか知っておきましょう。
給食は非常食
保育園や幼稚園では、慣れない非常食で子どもがストレスを抱えないように、「防災の日」の給食に乾パンや災害用レトルトカレーなどを食べることもあります。
そうすることで、子どもなりに災害を疑似体験することができ、また、多くの子どもが興味を持つ「食」をきっかけに、防災について考える機会にもなります。なかには、災害時の炊き出しを想定して、豚汁などを出す園もあるようです。
防災訓練
「防災の日」の取り組みでもっとも大事なのは、やはり防災訓練。大きな災害が起きたときに、動揺したり不安を感じて、動けなくなったり泣き出してしまう子もいるかもしれません。そうなることを少しでも防ぎ、すみやかに避難できるよう、防災訓練では実際に防災頭巾をかぶり、机の下などに隠れ、先生の誘導のもと避難場所まで移動する、といった一連の動作について確認します。
また、保育園や幼稚園の避難訓練では、先生たちの役割分担を確認する狙いもあるでしょう。幼い子どもたちを安全に避難させるためには、先生たちが落ち着いて行動することも大切です。それぞれの園で防災マニュアルなどが用意されているはずですので、それに沿った避難行動の確認が行われます。
保護者への連絡・引き渡しの確認
子どもが保育園や幼稚園にいるときに災害が起きたら、避難した子どもを安全に保護者に引き渡す必要があります。そのため、園と保護者の連絡が大事になってきます。それぞれの園ごとに一斉メールシステムなどの連絡手段が決められているはずです。「防災の日」には、そのような緊急時の連絡方法について確認する園もあります。子どもを守るためにも、普段から親と園との間での密接なコミュニケーションが必要になるでしょう。
防災の日に家で行いたいこと

災害はいつどこで起きるかわかりません。家の外にいたときに発生することも考えられますが、まずは各家庭ごとに災害時の対応について話したり、備えについて見直したりしましょう。
防災マップで地域の避難場所を確認する
国土交通省や各市町村で防災マップやハザードマップなどが作られています。それらで、自分が住んでいる地域でどんな災害が予測されるかを把握し、自宅から近い避難場所がどこにあるのかを確認しましょう。また、家族で自宅からその避難場所まで実際に歩いてみて、どんな経路で行くことができるかを確認しておくとさらに安心です。
防災グッズを確認する
携帯ラジオや非常食、救急品などを詰めた防災リュック(非常リュック)は、いざというときにそのまま手にして非難することができます。そのためにも、リュックの中に入っているものが十分か、非常食が古くなっていないか、定期的に確認することも大切。「防災の日」には、防災リュックの中身も確認するようにしましょう。
家具の転倒防止対策を行う
これまでに起きた地震では、倒れてきた家具の下敷きになり亡くなったりケガをした人がとても多くいます。本棚、テレビ台、食器棚など、家具が倒れてくることを想定して、転倒防止グッズでしっかり固定しましょう。特に、子どもがいつも過ごすリビングや子ども部屋は、改めてチェックすることをおすすめします。
食料や飲料の備蓄を確認する
万が一の場合に備えて、非常食や飲料水を1週間分ほど準備しておきたいもの。これらの備蓄品は定期的に新しいものを購入して、古いものは食べて処分し、新しいものを常備できるようにしましょう。
家族同士の連絡手段を確認する
災害時は電話がつながりにくくなることが想定されますが、携帯電話や固定電話から利用できる、NTT災害伝言ダイヤル「171」などで安否確認を行うこともできます。また、SNSで連絡を取り合うこともあるかもしれません。家族同士で、緊急時にどうやって連絡をとるか、事前に決めておきましょう。
2025年の防災イベント
2025年には防災イベントが各地で開かれます。親子で参加して、防災意識を高めるためのきっかけにしてみてください。
ぼうさいこくたい2025
「自助・共助」「多様な主体の連携」「地域における防災力の向上」を促進するため、国民の防災意識の向上、災害に関する知識や経験等の共有、防災に取り組む方々の連携構築を図ることを趣旨としている、日本最大級の防災イベントです。10回目の開催となる今年は、現地参加とオンライン参加を組み合わせたハイブリッド形式で開催します。
開催日時:9月6日(土)、7日(日)
開催場所:朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター(一部オンライン配信)
第10回 防災フェア in お台場
自衛隊や法務省等の防災車両展示、ミニP-3C演技、音楽演奏、キッチンカーでの販売などが行われる、防災フェアinお台場は今年で10回目を迎えます。東京都江東区の青海にあるシンボルプロムナード公園(ガンダム立像周辺)が会場となっていますから、ぜひ親子で参加してみましょう。
開催日時:10月4日(土)、5日(日)
開催場所:シンボルプロムナード公園(セントラル広場)
北海道 災害リスク対策推進展2025
北海道胆振東部地震では、人的被害をはじめさまざまな二次被害も発生し、その時の記憶は今でも北海道民の心に鮮明に刻まれています。地域住民の安全、持続的な経済基盤構築、観光産業の体制整備の観点から官民が一体となって災害リスク対策を推進するため、災害リスク対策推進展2025が開催されます。
開催日時:10月8日(水)、9日(木)
開催場所:アクセスサッポロ(札幌市・白石区)
防災の日に関するよくある質問
ここからは、防災の日に関する質問にお答えします。
Q. 防災の日はなぜ9月1日?
1923年の関東大震災が起きた日であり、台風シーズンでもあるため、防災意識を高める目的で制定されました。
Q. 子ども向けに防災を説明するには?
「地震が来たら机の下に隠れる」など、具体的な行動を絵や遊びを通じて伝えると理解しやすくなります。
Q. 家庭でできる防災対策は?
家庭では、防災マップで地域の避難場所を確認する、防災グッズを確認する、家具の転倒防止対策を行う、食料や飲料の備蓄を確認する、家族同士の連絡手段を確認するといったことを行いましょう。
防災の日は、緊急時の保護者間の連携を見直して
子どもが保育園や幼稚園にいるときに災害が起きることも、十分に考えられます。そんなときに、親がすぐに園に子どもを迎えに行けないこともあるでしょう。保育園や幼稚園の先生との連携ももちろん必要ですが、保護者同士のつながりも重要。緊急時に連絡を取り合ったり、お互いに助け合ったりできるよう、普段から保護者間のコミュニケーションも大切にしておきましょう。
あなたにはこちらもおすすめ
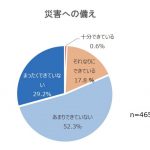
文・構成/HugKum編集部





