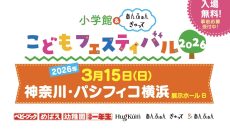丸亀城って、どんなお城? 基本情報をチェック
「丸亀城(まるがめじょう)」は、大阪城や姫路城などに比べると知名度は高くないかもしれません。しかし、江戸時代から残る天守や美しい石垣など、多くの見どころがあります。

香川県丸亀市にある「日本100名城」の一つ
丸亀城は、香川県丸亀市にある城です。「日本100名城」の一つにも数えられており、石垣の高さと美しさから「石垣の名城」とも呼ばれています。江戸時代初期の優れた技術で造られた、さまざまな石垣が見どころです。
天守までの四層の石垣は合計で約60mあり、全国一の高さとされています。一層だけで見ても最高約31mで、大阪城に次ぐ高さです。
丸亀城は、大手門から天守に至るまでの道筋が「らせん状」になっているため、ほとんどが坂道です。
この場所では、例年1月に「丸亀城福男(ふくおとこ)選手権」も開催されています。2023(令和5)年で4回目になるこの催しは、傾斜約10度の「見返り坂」を約100m駆け上がってタイムを競うものです。丸亀城内の急な傾斜がうかがえるでしょう。

丸亀城には、約400年の歴史がある
丸亀城は再建されて約400年、築城から数えれば、さらに長い時間が経過した城です。城だけでなく、町造りも安土(あづち)城や大坂城を手本にしたとされる、丸亀城の歴史を見ていきましょう。
安土城や大坂城を手本に築城された
丸亀城は自然の地形を利用して、標高約66mの小山「亀山(かめやま)」の上に築かれました。そのため、亀山城とも呼ばれています。
讃岐(さぬき)国の領主となった生駒親正(いこまちかまさ)と、息子の一正(かずまさ)によって築城が始まったのは1597(慶長2)年のことです。親正は讃岐国を与えられたのに伴い、高松(たかまつ)城を築城、居住しました。引き続き丸亀城を築いたのは、讃岐西部の支城とするためです。
丸亀城には、安土城や大坂城にならった「総構(そうがまえ)」を採用しています。武家屋敷や城下町も塀や土塁(どるい)で囲って、防御力を高めているのが特徴です。
一国一城令により廃城
1615(元和元)年6月、江戸幕府から「一国一城令」が出されました。各国大名の居城以外の城を破却することを命じる内容により、文字通り城は一国に一つとなります。それから数日のうちに、全国で丸亀城を含む約400の城が廃城とされ、讃岐国では高松城のみが残りました。
一国一城令の目的は、西国諸大名の軍事力を抑制することでした。翌月には、大名を統制するための法令「武家諸法度(ぶけしょはっと)」も出されます。武家諸法度には、新規築城の禁止や居城の修理制限も含まれていました。
再築後は、明治まで存続
1641(寛永18)年、転封(てんぽう)となった生駒氏の代わりに、天草郡富岡城主だった山崎家治(やまざきいえはる)が西讃岐に入封(にゅうほう)します。5万石あまりを与えられた家治は、丸亀藩主となり、翌年には生駒氏城跡地に築城が許されました。
1643(寛永20)年には幕府から銀300貫を下賜(かし)され、丸亀城の再建に着手します。瀬戸内海の島々に潜むキリシタンの蜂起(ほうき)を警戒した幕府は、丸亀城の存在が抑制になると期待したのです。家治の参勤交代を免除してまで再建を急いだことからも、その重要性がうかがえるでしょう。
山崎氏の断絶後、1658(万治元)年に京極高和(きょうごくたかかず)が藩主となります。高和は丸亀城の再建を進め、1660(万治3)年には天守も完成しました。以後、1869(明治2)年に藩主・京極朗徹(あきゆき)が版籍を奉還(ほうかん)するまで、丸亀城は京極氏の居城となります。

石垣の名城・丸亀城の見どころ
丸亀城は、有名な石垣をはじめ、多くの見どころがあります。訪れたら、ぜひチェックしたいポイントを見ていきましょう。
江戸時代から現存する天守
丸亀城の天守は、「現存12天守」の一つとして有名です。
現存する天守では最も小さい三階三層ですが、三重目の屋根の長辺(「平」と呼ばれる)に、本来は短辺(「妻」という)につける入母屋破風(いりもやはふ)をつけています。城下から見上げたときに、奥行きがあるように見せる工夫です。実際の三層目の奥行きは2間あまり、つまり4mほどしかありません。
天守は小規模ですが、見晴らしは抜群で、城下の丸亀市街から瀬戸内海まで、美しい景色が楽しめます。
丸亀城は、江戸時代から当時のまま残ったことで、1943(昭和18)年に国宝に指定されました。現在は重要文化財となり、観光地・市民の憩いの場として大切に保存されています。

さまざまな工法が見られる石垣
石垣の美しさに定評のある丸亀城内では、さまざまな工法が見られます。主な工法は、割って加工した石を積み上げる「打ち込みハギ」です。各段が一列に組まれた整層積みや布積み、横目地を一部崩した布積み崩しがあります。
大手枡形(おおてますがた、城の正面玄関)には、鏡石と呼ばれる高さ約2mの石があります。鏡石は城主の権力の象徴です。丸亀城の鏡石は大きさも見どころですが、もう一つのポイントで人気を集めています。二つの鏡石の間に「幸運のハート石」と呼ばれるハート型の小石があるので、探してみるとよいでしょう。
三の丸北側の石垣には、算木積み(さんぎづみ)という工法が用いられています。長方体の石を使って長い面と短い面を交互に組み合わせ、角部分を角脇石(すみわきいし)で補強するのが特徴です。強度だけでなく滑らかさのある仕上がりで、「扇の勾配」と呼ばれるほどの優雅な曲線を実現しています。
貴重な展示物がある丸亀市立資料館
丸亀城内には、貴重な展示物を無料で観覧できる「丸亀市立資料館」があります。
屋外の「民具展示室」では、暮らしに関する道具が展示されています。芝生広場に並ぶのは、金毘羅(こんぴら)街道丁石(ちょういし)や常夜燈(じょうやとう)などの石造物です。常設展示室では、丸亀城と城下町に関する資料、歴代藩主の絵図や古文書などを中心に、丸亀市の歴史を紹介しています。
そのほかの所蔵品として、吉岡神社前方後円墳からの出土品や京極家伝来の品々、1670(寛文10)年の改築の際に幕府に提出したものの写しとされている丸亀城木図(きず)、豊臣秀頼から京極忠高に下賜された「ニッカリ青江脇指(あおえわきざし)」などがあります。ただし、これらは常設展示されていないので注意しましょう。
●住所:香川県丸亀市一番丁(丸亀城内)
●電話:0877-22-5366
●Fax:0877-25-2439
●開館時間 :9:30~16:30
●休館日: 月曜日・祝日(企画展開催中は開館の場合あり)・年末年始・資料整理期間中
●入館料:無料(企画展は有料の場合あり)
丸亀市立資料館 ご利用案内 – 丸亀城 – 丸亀市公式ホームページ
丸亀城の歴史や魅力を知ろう
丸亀城は、江戸時代からの天守が残る数少ない城です。石垣の美しさや天守からの眺めなど、多くの見どころがあります。いったんは廃城となったものの、再建後は明治維新まで引き継がれたというドラマティックな歴史も魅力です。
大手門から天守までの坂道を上るのは大変かもしれませんが、同じ道を歩いた昔の人の気持ちを想像できるのではないでしょうか。天守に立って景色とともに、丸亀城の辿(たど)ってきた歴史に思いをはせてみましょう。
こちらのお城もチェック!

構成・文/HugKum編集部