目次
「なぜ夏休みに宿題が必要なの?」と聞いてもだれも答えられない

――澤田先生が夏休みの宿題を廃止したのは2019年の夏前ですね。どのような経緯だったのですか?
澤田先生:私は、もともと夏休みの宿題を出すことに、意義を感じていなかったんです。「なぜ夏休みに宿題を出すんですか?」と先生方に聞いてもだれも答えることができません。あえて言うなら「昔から宿題を出していたから出す」ということでしょう。単なる慣習です。であれば、宿題はなくてもいいのではないかと思っていました。
夏休みを控えた時期に小学校の先生方と会議をすると、休み中の登校日の話題になりました。「子どもたちの夏休みの宿題を集めるために、休み中の登校日が必要だ」と。理由は、9月初旬に読書感想文コンクール応募の締め切りがあるからです。

子どもたちには、夏休みに読書感想文を書かせるわけですが、休み明け9月1日に感想文を集めていては、コンクールの出品に間に合わない。だから8月に登校日を設けて、その日に子どもたちの感想文を提出させ、先生方は集めた感想文を読んでコンクールに出す準備をするわけです。これがなかなか大変なんですね。
「ならば読書感想文をやめたらいいし、自由研究やドリルなども含め、夏休みの宿題をみんなやめてしまったらどうか」と会議で話しました。先生方はびっくりして「そんなことをしていいんですか?」と心配していましたが、その年の夏休みの宿題を全廃したんです。
宿題を出すなら、前もって宿題の指導をしておくべき
――つまり、きっかけは先生方の「働き方改革」のようなものですか?
澤田先生:それもあるけれど、子どもたちにとっても、こうした宿題の出し方はどうなのか、という疑問がありました。「読書感想文を書きなさい」と言うだけで、きちんと書き方の指導をする時間も持てない。
たとえば読書感想文コンクールで賞を取るような作品を書くためには、テクニックがいります。文章の構成の仕方もあるし、どんな作品が上位になりやすいかの傾向もある。しかし、なんの指導もされずにただ感想文を書けといわれた子どもたちは、四苦八苦して本を読んで、やみくもに作文することになります。
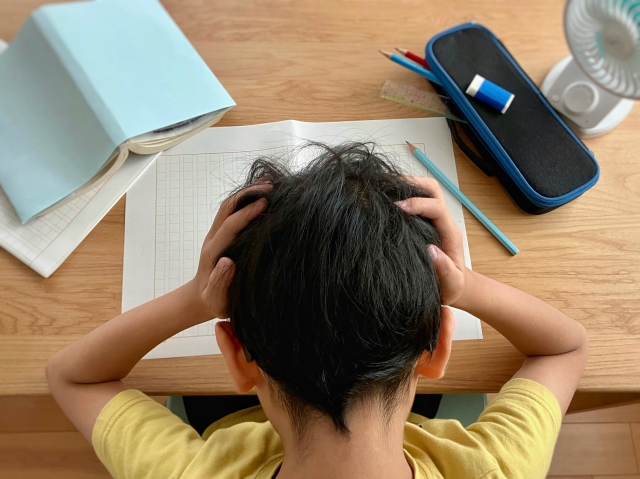
自由研究も同じです。自分なりの興味をどのように広げたり深めたりしてまとめたらいいのか、宿題を出す前に指導すべきなのです。でも、日頃の教科の指導で時間がいっぱいでやる暇がありません。そもそもコンクールのために宿題を出すというのも、本末転倒です。
夏休みに宿題がないのは保護者も賛成。でも不安はある……
――「夏休みに宿題を出さない」と言ったときの保護者の反応はどうでしたか?
澤田先生:ほとんどの方が賛成で、拍手がわきました。保護者の方も、子どもに宿題をさせるのが大変ですので、不満を言ってくる人はいませんでしたね。でも、不安に思う方はいました。「ほかの学校は宿題があるのに、この学校だけないとなると、うちの子、学力が落ちるんじゃないか」って。
私は「大丈夫ですよ」と言いました。その小学校では、子どもたちがのびのびと好きなことに取り組めるように、普段から全校で応援していました。子どもたちは、時には校長室にまで乗り込んできて「あれがしたいんだけれど、いいですよね?」と言ってくる。やりたいことはやり遂げるという子が多かったので「子どもたちを信じましょう」と。

読書感想文だって、自分が書きたいと思えばもちろん書けばいいし、全員が強制的にやる必要はない、というのが私の考えでした。感想文を強制的に書かせられることで、読書ぎらいになる子もたくさんいます。
しかも、夏休みの読書感想文は課題図書の中から選ぶことが多いでしょう? 自分が読みたい本や感動した本について書くわけではないですからね。読んで「つまらない」と思ったら意欲を持って書けるとは思えません。それよりも、たっぷりと時間のある夏休みに、好きな本を好きなだけ読む経験をしてほしい。
やることが増えた今、子どもも先生も忙しすぎる
澤田先生:そもそも、子どもたちも先生方もやることが多すぎるのです。昔はなかった「情報」や「英語」の授業もあります。やることは増えているのに、今までやってきたことも切り捨てることができない。そんなことを言っているとどんどん積み重なって、児童も先生もきつくなり、自由度もありません。
私は宿題をなくした翌年に定年退職したのですが、次の校長先生が私の思いを継いでくれました。現在は、豊田市のほかの小学校でも、夏休みの宿題を出さないところが増えています。
子どもたちには「自分で自分を鍛えるように」と指導
――子どもたちは夏休みの宿題がなくなって大喜びでしたか?
澤田先生:そうですね。でも、私は子どもたちに言いました。「夏休みの宿題をなくしたら、『これをやりなさい』って与えられるものはない。そのぶん、自分で計画を立てて勉強しないといけない。宿題がないって大変なことなんだよ。自分で自分を鍛えないといけないんだから」と。
保護者の方も、「宿題、終わったの?」と聞き「終わった」と言われればホッとしてしまう方が多いと思います。でも、宿題さえ終わっていればそれでいいのでしょうか。
宿題の代わりに子どもたちに夏の家族旅行の計画を任せてみる
――たしかにそうですね。親も子どもも「どんな学習なら積極的に取り組めるのか」を考えていないかもしれません。とはいえ、何をしたら子どもたちが意欲的になれるのでしょうか。
澤田先生:子どもたちには「今日何か楽しいことあった? 新しい発見があった?」と毎日聞いてほしいです。子どもは、必ず毎日何かを発見したりワクワクしたりしているはずなので、それを聞いて「わー、すごいねぇ!」と認めてあげてください。
子どもたちは、「昨日と今日の自分が変わっている、成長している、活躍している」という姿を一番身近な家族に認めてほしいと思っています。そこを認めて刺激していくことで、子どもたちはとても前向きになるんです。
また、夏休みなら家族旅行の計画を子どもに立ててもらうのもおすすめです。たとえば「予算は10万円、家族が楽しめる計画を立てて」と。すると、子どもは自分が行きたいところや親も楽しめるところなど、いろいろ考えて実践し始めます。親御さんは、子どもが立てた計画を存分に楽しんでください。

親に「勉強しなさい」ってただただ言われ続ける子は、勉強がつまらなくなります。逆に、親が楽しそうにしていれば子どももそれが楽しいんだって思います。親が「この本おもしろい!」って言いながら読書をすれば、お子さんも「読書って楽しいんだな」と思って取り組めます。身近な大人が「学ぶって楽しいことだ」ということを表現していけるといいですよね。
子どもは周囲の大人が学び成長することを楽しんでいれば、それを見て自然と自分も勉強をしたいと思うものです。勉強を「できなくなろう」なんて思っている子はいないのですから。
日常の小さな疑問をノートに書き留めて追究することこそ「探究」
――先生は、日ごろから子どもたちが好きなことに取り組めるようにしていた、ということでしたが、どんなことをしていたのでしょうか。
澤田先生:たとえば、担任時代には思ったことを記しておく「はてな帳」を書く取り組みをしていました。ふだんから「これってなんだろう?」と疑問を持ったら、それをノートに書く習慣をつける。どんなくだらないことでもいいんです。はてなを追究し、「こんなことを研究したい」と思ったことを書き留めて、やりたいと思うことをやればいい。それが「探究」でしょう?
教員は「子どもが自ら動き始めるようにする戦略」を、いつも意識すべきだと思いますし、ご家庭でも意識してもらえれば、子どもたちは変わっていくのではないでしょうか。夏休みの宿題に意味があるのかどうかも、そこから考えてもらえるといいですね。
――夏休みの宿題はなぜやるのか、どう取り組めばいいのか。根本的なところから考えていくことが大切。お子さんが成長できる学びを一緒に探し、その学びをともに喜べる夏にしたいですね!
お話を聞いたのは…?

1960年名古屋市生まれ。愛知教育大学を卒業後、豊田市の小中学校の教員に。体育が専門。定年前の小学校校長時代に「夏休みの宿題をなくした校長」として注目を浴びる。私立幼稚園園長を務める傍ら、3つの大学(愛知東邦大学、愛知教育大学、金城学院大学)で教員養成に関わる。2025年5月からは名鉄学園杜若高等学校で保健体育の非常勤講師として週に15コマの授業を行う現役教師でもある。近い将来、「子どもたちがくつろげる居場所」を作るのが目標。
取材・文/三輪泉






