お話を伺ったのは、三児の母であり、米シリコンバレーや日本で幼稚園を複数運営する中内玲子先生です。幼稚園教諭と保育士の資格やモンテッソーリ教育の国際免許を持ち、独自の幼児教育をつづった「シリコンバレー式『世界一の子育て』」の著者でもあります。
(以下、中内玲子先生談)
「叱る」と「怒る」の違いとは?
「叱る」と「怒る」は似ているようで違います。相手を良い方向に導くのが「叱る」、感情をぶつけるのが「怒る」です。
「叱る」は、子どもの成長や学びを延ばす意図的な行為であり、問題行動への解決策や安全な対策を提案することです。一方で、「怒る」は、親自身の感情的なものが強くなります。
どちらも投げかける言葉は同じだったとしても、「叱る」は冷静な状態で子どもの間違った行動を指摘しているのに対し、「怒る」は親の感情のままに言葉をぶつけている状態です。
例えば、子どもに新しくおもちゃを買ってあげたときに、すぐに壊してしまったとします。
やりがちなのが、「何やってるの!せっかく買ってあげたのに!二度と買ってあげない!」と怒鳴ってしまうこと。これには親の失望や落胆が表れています。
ここでは、子どもにものの大切さを冷静に教える「叱る」が正解です。
けれど、親の感情を子どもに伝えるのは決して悪いことではありません。親も人間なので、どうしても感情が入ってしまうものです。
「せっかく買ってあげたのに、〇〇がすぐに壊してしまって、ママ(パパ)すごく残念だな」
このように伝えることで、子どもに「おもちゃを壊すとママ(パパ)が悲しんでしまう。だからよくないことなんだ」と思わせることにつながります。
大きな違いは、感情をぶつけるか、冷静に子どもの成長のために適切な言葉を選んで伝えるかという「目的」なのです。
やってはいけない叱り方

「叱る」と「怒る」の違いを知ると、普段、子どもに注意をするときに「あれは怒るだったな」「あのときはちゃんと叱れたな」とある程度、判断がつくかもしれません。そんな風に反省する際には、ぜひ次の「やってはいけない叱り方」も思い出してみてください。
恐怖を与える
子どもがあまりにも予想外の行動をしたときに、自分でも抑えられないほど猛烈に怒ってしまった経験はありませんか?
例えば、子どもは外で衝動的に走ることがありますが、車や歩行者にぶつかりそうになったときに「危ないっ!」とつい大声をあげてしまうことがあるでしょう。
けれど、このとき子どもは「パパ(ママ)が大声をあげて怖い!」と感じます。実際は「車や歩行者にぶつかる」ことのほうが怖いはずなのに、そうではなく、「パパやママが怖い」と受け止めてしまいます。いきなり走り出すことは「危険だからいけない」のではなく、「パパやママが怖い声をあげるから、やらないほうがいいんだ」とインプットされてしまうのです。
交通事故などを防ぐためには、恐怖を与えて学ばせても問題ないかもしれませんが、本来の学びにはなりません。恐怖だけが残り、「なぜやってはいけなかったのか」を学習していないからです。
私も長男が5歳のときに取った行動に対して猛烈に怒ってしまった経験がありますが、15歳になった今、その当時のことを聞くと、「あのとき、ママがものすごく怒っていて怖かった記憶しかない」と話します。
教育の観点からすれば、子どもが冷静になっている状態で叱らないと意味がないのです。
自尊心を傷つける叱り方をする
いくら冷静に叱ったとしても、子どもの自尊心を傷つけるような発言は絶対にNGです。
例えば「とろいんだから」「覚えが悪いわね」などは自尊心を傷つける発言です。
また兄弟姉妹や友達と比べて劣っていることを指摘したり、友達の目の前で叱ったりするのもよくありません。いずれも自尊心を傷つける行為です。絶対に避けましょう。
後から叱る
子どもの脳はまだ発達段階にあるため、その場で叱らないと効果的ではありません。
後から「あのときはこんなことをしていたけど、あんなことをしちゃだめよ」と注意しても、子どもは過去にどんなシチュエーションで、どんな気持ちだったのかを思い出すのが困難なので、なぜいけないのかも理解しにくくなります。
子どもが悪事を働いたり、危険なことをしたりしたら、すぐにその場で叱り、その場で学ばせることが大切です。
子どもにとって効果的な叱り方

「叱る」ということは、子どもに学びの機会を提供する必要な場面です。よって、より効果的に叱ることで、子どもの学びと成長につながるでしょう。そこで、子どもにとって効果的な叱り方をご紹介します。
冷静に説明する
先ほどもお伝えしましたが、感情をぶつけて「怒る」のではなく、とにかく冷静になることが大事です。怒りがこみあげてきても、ぐっとこらえて冷静に伝えるようにすることで、子どもは学びやすくなります。
「性格」ではなく「行動」に焦点を当てて指摘する
自尊心を傷つけないための対策として、子どもの「性格」ではなく「行動」に焦点を当てて指摘しましょう。
例えば子どもが危ない場所で走り回ったとしたら、「どこでも走り回る悪い子ね!」ではなく「危ないところで走り回ったらだめ!」と「走り回った」行動自体を取り上げて叱ります。
これによって、自尊心を傷つけず、子どもは「走り回る」という行動を正せばよいんだと認識するようになります。
子どもの気持ちに共感する
まずは子どもの気持ちに共感して、その後で叱るようにすると効果的です。
うちの長男は幼少期、言葉で伝えるのが苦手で、すぐに手が出てしまうタイプでした。時には友達のおもちゃをうばいとってしまったこともありました。
そんなときには、いきなり「ダメだよ!」と叱るのではなく、いったん子どもの気持ちに共感してあげるようにしていました。「イライラしたんだね」などと言葉にして共感してあげると、長男の気持ちが落ち着くのがわかるのです。
そうして落ち着いた後に「してはいけない」ということを伝えると、聞き入れやすくなるように感じました。
一貫性を持って叱る
そのときの気分によって叱り方が変わってしまうことはありませんか?
例えば、スーパーの駐車場で子どもが走り回ったときに「今日は車が停まっていないから走っていいけど、車が多い日は走っちゃだめよ」というのはNGです。それでは「駐車場は危ないから走ってはいけない」ということの学びにならないからです。
一貫性を持って叱ることが大事です。
《まとめ》つい怒ってしまう親の予防策
幼児期の子育てはやるべきことも多く、寝不足になりがちで余裕がないこともあり、感情的になってしまうこともあるでしょう。冷静になるといっても、我慢できないときもあるはずです。そんな自分に気づいたときは、自分を満たしてあげることも大切です。
海外の親を見ていると、日本の親は子どもに自分のすべてを捧げ尽くしているなと感じます。そのため、感情のアップダウンは、すべて子どもが原因になってしまうのです。きちんと休息と睡眠をとるなど、たまには自分を満たしてあげましょう。
つい怒ってしまったときは、後で「あのときは言い過ぎたかも。ごめんね」と素直に謝って子どもとの信頼関係を築くのも大切ですよ。
自分自身の「叱る」と「怒る」のすみわけをうまく行って、子どもの学びと成長を一緒に喜べる日が来るとよいですね。
シリコンバレー式『世界一の子育て』
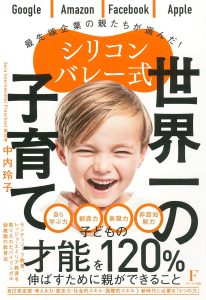
記事監修

構成・文/石原亜香利





