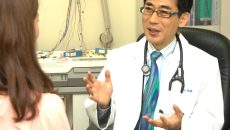小学校の算数は得意でも、中学に入って数学でつまずく子は少なくありません。 その背景には、“計算力”と“考える力”の違いがあります。今回は小学生のうちから身につけておきたい「数学的思考力」の育て方についてご紹介します。

「算数はできるのに数学が苦手」の理由
「算数は得意だったのに、数学になると急につまずく」そのような経験をする子どもは少なくありません。
この理由は、算数と数学で求められる力に違いがあるためです。
算数では「正確に計算し、正解を出す力」が重要視されます。四則計算や繰り上がり・繰り下がりのルールを理解したり、面積の公式などを覚えたりして、順序通り計算すれば正解に辿り着けます。
一方、数学では、「なぜその式になるのか」「どうして解けるのか」といった考える行程や理由を説明する力、つまり「論理的に考える力」が求められます。
小学生のうちから、早く正確に計算する「計算力」ばかりを伸ばして算数を得意にしていた子は、「考える力」を意識した学びに取り組むことが重要です。中学生になり、計算力だけでは乗り越えられない問題に直面したときに苦手意識がついてしまい、算数と数学の点数にギャップが生まれてしまいます。
苦手やつまずきを乗り越える力について気になる方は、下の記事も参考にしてください。
▼関連記事はこちら
小学生のうちに育てたい「考える力」
では、小学生の頃から考える力を育てるには、どのようなことを意識すればよいでしょうか? 具体的な取り組み方について紹介します。
「どうして?」を問いかける
問題を解くときには「なぜその式になるの?」「他の解き方はある?」と問いかける習慣をつけることが大切です。
文章問題では、ひとつの答えにたどり着く方法が複数ある場合もあります。それぞれの解き方を比較しながら、よりスマートな解法はどちらか、思考力を育てるトレーニングにもつながります。
お子さん自身が自分で問いかける習慣を身に付けられることがベストですが、初めのうちは、おうちの方が「どうしてそう考えたの?」と思考を深める声掛けをしてあげるとよいでしょう。
思考力を育てるには、スピードよりも「じっくり考える姿勢」を大切にし、ひとつの問題に時間をかけて取り組むことが大切です。

図や表で内容を整理する
条件が複雑な問題や文章が長い問題を考えるときには、図や表で内容を整理する習慣を付けておくとよいでしょう。
社会人でも「あの人は頭が良いな」と思う人は、複雑な会議の内容の要点を絞って、図や表にわかりやすく整理することに長けている方が多いでしょう。問題を考えるときに、ノートの空いたスペースに図や表をさっと描けるようになると、問題の要点や、答えるべきポイントを明確に整理して考えられるようになります。
小学生の頃から「まず、図や表にしてみよう」などと意識すると、中学以降の学習にも役立ちます。
考える力を育てる教材を利用する
学習を進める際に「考える力を育てる教材」を上手く利用する方法も有効です。
例えば、小学館「ポケモンパズルドリル 論理たっぷり編」のような教材があります。この教材は、ポケモンの世界観を活かしたクイズや迷路などで楽しく問題を解きながら、思考力を伸ばすことができる内容になっています。算数=計算ドリルだけではなく、様々な教材に目を向けてみましょう。
またRISUでは、小学生が“数学的思考力”を育めるよう、「数学コース」を設けています。基礎はもちろんのこと、代数・図形・統計など、興味のある分野を選び、自分のペースで数学的思考力を育むことができる構成です。
▼RISUの「数学コース」について詳しくはこちら≪
数学的思考力があると将来どう役立つ?
数学的思考力を育てておくことは、中学以降の数学だけでなく、他の教科や進路選択にも良い影響があります。
例えば、「数学的思考力=論理的に考える力」があれば文章の構造を整理しながら読み解く力が育ち、応用問題や記述問題に対応しやすくなります。
また高校での進路、文理選択をする際に、なかには「数学が苦手だから」というネガティブな理由で文系を選ぶ子も多いですが、数学が得意であれば自信を持って理系を選択することができます。
さらに、理系分野が得意であることは、将来の職業選択にも有利に働きます。
▼関連記事はこちら
まとめ
今回は、算数から数学でつまずかないための小学生期の学び方についてご紹介しました。
中学以降のつまずきを防ぐには、小学生のうちから「考える力」を育てておくことがカギとなります。 難しい内容を詰め込む必要はなく、「なぜ?」「どうして?」を楽しむ姿勢が、未来の学びにつながるのです。
こちらの記事もおすすめ
記事執筆

京都大学大学院エネルギー科学研究科修了。ユーザー行動調査・デジタルマーケティングのbeBitにて国内コンサルティング統括責任者を経験後、2014年、RISU Japan株式会社を設立。小学生の算数のタブレット学習教材で、延べ30億件のデータを収集し、より学習効果の高いカリキュラムを考案。国内はもちろん、シリコンバレーのスクール等からも算数やAI指導のオファーが殺到している。HugKumでの過去の記事はこちら≫
〈タブレット教材「RISU算数」とは〉
「RISU算数」はひとりひとりの学習データを分析し、最適な問題を出題するタブレット教材。タイミングの良い復習や、つまずいた際には動画での解説の配信を行うことにより、苦手を克服し得意を伸ばします。
期間限定のお試しキャンペーンはこちら>>
『小学生30億件の学習データからわかった 算数日本一の子ども30人を生み出した究極の勉強法』
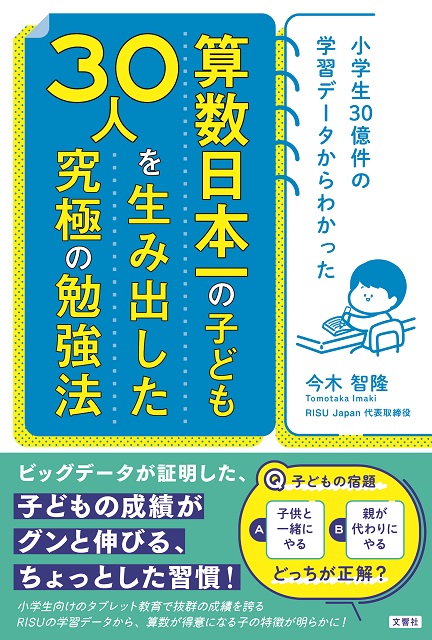
構成/HugKum編集部 協力/RISU