
立体図形は、小学生が苦手を感じやすい単元の一つです。特に「見えない面がわからない」「展開図がイメージできない」といった声もよく聞かれます。今回は、立体図形をスムーズに理解するための学び方や、家庭でできるサポートをご紹介します。
▼小学生がつまずきやすい他の単元については、こちらの記事を
なぜ立体図形が苦手になりやすい?
立体図形は多くの子どもがつまずきやすい単元です。その理由には主に3つの背景があります。
① 平面から立体を「イメージする力」が足りない
展開図や複雑な図形を考えるには、頭の中で立体を思い浮かべる力「空間認識力」が必要です。そのため、教科書などの紙面だけではイメージが湧かず、答えを導くのが難しくなります。
実際に積み木のような立体に触れた経験があるかないかで、単元の理解度に大きな差が出ます。
② 用語や公式を「なんとなく」覚えている
立体図形の問題には、様々な用語と公式が登場します。たとえば、角と頂点など似た場所を指しながら全く意味が違う言葉があります。
用語の意味をあいまいに覚えたままでは、問題文の理解に時間がかかってしまいます。また、公式も暗記だけでは応用が利かず、手が止まってしまいます。
③ 図形の特徴を「言葉で説明できない」
図形の定義や特徴を言語化できていない子どもは、見た目だけで判断しがちです。たとえば「正三角形かどうか」を調べるとき、3辺の長さがすべて等しいという特徴を理解していないと、定規で測るという発想が出ず、「なんとなく正三角形っぽい」と視覚に頼ってしまいます。
また、定義や特徴を言語化できていない場合、単位(cm、㎠、°など)の使い方も不十分な傾向があります。
3つのつまずきポイント別・理解のヒント

では、これら3つのつまずきポイントに対処するための方法をお伝えします。
①「イメージする力が足りない」に対処するには
立体図形の理解に欠かせない空間認識力が欠かせません。この力を育てるためには、手で立体を作る経験を増やすのが効果的です。
たとえば、お菓子の空き箱などを使用し、どの辺を切ったらどんな形に展開されるか、開いたりまた組み立てたりして観察します。円柱や円錐、三角錐など難しい形にも挑戦しましょう。
また、積み木を積んで、上や横から見るのもおすすめです。見えない場所に積み木がいくつ隠れているかなど想像して数えることで空間をイメージする力が自然と育ちます。
②「用語の意味があいまい」に対処するには
教科書に出てくる用語は、実物と照らし合わせながら理解するのが効果的です。実際に立方体を手に取り確かめながら、言葉と意味をつなげる工夫をしていきます。「辺や頂点はどこを指しているのか?」「垂直な面とはどのような状態?」など、立体図形の問題に出てくる用語の意味をイメージできるようにしましょう。
例として、似ているようで意味の異なる用語をいくつか挙げてみます。
- 角と頂点
- 辺と面
- 直角と垂直
- 半径と直径
- 線対称と点対称
- 合同と相似
それぞれの意味をしっかり理解できているか確認してみましょう。
③「図形の特徴を言語化できない」に対処するには
図形を理解するには、その性質を言葉で説明できることが大切です。まずは図形の性質を整理し、実際にそうなっているか辺や角を測って確かめます。
たとえば、「三角形は直線3本で囲まれた図形」のように大人から見れば当たり前に思う図形の定義でも、子どもにとっては初めて学ぶことです。作図をして言葉と図形を一致させることで、より理解が深まります。
さらに三角形や台形の面積を求める公式は、図形の性質をもとに成り立っています。図形の性質を言語化し、しっかり理解できていれば、なぜ公式を使ってよいのかがわかるようになります。より応用的な問題にも対処できるようになります。
学年別の図形対策

ここからは、図形問題の対策方法を学年別に解説していきます。
幼児期
幼児期は、図形にたくさん触れて直感的・視覚的に理解していくことが大切です。遊びの延長で図形に親しめるような環境づくりを心掛けましょう。
たとえば、次のような遊びが効果的です。
- 折り紙・切り紙
- お絵描き
- 積み木・ブロック・立体パズル
- 空き箱工作
低学年
低学年は、感覚的な理解から具体的な理解へと移行していく時期になります。1年生・2年生では、辺・頂点といった用語を学んだり、三角形・四角形などの基本的な形を見分けたりします。ものの大きさや長さを比べながら、イメージ力を育てることがポイントです。
図形の学習が本格化するのは3年生からです。
- 二等辺三角形・正三角形・円・球など、より具体的な図形の性質
- コンパスや三角定規の活用
- 円や直線
- 角度の概念
図形の性質を理解し、基本的な作図ができるようにしておきましょう。正しい方法で何度も作図することで、自然とコンパスや三角定規に慣れることができます。

高学年
高学年では、図形問題がより抽象的になります。そのため、図形をイメージしたり、言語化したりする力がより一層必要になります。
4年生になると、面積を求める学習が始まります。計算力も大切ですが、「なぜこの公式を使うのか?」を理解することが重要です。
5年生と6年生では、立体図形の展開図、体積の計算、図形の拡大・縮小など、さらに複雑な内容を学びます。
これまでの知識を活用しながら計算する内容が中心ですので、4年生までに積み重ねた知識を思い出しながら進めていきましょう。もし、わからない・難しいと感じたときは、思い切って前の学年の内容までさかのぼって復習をすることが大切です。
[まとめ]ふだんから立体感覚を養う工夫を
今回は、立体図形の苦手を克服するための対策方法をご紹介しました。立体図形は、「見る・触る・作る」体験をたくさんすることで、理解しやすくなる分野です。 家庭でも楽しみながら学べる工夫を取り入れて、空間認識力と図形感覚を育てましょう。
こちらの記事もおすすめ
記事執筆

京都大学大学院エネルギー科学研究科修了。ユーザー行動調査・デジタルマーケティングのbeBitにて国内コンサルティング統括責任者を経験後、2014年、RISU Japan株式会社を設立。小学生の算数のタブレット学習教材で、延べ30億件のデータを収集し、より学習効果の高いカリキュラムを考案。国内はもちろん、シリコンバレーのスクール等からも算数やAI指導のオファーが殺到している。HugKumでの過去の記事はこちら≫
〈タブレット教材「RISU算数」とは〉
「RISU算数」はひとりひとりの学習データを分析し、最適な問題を出題するタブレット教材。タイミングの良い復習や、つまずいた際には動画での解説の配信を行うことにより、苦手を克服し得意を伸ばします。
期間限定のお試しキャンペーンはこちら>>
『小学生30億件の学習データからわかった 算数日本一の子ども30人を生み出した究極の勉強法』
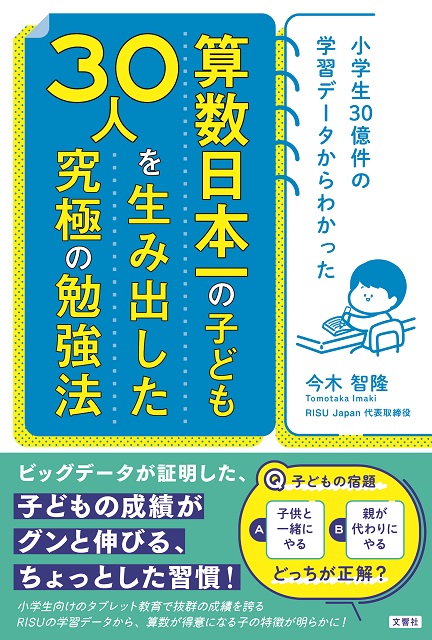
構成/HugKum編集部 協力/RISU








