目次
適度な負荷がかかることで計算力が上がる!『リ:チェント』/Gakken【応用編】

今回の応用編は初級編に比べてカードの枚数が増えたり、ゲーム性がプラスされ論理的思考が育ったりと、レベルアップしたゲームをご紹介します。学校で勉強をすぐに生かした遊び方もあるので、学習の復習にもよさそうです。
『チェント(CENTO)』は、イタリア語で「100」という意味で、世界的に活躍するパズル作家・稲葉直貴氏の名作ゲーム。その『チェント』を増補改訂したのが『リ:チェント』です。算数で習う「100までの数」「たし算・ひき算」「かけ算・わり算」をテーマにした3つのゲームが楽しめます。
今回紹介するおすすめの遊び方は「たし算・ひき算ゲーム」。
1~30の30枚のカードを用意して中央に裏返しに置き、山札にします。
ここから6枚とって山札の周りに表にして並べます。これを場札と言います。
山札の上からカードを1枚とって表にして置き、プレイヤーは場札を足したり引いたりしながらお題の数になる計算式を考えます。
場札は何枚使ってもOKで、使った場札の枚数とお題のカードの枚数が得点になります。


吉田先生「1から100までが全部あるカードって、意外と特殊でなかなかないんです。通常カードゲームの数字カードは30枚とか40枚が多いんですが、これは1から100までが1枚ずつあるんですよね。30枚に慣れたら、カードを100まで並べてみて、二けたの計算にするといいトレーニングになります。
子どもたちはわりと『札の数字を得点にしたい』などとルールを変えたがります。ルールを『やってみよっか』って自分たちなりにどんどん変えられるのもカードゲームの醍醐味です」
文章題が苦手な子のトレーニングにもなる
吉田先生「計算ドリルのようにきれいに計算式が並べられていると解けるけど、文章題になるとキャパオーバーになっちゃうような子は、こういったカードでの計算も苦手な子が多いです。そういう意味でもカードで計算することでより柔軟にできるようになります。
たし算ひき算だけでなく、お題より大きい数や約数、倍数のカードを連続で出せる遊び方もあるんですが、これはより上級者の子たち向き。学校で覚えたきたばかりの知識を駆使して、なかなか割り切れない素数のカードを出してみたり、いろいろな知識を組み合わせてコンボしていく爽快感も味わえます。ここまで楽しめるのはやはり1~100までのカードがあればこそ。これもこのカードゲームのよさですね」

論理的思考も育つ! 数当てゲーム『アルゴ プラス 』/Gakken【応用編】

算数のカードゲームというと一番先に名前が挙がることが多い、算数好きには有名なゲーム『アルゴ』が進化したのが『アルゴ プラス』。今回はベーシックなアルゴの遊び方で、ふせてある対戦相手のカードの数字を推理します。
一番単純なルールで進めます。
0~11までそろった黒と銀のカードを混ぜて各プレイヤーに4枚ずつ配り、残った分は山札にします。
プレイヤーは配られたカードを自分から見て左から右に数字が大きくなるように並べます。
黒と銀で同じ数字の場合は黒のほうが小さくなります。
隠された数を当て合って、相手のカードを全部当てることができたら終了。
吉田先生「僕自身がカードゲームをやるようになったきっかけがこの『アルゴ』でした。遊び方を細かく説明すると、まず自分の数字を確認して、相手が何を持っているのかを予想します。そして相手が持っているカードに対して「アタック『3』」などと予想した数字を伝えます。
数字が当たっていれば、相手はその場でそのカードをオープンに。もし外れれば自分のカードを表にして自陣に置きます。置き場所は左から右に大きくなるように決まっているので、オープンになった数字の置き場所により、ほかのカードがそれより大きい数なのか、小さい数なのかがわかるわけです」

数字だけでなく論理的な推理も楽しめる
吉田先生「カードを当てるためには、相手がどの数字を言ったかも大事。前提として同じカードは存在しないので、相手が自分にアタックしてくる場合、相手自身が持っているカードはアタックするはずがない。ここは7でもあり得るのに8って言ったってことは相手は7持ってるんだな、など論理的にも推理できるんです。
このゲームの魅力は相手の数字を推理する人狼ゲーム的な思考や連続して当てられるところ、揃った時の爽快感があるっていうのもありますね。数当てゲームでは完成形なんじゃないかなって思うぐらいのゲームです。
この『アルゴ プラス』はジョーカーが使えるようになっていたり、色のカードも増えて、アルゴで遊び慣れている人も新しい楽しみ方ができるようになっています」

【最新作】吉田先生考案ゲーム『クリア立体カード』は図形の勉強に役立つ
取材の最後に、先生が新しく監修したカードゲームを紹介してくれました。それが『クリア立体カード』。

吉田先生「クリア素材に立体図が書かれていて、平面で積み木が積めるんです。形遊びができるうえ、ゲームシートがついていてサイコロを振って出た数によって、作る形を決めたり、立体を倒した図を再現する遊びも。早く作れたほうが勝ちです。
子どものなかにはペーパー問題になると図形でつまづく子が多いんですね。紙の問題をブロックなど実物で考えることももちろん大切なんですけど、実物だけだと乗り越えられない子もいて、平面で立体を操作できたら解決するのではないかと作りました。
また、積み木だと奥に隠れている図形がわかりにくいですが、これは奥の図形が透けて見えるのでわかりやすくなっています」
現場を知っているからこそリアルな需要にこたえた。中学受験にも役立ちそうなゲーム。実際に子どもたちに教える中であったらいいなを形にしたそうで、ありそうでなかった教材です。

カードゲームを選ぶ際はQRコードをチェック!
授業で習ってきたことも、ドリルで復習するよりはカードゲームで意識しないままで復習できているほうが、子どもも楽しく学べそう。また、数字でここまで遊べることがわかれば、たとえ算数嫌いの子どもでも「算数って楽しいかも?」と意識が変わりそうです。
今回は初級編の記事とあわせて、この応用編と全部で4つのカードゲームをご紹介しましたが、世の中には本当にたくさんのカードゲームはあります。そこで、カードゲームを選ぶ際のコツを吉田先生に聞いてみると・・・。
「残念ながらパッケージを見るだけでは情報量も少なく、どんなゲームかわかりにくいと思います。お店で購入する際は、最近は箱にORコードがついていることが多いので、そこから遊び方などを見て選ぶのがおすすめです。Amazonなどで買う際も、同様に動画が掲載されていることが多いのでぜひチェックして選んでください」と、ちょっとしたコツを教えてくれました。
この年末年始、家族で一緒にカードゲームで盛り上がってみるのはどうでしょう。
〈低学年・初級編〉の算数カードゲームについてはこちら

記事監修
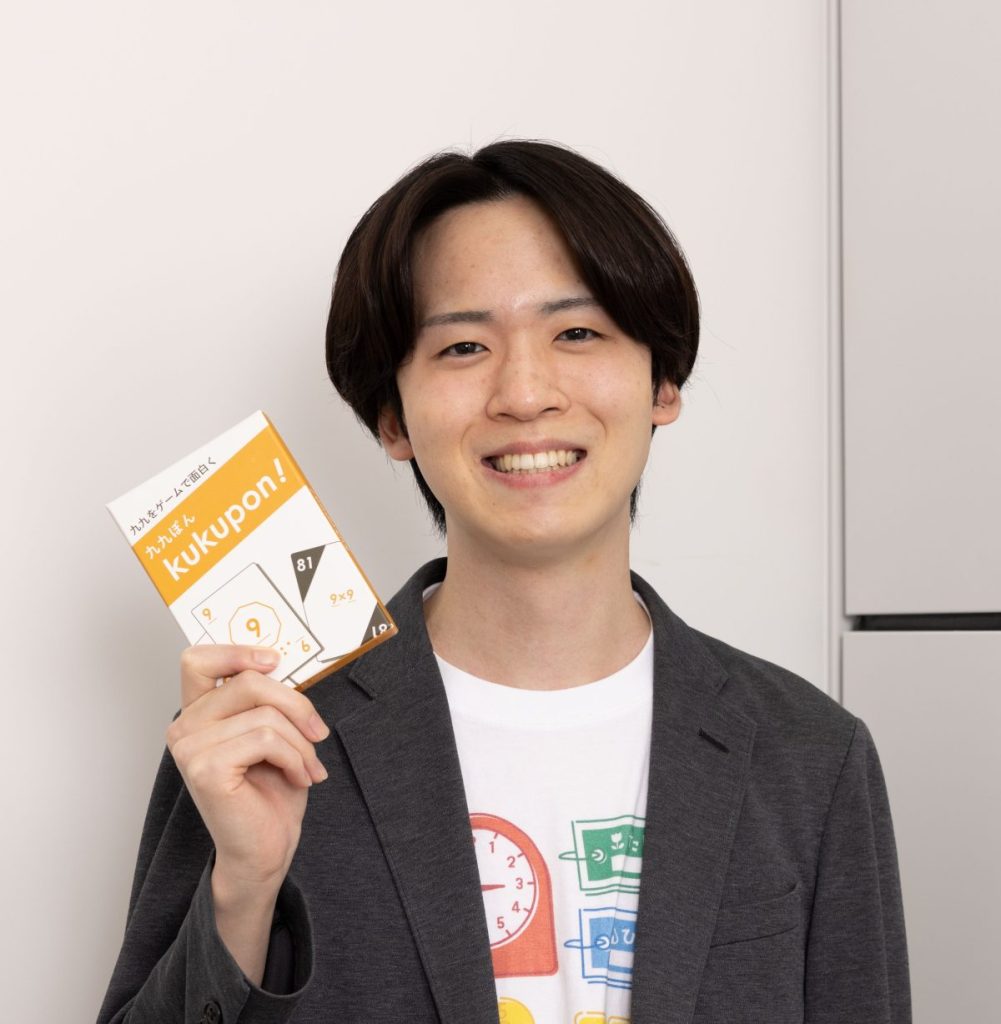
公式X(旧Twitter)https://x.com/shinya_workshop
math channel のホームページ https://mathchannel.jp/
math channelのYouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@mathchanneltv





