目次
憲法の「勤労の義務」とはどういう意味?
憲法の「勤労の義務」とはどういう意味か見ていきます。言葉のまま受け取って「全ての国民は働かなければならない」と考えるべきなのでしょうか。国民の三大義務とあわせて確かめます。
憲法に定められた「国民の三大義務」の1つ
憲法で定められた国民の三大義務とは、教育の義務・勤労の義務・納税の義務のことです。憲法に書かれた内容は次の通りです。
・第26条第2項:「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」
・憲法第27条:「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」
・憲法第30条:「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」
憲法の「勤労の義務」について語られる場合、根拠はこの文面にあります。
出典:日本国憲法 第26条第2項、第27条、第30条 | e-Gov 法令検索
勤労を強制するものではない
勤労の義務と聞くと、「全ての人は働かなければならない」と解釈する人もいます。しかし、憲法第18条には「奴隷的拘束の禁止」が、労働基準法第5条にも「強制労働の禁止」が明記されています。つまり、強制労働は憲法違反であり、労働基準法違反でもあるわけです。
また、不労所得で生活している人もいますが、憲法違反として罪に問われることはありません。勤労の義務は「義務」という表現を使っても、法的な力で労働を強制するものではないといえます。
出典:日本国憲法 | e-Gov 法令検索 第18条|日本国憲法
:労働基準法 | e-Gov 法令検索 第5条|労働基準法
国の指針または国民のあるべき姿を示したもの
そもそも憲法とは、国家権力が国民の自由と権利を侵害しないようにするための決まりです。つまり、国民が国を縛るものであり、基本的には国が国民を縛るものではありません。
この前提と、強制労働が憲法違反であることを合わせると、勤労の義務は「働けるのに働かない人を国が保護する必要はない」「働けるなら自分で生活費を稼ぐべき」という意味だと考えられます。
働く能力はあっても働く意志を見せない人が生活保護を受けられないのも、勤労の義務の考え方に基づいています。
出典:保護の要件(稼動能力の活用)の在り方について|厚生労働省
専業主婦・主夫は「働いていない」のか?

専業主婦・主夫の中には、周りから「働いていない」と言われたり、外で働いていないことに後ろめたさを感じたりして肩身の狭い思いをしている人もいるようです。
専業主婦・主夫の無償労働や、専業主婦・主夫とニートの違いについて解説します。
家事や育児・介護は無償のケア労働
「勤労」の辞書的な意味は、賃金をもらって働くことです。専業主婦・主夫が「働いていない」とは、賃金をもらっていないという意味でしょう。
家の中で行う家事や育児・介護などは「無償労働」と呼ばれます。無償労働は、家庭や社会を支える重要な労働でありながら、経済学において低い評価を受けてきました。
内閣府は1997年から、無償労働の社会的コストを可視化するため、無償労働の貨幣評価を発表しています。家の外で家事や育児と同じような仕事に就けば十分稼げるという事実は、無償労働も立派な労働であることを意味します。
専業主婦・主夫とニートの違い
厚生労働省によれば、「ニートとは15~34歳の非労働力(仕事をしていない、また失業者として求職活動をしていない者)のうち、主に通学でも、主に家事でもない独身者」を指します。
つまり、学校に通っている学生や家事に従事している人はニートではありません。
一方、専業主婦・主夫は家の外で働いていないため、外で働いている人から「楽で暇な立場」としばしば誤解されます。また、世間的には「ニートは社会で賃金をもらわない人」というイメージがあります。
しかし、専業主婦・主夫は家事や育児など家庭の仕事をしている点で、ニートとは違う存在です。
扶養される主婦・主夫を取り巻く制度が変わろうとしている
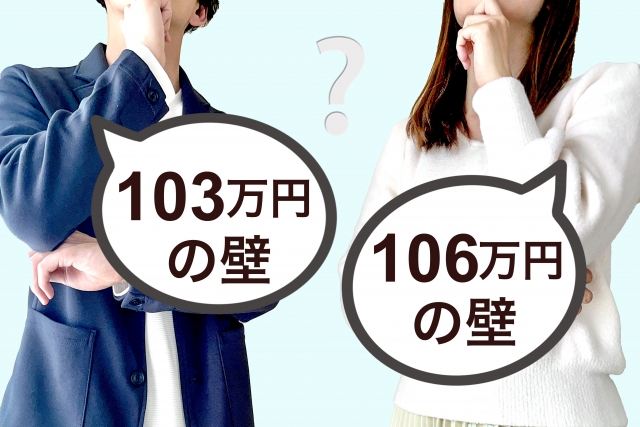
家事や育児などの無償労働に専念している人や、パートタイムで働いている主婦・主夫に関わる制度が、今後大きく変わるかもしれません。制度改革が実行されたとき、扶養される主婦・主夫にどのような影響があるのかも説明します。
第3号被保険者制度の廃止・縮小が議論されている
社会保険の分類で、会社員や公務員などの配偶者に扶養されている、20歳~60歳未満の主婦・主夫は「第3号被保険者」になります(年収が130万円未満、かつ配偶者の年収の1/2未満が条件)。
現在、第3号被保険者は社会保険料を納めなくても、老後に年金をもらえる仕組みです。第3号被保険者制度の見直しは以前から議論されてきました。
2011年12月に開かれた厚生労働省の社会保障審議会では、基本的に「短時間労働者への厚生年金の適用拡大」「配偶者控除の見直し」の方向性で見直しが進められています。
2022年10月からは従業員数101~500人、2024年10月からは従業員51~100人の企業で働くパート・アルバイトに社会保険が適用され、実質的に第3号被保険者制度は縮小されています。
出典:た行 第3号被保険者|日本年金機構
:第3号被保険者制度についてp18|厚生労働省
:事業主のみなさまへ 社会保険適用拡大ガイドブックp1、3|厚生労働省・日本年金機構
第3号被保険者制度の廃止・縮小のメリット・デメリット
第3号被保険者制度が廃止または縮小された場合、第3号被保険者から外れた人は自分で「国民年金保険料」「国民健康保険料」を払う形になります。デメリットは、「国民年金保険料」「国民健康保険料」の分だけ家計の負担が増えることです。
メリットは、今まで健康保険・厚生年金への加入義務が生じていた「年収106万円の壁」がなくなることです。「年収106万円の壁」を理由に働き控えしていた人にとっては、より長時間働けるようになります。年収がアップすれば将来受け取れる年金金額も増えるでしょう。
「年収103万円の壁」を引き上げる動きが出ている
2024年10月27日の衆議院議員総選挙で、国民民主党が打ち出した「103万円の壁をなくす」という政策が実現しようとしています。
103万円とは、給与所得控除額55万円と所得税の基礎控除額48万円を合わせた金額のことです。年収が103万円を超えると所得税がかかり、パートで働く主婦などの場合は配偶者控除が受けられなくなるため「103万円の壁」と呼ばれるものです。
国民民主党は、103万円から178万円へ引き上げることを主張していましたが、与党の自民党は123万円を主張して折り合わず、引き上げ金額はまだ不明です。(2025年2月現在)
出典:No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか|国税庁
「年収103万の壁」を引き上げた場合のメリット・デメリット
「年収103万の壁」を引き上げた場合、年収103万円以上働いても所得税が発生しません。パートタイムの主婦・主夫であれば、年収103万円を気にせずに、今までより多く働けるようになります。
その結果、多くの家庭にとって世帯収入を増やせるのはメリットです。一人のパートがより長い時間働けるということは、その分の労働力が増え人手不足を緩和できるでしょう。
課題は、国や自治体の税収が減る可能性が高いので、減少分をどのように補うかです。また、新しく設定される壁に合わせた個人の年収調整も必要になります。
第3号被保険者制度の廃止・縮小の背景

第3号被保険者制度の廃止・縮小といった見直しの背景には、社会の変化が深く関わっています。少子高齢化による深刻な労働力不足や専業主婦の減少など、原因となる社会変化を紹介します。
「年収の壁」による働き控えと労働力不足
「年収の壁」とは、税金や社会保険料などを払う義務が生じる条件です。例えば、以下のような壁があります。
・100万円の壁:住民税が生じる
・103万円の壁:所得税が生じる・配偶者控除の代わりに配偶者特別控除が適用
・106万円の壁:勤めている企業規模によっては社会保険料の支払いが生じる
手取り額が減らないように、扶養に入っている主婦・主夫の中には年収の壁を超えない範囲で働く人が珍しくありません。
この働き控えは、社会的な労働力不足の一因になっています。
自営業の配偶者や独身者への配慮
会社員・公務員などの配偶者で扶養に入っている人は、第3号被保険者として、社会保険料を支払わなくても老後の年金を約束されています。
第3号被保険者に当てはまらない自営業の配偶者や独身者は、対照的に自分で「国民年金保険料」「国民健康保険料」を支払っています。この構図は、多くの自営業者や独身者にとって不満の原因です。
「会社員・公務員の配偶者だけが働かなくても年金をもらえるのは不公平だ」という不満を解消するため、より公平感のある社会保険制度への見直しが進められています。
専業主婦の減少という社会変化
第3号被保険者制度に関する廃止・縮小の検討は、共働きが増えて専業主婦が少なくなってきた社会的変化も影響しています。
もともと1986年に第3号被保険者制度が始まったのは、収入のない専業主婦が老後資金を得られるようにするための配慮でした。制定された時代は、専業主婦の女性が多かったためです。
近年は女性の社会進出が進み、社会の変化に合わせて保険制度も変えていくべきという考え方が強くなっています。
収入減に備えて今からできること

扶養される主婦・主夫にとって、第3号被保険者制度の廃止・縮小は、年収の減少につながる恐れがあります。収入減に備えて今からできることをチェックしていきましょう。
収入アップの道を探す
収入減対策として、まず世帯年収をアップする方法が考えられます。例えば、家事や子育てと両立しやすい仕事環境には次のような条件が挙げられます。
・在宅ワークや短時間労働が可能
・残業が少なく家族と過ごす時間を確保できる
・子育てしながら働いている人が多い
・通勤する場合も、保育園と勤務地が近い
具体的にどんな仕事でどれだけ働けるのか試算してみましょう。もし子どもがある程度大きくて時間が取れるなら、将来に備えた資格の勉強をするのも一つです。
家計を見直す
生活の支出を見直して節約するのも収入減対策になります。今から老後の暮らしをイメージして、必要な資金をシミュレーションすると貯蓄の目標金額が分かります。
家計のうち、居住費・光熱費・通信費・保険費などの固定費は、節約の見直しポイントです。
固定費は支出の大きな部分を占める上、一度変更すれば簡単に節約できて効果を感じられやすいためです。無理のない範囲で節約・貯蓄計画を検討しましょう。
無償のケア労働も労働のうち
専業主婦・主夫を指して「働いていない」「勤労の義務違反だ」という意見は、「賃金をもらわなければ労働ではない」という考え方からきているようです。
確かに、専業主婦・主夫は賃金をもらっていないものの、家事や育児などを通して家庭や社会を支えています。その点でニートとはいえません。
しかし最近は共働きが増え、専業主婦・主夫を取り巻く制度が変わりつつあります。第3号被保険者制度の見直しや年収の壁に関わる変化を見越して、今後の対策を考えましょう。
こちらの記事もおすすめ

構成・文/HugKum編集部





