目次
子どもの将来に役立つ習い事ってあるの?
「習い事をさせないと子どもを伸ばせないか?」というと、決してそんなことはありません。
今は習い事をたくさんやっている子が多いので、親御さんも「うちも何かやらせなければ…」という前提で考えがちだと思いますが、学校から帰ってきてその子が大好きなことに集中する時間あれば、別に習い事に行かなくてもいいんです。
また、親御さんは”将来役立つ習い事”をさせたいと考えがちですが、子ども本人が好きでもなくやる気も持てないようなものでは時間とお金と労力のムダになるだけです。それに、今は変化の激しい時代なので将来役立つ保証はありません。それよりも、子ども本人の好きを伸ばすことが大切です。
習い事を決める時のポイントは2つ
①子どもをよく観察する(自分から進んでやっていることを応援する)
②お試しでやってみる(やめたくなったら無理に続けることはしない)
「子どもに何をさせるか」と考えるよりも、「子どもが何をしたいのか」をよく観察してあげてください。好きなことは何なのか、何に熱中しているのかをよく観察して、お家でやる以上にやりたいと思っている場合には、習い事としてお教室に通わせるのもいいと思います。

大好きなことに熱中している時、子どもの脳は血流が爆上がりしてドーパミンが大放出します。この状態になると、脳のシナプス(神経回路)をどんどん増やし、それによって脳神経細胞のネットワークが成長し、脳の処理能力が向上します。これが地頭が良くなる仕組みです。
地頭がよくなっていれば、勉強もスイスイ頭に入ります。目先の学力や役に立つかどうかに惑わざれず、今目の前にいるお子さんの姿をよく観察し、好きなことをやらせてあげましょう。
習い事をスタートさせる適したタイミングは?
習い事をスタートさせるタイミングは、いつでもいいと思います。例えば、スポーツの試合を観に行ったことをきっかけに「やってみたい」と言い出すかもしれません。そしたらやってみるという流れで良いと思います。本人がやる気になった時がタイミングなんです。
習い事によっては4月はじまりのコースなどもあるかと思いますが、あまり気にせず、子どもの気持ちを優先してあげてください。

習い事をやめさせる、継続させる…見極めのポイントは?
「やめ癖」という言葉がありますが、私はやめ癖なんてないと思っています。昔は限られた習い事しかありませんでしたが、お父さんお母さんの時代と今とでは環境が違います。自分たちが歩んできた道を子どもにも歩ませるのは通用しない時代なのです。
世間的に”飽きっぽい”と言われるお子さんは、好奇心が旺盛です。いろいろやってみるけど、すぐにやめてしまったりもします。しかし、それはその子の経験(引き出し)が増えるという意味で全く問題ないわけです。いろいろ試す中で、もっとやりたいと思えるものが自然に見つかれば、それを続ければいいのです。
今は、子どもが興味を持ったことのほとんどを体験させてあげることができます。やってみたいことはやらせてみて、子どもの可能性を伸ばしてあげましょう。そして、子どもの人生は子どものもの。やめたくなったらやめさせてあげる、でよいのです。
行き渋りや、やめたい時の対応はどうするのが正解?
ただし、子どもは言葉足らずなこともあり、やめたいわけではないのに「やめたい」という言葉を使うこともあります。
例えば、習い事の先生と合わない、習い事が一緒の友達が合わないなど、習い事をやめたいわけではないのに、「やめたい」と表現する場合があります。ピアノは嫌いじゃないけど、発表会が嫌いなお子さんもいます。これらの場合は、先生を変えたり、曜日や時間を変更する、発表会には出ない、などの選択をするだけで継続することができます。子どもの話によく耳を傾けて、行きたくない原因が何なのかを探ってあげましょう。
「やめたいのに言えない」場合は注意が必要

逆に、やめたいのに「やめたい」と言えないお子さんもいます。特に、早熟脳のお子さんです。
早熟脳のお子さんは、自己管理力があり、人の気持ちを理解する能力に長けています。さらに時間の概念もあり、見通しをつけた行動を取ることができるので忘れ物が少ない傾向にもあります。そういうお子さんの場合、親御さんの気持ちをくみ取り、親の期待に応えたいと思ってしまいがちです。本当はやめたいのに言い出せない、「自分はやめたいとは思っていない」と思い込んでしまうことさえあります。
ある日燃え尽き症候群になった女の子
私がいた学校に、何でもできて習い事もたくさんしている女の子がいましたが、4年生の時に突然燃え尽き症候群になってしまいました。学校にも来られなくなり、自傷行為をしてしまったり…。それで、心療内科に通うようになって、医師から「この子はやりたくないことを一生懸命やってきたんですね」と言われて、親御さんは驚いたんです。今まで習い事の準備も自分でやって、一度も休みたいとも言ったこともなかった。でも、お子さんの心はすっかり疲れきってしまっていたんですよね。
共働きのご家庭は、学童の代わりに習い事をいくつもせるご家庭もあると思います。その場合でも、子どもの様子をよく観察してあげることが大切です。毎日習い事をしていても元気で楽しそうなお子さんもいれば、ゆっくりする時間が必要なお子さんもいます。子どもが疲れていないか、心から楽しんでいるのかを観察してあげてください。
才能があることと”好き”は一致しない?
子どもの大好きなことが見つかった場合でも、「本当にこれがうちの子に合っているものなのか」「他にもっと合っているものがあるのではないか」と、心配する親御さんがいらっしゃいます。それでも、”子どもの好きを応援すること”が重要です。
本人が好きでやっていて、能力的にも向いている場合は問題ありませんが、好きだけど結果が出ない場合は、親御さんが心配してしまうこともあります。それでも、好きで楽しそうなら続けさせてあげてください。

逆に、結果を出していても、本人が好きじゃない場合もあります。
私が勤務していた学校に、とても走るのが早い女の子がいました。いろんな大会に出場し、数々のメダルや賞状をもらっていたんですが、中学に入って突然「本当は走るの好きじゃなかった」と言って吹奏楽部に入り、走るのを一切やめてしまいました。
このように、周りから見ても才能があるのに、本人は好きではないこともあります。そういう時は、もったいないと思っても子どもの気持ちを尊重してあげましょう。
家にいたらゲームや動画ばかり?
家にいるとゲームや動画を観てばかりいるので、だったら習い事をさせる、というご家庭もあるかと思います。その場合でも、ゲームや動画と同じくらい夢中になれる習い事であることがポイントです。
ゲームや動画を一概に悪いとも言えないんですよね。それらに熱中しているようであれば、どんなゲームをやっているのか、ぜひ親子で会話をしてください。子どもはゲームの中で目標設定をして、それに向かって研究していたり、努力をして頑張っています。その話を聞いてあげてください。
子どもにとって大事なものを親が一方的に否定していると、子どもは孤独を感じてしまいます。孤独の状態が続くと、依存症になりやすいと言われています。ゲーム依存症にさせないためにも、対立するのではなく褒めたり共感してあげてください。そういう会話の中で、親子の信頼関係は高まっていきます。

共感的で民主主義な会話が大切
とは言え、子どもがハマっていることがゲームや動画ばかりになると心配なこともありますよね。そんな時こそ、共感的で民主主義な会話が大切です。親が勝手に1日の使用時間を決めてしまうと、子どもは「どうせ共感してもらえない」と思います。そう思うようになると、隠し事をしたり、ルールを守らなくなったりします。
そうならないためにも、子どもの希望を聞き、親の考えを話し、お互いが納得できる使い方のルールを話し合いましょう。
あなたにはこちらもおすすめ

お話を聞いたのは
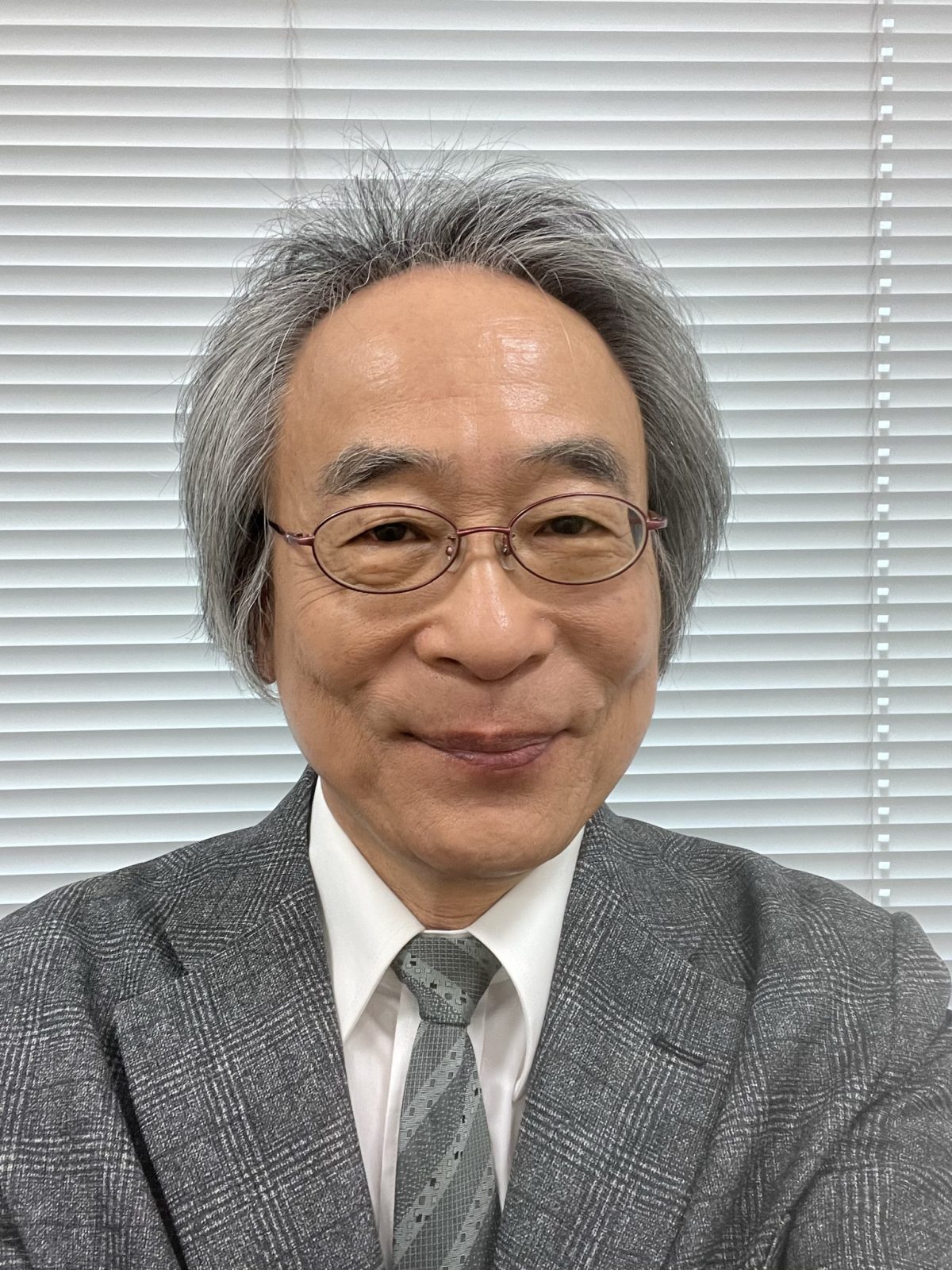
文・構成/鬼石有紀





