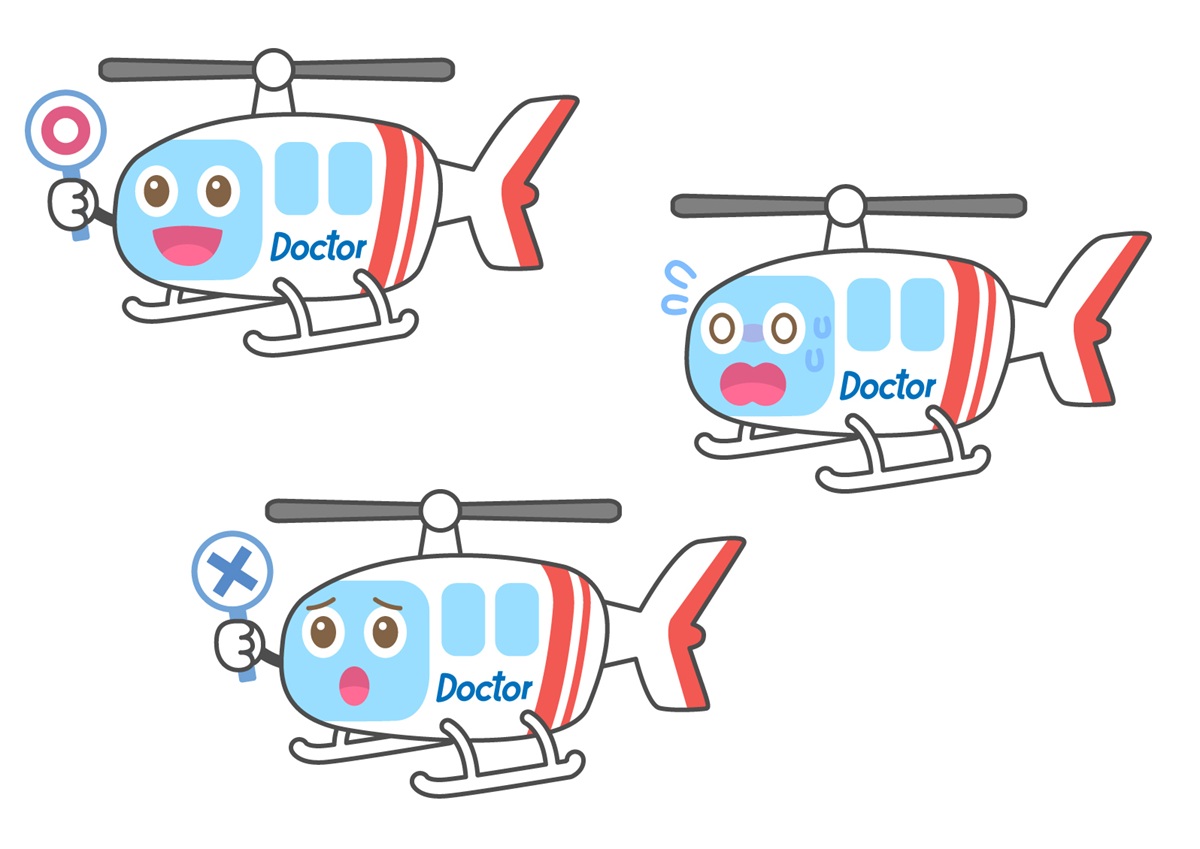過保護は子どもの成長に好ましくない影響を与えると、幾つもの研究が明らかにしています。過保護を自覚する親の存在の多さもHugKumの過去記事で紹介しました。
関連:「妻が子どもに対して過保護」に悩むパパ必見! カギは夫婦間コミュニケーションにあり【家族相談士がアドバイス】
そんな過保護の親を形容して「ヘリコプターペアレント」「カーリングペアレント」なる言葉も生まれているそうです。
そこで今回は、夫婦の悩み相談カウンセラーにして、家族心理学の専門家・家族相談士でもある沢野まもるさんに、ヘリコプターペアレント、カーリングペアレントのセルチェック診断表を作成していただきました。

「ヘリコプターペアレント」や「カーリングペアレント」って何?
自分が、ヘリコプターペアレントやカーリングペアレントに当てはまっていないかどうかチェックする前に、もう一度言葉のおさらいを。
ヘリコプターペアレント、カーリングペアレントとは印象的な言葉ですが、どういった意味の言葉なのでしょうか。沢野さんに聞きました。
「どちらも、過保護な親の関わり方を意味する言葉です。
ヘリコプターペアレントとは、子どもが困った時にすぐに介入し、解決してしまう親。ヘリコプターのようにずっと子どもの上空についていて、子どもに問題が起きるとすぐに降下し、助けるような親の姿を言います。
一方で、カーリングペアレントとは、子どもが困る前に、先回りして障害を取り除こうとする親を意味します。カーリングのストーンの進む先の氷をブラシで熱心にこすって障害を一切取り払ってしまうような親の姿を言います。
結果的に、どちらも、失敗や挫折のチャンス、葛藤する機会を子どもから奪います。
悩みや失敗を経験できない子どもは、心理的にも人間的にも自立できません。その意味で、この手の過保護・過干渉は、子育てにおいてマイナスの影響を与えると考えられます」(沢野さん)
とても、印象的な言葉ではないでしょうか。調べてみるとどちらも、日本で生まれた言葉ではなく海外で生まれた言葉だと分かります。
ヘリコプターペアレント(helicopter parent)という言葉は、Haim Ginott博士の著書『Between Parent & Teenager』(1969年に)の中で紹介され、ティーンエイジャーが親について『ヘリコプターのように自分の上をホバリングしている』と述べた発言に由来するとの話。
カーリングペアレント(curling parent)という言葉は、ヘリコプターペアレントに類似する言葉として、デンマークやスウェーデンなど北欧で使われ始めた言葉とされています。
子どもの独立性を育む立場とは真逆で、子どもの問題解決を学ぶ機会を奪う親の過度な介入を意味します。「あの人そうだ」と、身近な誰かを思い浮かべた人もいるかもしれません。

過保護のセルフチェックリスト
とはいえ、人の過保護はすぐに分かっても、自分の過保護となるとなかなか気づけません。
自分自身が、ヘリコプターペアレントやカーリングペアレントになっていないか、判断するポイントなどはないのでしょうか。その点を沢野さんに聞くと、チェックリスト風にまとめてくださいました。
ここでは、未就学児を持つ保護者向けのチェックリストと、小学生のお子さんを持つ保護者向けのチェックリスト、さらには両者共通のチェックリストを用意してもらいました。
ヘリコプターペアレントもカーリングペアレントも、結局は過保護な親を意味する言葉です。自分が、どちらのタイプかというより、親としてどれくらい過保護かどうかを客観的にチェックするツールとして利用してみてください。
【チェックリスト】基本的な姿勢 (共通)
「はい」「いいえ」 でチェックしてください。
● 子どもが自分でできそうなことでも、うまくできなさそうなら親がやってしま う。
□ はい □ いいえ
● 「子どもが自分で決める」よりも、「親が正しい選択肢を教える」ことが大事だと思う。
□ はい □ いいえ
● 失敗を回避するために、子どもの行動をあれこれ指示することが多い。
□ はい □ いいえ
● 子どもが「自分でやる!」と言っても、子どもが困るのではないかと心配になってしまう。
□ はい □ いいえ
● 子どもが挑戦する前に「まだ無理だからやめておこう」と言ってしまうことが ある。
□ はい □ いいえ
● 子どもが困ったとき、すぐに解決策を提示してしまうことが多い。
□ はい □ いいえ
【チェックリスト】未就学児(3~5歳) 向け
「はい」「いいえ」でチェックしてください。
● ほかの子どもとケンカになりそうになると、すぐ仲裁に入る。
□ はい □ いいえ
● 公園や遊び場で、転びそうな場所に行かないよう先回りして制止する。
□ はい □ いいえ
● 子どもが自分で着替えをしようとすると、時間がかかるので手伝ってしまう。
□ はい □ いいえ
● 子どもが遊んでいるとき、「もっとこうしたら」と遊び方を過剰に指示したことがある。
□ はい □ いいえ
● 遊んでいる最中、子どもが楽しんでいるのを見て「こんな遊び方じゃもったいないよ」と遊び方を変えさせたことがある。
□ はい □ いいえ
【チェックリスト】小学生向け
「はい」「いいえ」でチェックしてください。
● 子どもの学校の持ち物や宿題を毎日チェックし、忘れ物がないように準備する。
□ はい □ いいえ
● 子どもが自由研究や作文に取り組むとき、「こういうテーマがいいんじゃない?」と親が決めてしまう。
□ はい □ いいえ
● 先生や友達とのトラブルが起きたとき、親がすぐに介入して解決しようとする。
□ はい □ いいえ
● 子どもが宿題を始める前に、「間違えないように気をつけてね」と毎回声をかける。
□ はい □ いいえ
● 遠足や運動会の準備を、子どもがやる前に親が先にやってしまう。
□ はい □ いいえ
チェックリストの診断
✅ 「はい」が7個以上 → ヘリコプターペアレント or カーリングペアレントの可能性が極めて高いです。子どもを思う気持ちが強いあまり、自主性を奪ってしまっているかもしれません。「見守る」を意識してみましょう。
✅ 「はい」が4〜6個 → やや過保護傾向あるかもしれません。つい手を出してしまうことがあるかもしれません。子どもの「自分で考える力」を育てる意識を持つといいでしょう。
✅ 「はい」が3個以下 → 自立を促す良いバランスがとれている可能性が高いです。子どもの自主性を尊重しながら適切なサポートができています。この調子で成長を見守りましょう。
過保護の乗り越え方とは

では、最後に、自分の過保護を自覚した時、言い換えると「はい」が多いと明らかになった時、どのように振る舞い、どのように自制すればいいのでしょうか。あるいは、どういったサポートを周りに求めればいいのでしょうか。
沢野さんによれば「大前提として、過保護である自分を責めないでほしいです」との話。
特に女性の場合は、過保護・過干渉の弊害を頭では分かっていながら、どうしても過保護・過干渉になってしまう生理的メカニズム、および社会的な要因が存在するといいます。
関連:「妻が子どもに対して過保護」に悩むパパ必見! カギは夫婦間コミュニケーションにあり【家族相談士がアドバイス】
その仕組みをまずは自分で理解した上で、自分を責めずに、次のような行動を心がけるといいとアドバイスがありました。
「『失敗させてはいけない』『傷ついてほしくない』という強い恐れや不安が、根本的な要因としてあります。子どもの勉強やスポーツの成果にこだわりすぎるなど、自己愛を満たす手段として子どもを捉えている場合もあります。
しかし、その恐れや不安を紛らわそうとしたり、自分のこだわりを抑圧しようとしたりしても効果的ではありません。
まずは、ノートや日記・メモに『今、どんなことで不安や焦りを感じているのか』を書き出してみてください。頭の中でぐるぐるしている不安や焦り、こだわりが可視化されるだけでも心が落ち着きます。
さらに、パートナーが話を聞いてくれる人であれば、自分の不安や恐れをじっくりと聞いてもらってください。
そうしたプロセスを通じて、少し変な言い方ですが、恐れや不安をちゃんと味わってください。恐れや不安を可視化して、正面から向き合えば、恐れや不安は薄らいでいきます。
もし、話を聞いてくれるパートナーがいない、自分一人で扱えないという場合は、カウンセラーのような専門家に話しを聞いてもらう機会も有効です」(沢野さん)
以上、過保護な親を意味するヘリコプターペアレントやカーリングペアレントの意味、セルフチェック表、さらには対策をまとめてみました。
沢野さんいわく、過保護・過干渉は別に珍しい話ではなく、仕方ない面も十分にある様子。自分を責めずに、恐れや不安、こだわりに向き合いたいですね。
お話を伺ったのは

note|夫婦の悩み相談カウンセラー 沢野まもる
こちらの記事もおすすめ

取材・文/坂本正敬
【参考】
・ もしかして、私って『毒親』!? – 合同会社serendipity
・ Helicopter parent – Haim Ginott
・ A Curling Parenting Style Has Its Costs – Common Chord
・ Curling Parents and Middle Aged Children – Schubart