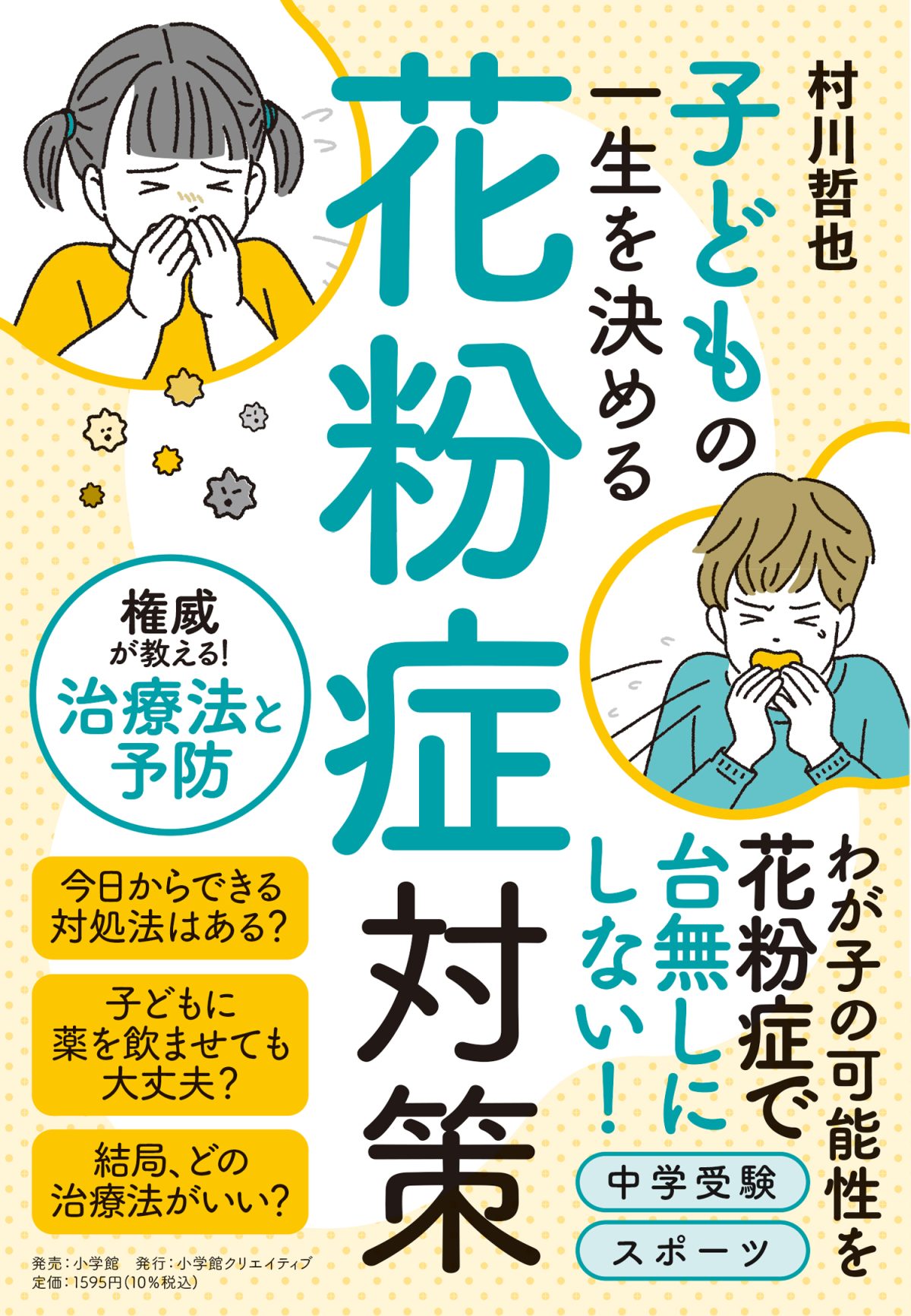※ここからは『子どもの一生を決める花粉症対策』(小学館)の一部から引用・再構成しています。
Q.小さいうちからでも花粉症になるの?
A.2〜3歳で花粉症になることもめずらしくありません。
子どもの花粉症は年々増えていて、スギ花粉症の年齢別の発症率は5〜9歳で30.1%、10〜19歳で49.5%とする調査結果があります。
この調査結果を見ると、19歳以下の半分近くが花粉症にかかっていることになりますし、飛散量が増加傾向にある中で今後、子どもの花粉症患者はどんどん増えていくと考えられます。
生後間もない乳児は外に出ることがあまりなく、浴びる花粉も少ないため、花粉症になることはほとんどありません。
ところが、外に出かけられるようになると、花粉を浴びる機会が増えるため、花粉症を発症するリスクが高くなり、早い子であれば2〜3歳で発症します。
花粉を早いうちからたくさん吸っていると重症化しやすくなります。
たとえば、小学校に上がる前は花粉症ではなかったにもかかわらず、小学校高学年になると重症化して見つかることもあります。
本州、四国、九州の場合、スギ花粉はどこでも飛んでいて、逃がれることはできません。
知らず知らずのうちに花粉症になっており、気づかずに症状が進行していることがあるのです。
花粉症は軽症のうちなら根治できる!
子どもの花粉症で注意が必要なのは、花粉症であることを見過ごされてしまう点です。
スギやヒノキの花粉が飛散する時期は季節の変わり目で、風邪の流行時期と重なります。
そのため、くしゃみや鼻水が出ていたとしても、 「風邪だろう」と親御さんが判断してしまうことがよくあるのです。
さらに、小さいうちは、症状を親御さんに具体的に訴えることもないので、花粉症であるのを見過ごされやすいのです。
花粉症は軽症のうちであれば、比較的短い治療期間で根治することが期待できます。
ところが長年治療も受けないまま花粉を浴び続けると重症化します。
症状が重くなると、花粉シーズンは常に鼻づまりや鼻水、くしゃみが出て、つらい思いをすることになります。
常に鼻がつまっていると、頭がぼーっとして集中力も欠きますし、夜に鼻づまりやくしゃみが出ると、よく眠ることができず、日中に眠気に襲われ、授業をまともに受けられなくなります。
子どもの異変には親御さんが気づいてあげないといけません。特に、春や秋に熱がないのに鼻がつまっていたり、頻繁に目をこすっているなと思ったら、すぐにでも耳鼻咽喉科を受診しましょう。
Q.大人と子どもの花粉症の違いってあるの?
A.出やすい症状が少し異なります。
鼻水、鼻づまり、くしゃみなど基本的な症状は、大人も子どもも変わりはありません。
ただ、大人と違って、子どもは具体的な症状を言葉で訴えることは少なく、目をこする、鼻をやたらにいじるなど、行動面で花粉症特有の不快感をあらわすことが多いです。
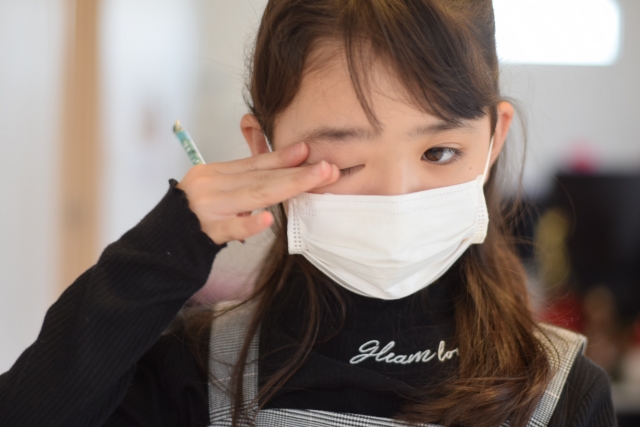
子どもはアレルギー症状が目に出やすく、大人よりもかゆみを感じやすいのが特徴です。
そのため、かゆさをがまんできずに、目を強くこすってしまいます。
目のまわりは皮膚が弱く、デリケートなため、強くこすると赤み、かゆみが余計に強くなり、炎症を起こしてしまいます。
また、目をこすると角膜を傷つけることになるので、視力などにも影響を及ぼします。
子どもがいつもと違う仕草をしていないか、見てあげてください。具体的に、わが子が次のような行動をしていたら、花粉症を疑いましょう。
【目】
●目をかく
●目が赤く充血している
●目をしょぼしょぼさせている
【鼻】
●鼻水がよく出る
●鼻がつまっている
●鼻をよくすする
●鼻でいびきをかく
【口】
●くしゃみを頻繁にする
●口をよく開けている
また、大人の場合、鼻水がサラサラしていることが多いのですが、子どもは粘り気のある鼻水が出ることが多く、くしゃみよりも鼻づまりの方が起こりやすいです。
そのため、口呼吸をするようになり、口を開けて息をしていることが多く見られます。
皮膚からアレルギーになりやすい乳児期は特に注意が必要
さらに、子どものうちは花粉症に限らず、さまざまなアレルギーになりやすいとされています。
特に赤ちゃんの場合は皮膚から入ったアレルゲンによって、アレルギーを引き起こす可能性が高いのが特徴です。
少しでも皮膚に傷がついていると、そこから異物が混入した場合、拒絶反応が出てアレルギー反応を引き起こすことになります。
卵や小麦などの食物アレルギーは、目には見えないサイズの食べこぼしが、皮膚の小さな傷から入ることで起こります。
赤ちゃんはちょっとした刺激で皮膚が傷つきやすく、皮膚バリアがこわれてしまうので、親御さんが注意しなくてはなりません。
食べこぼしは衣服に付着するので、親御さんは食事中もエプロンを着けましょう。
子どもを抱っこするときに自分のエプロンをとれば、衣服にアレルゲンはついていないので、安心して子どもに触れることができます。
食物アレルギーになったうえに、花粉症となると、子どもにとてもつらい思いをさせてしまいます。
できるだけアレルゲンを避ける生活を心がけることが大事です。

Q.花粉症は遺伝が関係しているの?
A.100%ないとはいい切れません。
まだ子どもが発症していなくとも、「自分が花粉症だから子どもも花粉症なのではないか」と不安な方も多いかと思います。
とはいえ、父親や母親が花粉症だからといって、必ずしも子どもが花粉症になるとは限りません。
ただ、両親のどちらかがアレルギー体質だと、子どももアレルギー物質に反応しやすくなります。
そのため、両親のどちらかが花粉症の場合は、子どもも花粉症になりやすい可能性があります。
その一方で、両親が花粉症でなくとも、子どもが花粉症になるケースが多々あります。
「自分が花粉症でないから、子どもも大丈夫」とは思わずに、疑わしき症状が出たら耳鼻咽喉科にかかってほしいと思います。
また、ここまで述べてきたように花粉症の発症や重症化には、遺伝以外に食生活や住環境が大きく関係してきます。まずは、できることから改善していくのが現実的な策になるでしょう。
Q.花粉症は子どものうちに治療したほうがいい?
A.症状が初期であれば早く治せることも見込めるので、早期治療が重要です。
たびたび繰り返して恐縮ですが、わが子を見ていて「花粉症にかかっているかな?」と思ったら、すぐにでも近くの耳鼻咽喉科を受診してください。
というのも、小さいうちから花粉を大量に吸っていると花粉症が重症化するからです。
花粉症は軽症時であれば、くしゃみや鼻水が出ることも少なく、鼻づまりもあまり起こらないので、日常生活に大きな支障をきたすことはありません。
軽症のうちに治療しておけば、治療期間も短く済みます。
ところが、重症化すると頻繁にくしゃみをし、一日中鼻がつまっている状態になります。
花粉症で死ぬことはありませんが、生活の質は確実に下がります。

一日中鼻がつまっていると、呼吸がうまくできないようになり、頭がぼーっとしてしまい、勉強にも身が入りません。小学生は人生に必要なことをたくさん学ぶ時期ですし、鼻づまりで頭がぼーっとしていたら、遊びやスポーツも楽しめません。
また、鼻づまりによって口呼吸をするようになると、多くの悪影響をもたらします。
口から細菌が入ることによって、のどにある扁桃(腺)に炎症が起きやすく、それがさまざまな病気を引き起こすことになります。
そのうえ、口を開けっぱなしにすると口の中が乾燥します。口の中が乾燥すると唾液の分泌量が減ります。唾液には殺菌作用があるため、分泌量が減ると感染症のリスクが高まるのです。
また、虫歯や歯周病にもなりやすく、口に締まりがなくなることで、歯並びも悪くなり、将来の顔立ちにも影響を及ぼすことになります。
何よりも長い間、鼻がつまって苦しい状況が続くのはかわいそうです。今すぐにでも治療を受けさせてあげましょう。
※ここまでは『子どもの一生を決める花粉症対策』(小学館)の一部から引用・再構成しています。
『子どもの一生を決める花粉症対策』(小学館)
本書は花粉症に苦しむ子どもをもつ親御さんに向けた必読の一冊です。上でご紹介した内容のほか、すぐにできる対策から子どもに負担をかけずに根治可能な治療法まで、花粉症治療の名医がわかりやすく解説しています。
■こんな人におすすめ
・花粉症に苦しんでいるわが子の症状をラクにしてあげたい
・自分が花粉症(アレルギー体質)だから、子どもにも同じ症状が出るのではないか、と心配…
・子どもに花粉症らしき症状が出ているものの、治療せずに毎年そのままにしてしまっている
・花粉症治療の「正解」を知りたい
 著者/村川哲也(むらかわ・てつや)
著者/村川哲也(むらかわ・てつや)
医師・医学博士。日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会専門医・日本気管食道科学会認定専門医・日本レーザー医学会専門医。防衛医科大学校卒業後、カリフォルニア大学バークレー校ローレンスバークレー国立研究所勤務などを経て、2007年に喜平橋耳鼻咽喉科を開業、現在に至る。花粉症治療の中でも、特に舌下免疫療法の治療実績は日本有数を誇る。
2025年3月16日(日)、上記書籍の出版を記念して出版講演会が開催されます。講演会では著者の村川哲也先生によるさらに詳しい花粉症対策のほか、衆議院議員・玉木雄一郎さんなどスペシャルゲストとのクロストークも予定。著書を購入した方は無料で参加できます。
詳しくはこちら≪をご覧ください。
こちらの記事もおすすめ

構成/国松薫