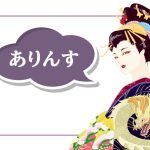江戸時代から使われていた「命の洗濯」という言葉
みなさんにとっての「命の洗濯」って何ですか?のんびりと旅行に行くとか、お風呂に入ってゆったりと湯船に漬かるとか、いろいろでしょう。
「命の洗濯」は、日ごろの苦労から解放されて、寿命がのびると感じるほど思う存分に楽しむことをいいます。最近のことばのようですが、実は江戸時代からある語です。江戸の人だって「命の洗濯」をしたかったのでしょう。
たとえば井原西鶴(いはらさいかく)の浮世草子(うきよぞうし)『好色一代男(こうしょくいちだいおとこ)』(1682年)で、次のように使われています。
「さて今日よりは色里の衣装かさね、これをみる事命のせんだく」(巻七・新町の夕暮れ島原の曙)

「色里の衣装かさね」は、菊の節句(9月9日)に遊郭の高級遊女たちが着物や持ち物などを披露することです。これを見物することが「命の洗濯」だというのです。遊女たちが各自の全盛を競い合った行事でしたから、さぞかし華やかなものだったでしょう。でもそれを「命の洗濯」とまでいうのは、今の時代ではいささか違和感があります。今でしたら「目の保養」くらいでしょうか。
ただ、今ほど娯楽のない江戸時代では、男が「命の洗濯」をするのはどうしても遊郭ということになったのかもしれません。「命の洗濯講(せんだくこう)」などと称して、それぞれが割り前を出し合って講をつくり、遊郭に行くなどということもあったようです。
もちろん、遊郭に行くことだけが「命の洗濯」だったわけではありません。式亭三馬 (しきていさんば)作の髪結床(かみゆいどこ)を舞台にした滑稽本 (こっけいぼん)『浮世床(うきよどこ)』(1813~23年)では、髪結床の弟子の小僧が朝早くから店を開けさせた隠居にこんなことを言っています。
「隠居さんこそ寐倦(ねあき)なはるから、夜の明(あけ)るのを待兼(まちかね)なはるけれど、わっちらは寐たうちばかりが命の洗濯だア」(初編・上)
「ねあきる」はいやになるほど寝るということで、年寄りの隠居に朝早くから起こされたことに文句を言っているのです。寝るのが「命の洗濯」と言っていますが、小僧の気持ちもよくわかります。小僧からこのように言われた隠居は、「命の洗濯よりもふんどしの洗濯をしろ」などとやり返していますが。
「洗濯」は古くは「せんだく」と発音されていた
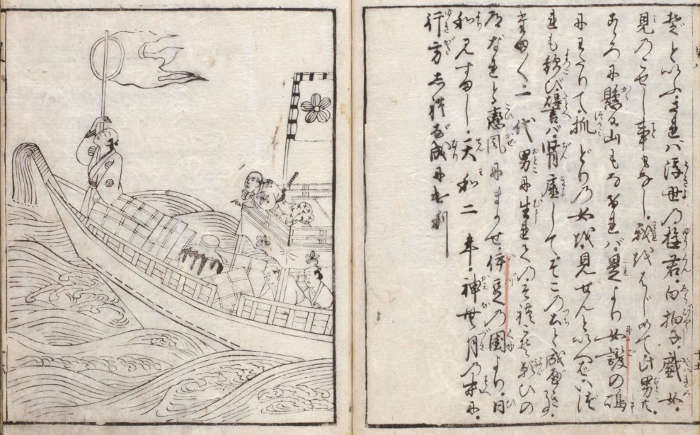
ところで、『好色一代男』では「洗濯」を「せんだく」と書いているのに気づいたでしょうか。そうなんです。「洗濯」は古くは「せんだく」と濁って発音されていたのです。日本イエズス会がキリシタン宣教師の日本語修得のために刊行した『日葡辞書(にっぽじしょ)』(1603~04年)という辞書があります。これには「センダク」のほうが「センタク」よりも良い言い方であると記されてっgいます。ひょっとすると、西日本では今でも「センダク」と濁って言っているかたがいらっしゃるかもしれませんね。古くは「センダク」だったのです。
こちらの「べらぼう」話もおすすめ