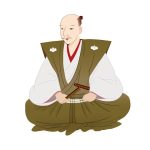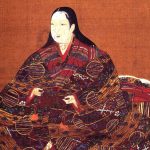10代の頃から頭角を現した浅井長政
浅井長政(あざいながまさ)の生まれた戦国時代は、臣下が主君を打ち倒して成り上がる下剋上(げこくじょう)も珍しくありませんでした。浅井家の関わった権力争いの影響で、浮き沈みの多かった長政の子ども時代を紹介します。
北近江の六角家に従属していた浅井家
浅井長政は北近江(きたおうみ:現在の滋賀県辺り)の出身で、1545(天文14)年に浅井久政(ひさまさ)の嫡男として生まれます。
祖父の浅井亮政(すけまさ)の時代、浅井家は主だった京極家を追放して北近江のトップになります。越前(現在の福井県辺り)の朝倉家とは、この頃から親交があり支援を受けていました。
しかし、父・久政が六角義賢(ろっかくよしかた)に負けたため、幼い長政は母親と共に六角家の人質になっていたといわれます。
浅井家が六角家の臣下であることを示すため、長政は15歳のときに六角義賢の一字を取って賢政(かたまさ)と名乗り、六角氏の家臣の娘を正室にすることを強いられました。

六角家から独立し朝倉家と同盟を結ぶ
長政が16歳の頃、浅井家の状況は一変します。六角家に従うことに不満を募らせていた浅井家の家臣たちが反乱を起こし、当主の久政を隠居させて長政を新しい主にしました。
そして、六角家から押し付けられた長政の正室を実家に帰し、長政の名前も賢政ではなく以前の名前に戻します。この事件によって六角家と争いが始まりますが、長政は若いながら家臣を率いて勝利し六角家からの独立に成功します。
その後、浅井家は朝倉家と同盟を結び、その支援を背景に北近江での勢力を強めていきました。
浅井長政と織田信長の同盟と裏切り

浅井長政と織田信長(おだ・のぶなが)の関係は同盟関係で始まりました。長政が信長を裏切った理由は何だったのか、同盟の成り立ちと2人の関係性、その後の流れを解説します。
信長が美濃平定のために同盟を持ち掛ける
浅井家が六角家から独立した頃、織田信長は美濃(みの:現在の岐阜県南部)の斎藤龍興(さいとうたつおき)と争っていました。
信長は美濃を挟み撃ちにするため、隣国である北近江の浅井家に同盟を持ち掛け、その条件として妹の市と長政の結婚を申し出ます。
長政にとっても、信長と手を結ぶことは六角家に対して有利になるというメリットがありました。長政は、先に同盟相手だった朝倉家に織田が戦を仕掛けない、という約束で同盟を受け入れたといいます。
お市の方と長政は同盟強化のための政略結婚でしたが、とても仲の良い夫婦だったようです。また、結婚の際には信長の1字をもらって新九郎から「長政」と改名しています。
信長は足利義昭を援助して京都へ
やがて、信長は助けを必要としていた足利義昭(あしかが・よしあき)を援助して京へ上ります。京では義昭を室町幕府の15代将軍に就任させ、織田家の力を諸大名に示しました。
しかし、義昭と信長の間は次第に険悪になっていき、信長は将軍の実権を奪うような「五箇条の条書」を義昭に送って認めさせます。また諸大名に対して、新将軍の義昭と天皇にあいさつするため京へ来るよう求めますが、朝倉義景(よしかげ)は拒否して信長と敵対します。
朝倉義景が信長の求めに応じなかったのは、自国を長く空けることへの不安と、信長に臣下の礼を執りたくないという反発からでした。
長政が信長を裏切った「金ケ崎の戦い」
信長は将軍への謀反を名目に、越前へ朝倉征伐へ乗り出します。こうして信長は、朝倉家を攻めないという長政との約束を破りました。
このとき、朝倉の城だった「金ケ崎城」を攻めたのが、1570(元亀元)年4月の「金ケ崎の戦い」です。
長政は戦の報告を聞いて、朝倉と織田のどちらに味方するか選ぶ必要に迫られます。長政が信長を裏切った理由は、朝倉家との関係以外にも信長のやり方に不満を抱いていた、足利義昭から信長討伐命令があったなど、さまざまな説があります。
最終的に長政は朝倉への加勢を決断し、ちょうど浅井の領地に背を向ける形で戦っていた織田信長・徳川家康(とくがわ・いえやす)軍の背後を襲いました。信長は絶体絶命の立場に追い込まれ、部下の助けでようやく京へ逃れます。
▼織田信長についてはこちら
浅井長政の最後

信長にとって長政の突然の裏切りは許せないものでした。命からがら京へ逃げた後、信長はすぐに軍を立て直します。同盟を結んでいた徳川家康・織田の連合対浅井・朝倉連合の戦いの行方と、浅井長政の最後を見ていきます。
信長による長政へのリベンジ「姉川の戦い」
金ケ崎の戦いから3カ月後の1570(元亀元)年6月、信長は報復のため長政の居城・小谷城(おだにじょう)を攻めます。
この戦いは織田・徳川連合の約2万5,000人と、浅井・朝倉連合の約1万3,000人がぶつかる「姉川の戦い」に発展します。初めのうち、戦いは浅井・朝倉連合が有利で、織田軍の本陣にまで迫るほどでした。
しかし、好機をうかがっていた徳川軍が浅井・朝倉軍を横から攻撃したことが転機となります。隊列が乱れたところを織田軍にも攻められて浅井・朝倉側の敗北が決まりました。戦死者は数千人、姉川が血で染まるほどの激戦だったといいます。
▼姉川の戦いについてはこちら
信長包囲網の結成と崩壊
姉川では勝利した信長ですが、金ケ崎の戦いにおける敗北をきっかけに、反織田勢力が次々に戦を仕掛けた「第1次信長包囲網」に悩まされることになります。
浅井・朝倉以外で包囲網に参加したのは、比叡山延暦寺、石山本願寺、伊勢長島の一向一揆(いっこういっき)、三好三人衆(みよしさんにんしゅう)などです。有名な「比叡山の焼き討ち」もこの時期に起きました。
一度は朝廷と将軍・足利義昭の調停で和睦しますが、武田信玄が上洛するという知らせで「第2次信長包囲網」が始まります。
しかし、朝倉軍の勝手な撤退や武田信玄の病死などが重なり、ほころびを見せた織田包囲網は信長に打ち破られました。第2次信長包囲網に参加していた将軍・足利義昭は追放されてしまいます。
重なる裏切りと長政の自害
第2次信長包囲網が失敗した後、信長は以前にも増して勢力を広げていきます。1573(天正元)年には、浅井の家臣が次々と織田に寝返っていきました。不利を悟った朝倉義景は越前の「一乗谷城(いちじょうたにじょう)」へ退却しますが、なおも攻めかかる織田軍に義景は自ら命を絶ち、ついに滅ぼされてしまいます。
信長は、残された浅井軍の立てこもる小谷城を包囲し降伏を勧めましたが、長政は投降を拒みました。妻である市と3人の娘を織田軍に引き渡した後に自害を選びます。享年29歳の若さでした。
長政の嫡子・万福丸も処刑され朝倉家は断絶しますが、助かった長政の娘たちによって朝倉の血は受け継がれていきます。
浅井長政と豊臣秀吉の関係

あまり知られていないかもしれませんが、浅井長政の動きと豊臣秀吉(とよとみ・ひでよし)の人生には大きな関係性がありました。秀吉の側室となった淀殿(よどどの)の話も併せてチェックします。
「金ケ崎の戦い」の戦いで秀吉は武功を上げる
信長軍が危機に陥った金ケ崎の戦いで、豊臣秀吉は明智光秀(あけち・みつひで)や池田勝正(いけだ・かつまさ)とともに殿(しんがり)を任されます。
殿とは軍隊が退却する際に最後尾を担当し、撤退する際は味方が無事に逃げられるようにサポートしつつ敵を防がなければならない危険な役目です。
この退却戦を「金ケ崎の退き口(のきぐち)」と呼び、秀吉が織田軍の中で重用されるきっかけになりました。
秀吉はほうびとして信長から黄金数十枚をもらったと伝えられ、その後の戦でも手柄を上げて出世していきます。
最終的に長政を自害に追い込んだのは秀吉
浅井長政の居城だった小谷城は、戦国時代における難攻不落の山城として有名です。『信長公記』によれば、最終決戦において、織田軍は長政のこもる「本丸」と、長政の父・久政の「小丸」の連携攻撃にてこずります。
そこで、秀吉は二つの間にあった「京極丸」を攻め落とし、連携を断ち切ることで長政を自害に追い込みます。浅井長政の最後でした。
この小谷城の戦いにおける活躍により、37歳の秀吉は浅井家の領地だった北近江3国を信長から与えられ、ついに城持ち大名になります。秀吉は小谷城を放棄して琵琶湖の近くの今浜に新しい城を建てます。また、信長の名前から一字をもらい、今浜を「長浜」と名付けました。
秀吉の跡継ぎを生んだのは浅井長政の娘
浅井長政は自害する前に、妻の市と3人の娘を織田軍に引き渡しました。3姉妹の名前は、上から順に茶々(ちゃちゃ、後の淀殿)、初(はつ)、江(ごう)です。
信長が亡くなった後、お市の方は柴田勝家(しばたかついえ)に嫁ぎますが、勝家もまた秀吉に攻められ滅ぼされてしまいます。お市の方は勝家とともに亡くなり、一緒にいた3姉妹は秀吉に保護されます。
成長した次女の初は京極高次(きょうごくたかつぐ)に、三女の江は2度の結婚後、徳川幕府の第2代将軍となる徳川秀忠(ひでただ)に嫁ぎました。
長女の茶々は1588(天正16)年ごろ、20歳以上年の離れた秀吉の側室となります。やがて嫡男となる秀頼を生みますが、その5年後に秀吉が亡くなってしまいました。そして淀殿となっていた茶々は、幼い秀頼の後見人として豊臣家の実権を握ることになります。
浅井長政は波乱万丈な生涯を送った戦国武将
浅井長政は、織田信長との同盟関係とその突然の裏切りが有名です。もし長政が信長を倒していたら歴史は変わっていたかもしれません。一方で、実は豊臣秀吉の出世にも、間接的・直接的に大きく関わっていました。
長政は、大人同士の権力争いに巻き込まれた子どもの頃から当主となった後まで、波乱万丈な人生を送っています。多くの戦いに彩られた29歳の生涯は、戦国大名らしいともいえます。
長政と他の大名の関係性をチェックすれば、戦国時代の勢力図が見えてきて大河ドラマ『豊臣兄弟!』もより楽しめるでしょう。
長政と他の大名の関係性をチェックすれば、戦国時代の勢力図が見えてきて大河ドラマ『豊臣兄弟!』もより楽しめるでしょう。
こちらの記事もおすすめ
構成・文/HugKum編集部
参考:日本国語大辞典(小学館)、日本の歴史 年表事典 (小学館)