2025年の海の日はいつ?
「海の日」とは、7月にある国民の祝日です。2025年の海の日は、7月21日(月祝)になります。
「海の日」は、ハッピーマンデー制度で毎年「7月の第3月曜日」と定められています。2025年以降の海の日は以下になっています。
2025年:7月21日(月曜日)←今ココ
2026年:7月20日(月曜日)
2027年:7月19日(月曜日)
2028年:7月17日(月曜日)
2029年:7月16日(月曜日)
2030年:7月15日(月曜日)
海の日とは?どんな祝日?
では、そもそも「海の日」とはどんな祝日なのでしょうか? この祝日の意味や、海の日がいつから始まったのかについても調べてみましょう。
海の日の意味
元日や憲法記念日など世界の国々に共通する祝日もいくつかありますが、「海の日」という祝日があるのは日本だけなのだとか。日本は海に囲まれた島国であり、身近に海があることで反映してきた歴史があります。そのため「国民の祝日に関する法律」で「海の日」の意味については「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う」と記されています。
昔から日本では、魚や貝、海藻など海の恵を食料として得るほか、海を通して世界の国々から荷物を受け取ったり送ったりしてきました。そのように海は日本の暮らしにとって欠かせない存在です。そのため簡単に言えば、「海の日」は海に対して感謝をする日のこと。子どもたちには、そんな風にやさしく説明すると良いでしょう。
始まりはいつ?日付が変わった理由とは
「海の日」が国民の祝日として施行されたのは、1996年のこと。このときは7月20日が「海の日」として決められていました。しかし2003年に祝日法が改正となり、一部の祝日を月曜日に移動させて、土曜日、日曜日とあわせて3連休とする「ハッピーマンデー制度」が始まりました。これに伴い、2003年から「海の日」は「7月第3月曜日」となったのです。また7月1日から7月31日までの1カ月間は、「海の月間」となっています。
▼関連記事はこちら
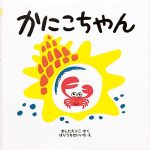
海の日の由来

次に「海の日」ができた由来について見てみましょう。海の日の由来は、明治時代までさかのぼることとなります。
明治天皇が初航海から寄港した日
もともと「海の日」に定められた日付は、7月20日でした。この日が「海の日」に決められたのは、7月20日が「海の記念日」だったことと関係あります。この日は、明治天皇が1876年(明治9年)に初めて、「明治丸」と呼ばれる船に乗って東北地方を巡幸し、横浜に寄港した日。明治天皇が船での旅を無事に終えたことで、船の安全性が証明され、日本での船旅や海運が盛んになるきっかけとなりました。
まさに海に囲まれた日本の新しい幕開けにふさわしい日だったことから、7月20日は長い間「海の記念日」と呼ばれてきた経緯があります。そのため、この「海の記念日」が「海の日」の祝日になったのです。「海の日」は、海に囲まれた日本ならではの祝日のひとつと言えます。
7月第3月曜日を海の日とするハッピーマンデー制度のメリット・デメリット
2003年から「海の日」は、ハッピーマンデー制度で「7月第3月曜日」に制定されました。しかし「海の日」に限っては、ハッピーマンデー制度の対象とはせず7月20日に固定しようという意見もあります。そこで「海の日」を「7月第3月曜日」にした場合のメリットとデメリットについて、考えてみましょう。
メリット
ハッピーマンデー制度が始まり、土曜日と日曜日とあわせて3連休が増えたことで、旅行や外出する機会が増えていることは確か。ハッピーマンデー制度に関するアンケート調査などでも、好意的に受け入れている人が多くいます。特に海の日を含めて3連休になれば夏休みも近いため、夏の旅行などにも利用しやすいというメリットがあり、経済効果も大きいと考えられます。
デメリット
ハッピーマンデーで「海の日」が毎年移動することについては、祝日の意味が見失われやすいことがあるかもしれません。なぜその日が祝日なのか、子どもに説明する機会も少なくなってしまうことも考えられます。
7月20日に海の日を固定するメリット・デメリット
一方で、以前のようにハッピーマンデー制度が導入されず、「海の日」は毎年7月20日に固定されていたら、どんなメリットとデメリットがあるでしょうか?
メリット
一般の人にはあまり知られていませんが、7月20日が「海の記念日」というのは海事関係者ではよく知られています。そのため「海の日」が7月20日に固定されれば、海の日の意味や由来に対する一般の人の意識も高くなると期待できます。
デメリット
海の日が7月20日に固定されていると、7月にはこの祝日しかなく、連休にはならない可能性もあります。その場合、旅行などを促進することは難しくなります。
海の日におすすめの過ごし方
海の日は、子どもと一緒に夏を満喫できる特別な日です。家族で楽しい思い出を作るために、おすすめの過ごし方を紹介します。
海辺で遊ぶ
夏といえば海!砂浜で貝殻を拾ったり、海の生き物を観察したりすることで、自然と触れ合いながら学びの機会を得られます。泳ぐのが難しい小さな子どもでも、波打ち際で遊んだり水遊びを楽しんだりできます。
海の生き物について学ぶ
水族館を訪れるのもおすすめです。イルカショーや海の生き物の展示を見ながら、海の生態系について学べます。興味を持った生き物について図鑑などで調べることで、さらに理解を深めることができます。
海をテーマにした工作をする
自宅で過ごす場合は、海をテーマにした工作を楽しんでみてはいかがでしょうか。貝殻を使ってフォトフレームを作ったり海の生き物を描いたりすることで、創造力を育てながら楽しい時間を過ごせます。
海の日に行われるイベント
ここからは、海の日に行われる各地のイベントをご紹介します。
「大成丸」一般公開
30回目の海の日を記念して、海技教育機構 練習船「大成丸」に乗船できるイベントが開催されます。自動車船体験乗船は、小学生から高校生に自動車船の仕組みや船内で働く人たちの仕事を知ってもらうために、商船三井と協力して実施。小学生から高校生を含むグループのみ申込を受け付けます。
日程:2025年7月21日(月・祝)11時~17時
会場:東京国際クルーズターミナル
C to Sea 海ココ
BLUE SANTA ごみ拾い
2016年から毎年海の日に開催されてきたBLUE SANTAのイベント。10年目となる今年は、海の素晴らしさや、海の現状に目を向けて、海をキレイにする文化が生まれることを願いごみ拾いを実施します。海の日に、青いアイテムを身につけて、みんなで海の未来を変える挑戦をしましょう。
日程:2025年7月21日(月・祝)16:00~17:30(受付15:00〜)
会場:片瀬東浜海水浴場 片瀬東浜交差点の目の前のビーチ
BLUE SANTA
第21回明治丸シンポジウム
東京海洋大学では、海の日の由来となった「明治丸」のシンポジウムが開催されます。
・我が国の観光政策の現状
・観光による街おこし
・江戸から明治をたどる深川めぐり
が題目です。また同時に、明治丸にまつわる特別展示も開催される予定です。
日程:2025年7月21日(月・祝)13時~
会場:東京海洋大学越中島会館講堂
第21回明治丸シンポジウム
第79回 海の日名古屋みなと祭
海の日名古屋みなと祭協賛会が開催するお祭り「海の日名古屋みなと祭」。このお祭りでは、名古屋市指定無形民俗文化財である筏師による「筏師一本乗り大会」、神楽揃えや和太鼓などのステージ、海洋少年団や愛知県警察音楽隊などによるパレード、花火大会などが催されます。
日程:2025年7月21日(月・祝)
会場:名古屋港ガーデンふ頭一帯
海の日名古屋みなと祭
「世界海の日」とは
「世界海の日」とは、海を讚え、海洋の恵みを賛美しながら、海本来の価値に感謝をする重要な機会として定められています。
1992年の環境と開発に関する国際連合会議(通称:リオサミット)で初めて提唱、2008年に国連総会で公式に採択され、毎年6月8日が「世界海の日」と制定されました。
「世界海の日」は「世界海洋デー」とも言われ、毎年テーマに沿った様々なイベントや活動が世界中で行われます。例えば、ビーチクリーニング(海岸清掃)や芸術と音楽の祭典、研究発表などがあります。
2025年に掲げられたテーマは「Wonder: Sustaining What Sustains Us (ワンダー:私たちを支えるものを支える)」です。Wonder (ワンダー)は海洋の美しさ、多様性、そして神秘的な力を称えること。Sustaining (持続可能にする)は
海洋の恵みを将来世代のために守り、持続可能な利用を促進すること。そしてWhat Sustains Us (私たちを支えるもの)は海洋が私たちに与える恵み、食料、資源、気候調節機能などを認識し、その重要性を理解することを意味します。
2025年のイベントを記念して、モナコからニースまでの世界海洋デーのボートパレードと、世界中での世界海洋デー旗の掲揚が予定されています。また世界海洋デーのボートパレードと世界海洋デーの旗掲揚が、6月8日午後3時から4時(中央ヨーロッパ夏時間)までニース港から観覧できます。
United Nations World Oceans Day 2025
「海の日」は家族で楽しもう!
「海の日」は、海洋の生態系や資源の重要性を人々に伝え、海洋保全の意識を高めるための重要な機会でもあります。また、「海の日」は7月に3連休をもたらしてくれる国民の休日でもあります。「海の日」は、家族と一緒に海への関心を深めてみてはいかがでしょうか?
あなたにはこちらもおすすめ
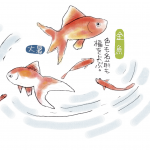
文・構成/HugKum編集部





