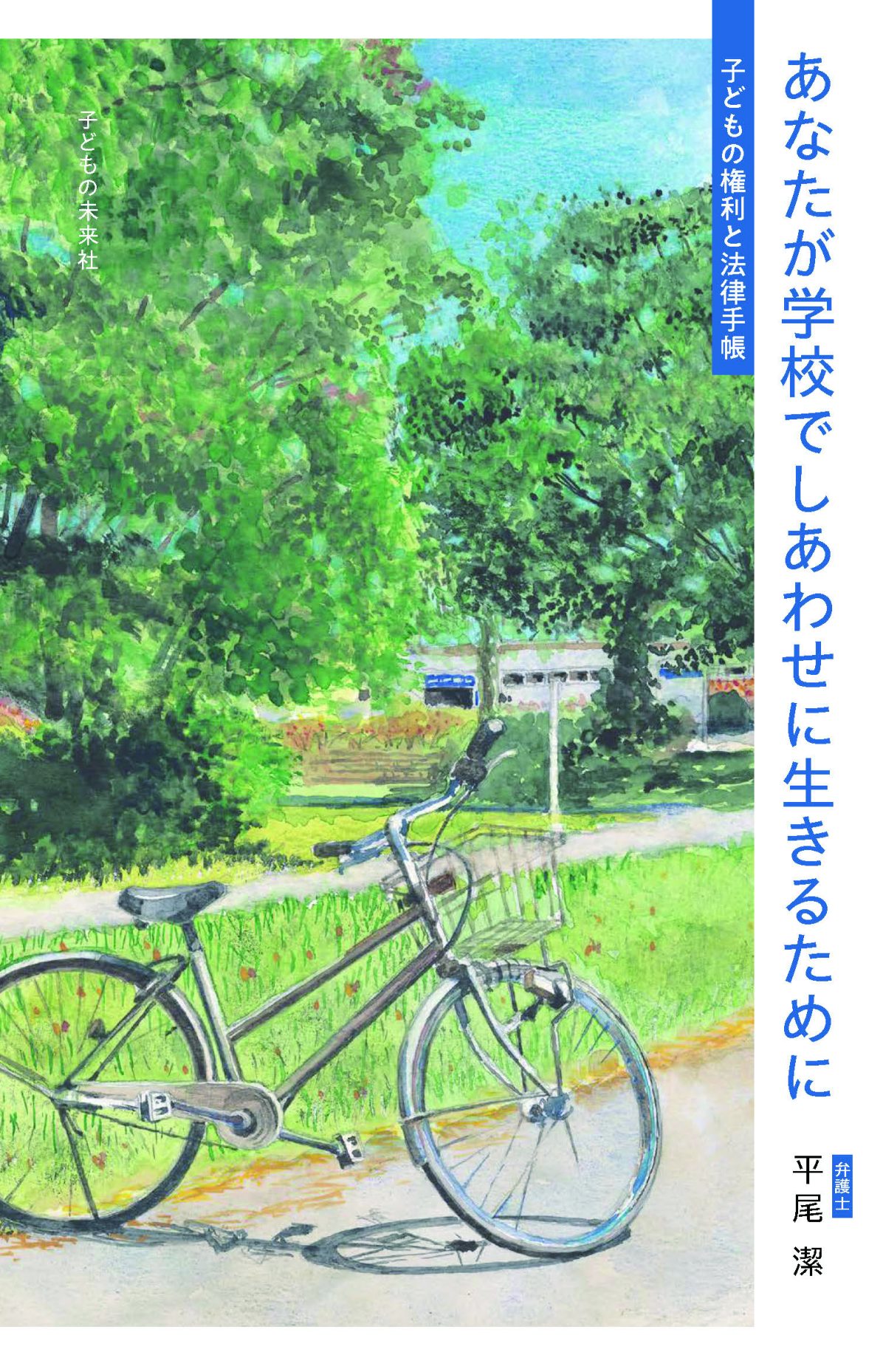※ここからは『あなたが学校でしあわせに生きるために 子どもの権利と法律手帳』(子どもの未来社)の一部から引用・再構成しています。
Q:厳しい校則を変えたいけれど、どうすればいい?
私の通う高校では、放課後に寄り道をすることや、保護者の同伴なしにカラオケやゲームセンターに行くことが禁止されています。学校から直接塾に行くときに、ちょっとコンビニに寄ることも校則違反になります。
この校則を変えたいのですが、どうすればいいでしょうか。
A:校則は変えられる可能性があります
あなたは、こういった校則に納得がいっていないのですね。それでも決まりだからがまんしなければならないのでしょうか。
そんなことはありません。実際に校則を変えた例も出てきています。
幸福追求権と意見表明権を行使する
みなさんは本来、自分の決めたように、自分で決めた目標に向かって、自分で判断して生きる、という権利が保障されています。このように生きることは、幸福追求権として、憲法で定められた基本的人権の一つとして認められるべきものです。
権利というものは、みんなでこころがけましょう、という、交通標語のような「道徳」ではありません。この権利を使って裁判を起こすこともできる、憲法の裏付けのあるもので、強くあなたを支えてくれるものなのです。
自分らしく生きるためには、それをじゃまするものは取り除かなければなりません。そのために、みなさんには、意見を述べる権利が与えられています。それは「意見表明権」です。
*子どもの権利条約12条 意見を表明し参加できること(意見表明権)
子どもは、自分に関係することに自由に意見を述べることができます。おとなたちは、その意見を子どもの発達に応じて十分に考慮しなければなりません。
あなたが、校則がおかしい、変えたい、と思ったとき、それはあなたの幸福追求権の行使であり、その意見を述べることは、子どもの権利条約で認められた意見表明権の行使です。表明された意見を、おとなたちは十分に考慮しなければなりません。
生徒指導提要の改訂で、校則が変えられるかも!

現在、校則を見直そうという大きな流れが出てきています。2022年12月に生徒指導提要が改訂されました。改訂後の生徒指導提要には以下のように書いてあります。
・目的を適切に説明できないような校則については、あらためて学校の教育目的から見て適切なものか、現状にあう内容に変更する必要がないか、本当に必要なものか、絶えず見直しを行うことが求められます。
・校則によって不必要に行動が制限されるなど、マイナスの影響を受けている子どもがいないか、いる場合にはどのような点に配慮が必要か、検討し、見直しを図ることもたいせつです。
・校則のあり方については、子どもや保護者などの意見を聴いた上で決めていくことが望ましいと考えられます。
・校則の見直しは、児童会・生徒会や保護者会といった場で、校則について確認したり議論したりする機会を設けるなど、いつも積極的に見直しを行っていくことが求められます。
・校則の見直しには、校則を決めたり、見直したりする場合にどのような手続きを踏むことになるのか、についても示しておくことが望まれます。
校則は、みなさんの力で変えることができるべきものと、書かれているのです。
では、具体的にどんな方法があるのか、見ていきましょう。
生徒の声を集める
校則を変えるというのは、学校全体の問題になりますから、一人の声だけで変えるのはなかなかむずかしいことです。まずは生徒の意見を集めることが必要です。
広島市の私立安田女子中学・高等学校は、生徒たちの力で校則を変えることに成功しました(「生徒みんなで校則変えた 広島・安田女子中高の挑戦」中国新聞デジタル 2021年4月18日)。これは、生徒指導提要改訂の前の話です。
この学校には、スマートフォンの持参禁止、放課後は寄り道してはいけない、カラオケやゲームセンターなどへ行くときは保護者同伴、といった校則がありました。
まず、中心となる有志グループが、どの校則を見直すか、全校生徒にアンケートを取って決めました。廊下に紙を貼り、生徒が自由に書きこめるようにもして、みんなの意見を集め、それを集約することに成功しました。
よく、生徒会が校則見直しを学校に掛け合うことがありますが、単に生徒会の意見として伝えるよりも、全校生徒の意見を集約した結果をもって学校と交渉するほうが、説得力が大きくちがってきます。

信頼できる先生に相談する
学校の校則は、校長に決定権がありますが、実際に校長だけで決定している学校ばかりではありません。生活指導主任が実質的な決定権を持っていたり、職員会議で決定したりする学校もあります。ですから、まずは、
また、生徒側の意見をきちんと学校に伝えてくれる先生も必要になってきます。だれがキーパーソンで、どのように話をもっていけばうまくいくのか、相談できる先生を味方につけることができれば、話の進め方を検討する有力な材料になります。
申し入れは書面で行い、継続的な話し合いの場を持つ
学校への申し入れは、単に「校則を変えてください」とか「スマホを学校に持ってくるのを許可してください」と口頭で言うだけでは不十分です。まず、書面にしましょう。
書面に書くことは以下の内容です。
①どの校則をどう変えたいか
②意見表明権の一環として申し入れを行っていること
③多くの生徒が同じように求めていること
④校則には、必要性と合理性が求められること
⑤この校則に必要性と合理性がないこと
⑥この申し入れをきちんと検討し、回答をいただきたいこと
これらを、きちんと書くとよいでしょう。
よく、学校の先生が、「これは校則だから変えられない」「へりくつを言うな」などと、あまりまじめに生徒の話を聞かずに門前払いのような返事をすることがあります。
そういうことを許さないためには、準備はたいへんでも、きちんと主張を書面化し、それに対する回答を求めることが必要です。
おとなの力を借りる
校則についての話し合いがうまく軌道に乗らないときは、おとなの力を借りることも考えましょう。
一番身近なのは、保護者やPTAです。もっとも、PTAが必ず味方をしてくれるとはかぎりませんので、そこはまず話をして、助けてもらえそうであればお願いするのがよいでしょう。

また、地域の自治体に「子どもの権利救済」を目的とした機関(※1)があれば、そこに話を聴いてもらうとよいでしょう。こういう機関は、子どもの話をていねいに聴き、それを踏ふまえて、学校との話し合いの橋渡しを手伝ってくれるかもしれません。
※1 子ども条例に基づく子どもの相談・ 救済機関(公的第三者機関)一覧:救済機関設置順(2024年5月現在)
弁護士会も、各地で子どものための相談窓口を設置(※2)しています。ここに電話をしたり、面談をして、主張の内容や書面の書き方などのアドバイスをもらうこともできるのではないかと思います。
※2 弁護士会の子どもの人権相談窓口一覧(2024年7月現在)
自分たちで決めたことを守る
学校は、もし校則をなくしたら何か問題が生じるのではないかと心配をするかもしれません。校則をなくすこと、変えることに抵抗感があるのです。
ですから、校則を変えることができた場合、それによって問題が生じないよう、自分たちの生活をコントロールする必要があります。そうしないと、ほらみたことか、とばかりに、校則を元にもどそうという動きが出てきます。ここは、注意が必要です。
実際に、小学校の、体操服の下に下着を付けてはいけない、という校則は、世論の批判を浴びて、教育委員会主導で見直されました。東京の世田谷区では、不合理な校則を見直すこととなり、たとえば髪型について、今後は男女の区別なく「清潔で活動しやすい髪型を基本とする」などに改められました。
このような流れに乗って、今後、すべての学校で、校則についてみなさんの意見が反映される日が来ることを、大いに期待しています。
※ここまでは『あなたが学校でしあわせに生きるために 子どもの権利と法律手帳』(子どもの未来社)の一部から引用・再構成しています。
『あなたが学校でしあわせに生きるために 子どもの権利と法律手帳』(子ども未来社)
長年スクールロイヤーとして「いじめ問題」に取り組んできた弁護士が、子どもたちに「しあわせに生きる権利」があることを伝え、学校で人権が踏みにじられそうな時どうしたらよいかを、子どもの権利と人権の面から具体的に対策をアドバイスします。困ったときにはぜひこの本を開いて活用してください。
平尾潔(ひらお・きよし)
早稲田大学法学部卒。サラリーマンとして働く傍ら、司法試験を目指すようになり、2000年弁護士登録(第二東京弁護士会)。以後、一貫して子どもの権利に関する分野に携わる。「弁護士による、いじめ予防授業」を単身で始め、ライフワークとなっている。現在、日本弁護士連合会子どもの権利委員会幹事、第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会委員、世田谷区子どもの人権擁護機関子どもサポート委員、子どもいじめ防止学会会員。少年野球チームサクラ野球クラブ代表。著書に『いじめでだれかが死ぬ前に』(岩崎書店)。
こちらの記事もおすすめ

構成/国松薫