フェイクニュースとは
フェイクニュースとは、具体的にどのような情報を指すのでしょうか? 基本的な定義と、実際にあった事例を紹介します。フェイクニュースを個人が対策するためには、どのようなものなのかを理解しておかなければなりません。
不確かな記事・情報を指す
フェイクニュースとは、英語で偽造や偽者を意味する「fake」と、情報を意味する「news」が組み合わさった言葉です。
英語の意味の通り、本当ではない偽の情報を指します。主にインターネットやSNSなどで発信される不確かな記事や情報が、フェイクニュースと呼ばれているようです。
フェイクニュースには、「誤った情報」「わざと作られた偽物の情報」「一部が正しくない情報」などが含まれます。また、「悪意がないもの」と「悪ふざけやだまそうとする悪意があるもの」が混在していることが特徴です。
実際にあったフェイクニュースの事例
フェイクニュースという言葉が広まるきっかけになったのは、2016年のアメリカ大統領選挙といわれています。大統領選挙の前に、さまざまな偽情報が出回りました。
日本でも、フェイクニュースは問題視されています。例えば、2016年の熊本地震では「ライオンが逃げた」という事実ではない情報が投稿され、騒ぎになりました。実際には起こっていない出来事にもかかわらず、いかにもライオンが街を歩いているかのような画像とコメントが投稿されたことで、混乱が起きてしまったようです。
また、2024年の能登半島地震では偽の救助要請が投稿されており、災害時のこのようなフェイクニュースは深刻な問題です。そのほかにも、特定の商品が品切れになるといったフェイクニュースが出回るケースも見られます。
フェイクニュースを見極めるための対策
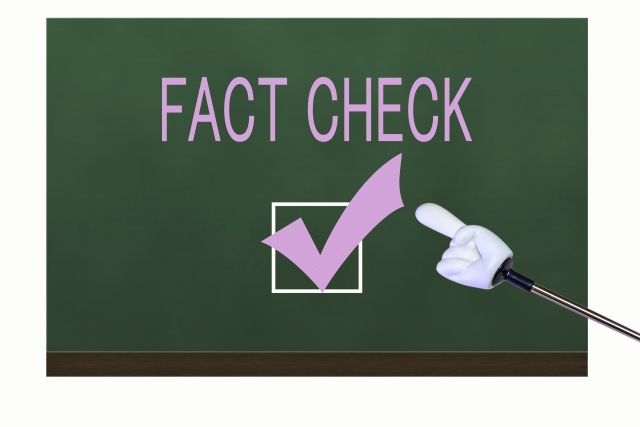
フェイクニュースにはさまざまなタイプがあり、だまされると実害が起きるものもあります。見極めるためには、何をすればよいのでしょうか? 不確かな情報を見かけたときに心掛けたいポイントを紹介します。
別の情報と比較してみる
インターネットやSNSで記事や情報を見かけたときは、別の情報と比較してみるのがおすすめです。
同じ情報について書かれているはずなのに違いがある場合は、自分が見た情報にフェイクが含まれている可能性があります。
比較できる情報がない場合や、該当の記事を発信源としたうわさ話しか見当たらない場合は、不確かな情報といえます。正しい情報がリアルタイムで発信されている可能性はあるものの、発信者によっては誤報のリスクもあります。
情報発信者をチェックする
気になる情報を発信している人やアカウントが、専門家や信頼できる会社の場合は、情報の精度が高まります。裏付けとなる知識や情報がそろっていると考えられるためです。
記事や情報を見たときは、誰がその情報を発信しているかを確認しましょう。特に、SNSはさまざまな人が情報を拡散しているため、発信源となっている最初の投稿を突き止めることが重要です。
情報を拡散している人は善意で広めている可能性がありますが、発信源が信頼できないアカウントの場合、誤りやフェイクが含まれる可能性は否定できません。
いつどこで書かれたものか確認する
フェイクニュースの中には、現在の状況と一致しない古い情報も含まれます。例えば、発信の根拠となっている情報自体が数年前のものであれば、現状とは変わっているかもしれません。
また、画像や動画のみ、別の時期に撮影されたものが使われていることもあります。例えば、過去に別の場所で起きた災害の写真を使って、偽情報を拡散するパターンが該当するでしょう。同じ画像が過去に使われていないか調べてみるのも、対策になります。
一次情報を探してみる
実際には正しいニュースだったものが、インターネットやSNSのうわさ話を通して誤った情報にすり替わることもあります。また、最初の情報自体に誤りが含まれているというケースもよくあるパターンです。
その情報が正しいかどうか判断するためには、「一次情報」を探してみましょう。最初の発信者の発言だけでなく、その発信者が何に基づいてコメントしているのか、データや根拠となる情報を調べます。
政府や公的機関が発表している情報と相違や違和感がないか、確認してみるのもよいでしょう。
フェイクニュースが拡散されやすい理由と対策

フェイクニュースには、人が拡散したくなる要素が含まれています。なぜ拡散されてしまうのか、個人が対策として何ができるのかを把握しておきましょう。
感情に響く要素が多く含まれているため
フェイクニュースには、これまでにあまり目にしたことがないような情報が含まれています。事実ではないことや、注目を集めようと作られた偽の情報であるのですから、当然です。
「誰かに教えたくなるような新しい事実」「早く多くの人に伝えなければならないと強く感じるような内容」が含まれていると、情報は拡散されやすくなります。
フェイクニュースを全員が信じ込んでいるわけではないとしても、「伝えたほうがよい」と多くの人が感じる内容であれば、拡散はされやすくなるでしょう。
むやみに拡散させないことが対策になる
インターネットには、事実なのか判断できない情報があふれています。もし、怪しい情報を見たときは、拡散しないように心掛けるだけでも対策になるでしょう。
多くの人が拡散に関わらなければ、偽の情報が存在してもだまされる人は少なくなります。周囲を巻き込まないためにも、自分で判断できない情報を広げるのは避けましょう。
特に、「誰かの名誉を傷つける内容」や「人や施設に迷惑をかける内容」については、たとえ事実が含まれていたとしても注意が必要です。拡散に関わっただけでも、罪に問われるリスクがあります。
不確かな情報から子どもを守るには

子どもの場合、情報の真偽を見極めることが難しく、だまされてしまうリスクが高くなります。子どもを守るために家庭でできる対策も確認しておきましょう。
スマホのセキュリティを活用する
子どもがスマホを契約する場合、保護者が行動を見守れるようにフィルタリング機能を活用できます。
契約している通信会社に設定方法を確認し、危ないサイトを閲覧できないようにするのも有効な対策です。
有害なサイトをブロックするだけでなく、SNSの利用を制限することもできます。特に小さい子どものうちは、悪意を持った人からの接触を防ぐため、フィルタリング機能を積極的に活用しましょう。
子どもにフェイクニュースのことを伝えておく
子どもがある程度、善悪やフェイクニュースについて理解できる年齢である場合は、家庭で普段からフェイクニュースについて話しておくのもおすすめです。
子どもが「インターネットには偽の情報もある」と判断できるように、実際の事例を挙げて説明すると伝わりやすくなります。
また、親しい人からの情報であっても信じ込むのではなく、気になることがあれば保護者に相談することも、あわせて伝えておきましょう。
家庭でインターネットの使い方を話し合っておく
フェイクニュースの中には、購入の誘導や詐欺に関連するものもあります。トラブルに巻き込まれることを避けるために、家庭内でルールを決めておくのもよいでしょう。
例えば、以下のようなルールづくりが対策として有効です。
・個人情報の入力はできる限り避ける
・セキュリティソフトをインストールしておく
・購入や課金は信頼できるサイトのみに限定する
あわせて、普段と異なる行動を取るときは、保護者に相談する仕組みをつくっておくと、子どもがだまされるリスクも少なくなります。
フェイクニュースの対策はいくつもある
フェイクニュースは、事実ではないニュースのことです。見極めるために対策をしようと考えるなら、まずは不確かな情報を見たときに内容を細かくチェックしましょう。
ほかの情報と見比べることや、発信者を確認するだけでも、だまされる可能性は低くなります。子どもをフェイクニュースの脅威から守りたいときは、子どものスマホ管理や家庭でのルールづくりが重要です。
悪意のあるフェイクニュースに周囲を巻き込まないためにも、普段から対策を心掛けましょう。
こちらの記事もおすすめ

構成・文/HugKum編集部





