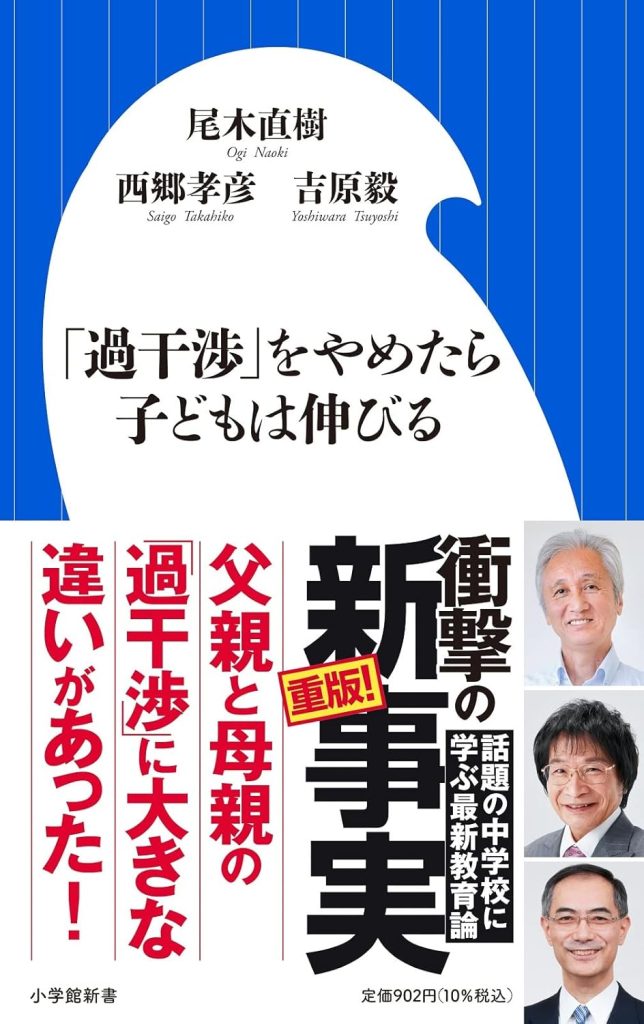「勉強しろ!」は教育虐待
――教育虐待について危機感を持っている、ということでしたが、詳しく教えていただけますか?
「教育虐待というのは、“見えない虐待”です。日本においては“教育熱心”という言葉で虐待の実態が見えなくなっているのです」
――どう違うのでしょうか。
「子どもには成長の過程でその年齢に必要なことってありますよね? 例えば一緒に外で遊ぶとか、添い寝をしてあげるとか、読み聞かせをするとか。そういう遊びやスキンシップがすっぽり抜け落ちて、小さい頃から“勉強しろ”と駆り立てる。中には、幼稚園や保育園に預ける前から、塾に通わせる親もいます。
海外では、“教育虐待”という問題が認識されていて、行き過ぎた親は関係各所から厳しく指摘されます。ところが日本では、“あの家庭は教育熱心だ”という言葉で捉えられ、賞賛されることさえあります」
――児童相談所に通報することはできないのでしょうか。
「現状としては、なかなか虐待として扱ってもらえません。そもそも児相は、なかなか家庭の事情に立ち入りたがりません。教育虐待で追い詰められた子がリストカットしても、そのことの背景に教育虐待があったとは考えないんです」
――教育虐待をしてしまう親は、どういった人が多いんですか?
「ひとつは、両親のどちらかが、自分が成し遂げられなかったことを子どもに強いる場合。子どもを自分の代理として、成し遂げようとするケースが多いんです。
例えば自分は医者になろうとしていたがなれず、自分の子にその夢を託して、小さい頃から勉強漬けにする。大学に行きたかったけれど行けなかった親が、子どもを大学に進学させるために、追い込むというのもよくあります。
もちろん、子どもに対して“自分より幸せになってほしい”と思う気持ちは、誰しも持っていると思いますが、それが極端でかつ病的であるということです」
「いい学校に行かせたい」のはなぜ?

「『代理ミュンヒハウゼン症候群』という病名を聞いたことがありますか?
ほかの人に自分のつらさをわかってほしい。ほかの人に認められたい。そういった願望を、自分以外の人間を傷つけ、それを世話することで満たそうとする精神障害の一種です。
たいていの場合、自分の子どもに毒を盛ったり、傷つけたりして、そういうかわいそうなわが子を看病している子順悩な親、という役割を演じます。
教育虐待は、これに似ている。例えば子どもが東大に入ったとしましょう。東大に入ったのは子どもががんばったからだと思いますが、こういう親はそう思わない。『こんな出来のいい素晴らしい子を育てた私はなんていい親だ』となる。自分が賞賛されたいし、自分が認められたいのです。受験体験本の多くは、”わが子をこうして難関校に入れた”という自慢本です。
それにもうひとつ考えてほしいのは、いい高校、いい大学に入ることがはたして幸せでしょうか。いい大学を出て、いい会社に入れば安泰という時代ではありません。大事なのは、自分で考えること。自分の好きなことを見つけること。そのためにやるべきことは、塾通いではありません」
――しかし親は、古い価値観に縛られたままです。
「しかも親が“いい学校に行かせたい”と強く願うその裏で、子どもたちが苦しんでいる。
考えてみてください、偏差値の高い高校、偏差値の高い大学に進ませたがるのは、実際は親が賞賛を得るためなんですから。教育熱心な親が多い、といわれる地域には、そうやって子どもを追い込んでいる親が多くいます」
――たしかに、世間では「わが子を東大に入れた」という親を持てはやします。
「親が東大を望み、子どもがそれに応えた。目に見える結果が出ている場合は、問題が覆い隠されます。でも全員が全員、そういうことにはなりません」
――親が望む学校に入れなかった場合は?
「子どもがいちばん傷つきます。親の期待に応えられなかったわけですから。結果、自己肯定感はどんどん下がっていきます。
桜丘中学校には、中学受験を失敗した子どもも入学してきます。
最初、そういう子のひとりを見たとき、”なんでこの子は、こんなにおとなしいのだろう”と思ったんです。自分の意見を口にする子が多い桜丘中学校にあって、逆の意味で目立っていた。
勉強にも熱が入っていない様子で、徐々に問題行動が多くなっていきました。保護者と話をして初めて、この生徒が中学校受験に失敗していたと知りました。
以前なら、そういう挫折をした子は、いったん非行に走って大暴れしました。そうすることで、心の中にため込んでいたものを吐き出していた。すると物の怪(け)が落ちたように落ち着いてくるということがありました。ところが最近は、非行に走るという気力も出ない。だからますます自分の中に鬱屈した気持ちをため込んで、気づいたときには手に負えなくなってしまいます」
――そういう挫折を味わった子どもに対して、どう接すればいいのでしょう?
「温かく見守るしかありません。すぐに元気になると考えてはダメ。じっくり時間をかけて見守っていきます。元の自分に戻るには長い時間が必要です。ただ……」
――ただ?
「一度、受験に失敗しているので、せっかく落ち着いたとしても、高校受験でまた不安定になってしまうことも少なくありません。そういう時も、決して本人を追い込んではいけません。中学受験同様、高校受験もそれがすべてではないのです。優しく接し、結果ではなく過程を褒めてあげることで、自分を取り戻してあげないといけません!」
「わが子はもっとできるはず」は間違い
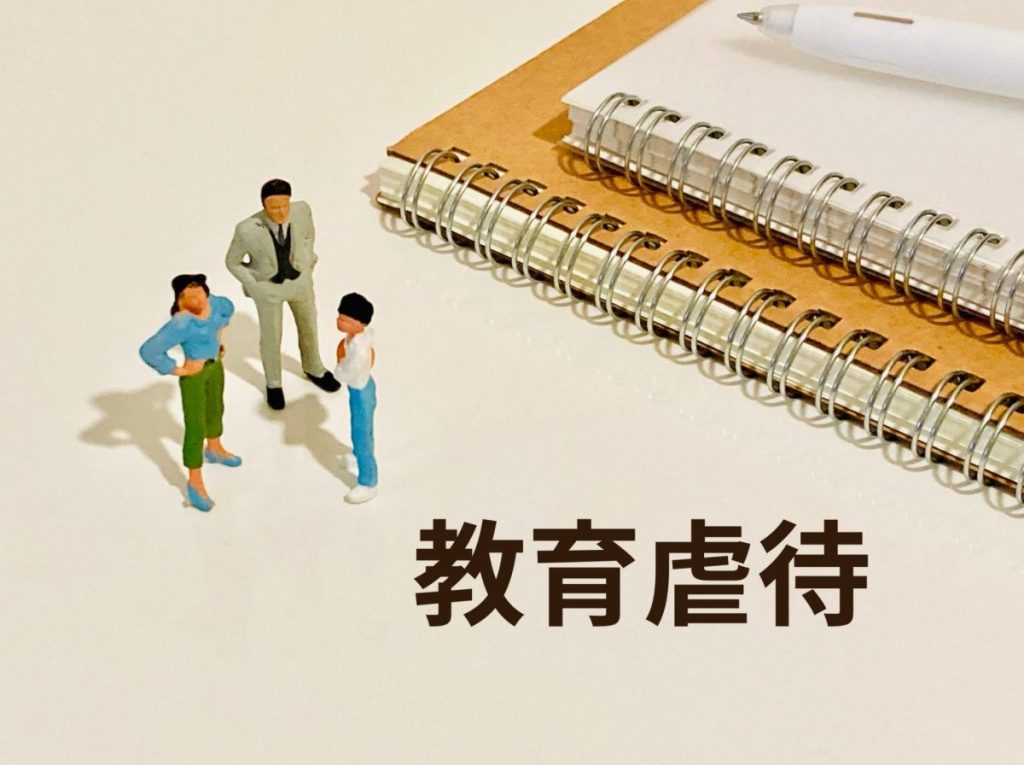
――教育虐待はなぜなくならないのでしょう?
「親御さんの多くは、自分が受けた教育しか知りません。それを基準に子どもを判断してしまっています。まずそこから改めてほしいと思います。自分たちの時代と、高校や大学のレベル、難易度は変わってきていますし、勉強の内容や受験のやり方も変わりました。
何より、世の中が変わってきています。そんな中で、自分の教育観を振りかざすことは、子どもにとってマイナスでしかありません」
――しかし「自分の子ども」と考えると、「もっとできるんじゃないか」と思ってしまいます。
「私にも子どもがいて、そういう思いに駆られそうになったこともありました。でもそこでグッと我慢してください」
――我慢する?
「そうです。先回りすることを我慢する。口うるさく言うことを我慢するんです。例えば、自分の子が、絵がうまかったとしましょう。うれしいですよね? でもそこで先回りして、すぐに近所の絵画教室に通わせるとか、そういうことが教育虐待につながっていきます。
ゴッホや岡本太郎が絵画教室に通っていましたか? 才能があったら、放っておいても一流になります。好きならば言われなくても、その道に進んでいくのです。小さい頃から習い事や塾に通って貴重な時間を消費するよりも、わが子と一緒にボーッとした時間を過ごしてあげたほうが、どれだけいいかわかりません」
父親が過干渉だと子の自尊感情が低くなる
「これは実際、桜丘中学校の調査結果からもわかっているのですが、どうやら、子どもの自己肯定感、つまり自尊感情には、父親の影響が強いようなんです」
――これは意外でした。
「一緒に過ごす時間が多い母親は、口うるさいのが当たり前だと子どもが認識しているのかもしれません。口うるさい父親は高学歴というケースが非常に多く、社会的にも高い地位を持っている人が多いんです。その分、ストレスが多いのかもしれませんが、そのはけ口が自分の子どもに向かってしまっている。データによると、父親が“勉強しろ!”と強く介入した場合、子どもの自尊感情はガクッと下がります。これに男女差はありません」
――極端に自尊感情が低下するとどうなるのですか?
「男の子の場合は、“自分は臭いんじゃないか”と悩んだりします。「『自己臭恐怖症」(自臭症)と呼ばれる精神疾患で、自分の臭いが他人を不快にさせているんじゃないかと、常に不安に怯えるようになります。女の子の場合は、“自分は醜い”と劣等感を抱えるケースが多いようです。『醜形恐怖症』(身体醜形障害)と呼ばれています。
どちらも『対人恐怖症』のひとつで、実はこの言葉は日本特有の症状とされていて、専門用語も『Taijin kyofusho』とローマ字表記されます。こうしたものをひっくるめて、『社交不安障害』と称し、最近、大きな問題になっているのですが、その社交不安障害を引き起こす大きな要因のひとつが、口うるさい親の存在なのです」
――子どもに口うるさくすることは、百害あって一利なし、ですね。
「親に唯一できることは、小さい頃なら一緒に遊ぶこと。それも”こうしたら子どもの教育によい”などと考えずに、ひたすら遊びに付き合うこと。中学生以上なら、見守ることだけですね」
※この記事は、『「過干渉」をやめたら子どもは伸びる』の内容の一部を再構成したものです。
『「過干渉」をやめたら子どもは伸びる』
「教員や親の過干渉が子どもの考える力や判断力を奪っている」(尾木直樹)、「いまの日本経済に元気がなく、閉塞感があるのは、管理教育が行き過ぎているから」(吉原毅)、「親が「いい学校に行かせたい”と強く願うその裏で、子どもたちが苦しんでいる」(西郷孝彦)。実は、親や教員の押しつけ・過干渉が、子どもをダメにしていた。ではどうしたらいいのか――「もっと子ども本人に任せればいい」と3人は口を揃える。いまの教育に危機感を覚える3人が語り合った、「目からウロコ」の実践的教育論。いますぐ読む!
あなたにはこちらもおすすめ


さいごう・たかひこ 1954年生まれ。上智大学理工学部卒業。東京都の養護学校(特別支援学校)をはじめ、大田区や品川区、世田谷区で数学と理科の教員、教頭を歴任。2010年、世田谷区立桜丘中学校長に就任。「すべての子が3年間楽しく過ごせる学校」を目指した結果、校則や定期テスト、宿題、制服、チャイムの廃止等で注目される。生徒の発達特性に応じたインクルーシブ教育を取り入れ、個性を伸ばす教育を推進。『校則をなくした中学校 たったひとつの校長のルール』(小学館)が話題。
ドキュメンタリー映画『夢みる小学校』『夢みる校長先生』(ともにオオタヴィン監督)には、西郷さんの校長時代の様子も収録されている。
構成/HugKum編集部