目次
“理想の母親像”と現実のギャップ

自分が選ばなかった道がよく見えるのはなぜ?
主人公・村上詩穂(多部未華子)は、まだ幼い娘を抱える専業主婦。「専業主婦」であることに後ろめたさを感じています。
一方、お隣の長野礼子(江口のり子)は、未就学児の兄妹を抱えるワーキングマザー。仕事と育児を猛烈にこなす毎日を過ごし、ついにイライラが限界点に達し爆発! 家の中で子どもにブチ切れるというヒステリーを起こし……。
SNSでは、ふたりのそれぞれの悩みや葛藤に共感の嵐が巻き起こりました。
「対岸の家事1話観たけどつらすぎる🥲」
「私のほうが大変!」
「私もこんなはずじゃなかったのに!」
「糸がぷつんと切れる→子どもにきつく当たるところで共感しまくって涙腺崩壊」
ここまで共感の声が多いということは……、自分で選んだ道であっても、苦しんだり、葛藤したりしている人がいかに多いかということ。
第6話では「ビュッフェと人生は似ている」という礼子の元上司の女性先輩社員の言ったセリフがありました。人生という1枚のお皿に何を載せるかはすべて自由。ただし、全部は載せられない。
詩穂も礼子も、自分で選んだ道です。それでも自分と違う道を選んだ人をうらやましく思ったり、モヤモヤしたりしてしまうのは、なぜなのでしょうか?
すべてを頑張っても「まだ足りない」と感じてしまう社会的構造
世のお母さんたちは、めちゃくちゃ頑張っています。ですが、どれだけ頑張っても「もっとちゃんとしなきゃ」と思ってしまう……。それは個人の問題ではなく、そう思わせる社会の構造があるから。
メディアやSNSには“理想の家庭像”があふれ、「私もそうならなきゃ」と比較してしまっていませんか? 残念ながら、評価の軸が他者にある限り、自己肯定は難しくなります。
このドラマ内でも、この問題を浮き彫りにすべく、様々な立場の女性が登場しました。
礼子の元上司で、第一線でバリバリ働き続ける女性の先輩社員を見て、礼子は「自分は子どもを選んだから出世できなかった」と言い訳めいた引け目を感じてしまいます。
冒頭でも紹介しましたが「ビュッフェと人生は似ている」という核になるセリフがありました。そう自分で自分の人生を決められるにも関わらず、自分が選んだ人生を、無意識に人と比べて、勝手に自己肯定感を下げてしまう。
ママたちが他人と比較してしまう社会構造が問題なのですが、比較することの罠について、さらに深掘りしていきましょう。
隣の芝生はなぜ青い? 比較の罠
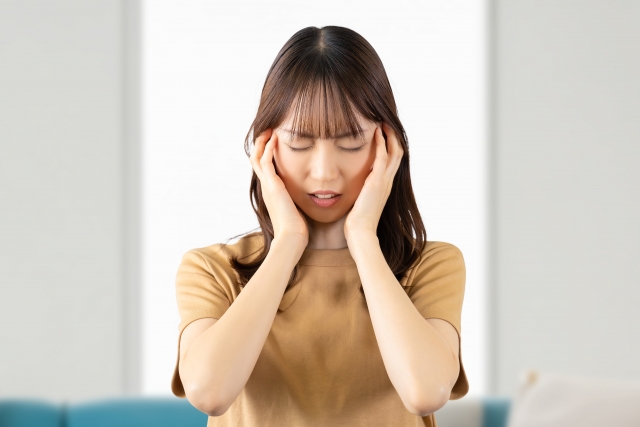
うらやましいと思っていた彼女も、実は自分と同じ?
筆者が印象的だったのが、詩穂と礼子がまだあまり仲良くなっていなかった頃、マンションの下ですれ違い、お互いをチラ見して、自分の選んだ道を納得させようとしているシーン。
お互いをうらやましいと感じるこのシーンが、まさに「隣の芝生」でした。
詩穂は、働いていないことへの後ろめたさを感じ、礼子は育児と仕事の両立で疲弊して、自分で自分を頑張っていると認めてあげないと、うらやましさと罪悪感で苦しくなる。そんな現代の生きづらさが浮き彫りとなっていました。
誰しも本当は頭ではわかっています。「他人と違う生き方を選んだとして、誰かに何か言われても、その人生を生きるのは他人ではなく自分なんだから」と。
しかし、今の生活やこの先の人生に迷いや不安、不満があるときほど「私、選択を間違えたのかな? このままでいいのかな?」となってしまうのです。
ワンオペ主婦、専業主婦(夫)、キャリア志向ママ…それぞれの苦しみ
ドラマでは、様々な立場の人が登場しました。
厚労省職員で男性育休を取得した中谷(ディーン・フジオカ)や、子どもや家庭を選ばずキャリアを築く女性、不妊治療中の女性、シングルマザーなど。
特に、中谷は、詩穂と出会った頃は「専業主婦は、贅沢」などと言い放ち、感じの悪い役どころでした。ところが、中谷自身も、実は日々子どもと一対一の環境で、孤独で追い詰められていることがわかります。
育休中、一度は「今日も一日誰とも喋らなかった」という経験が蘇ってきた人も多かったのでは?
子育ては大変で責任が重いのに、世間からは過小評価されがち
中谷は、もともとバリバリ働くキャリア官僚。初めは、専業主婦に対して偏見を持っていたものの、詩穂との出会いを通して、育児や専業主婦の現実を理解し、解像度を上げていく様子も描かれていました。
ドラマの中で、中谷が詩穂の夫・虎朗(一ノ瀬ワタル)に、家事を教えるシーンでは、
「放っておいたら死んでしまう、話の通じない子どもを相手に、ずーっとずーっと家事をする主婦のそのストレスは並大抵ではありません。」
と、世の中の主婦の声を代弁。このセリフにも、SNSでは称賛の声が相次ぎました。
仕事と違って、幼い子どもの育児中は、急な予定変更、想定外のトラブルなどが当たり前の世界。たまに予定通りに行くと奇跡レベル。よくぞ言ってくれたという中谷のこの言葉は、育児の大変さを経験した彼だからこそ出てきたものでした。
母としてじゃなく、“私”として選ぶ

自分の本音と向き合って、悩んだ末に選んだ道
ドラマの終盤、礼子が旦那・量平(川西 賢志郎)の転勤で、鹿児島に行くことに。会社を辞めて、旦那の転勤についていく決断をするも、心のどこかでは迷いがあり……。仕事は好きで、働き続けたい。でも家族がバラバラになるのも嫌。
そんな礼子も、自分の本音と向き合い、最終回には、退職せず働き続けることを選びました。誰かのためではなく、自分自身が納得できる選択をした結果でした。
“社会的な正しさ”よりも、“自分の納得”に目を向ける大切さ
ドラマの登場人物たちが選んだのは、社会的な正しさよりも、自分が心から納得できるかどうか。
「母親なんだから、家のことも完璧にすべき」「母親でもみんな働いているんだから、自分もそうしなきゃ」
“~すべき”、“~しなきゃ”で押しつぶされそうになる前に、一度自分の本音にも耳を傾けてあげることが大事なのだと気付かされます。世間から「~すべき」とされていることが、案外本当は自分自身で思い込んでいるだけかも? 義務感での選択をしなくなることが、自分らしい人生を始める最初の一歩になるのかもしれません。
他人の声に惑わされず、“私の人生”を肯定する生き方へ

今の時代、多様な生き方や価値観が選べるようになりました。
結婚する・しない、子どもを産む・産まない、働く・働かない。
選択肢や可能性が増えたという半面、それを自分で選びとっていかないといけないという決断や選ばない勇気が必要な時代とも言えます。自分が選ばなかった人生を生きている、隣のあの人がうらやましい。でも、自分はこの生き方を自分で選んだんだからと胸を張って言えるか。完璧な母親を演じるよりも、「私はこれでいい」と思える自分であること。それが、これからの時代を生きる女性たちに求められる強さなのかもしれません。
「母として」ではなく、「私として」選ぶ生き方。その一歩が、人生の景色を大きく変えていくのではないでしょうか。
この記事を書いたのは

株式会社LASSIC代表取締役CEO。主に法人向けにマーケティングPR支援事業と個人向けにキャリアデザイン事業を展開し、自身も国家資格キャリアコンサルタントの資格を取得。大手広告代理店勤務を経て、33歳で起業。自身が不妊治療と仕事の両立で悩んだ経験や“キャリア迷子”を経て独立した経験から、ワーママや女性のキャリア支援に尽力。会社設立から3か月後、第一子出産。現在は5歳&2歳の娘の子育てと起業に奮闘中。株式会社LASSIC【公式】サイトはこちら>>





