親と子どもは上下の関係ではなく対等である

何度言っても片づけをしない、走ってはいけない場所で走る、静かにするべき場所で大声を出すなど、子どものことを叱った方がいいと思える場面はよくありますよね。でも実は、子どもに対して「叱る」ということは必要ないんです。じゃあ、しつけはしなくていいの?いけないことをしたらどうするの?と思いますよね。今回は子どもを叱るということについてお話していきます。
「叱る」という行為は立場が上の人から下の人に対してする行為です。親と子はあくまでも対等。親の方が先に生まれているし、親から生まれた子どもだけど、大人が上で子どもが下という上下関係ではなく、子どもも一人の人格を持った人間で、我々大人も同じ人格を持った人間。あくまでも立場は対等であるべきで、お互いにリスペクトを持てる関係性を築いていきたいところです。
子どもは叱られるために悪いことをしているわけではない

子どもは叱られるために何か悪いことをしているのではありません。この世界のことを我々大人より知らないし、いろんなことを試したり、失敗したり、善悪や制限を学んでいる真っただ中。
大人からすると「なんでそんなことをするの?」「わかっているはずなのに…」「何回も言ってるのになんでわからないの?」などと、思ってしまいますよね。そんな時、子どもに対して上から叱るのではなく、繰り返し伝えるということを意識しながら関わっていくようにしましょう。
どうやったら子どもに言いたいことが伝わって、子どもの行動が少しずつ変わっていくのか、具体的な例を紹介していきますね。
走ってはいけない場所で走っている

子どもにはそこが走っていい場所か、そうじゃないかが分からないことがあります。この場合、して欲しい行動をなるべく具体的に伝えるといいでしょう。
NG「走らないで」「歩きなさい」
↓
OK「ここは歩くところだよ。お母さんとこうやって歩こうね」「人が多いから歩こうね。お父さんと手をつないで歩こう」
玄関で靴を脱ぎ散らかしている
靴を脱いだらそろえるということは、できればルール化したいことでもありますよね。しかし、子どもにはそれが難しく、なかなか定着させることができません。ここでも、具体的にして欲しい行動を伝えることが大事。そして、実際に大人がその行動をして見せることも有効です。

NG「散らかさないでよ」「いつも言ってるでしょ」
↓
OK「ちょっと来て。靴は玄関にそろえて置いて欲しいの。お母さんがやるから見ててね」
静かにして欲しい場所で大声を出している
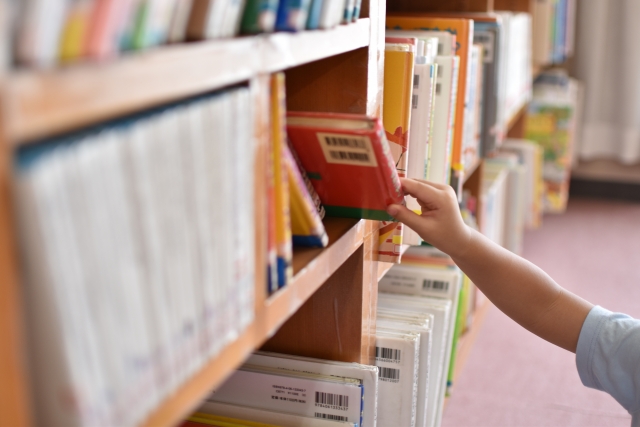
図書館や病院など、静かにしていて欲しい場所で大きな声で話すこともよくありますよね。子どもは声の音量を自由自在に調整できるほど、機能が発達していません。どのくらいの音量で話せばいいか、大人がその音量で話をして、子どもに聞かせてあげてください。
NG「うるさいよ」「静かにして!」
↓
OK「みんな本を読んでいるから、このくらいの声で話そうね」
おもちゃなどを片付けない

遊びに夢中になって、なかなか片付けをしないこともよくありますよね。ただ片づけないだけでなく、片付け方が分からないこともあるかと思います。なので、子どもに選択肢を示してあげるのもひとつです。そして、何をどこに片づけて欲しいのか、具体的に伝えるようにしましょう。
NG「いつまで遊んでいるの!」「さっき片付けなさいと言ったでしょ」
↓
OK「そろそろ片付けようか?どれから片付ける?」
「うるさい」「来ないで」など、言ってほしくない言葉を使う

親やお友達に対して「うるさいなー」「こっちに来ないでよ」など、あまり使ってほしくない言葉を使うこともあるかと思います。わざとその言葉を選んでいるのではなく、なんて言えばいいかがわからず、その言葉を選んでいる場合もあるので、どうやって言ったらいいかの具体例を示してあげましょう。
NG「そんな言い方しないの!」
↓
OK「そういう時は『いま、あそんでいるからちょっとまってね』と言えばわかるよ」
食事中に立ち歩く・遊び出す

食事に集中してくれないと悩む親御さんも多いですよね。前回の記事でも紹介したのですが、遊んでいる子どもに、どういう行動をとってほしいかを具体的に伝えてあげましょう。
NG「席を立たないで」「遊ばないで食べなさい」
↓
OK「このいすに座って食べようね。次は何を食べようか?」
やってほしいことを肯定的に子どもに伝えよう

「もうわかるでしょ」「こうしてよ!」と思うことは、日々、子どもと過ごしていると出てきますよね。物事の度合いによって、感情的になることもあれば、これは叱らなきゃ!という責任感から叱ってしまうこともあります。
しかし、忘れてはいけないのは、子どもは大人を困らせるためとか、叱られるためにやっているわけではなくて、まだまだいろいろなことを学んでいる真っただ中ということ。「いろいろことを吸収している段階なんだ」と捉えてあげて、繰り返し具体的な方法を示してあげましょう。
その際のポイントは、否定的に言うのではなく、肯定的に。否定の言葉ではなく、ポジティブで肯定的な言い方で、やってほしいことを具体的に伝えるという関わりをすることです。
記事監修

モンテッソーリ教師あきえ
幼い頃から夢見た保育職に期待が溢れる思いとは裏腹に、現実は「大人主導」の環境で、行事に追われる日々。そのような教育現場に「もっと一人ひとりを尊重し、『個』を大切にする教育が必要なのではないか」とショックと疑問を感じる。その後、自身の出産を機に「日本の教育は本当にこのままでよいのか」というさらなる強い疑問を感じ、退職してモンテッソーリ教育を学び、モンテッソーリ教師となる。「子育てのためにモンテッソーリ教育を学べるオンラインスクール Montessori Parents」創設、オンラインコミュニティ”Park”主宰。2021年1月に初著書「モンテッソーリ教育が教えてくれた『信じる』子育て」(すばる舎)、2022年3月に「モンテッソーリ流 声かけ変換ワークブック」(宝島社)を出版。
あきえ先生主宰オンラインスクール「Montessori Parents」
あなたにはこちらもおすすめ


取材/本間綾





