日銀とはどんな銀行?
「日銀」とは、「日本銀行」の略称です。銀行は銀行でも、私たちがよく利用している一般の銀行とは役割や業務内容が異なります。まずは、日銀の基本情報を確認しましょう。
日本で唯一の中央銀行
日銀は、日本で唯一の「中央銀行」です。中央銀行とは国・地域の金融機構の中枢となる銀行で、お金を発行したり、物価を安定させる政策を行ったりして、世の中の金融をコントロールしています。
例えば、アメリカでは「FRB(連邦準備制度理事会)」、イギリスでは「BOE(イングランド銀行)」、ユーロ通貨圏では「ECB(欧州中央銀行)」が中央銀行の役割を担っています。
一般的な銀行は株式会社ですが、日銀は株式会社や政府機関ではありません。日本銀行法と呼ばれる法律に基づいて設立された「認可法人」という組織で、財務省が所管しています。

設立の経緯とは
日銀が業務を開始したのは、1882(明治15)年です。明治維新以降、日本は近代化に向けた政策に取り組むための資金を不換紙幣(ふかんしへい)の発行で調達しました。
不換紙幣とは、金貨や銀貨などの正貨と交換できる保証がない紙幣(お札)です。西南戦争の勃発後、政府や各地の国立銀行が大量の不換紙幣を発行すると、物価が急激に上昇するインフレーションが起こります。
政府は不換紙幣を回収するために日銀を設立し、紙幣の発行を1カ所だけで行う決定をしました。
所在地と組織について
日銀の本店は、東京都中央区日本橋本石町にあります。旧館・新館・分館に分かれており、上空から見た建物の形は「円」の字に似ています。

本館である旧館は、1896(明治29)年に完成した石積みレンガ造りの建物です。分館には入館料無料の貨幣博物館が併設されているため、じっくりとお金の歴史を学べます。
日銀の支店は32カ所ありますが、全ての都道府県に設置されているわけではありません(2024年5月時点)。支店のほかに、国内事務所・海外事務所があります。
出典:所在地(本店案内図)・入館案内 : 日本銀行 Bank of Japan
:貨幣博物館
日銀と一般的な銀行の違い
日銀は金融機構の中心となる銀行でありながら、支店がある都道府県が限られています。街中に日銀のATMがないことを不思議に感じている人もいるのではないでしょうか? 日銀と一般的な銀行の違いについて解説します。
個人や企業と取引しない
一般的な銀行は、個人や企業を対象に、お金を預かったり貸し付けたりする業務をしています。日銀は、個人や企業とは取引をしません。日銀に預金口座を開設しているのは、銀行をはじめとする金融機関がほとんどなので、日銀は「銀行の銀行」と呼ばれています。
日銀と金融機関はネットワークシステムでつながっており、瞬時に資金の決済ができる仕組みです。金融機関が一時的に資金不足に陥り、ほかに手立てがない場合、日銀が金融機関に資金を供給します。そのため日銀は、「最後の貸し手」とも呼ばれます。
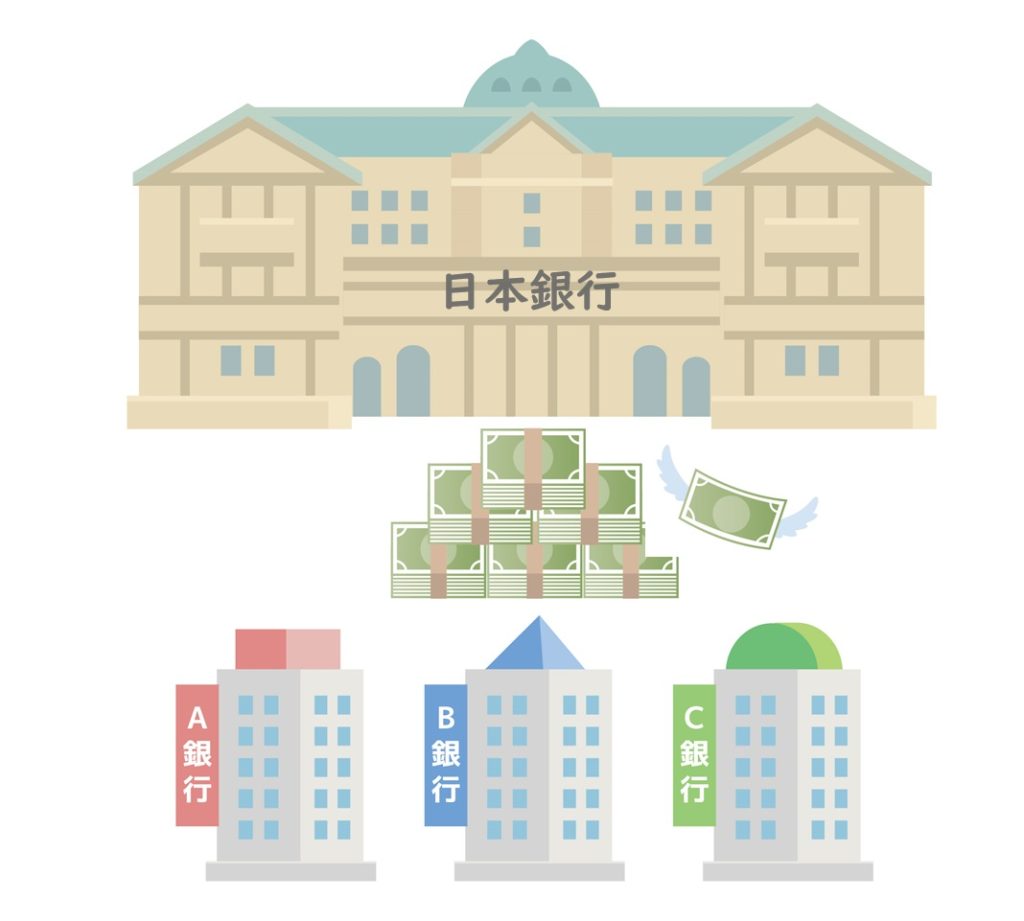
国のお金を管理している
日銀は銀行の銀行であると同時に、国のお金を管理する「政府の銀行」でもあります。日本政府は日銀に預金口座を開設し、「国庫金(こっこきん)」を預けているのです。
国庫金とは、国が所有するお金や国が一時的に預かっているお金を指します。日銀は日本銀行法や会計法などの法律に基づき、税金・社会保険料・交通反則金の受け入れや年金・公共事業費の支払いなどを行っています。
日銀では業務の利便性を向上させるため、国庫金や国債に関する事務などを民間の金融機関に委託しています。日銀の事務を代行している民間の金融機関は、「日本銀行〇〇代理店」という名称です。
日銀の3つの役割とは
日銀には、「紙幣の発行」「金融政策の実施」「金融システムの安定化」という重要な役割があり、どれか一つでも欠ければ、日本経済はうまく機能しなくなるでしょう。それぞれの役割を詳しく解説します。
紙幣の発行
日銀は日本で唯一、紙幣の発行ができる銀行です。ただし日銀が発行しているのは紙幣のみで、硬貨は政府が発行しています。紙幣は「銀行券」と呼ばれ、一万円券・五千円券・二千円券・千円券には「日本銀行券」と印字があります。
紙幣を発行しているといっても、日銀が紙幣を製造しているわけではありません。独立行政法人国立印刷局が紙幣を作り、日銀が費用を支払って引き取ります。全国の金融機関が日本銀行に保有している当座預金から紙幣を引き出すことで、世の中に紙幣が流通する仕組みです。

物価安定のための金融政策を実施
日銀では、物価を安定させるための金融政策を実施しています。「物価」とは、物やサービスの値段を総合した平均値で表したものです。
物価が上がり続ける、または下がり続けると、国民生活に大きな負担が生じるため、日銀では金融市場に出回っているお金の量を調整し、物価の安定化を図っているのです。
例えば物価が上がり続けている場合、日銀は金融機関の持つお金の量を減らし、金利を引き上げる政策を行います。「金利」とは、お金の貸し借りをする際、借り手が貸し手に支払う利息の割合です。
金利が上がれば、会社やお店は金融機関からお金を借りにくくなります。結果として経済活動が抑制され、上昇し続けていた物価が落ち着くのです。

金融システムの安定化を図る
「金融システム」とは、お金の受け払いや貸し借りをする仕組み全体のことです。日銀では世の中のお金の流れが滞らないように、以下に挙げるような取り組みを行っています。
●お金の受け払いや貸し借りをするサービスの提供
●金融機関への立ち入り調査やオフサイト・モニタリング
●支払い不能になった金融機関への資金供給
民間の金融機関の経営状態が悪化し、支払い不能になれば世の中のお金の流れが滞る恐れがあります。日銀ではリスクや経営状態を把握するために、金融機関に対する立ち入り調査やオフサイト・モニタリングを行っています。オフサイト・モニタリングとは、電話でのヒアリングや経営資料の分析などを通じた調査です。
日銀に関する豆知識
日銀は私たちの生活と密接に関わっていますが、一般の銀行と比べると存在を認識しにくいのが実情です。日銀をさらに深く理解するために、知っておくとためになる豆知識を紹介します。
日銀のシンボルマークは目玉?
紙幣表面のホログラムをよく見ると、目玉のような絵が印刷されています。それは日銀のシンボルマークで、本店の玄関口に掲げられた紋章でも同じマークを確認できます。

目玉のように見えますが、「日」という漢字の古代書体です。最初の紙幣である旧十円券が発行されたときはマークの突起部分が長く、周りに「日本銀行総裁之章」という文字が印刷されていました(上図・右)。
現在の紙幣は、表面に「総裁之印」、裏面に「発券局長」の印章があります。総裁之印の「総裁」とは、日銀総裁のことです。
日銀総裁とは何をする人?
日銀のトップは、「日銀総裁」と呼ばれます。ニュースなどで、日銀総裁の記者会見を目にしたことがある人もいるでしょう。日銀総裁の役割は、日銀の業務を取りまとめ、金融政策のかじ取りをすることです。
日銀では金融政策を決定するため、定期的に「金融政策決定会合」を開催しています。日銀総裁は会合の議長を務めており、総裁、副総裁を含む9人の政策委員会で意思決定が行われます。政策委員会は、日銀の金融政策の基本方針や運営に関する事項を審議し、決定する機関です。
日銀総裁の任期は5年で、国会の同意を得た上で内閣が任命します。歴代の日銀総裁は、日銀・財務省・旧大蔵省の出身者がほとんどです。

日銀の役割から金融や経済の仕組みを学ぼう
日銀には、「銀行の銀行」「政府の銀行」「紙幣の発行銀行」という三つの役割があります。普段の生活の中で、日銀の存在を意識する機会はそれほど多くありませんが、日銀の金融政策が私たちの暮らしに与える影響は非常に大きいものです。
日銀では物価の安定と金融システムの安定を維持するため、民間の金融機関と連携しながら、日々さまざまな業務をこなしています。役割や業務内容を知ることで、日本の金融や経済の仕組みが見えてくるでしょう。
こちらの記事もおすすめ

構成・文/HugKum編集部


