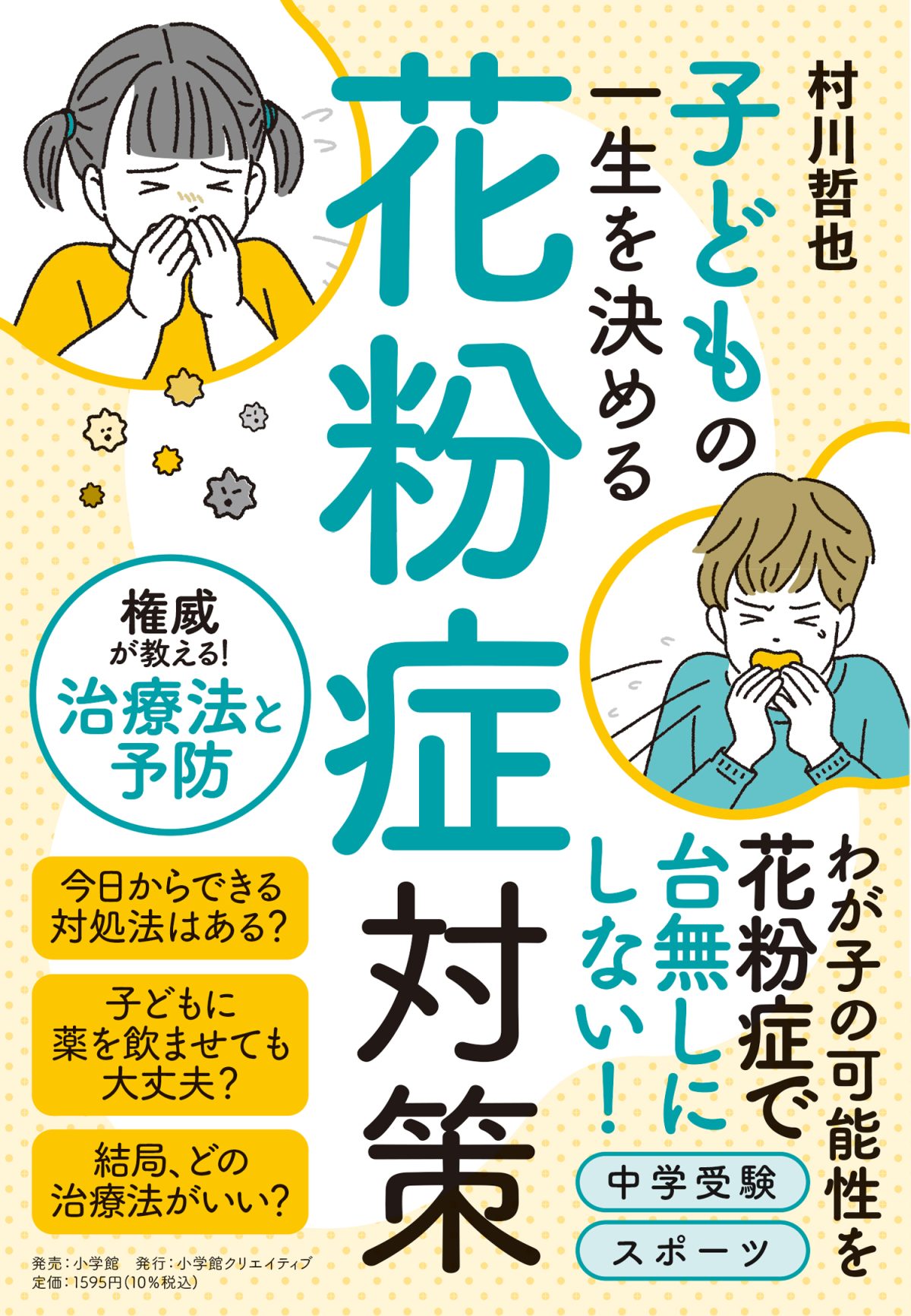※ここからは『子どもの一生を決める花粉症対策』(小学館)の一部から引用・再構成しています。
Q.子どもが鼻がつまって眠れない!どうしたらいいの?
A.鼻のまわりを温めて、血流を良くしましょう。
子どもによく見られるのは、鼻づまりがひどすぎて、夜、眠れないと訴えることです。よく眠れないと昼間に眠気に襲われ、授業中に寝てしまうこともあります。そのため、子どもの鼻づまりを解消し、よく眠れるような環境をつくってあげることが大事です。
鼻づまりは血流を良くすることで、改善します。
鼻のまわりを温めると、粘膜が広がり、鼻の通りが良くなります。寝る前に鼻に蒸しタオルを当ててから、鼻をかむとラクになります。
鼻づまりには湯船に浸かるのも効果あり!
入浴もシャワーで済ませるのではなく、なるべく子どもを湯船に入れて、体を温めてあげてください。40℃前後のぬるめのお湯に15分ほどつかるだけでも、体の血流が良くなり、鼻の通りも良くなります。
湯船の湯気も鼻の粘膜には良い働きをします。湯気を吸うことで鼻の粘膜がうるおい、鼻についた花粉などのアレルギー物質を排出する働きが活発になります。体を温めることは免疫力をあげることにもつながるので、鼻づまりがひどいときだけでも、湯船につかるように心がけてください。
それでも改善しないときは点鼻薬を使うことをオススメします。
点鼻薬は処方してもらえるので、近くの医療機関に相談してください。
そのほかユーカリやミントの香りが鼻づまりを良くするからと、アロマをたく人もいるかと思いますが、こちらははっきりとしたエビデンス(医学的根拠)はありません。
とはいえ、好きな香りをかぐと、リラックスして良く眠れる人がいることはたしかです。
アロマは医療目的ではなく、あくまでリラックス目的で使うようにしてください。

Q.花粉症予防になる食事ってあるの?
A.冷ましたご飯と小豆がオススメです。
私たちは主食として米、小麦を使ったパン、麺類を毎日のように食べます。
この米や小麦に含まれているデンプンに免疫力を高める働きがあることが最近の研究でわかっています。
従来、食品に含まれるデンプンはすべて消化酵素で分解され、小腸から吸収されてエネルギー源になるとされていました。ところが、デンプンには小腸で消化されずに大腸まで届き、食物繊維のような働きをすることが明らかになりました。
こうしたデンプンのことを「レジスタントスターチ(難消化性デンプン)」と呼びます。
レジスタントスターチは、米や小麦などの穀物類以外に、イモ類や豆類などの食品にも含まれています。
そして食物繊維のように、便通を良くし、乳酸菌などの腸内細菌のエサとなって善玉菌を増やす働きをしてくれることもわかっています。
レジスタントスターチは温かいものよりも、冷めたものに多く含まれます。
たとえば、ご飯なら炊き立てよりも、冷ました方が増えます。冷ますといっても、冷蔵庫に入れたようなヒエヒエのものではなく、手で触れて熱いと感じなければOK。
冷めるとご飯は少し硬くなりますが、よく噛んで食べることで満腹中枢が刺激され、満腹感を得られるため一石二鳥です。
レジスタントスターチの優等生・小豆の調理法
レジスタントスターチをとるのはご飯でもかまいませんが、効率良くとりたいなら小豆がオススメです。
小豆をたっぷりの水で柔らかくなるまで煮た後に、24時間冷蔵庫で冷やしてから食べれば手軽にレジスタントスターチがとれます。
ただし、注意したいのが砂糖を加えないこと。砂糖を加えるとおいしく食べられるかもしれませんが、砂糖のとりすぎはアレルギーを悪化させる原因にもなります。
アレルギーは「コルチゾール」というアレルギーに対抗するホルモン分泌が減少すると悪化するのですが、砂糖(糖質)が多い食べ物を食べるとコルチゾールの分泌が減ります。
そのため、花粉症をより悪化させる原因にもなるので、砂糖入りの小豆は避けた方が好ましいのです。
何も味つけをしない小豆は、子どもにウケが良くないかもしれません。
その場合は、小豆を入れた赤飯をたいて、それを冷まして食べさせても大丈夫です。
Q.花粉症の薬ってどんなものがあるの?
A.抗ヒスタミン薬が一般的
花粉症の治療で使われる薬は抗ヒスタミン薬、抗ロイコトリエン拮抗薬、漢方薬、点鼻薬などがあり、それぞれ用途や状況、体調によって使い分けられます。
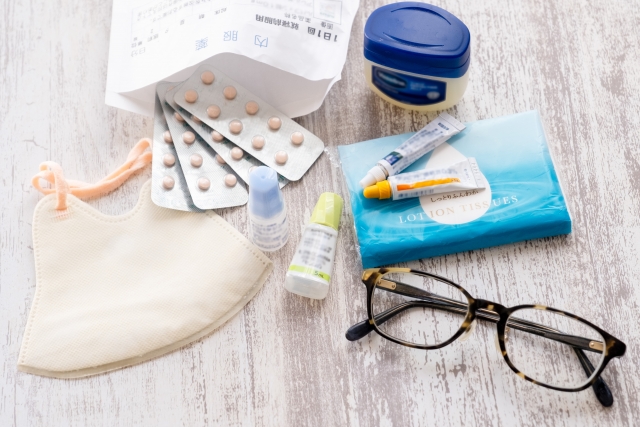
花粉症治療でよく使われ、一般的に知名度が高いのは抗ヒスタミン薬でしょう。
市販薬でも「アレグラ」や「アレジオン」などの名前で販売され、ドラッグストアなどで目にすることが多いかと思います。
「ヒスタミン」とは化学物質の一つで、免疫系の伝達物質や神経伝達物質として働きます。
花粉が侵入すると、体の中にあるマスト細胞などから、ヒスタミンが放出されます。
その後、ヒスタミンが受容体(H1受容体またはヒスタミンH1受容体)へ作用することでくしゃみ、鼻水、皮膚の腫れ、目のかゆみなどのアレルギー症状を起こすのですが、抗ヒスタミン薬はこの受容体をブロックし、ヒスタミンが作用しないようにします。
ヒスタミンの働きをおさえることで、アレルギー反応が出にくくなり、花粉による鼻水、鼻づまり、くしゃみなどの症状を緩和してくれます。
鼻水、鼻づまり、くしゃみが気になるなら、今すぐにでも薬を服用することをオススメします。
Q.眠気が出にくい薬はある?
A.「第2世代」の薬は副作用が少ないことで知られています。
「抗ヒスタミン薬が花粉症の症状を和らげてくれるのはわかったけれど、副作用が気になる」という人もいるでしょう。
しかし既出の通り、最近の抗ヒスタミン薬は眠気をはじめとした副作用が軽いものが多く、小さい子どもでも安心して飲めるものも増えています。
「抗ヒスタミン薬が眠気を引き起こす」というイメージをつくったのは、「第1世代」と呼ばれるものです。
抗ヒスタミン薬と一口にいっても、じつは開発された年代によって違いがあり、先に開発されたのが第1世代、第1世代から改良されたものを「第2世代」と呼びます。
第1世代と第2世代の違い
第1世代はポララミン(一般名:クロルフェニラミン)、アタラックス(一般名:ヒドロキシジン)、レスタミン(一般名:ジフェンヒドラミン)などがありますが、眠気や認知機能の低下など副作用が出やすいのが特徴で、今はほとんど処方されることはありません。
一方、第2世代は副作用が出にくいうえに効果が持続しやすく、アレルギーをおさえる働きも優れているため、花粉症治療には、この第2世代が使われるようになりました。

代表的な第2世代の抗ヒスタミン薬はアレグラ、アレジオン、ザイザル、ビラノアなどです。
抗ヒスタミン薬の中には錠剤以外にシロップもあります。
ザイザルシロップ(成分レボセチリジン塩酸塩)は、花粉症などのアレルギー性鼻炎のほか、じんましんや湿疹などの皮膚症状にも効き、生後6か月以上の赤ちゃんでも服用することができます。
アレルギー症状をおさえられ、さらに眠気や口の渇きなどの副作用が比較的少ないといった特徴があります。
ただ、自己判断で服用するものではなく、医師に相談する必要があります。
抗ヒスタミン薬の中には適用年齢が12歳以上や15歳以上のものなどがあり、親御さんの注意が必要です。
また、喘息に使われる抗ロイコトリエン拮抗薬は鼻づまりにも効果があるといわれていますが、子どもの場合は喘息と診断されない限り処方できません。
薬を服用したい場合は、必ず耳鼻咽喉科を受診して医師の診断を得てから、不安なことなどは薬剤師に相談してください。
※ここまでは『子どもの一生を決める花粉症対策』(小学館)の一部から引用・再構成しています。
『子どもの一生を決める花粉症対策』(小学館)
本書は花粉症に苦しむ子どもをもつ親御さんに向けた必読の一冊です。上でご紹介した内容のほか、すぐにできる対策から子どもに負担をかけずに根治可能な治療法まで、花粉症治療の名医がわかりやすく解説しています。
■こんな人におすすめ
・花粉症に苦しんでいるわが子の症状をラクにしてあげたい
・自分が花粉症(アレルギー体質)だから、子どもにも同じ症状が出るのではないか、と心配…
・子どもに花粉症らしき症状が出ているものの、治療せずに毎年そのままにしてしまっている
・花粉症治療の「正解」を知りたい
 著者/村川哲也(むらかわ・てつや)
著者/村川哲也(むらかわ・てつや)
医師・医学博士。日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会専門医・日本気管食道科学会認定専門医・日本レーザー医学会専門医。防衛医科大学校卒業後、カリフォルニア大学バークレー校ローレンスバークレー国立研究所勤務などを経て、2007年に喜平橋耳鼻咽喉科を開業、現在に至る。花粉症治療の中でも、特に舌下免疫療法の治療実績は日本有数を誇る。
2025年3月16日(日)、上記書籍の出版を記念して出版講演会が開催されます。講演会では著者の村川哲也先生によるさらに詳しい花粉症対策のほか、衆議院議員・玉木雄一郎さんなどスペシャルゲストとのクロストークも予定。著書を購入した方は無料で参加できます。
詳しくはこちら≪をご覧ください。
こちらの記事もおすすめ

構成/国松薫