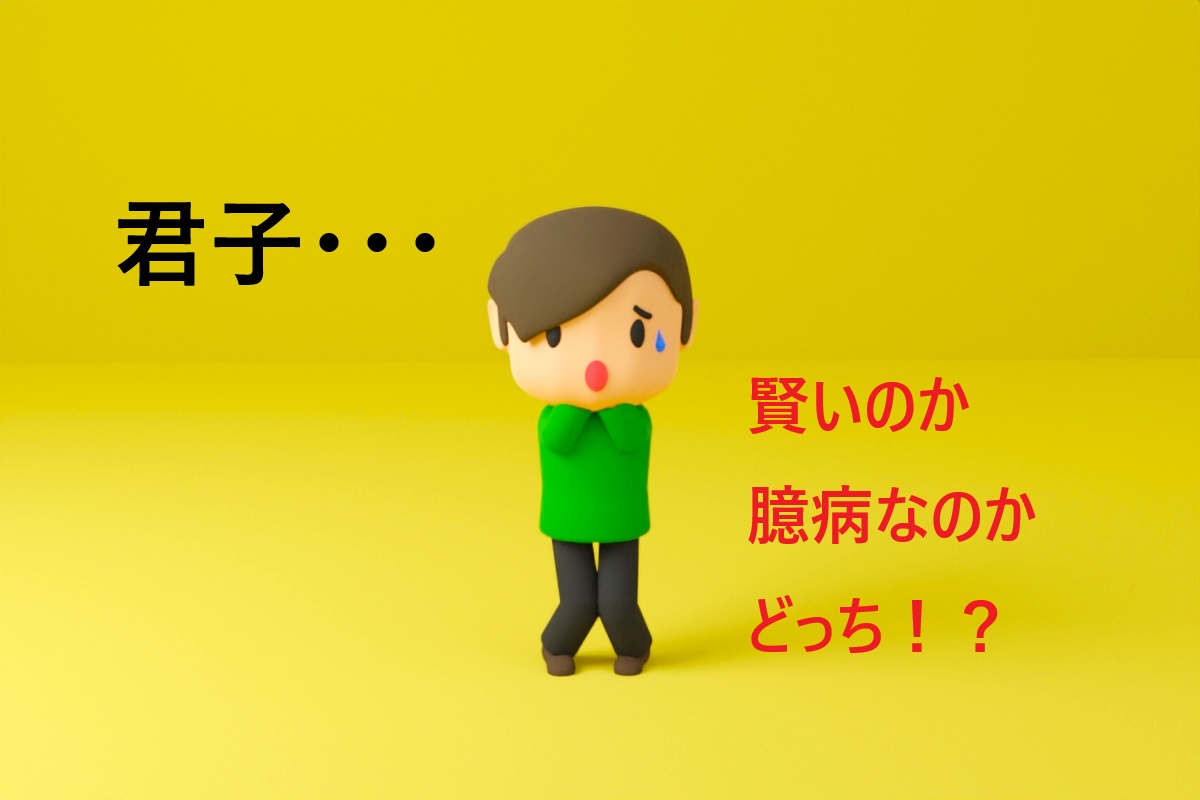目次
「君子、危うきに近寄らず」とは?
読み方と意味
まずは読み方と意味を確認しておきましょう。この言葉は『君子、危うきに近寄らず』と書いて「くんし、あやうきにちかよらず」と読みます。「危険なところには自ら近づかず、行動に気をつける」という意味です。
「君子、危うきに近寄らず」の由来・語源
「君子」とは古代中国の言葉で、学識・人格ともにすぐれた立派な人や、高い位についている人を指します。高い位や徳のある人は思慮深いため、危険なことに不用意に近づいて災難を招いたりしない姿が『君子、危うきに近寄らず』の由来となっています。
戒めや教訓、時には言い訳として使われることもある

慎重に行動するべきであるという教訓として用いられることも多く、危険な場所には近付いてはいけないという注意喚起としても用いられる『君子、危うきに近寄らず』。時には苦手なことを避けるための言い訳として使われることもあります。
それゆえ、『君子、危うきに近寄らず』を、危険を回避する賢さを称賛する言葉ととるか、臆病さを非難するニュアンスととるかは、そのときの文脈次第ということになります。
使い方を例文でチェック!
では、『君子、危うきに近寄らず』の使い方を例文でチェックしていきましょう。
1:台風が来そうな日に出かけようとしたら「君子、危うきに近寄らず」だよと警告された。
出かけてから後悔するような行動はとらないほうがいい、という戒めに『君子、危うきに近寄らず』使われる例文です。
2:短時間にもかかわらず、あまりにも高報酬のアルバイト募集を見て「君子危うきに近寄らず」という言葉が頭をよぎった。
あまりにも好条件だと、危険な「闇バイト」を疑い、回避する状況は『君子、危うきに近寄らず』と言えます。
3:割り込み運転を繰り返している車には「君子、危うきに近寄らず」で車間距離を取るようにする。
危険な運転をしている車には最初から近づかない、という行動はまさに『君子、危うきに近寄らず』と言えます。
類語や言い換え表現は?

では、『君子、危うきに近寄らず』を別の言葉で言い換えたい場合、どのような表現を使うことができるのでしょう。『君子、危うきに近寄らず』に似た表現を探してみました。
1:触らぬ神に祟りなし(さわらぬかみにたたりなし)
めんどうなことによけいな手出しをするな、という意味の「触らぬ神に祟りなし」。『君子、危うきに近寄らず』に似た表現です。
2:危ない事は怪我のうち(あぶないことはけがのうち)
危ないことは大きな怪我につながるから、最初から避けるほうがよい、という意味のことわざです。教訓としても『君子、危うきに近寄らず』に近い意味があります。
3:李下に冠を正さず、瓜田に履をいれず(りかにかんむりをたださず、かでんにくつをいれず)
「瓜を盗むのかと疑われるので、瓜畑では靴が脱げても履き直さない、スモモの木の下では手を上げると、実を盗むのかと疑われるから冠(帽子)をかぶり直すべきではない」、という意味で、疑いをかけられるような行いは最初からしないほうがいいという意味のことわざです。『君子、危うきに近寄らず』と同様、戒めや教訓として使われます。
4:三十六計逃げるに如かず(さんじゅうろっけいにげるにしかず)
めんどうなことが起こったときには、あれこれ思案するよりも逃げるのが得策であるという意味のことわざです。めんどうなことから「逃げる」点で『君子、危うきに近寄らず』に近い表現と言えそうです。
対義語は?
『君子、危うきに近寄らず』の反対の意味を表す言葉にはどんなものがあるのか考えてみました。
1:虎穴に入らずんば虎子得えず(こけつにいらずんばこじをえず)
危険を冒さなければ、大きな成功は得られないことをたとえたことわざです。危険なところに最初から近づかない『君子、危うきに近寄らず』とは逆の意味と言えます。
2:火中の栗を拾う
自分の利益にならないのに、他人のために危険を冒すたとえ。危険なところに行くことをいさめる『君子、危うきに近寄らず』とは反対の言葉と言えそうです。
3:危ない橋を渡る(あぶないはしをわたる)
危険な手段を取ったり、危険を承知で法律に違反するような行為を行ったりすることを表す「危ない橋を渡る」。危険を回避する『君子、危うきに近寄らず』とは反対の状況と言えそうです。
英語表現は?

では、『君子、危うきに近寄らず』は英語ではどのように言い表すことができるのでしょうか。最後に『君子、危うきに近寄らず』と言えそうな英語表現をご紹介します。
1:Keep out of harm’s way.
「危険なことには近づかない」という意味の定型文で、『君子、危うきに近寄らず』の英語表現と言えます。
2:Discretion is the better part of valor.
直訳すると「思慮分別が勇気の大部分」。勇気ある人は軽率な行動を取らない、という意味で『君子、危うきに近寄らず』と同じ意味になります。
3:A wise man never courts danger.
「賢い男は危険から遠ざかる」という意味の慣用句です。まさに『君子、危うきに近寄らず』に近い表現になります。
「君子、危うきに近寄らず」の意味と由来を知って、正しく使ってみましょう。
ビジネスの場でも使われる、『君子、危うきに近寄らず』。どんな状態か注意して使ってみてください。
あなたにはこちらもおすすめ

構成・文/kidamaiko