目次
修学旅行とどう違う? スタディツアーが深く学べる理由
― 他の学校の修学旅行や研修旅行と一番違うところは何ですか?
「何回も行く」、そして「テーマにフォーカスする」ことですね。修学旅行は1回きりですが、スタディツアーは中1から中3まで毎年、さらに高校でも継続します。何度も行けるからこそ、学びの続きが生まれる。それが一番の魅力だと思います。
― 同じ場所に何度も行く生徒もいるのですか?
はい。1回目の経験をもとに自分なりの問いや目的をもって関わることができるので、むしろ2回目以降の学びのほうが深まるくらいです。
― 「テーマにフォーカスする」というのはどういうことですか?
「防災を学ぶ」「伝統産業にふれる」といったテーマを決めて、現地の人から話を聞いたり、実際の活動に参加したりします。ただ名所を巡るのではなく、自分の中に「知りたいこと」を持って現地に行くので、そこでの感情が新たな問いのきっかけになるんです。
行き先を決めるのは自分。行き方を決めるのも自分

― スタディツアーでは、行き先を自分で選べると聞きました。
中学生は毎年複数箇所から1カ所、高校生は所属するコースにもよりますが以下のような全国15カ所以上から年2回選んで行くことができます。また、ゼロから旅をプロデュースする「オリジナルスタディツアー」もあります。
高校生が選ぶコースの一部を紹介
・北海道興部町:地元の高校生や教育サポーターと連携しながら、限界集落での6次産業化に向けた取り組みに触れる。
・三重県二木島:漁業の町での定置網漁体験から、地域のお祭りの復興お手伝いなどを経て「未来のコミュニティの在り方」を考える。
・三重県志摩市:地域住民の拠り所である市民病院にインターンとして参加し、一人の患者さんを担当して「ありがとう」をいただけるようなコミュニケーションをして行く。
・宮崎県都農町:高校が閉校になった地域の町おこしの取り組みを体験し、地元に根ざした企業にインターンする。
それぞれに魅力がありますが、ポイントは「選べる」ことなんです。行き先の候補は変わることもありますが、「どこへ行くか」「何をしたいのか」まで自分で決めるのがスタディツアーのスタート地点です。
― 旅の始まりからすでに“探究”が始まっているわけですね。
「自分が選んだ場所」「自分が選んだテーマ」だからこそ、生徒たちは本気になります。旅が“自分ごと”になると、姿勢もまったく変わるんですよ。ノートが真っ黒になっていて私たちも驚くくらいです(笑)。
― そうした体験は、進路や将来の選択にもつながりそうですね。
実際そうなんです。高校では、自分で旅を企画するプロジェクトに取り組む生徒もいますし、地方のインターンに参加する子もいます。スタディツアーで訪れた地域に就職を希望している卒業生もいるんですよ。旅を通して、自分の興味や問いがどんどん育って行くんです!
「6年間で100人の大人に出会おう」

― スタディツアーでは、出会いも大事にしているそうですね。
「6年間で100人の大人に出会おう」と言っていますが、卒業生に聞いてみると、高校時代だけで200名以上の大人に会っていると言っていました。6年間ですと、300名を超す出会いをしている生徒もいると思います。
子どもたちの周りにいる大人は、親、学校の先生、塾の先生などに限られていますよね。でも社会には、農家さん、漁師さん、観光業の方、起業した若者、福祉の現場で働く人…さまざまな大人がいます。
― 職業ではなく、“生き方”に触れるということですね。
そうです。「この人すごいな」と思える大人にリアルに出会うと、生徒たちの目が変わります。ある子が「この人、話してるときの目がすごかった」と感想を言っていました。その人から“伝わる何か”が、生き方のヒントになるのでしょう。
― 出会いが将来への“憧れ”にもつながりそうですね。
将来なりたい職業に直接つながるというよりは「ああいうふうに生きたい」と思うような価値観に出合えると、進路を決めるときにすごく効いてくると思っています。
つづきがある。それが、スタディツアーの学びの本質

「また行きたい」「次は自分が」問いのつづきが育って行くのはなぜ?
― 生徒たちは旅から戻ってどんなことを感じているんでしょうか?
とにかく「また行きたい」と(笑)。旅の中で人と関わる経験をすると、「次は自分が何かしたい」「少しでも役に立ちたい」という気持ちが自然と出てくるんですね。
― 実際にその後も関わりがつづいている子もいるんですか?
はい。祭りの手伝いに再び訪れたり、地元の商品を使った取り組みに関わったり。最初は“お客さん”だった子が、次は“地域の一員”として関わって行く変化が私たちもうれしいです。
― また行きたくなる旅なんですね。
また会いたくなるんでしょうね。誰かとの関係がつづいて行くことで、自分の中の問いも、気づきも、終わらずに育って行く。“つづき”があるところに学びの本質を感じます。
1回きりじゃない。旅で生まれた問いを「クロスカリキュラム」で深める
― スタディツアーは現地に行って終わりじゃないんですね。
そこが一番大事かもしれません。旅から帰ってきたあと、本校独自の「クロスカリキュラム」の時間を使って、旅の振り返りや探究活動を行います。ここでは、自分の感じた“モヤモヤ”や“ひっかかり”を言葉にして、「問い」に変えて行くんです。
― 「クロスカリキュラム」とはどのような活動ですか?
教科の枠を超えて、自分の「好き」や関心から学びを広げて行く探究型の授業です。毎週水曜日は丸一日このクロスカリキュラムにあてています。
― 旅が“問い”になって、さらに学びが広がって行くわけですね。
そうなんです。「あの場面で心が動いたのはなぜだろう?」と、問いを深掘りすることで、旅の体験が自分の中で生きて行きます。
高校生はゼロから旅をプロデュース
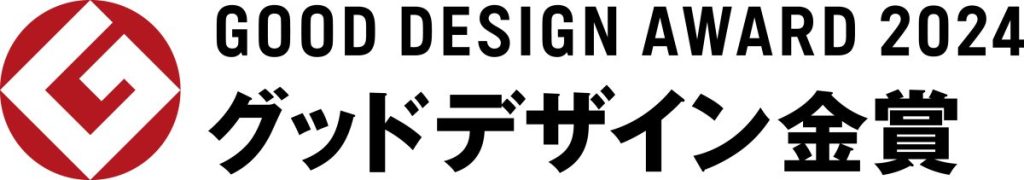
― 2024年、グッドデザイン賞を受賞したことでも注目されているスタディツアーですが、最近の取り組みで特に印象に残っていることはありますか?
はい、ありがたいことに、スタディツアーの仕組み全体が評価されて、経済産業大臣賞をいただきました。最近では、「戦争をテーマに学びたい」という声が生徒からあがり、高校生が広島のスタディツアーをゼロからつくりあげたのが印象的ですね。
― 生徒自身で企画したんですか?
広島の原爆資料館に行くだけでなく「現地の同世代と対話したい」と、戦争を語り継ぐ活動をしている地元の高校生ボランティアのみなさんに自分たちで連絡をとりました。彼らに案内してもらいながら一緒に資料館を回り、感想を語り合う非常に濃い時間を過ごしました。
― 最後に、スタディツアーの今後の展望を教えてください。
生徒たちが自ら動きだすことで、スタディツアーの形もどんどん進化していると感じます。今後は、旅の選択肢をもっと広げたり、より長期的な地域との関わりを設計したり、自由度の高いプログラムも検討しています。
スタディツアーは“行って終わり”の体験ではありません。出会いがつづいて行くこと、学びが時間とともに熟して行くこと。そこに私たちが目指す「未来に向かう教育」のヒントがあると思っています。
グッドデザイン賞2024受賞「新しい教育の在り方 [スタディツアー~地域と生徒の未来創造の旅~]」の紹介動画はこちら
著作権利者:(C)JDP
サイト名:GOOD DESIGN AWARD
リンクURL:https://www.g-mark.org
あなたにはこちらもおすすめ
お話を聞いたのは

さんとう・りょぶん 新渡戸文化中学校・高等学校副校長、担当教科は生物。一般社団法人 Think the Earth 、株式会社ゲイトなど複数の組織、企業と兼務。2004年に都立高校教員となり、オール実験の授業や生徒の「問い」だけで進める授業、生徒が主体的・自立的に学びを進める「対話式・双方向性授業」などを実践。企業やNPO、NGOとパートナーシップを組んだPBL(Project Based Learning)で多くのプロジェクトを生み出している。2019年から現職。同年、環境省グットライフアワード環境大臣賞受賞。2022年6月に一般社団法人 旅する学校を設立し代表を務める。
取材・文/黒澤真紀






