目次
「不惑」とは?
まずは、『不惑』の読み方と意味、由来をご紹介していきます。
読み方と意味
この言葉は『不惑』と書いて、「ふわく」と読みます。「40歳(正確には、数え年の40歳)」「(考え方などに)迷いのないこと」の2つの意味を持つ言葉です。
由来・語源
中国の思想家・孔子による書物『論語』には「四十而不惑(四十にして惑わず=40歳になると、自分の生き方に迷うことがなくなった)」という一節が登場します。
この一節に由来し、『不惑』は「40歳」「迷いのないこと」の2つの意味を表す言葉として使われるようになりました。
20歳、30歳、50歳……はなんて言う? 孔子の『論語』にふれてみよう

「40歳」を示す『不惑』の他にも、20歳、30歳、50歳……を表す言葉が存在します。
孔子の『論語』には、それらの年齢を表す6つの言葉の元となった文章が登場。以下では、該当する箇所の原文&書き下ろし文を見てみましょう。
◆原文
子曰、「吾十有五而志于学。三十而立。四十而不惑。五十而知天命。六十而耳順。七十而従心所欲、不踰矩」
◆書き下ろし文
子曰く、「吾十有五にして学に志す。三十にして立つ。四十にして惑わず。五十にして天命を知る。六十にして耳順う。七十にして心の欲する所に従えども矩を踰えず」
どれも晩年を迎えた孔子が自分の人生を振り返って述べたもので、ざっくりとではありますが、以下のように訳すことができます。
先生(孔子)は言われた。
「15歳に学問を志した。
30歳の時に学問を修めて自立した。
40歳には考え方に迷いがなくなった。
50歳で天命を悟った。
60歳で他人の意見に耳を傾けることできるようになった。
70歳で自分の心のままに行動しても道を踏み外すことがなくなった。」
これらの文章をもとに、『不惑』のように年齢を表す以下の言葉が生まれました。ぜひ、あわせて覚えておきましょう。
15歳:志学(しがく)
30歳:而立(じりつ)
40歳:不惑(ふわく)
50歳:知命(ちめい)
60歳:耳順(じじゅん)
70歳:従心(じゅうしん)
使い方を例文でチェック!

では、「不惑」は具体的にはどのように使うことができるのでしょうか。例文を通して使い方を見ていきましょう。
1:普段の彼女は優柔不断だが、自分の進路に関しては【不惑】の姿勢を貫いた。
『不惑』を「迷いのないこと」の意味で用いた例。決断力のある様や、自分が決めたことを貫く様などを言い表すことができます。
2:40歳になったということは、【不惑】の年になったということだ。孔子とは違って、わたしには未だに迷ってばかりだ。
こちらは『不惑』を「40歳」の意味で用いた例文です。そのまま『不惑』と言っても伝わらないことがあるので、「40歳」を指していることを示唆するような文脈で使うとよいでしょう。
類語や言い換え表現は?
では、『不惑』にはどのような類語があるのでしょうか。『不惑』が持つ「40歳」「迷いのないこと」それぞれの意味に類する言葉を集めてみました。
1:四十路(しそじ)
『四十路』とは、「40歳」を意味する言葉です。
十路とは10年の区切りを示す言葉で、40歳であれば『四十路(しそじ)』、30歳なら『三十路(みそじ)』、20歳なら『二十路(ふたそじ)』と表現されます。
2:初老(しょろう)
「老年に入りかけた年ごろ」の意味を持つ『初老』もまた、もともとは「40歳」を示す言葉でした。現代よりも人の寿命が短かったかつては、40歳になると初老のお祝いをすることがあったようです。
ただし、現在では『初老』と言われると50後半〜60代くらいをイメージされます。本来の意味と一般的なイメージにはギャップがあることを念頭に置いておきましょう。
3:不退転(ふたいてん)
『不退転』とは、「信念を持ち、自分の心を曲げないこと」を意味する言葉です。ビジネスシーンなどにおいて、強い決意を示すときに使われます。『不惑』を年齢ではなく「(考え方などに)迷いのないこと」の意とした場合、似た意味を持つ類語と言えるのではないでしょうか。
4:不撓不屈(ふとうふくつ)
『不撓不屈』とは「どんな困難に直面しても、くじけないこと」を意味し、標語や座右の銘として用いられやすい四字熟語です。「決断力が強い」ようなニュアンスは薄まりますが、『不惑』が持つ「迷いのないこと」を「意志が揺らがないこと」と解釈すれば、近い意味を持つ言葉と言えそうです。ただし、特定の年齢を表す語ではありません。
対義語は?
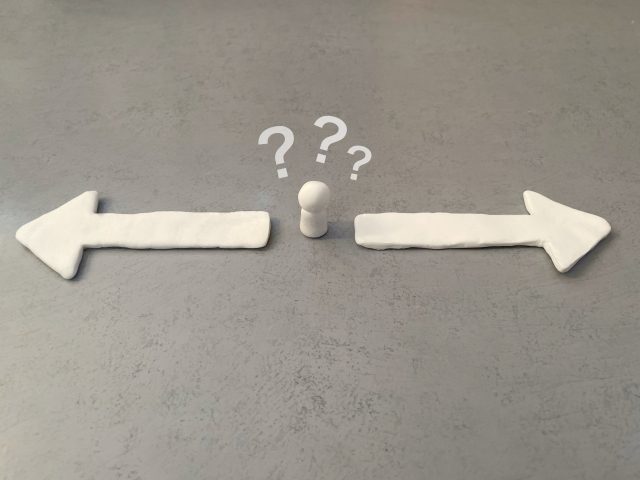
では、『不惑』の反対の意味を持つ言葉には、どのようなものがあるのでしょうか。『不惑』を特定の年齢ではなく、「迷いがないこと」の意に焦点をあてて、反対に近い言葉をご紹介します。
1:優柔不断(ゆうじゅうふだん)
『優柔不断』とは、「なかなか判断ができず、迷ってばかりいる様」を意味する言葉です。決断できない状態や、決断力のない様子を言い表すので、「迷いがないこと」の意を持つ『不惑』とは反対に近い言葉と言えます。
2:逡巡(しゅんじゅん)
『逡巡』とは、「決心がつかないこと」「ためらうこと」を意味します。ためらいや迷いのない『不惑』の反対の言葉として覚えておきましょう。
3:躊躇(ちゅうちょ)
「ためらうこと」を指す『躊躇』。決心が定まらない様子を言い表すので、自分の考えに迷いがない『不惑』とは反対に近い言葉として使うことができます。
4:意志薄弱(いしはくじゃく)
『意志薄弱』とは、「意志が弱くて決断できないこと」や「忍耐する気持ちが弱いこと」を意味する四字熟語です。「迷いのないこと」や「意志が揺らがないこと」のニュアンスを持つ『不惑』とは反対の意味を示しています。
英語表現は?

では、『不惑』は英語ではどのように表現できるのでしょうか。最後に『不惑』の英語表現を押さえておきましょう。
1:forty years old / the age of forty
「40歳」の意味をもつ『不惑』。英語にはこれに代わる単語がないので、「40歳」と言いたいときは、ストレートに“forty years old(40歳)/ the age of forty(40の年)”と言いましょう。
2:strong-willed
“strong-willed”とは、「意志が強い」と直訳できる形容詞です。“He is strong-willed.”といえば、「彼は意志が強い」という意味になります。『不惑』を「迷いがない」「意志が揺らがない」といったニュアンスで使った場合の英訳として使えそうです。
3:no delusions
“delusions”とは「誤った信念、思い込み」を意味する言葉なので、“no delusions”は「惑いがない」と直訳できます。『不惑』の語源となった、「四十而不惑」が “At forty, I had no delusions.”と英訳されていることから、あわせて覚えておきたい英語表現です。
30歳で自立、40歳には迷いをなくし、50歳で天命を悟る…『論語』から得る人生の指標
今回は、『不惑』という言葉の意味や語源、使い方、類語、対義語、英語表現までを一挙にお伝えしてきました。
「40歳」という年齢と「迷いがない」という意味、両方を表現できる興味深い言葉でしたね。30歳で自立し、40歳には迷いをなくし、50歳で天命を悟る…『論語』に書かれた孔子の生き方をなぞろうとすると、なかなかハードルが高いですが、目標として心に留めておくと志を高く保てるかもしれません。
あなたにはこちらもおすすめ

文・構成/羽吹理美





