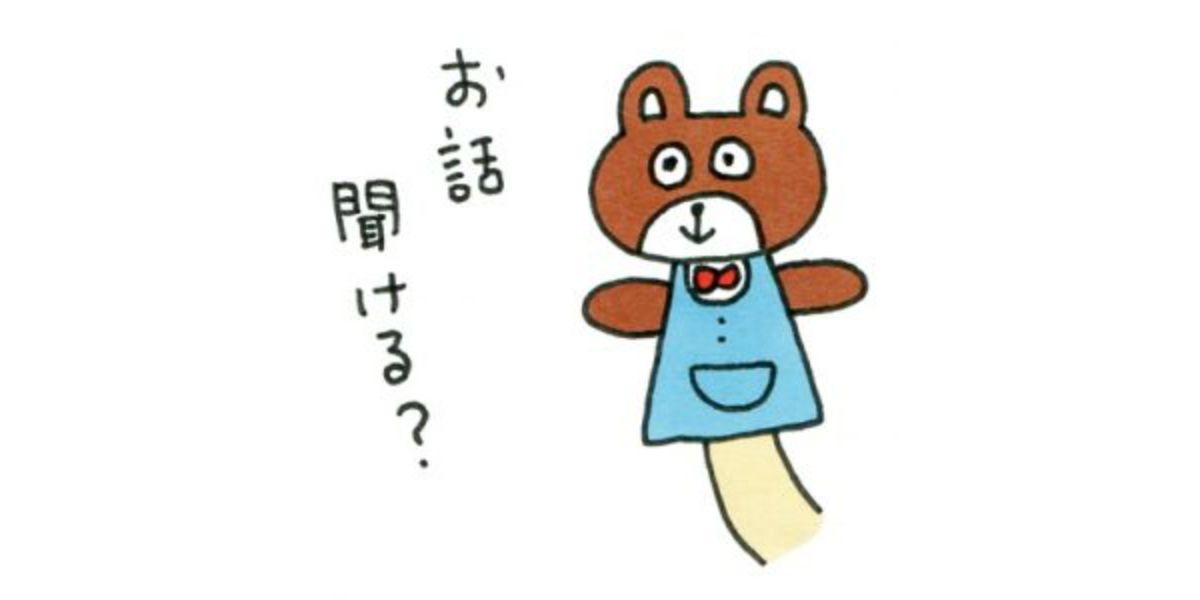目次
1歳児に絵本を読み聞かせるねらいとは?
言葉や絵に興味を持ち始める時期は、たっぷりと絵本を楽しんで
ひとり歩きも安定し、視野が広がって「自分の世界」がどんどんできてくる1歳児。個性が育ち始めるのもこの時期といわれています。
子どもの反応を丁寧に受けとめ、楽しいことを第一に読んであげましょう。たっぷりと絵本の楽しさを知った子どもは、やがて少しずつ1冊を聞きとおせるようになっていきます。読み聞かせは、本文以外の言葉を挟まないことが基本ですが、乳児のうちは“楽しい”ことが大前提。最初からきっちり読み通そうとはせず、遊びや会話の延長から、徐々に読み聞かせのかたちへと進んでいくと、絵本が苦手な子も絵本の世界にすんなり誘い込めます。文を読むペースは、ゆっくりと。言葉が聞き取れるように、はっきりと丁寧に読みます。
興味のあるページからでOK。しっかりコミュニケーションを
周囲の人と共感し合うことができるようになってきますから、ときには読み手が「楽しいね」「おいしそうだね」「きれいだね」などと声をかけてもいいでしょう。目を合わせてうなずいたり、手をたたいて笑ったりする光景も見られるはずです。集中できず、すぐに絵本を嫌がってしまう子には、最初から最後まで一度に1冊を読みきろうとせず、気になるページを開き、絵を見て親子で会話するところから始めてみましょう。そこで楽しそうな反応があれば次のページをめくり、前のページとの絵の変化を会話するというように、少しずつ進めてみてはいかがでしょうか。
絵本を読まない、聞かない1歳児への読み聞かせのコツ
始まりと終わりと告げてメリハリをつける
読み聞かせの時間の始まりと終わりは、はっきりと告げましょう。少しずつ読み聞かせの時間を生活のなかに習慣化させたい1歳児には、「お話の始まりの導入のかたち」を決めておくとよいでしょう。そうすれば家庭ではママやパパで読み手がかわっても、子どもは安心してお話の世界(読み聞かせ)に集中することができます。
0歳児と同様、パペットや手袋人形など、目に見えるものを用いて「お話が始まりますよ」と子どもの気持ちを導くのも一案です。子どもは好奇心を全開にして集中してお話を楽しみますから、その終わりもきちんと告げて、メリハリのある時間を作りましょう。
友だちと共感しあうことができるようになり、主人公になりきって楽しめる
段ボール箱を家に見立てたり、お人形を赤ちゃんに見立てた「見たて遊び」や、何かになったつもりの「ごっこ遊び」が始まるこの時期。読み聞かせにおいても、絵本と1対1で対話をする「赤ちゃん絵本期」からは一歩前進し、絵本の登場人物と自分を同一化して、お話の主人公になりきって楽しむことができるようになります。絵本を通して自分以外のほかの人の存在を認め、うれしいこと、楽しいことを他者と分かち合うことができるようになります。会話にはならなくても、「おいしいね」「たのしいね」と親子で共感し合うと楽しさも一層広がります。
「見る」「聞く」「嗅ぐ」五感で体験したことを手がかりに
この時期の子どもたちには言葉がどんどん蓄えられていきます。ものに名前があるということがわかり、耳で聞く情報と目で見る情報で、簡単なお話も理解できるようになります。
味わったことがあるもの、ふれたことがあるもの、嗅いだことのあるにおい……。自分の五感で体験したことが、子どもたちの興味の中心です。見て、知っているものが描かれた絵本であれば、よりすんなりとその世界に入っていくことができるでしょう。

1歳児への絵本選びのポイントは「オノマトペ」
二語文や繰り返しの言葉など、1歳児の成長に合ったしかけのある本を
「ママ、だっこ」「ワンワン、きた」など、ふたつの単語で成り立つ程度のおしゃべりから、徐々に語彙が増えていくころ。絵本の文章も「おくちを あーん」「あしを とんとん」などのように、二語文程度で綴られているものであれば、意味をちゃんと理解することができます。
さらに幼児は、単純な言葉のくり返しが大好き。日本語はオノマトペ(擬音語、擬態語)が豊富で、情景やものの様子を的確に表現している短い言葉がたくさんあります。
オノマトペは語彙の少ない幼い子どもにも伝わりやすく、たとえば「くんくん」と聞くと、においをかいでいるということが感覚的にわかるようです。乳児向けの絵本にはオノマトペが多く使われていますから、できるだけたくさんの言葉と出会わせてあげてください。その様子が伝わるように、頭の中でイメージしながら読むことが大切。「しんしん(と雪が降る)」と「どんどこ(と前へ進んで行く)」では、声の出し方も違ってくることでしょう。

1歳児への絵本の読み聞かせは「楽しい」ことが大前提
「おいしいね」「きれいだね」。ときには共感の言葉を投げかけて
本文以外の言葉を挟まないことが読み聞かせの基本ですが、乳児のうちは“楽しい”ことが大前提。最初からきっちり読み通そうとはせず、遊びや会話の延長から、徐々に読み聞かせのかたちへと進んでいきましょう。
文を読むペースは、ゆっくりと。言葉が聞き取れるように、はっきりと丁寧に読みます。
周囲の人と共感し合うことができるようになってきますから、ときには読み手が「楽しいね」「おいしそうだね」「きれいだね」などと声をかけてもいいでしょう。子ども同士で目を合わせてうなずき合ったり、手をたたいて笑ったりする光景も見られるはずです。
読書アドバイザーが選ぶ1歳児におすすめの絵本5選
【1】『あかちゃんたいそう』
鈴木まもる/作 小峰書店

まずは読み聞かせてください。2回めはゆっくり読みながら、動作をつけます。理想は大人と子どものペアですが、子どもがひとりで行うのも、ふたり1組で行うのもOK。ほっぺ・鼻・手・足と、それぞれ確認しながら、月齢差に留意して無理のない範囲で楽しみましょう。
ママパパの口コミ
「リズムがよくて読み聞かせしやすかった。」(20代・兵庫県・子ども1人)
【2】『だるまさんが』
かがくい ひろし/作 ブロンズ新社

「だ・る・ま・さ・ん・が」と、リズミカルに読み、十分に間をとってから次へ。「どてっ」で子どもは大喜び。間を十分取ることで次への期待感で絵本に集中します。だるまさんになって体を動かしたり、オノマトペを変えたり、さまざまに遊べます。ビッグブックもあり。
ママパパの口コミ
「小さい子でもわかりやすい内容と絵で1回読むともう1回と催促される」(20代・新潟県・子ども1人)
「1つずつの表現になっていて小さい子供でもわかりやすく楽しく読むことができた」(20代・神奈川県・子ども1人)
【3】『しあわせならてをたたこう』
デビッド・A. カーター/作 大日本絵画

「しあわせならてをたたこう、パチパチ」と、身近な動物が手をパチパチしたり、しっぽをパタパタしたりするしかけ絵本です。くり返し続けて読みましょう。1回めはゆっくり歌いながら、しかけを見せて読み聞かせます。2回めはテンポよく、子どもと一緒にパチパチと。
ママパパの口コミ
「歌いながら朗読すると子供がぐっすり休んでくれた。」(40代・福岡県・子ども2人)
【4】『どんどこ ももんちゃん』
とよた かずひこ/作 童心社

スーパー赤ちゃんは子どもたちに大人気。シンプルで単純なことが、おもしろさの秘密です。「どんどこどんどこ」のくり返しは、大げさにならないよう、一定のリズムでテンポよく読みましょう。最後のページは、「とん」と読んだら、たっぷり間をとって、絵を見せてください。
ママパパの口コミ
「保育園で月に1回週末に絵本を貸し出してくれる日があり、子供がももんちゃんシリーズが好きで何度もかりてきました。 同じような文章の繰り返しのリズムが聴いてる子供も読んでる親も心地良くて親子共に好きな絵本です。」(30代・長野県・子ども1人)
【5】『ねんねん ねこねこ』
長野ヒデ子/作 アリス館 こぐま社

そのまま読んでも楽しいのですが、全ページ「いとまきまき」のメロディーで読めば、子どもたちは大喜び。各ページの終わりで、「にゃん」と言葉を足すとさらに楽しくなります。くり返し読むと、子どもが一緒に「にゃん」。自然に声が出てきます。巻末に楽譜あり。
ママパパの口コミ
「絵がかわいい」(20代・千葉県・子ども1人)
1歳の子どもに絵本をプレゼントするなら、楽しいオノマトペ本がおすすめ!
子どもの誕生日に絵本をプレゼントしたいパパやママ。孫に、友人の子どもにプレゼントをしたいというときも……。ぜひ子どもの年齢に合った絵本を贈ってあげてください。絵本が心を豊かにしてくれることでしょう!
出典:『0~5歳 子どもを育てる「読み聞かせ」実践ガイド』/児玉ひろ美
教えてくれたのは

JPIC読書アドバイザー 台東区立中央図書館非常勤司書。日本全国を飛び回って、絵本や読み聞かせのすばらしさと上手な読み聞かせのアドバイスを、保育者はじめ親子に広めている。鎌倉女子大学短期大学部非常勤講師など、幅広く活躍。近著に『0~5歳 子どもを育てる「読み聞かせ」実践ガイド』(小学館)。
※本記事は、保育者向け専門誌の記事を、パパやママ向けに再構成したものです。
あなたにはこちらもおすすめ
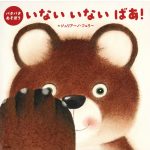
再構成/HugKum編集部、イラスト/小泉直子