前半の記事はこちら

目次
開発に没頭した高校時代。不登校どころか学校に「住んでいた」
――3年半の不登校から、学校に行き始めたのは、ロボット研究者、久保田憲司先生が教鞭を執る地元奈良の工業高校に行きたい、その一心でしたよね。入学してからは、どのような日々を過ごしていたのでしょうか?
久保田先生率いる開発プロジェクトに参加しました。高校3年生を中心に、車椅子の開発をしていたんです。車椅子は人が乗れる搭乗ロボット、オープンカーみたいなものです。プログラムで動かせば、自分が乗った状態で思うところに動くんですよ、バッテリーも強いエンジンも搭載されていて、すごくおもしろい。しかも、車椅子ってカッコイイものがないですよね。自分たちなら絶対カッコイイ車椅子が作れるはずだと、1年生にもかかわらず、お手伝いの形で参加させてもらいました。
――集団での活動は苦手ではなかったですか? つらさは感じませんでしたか?
好きなことでしたし、こういう開発は分担してすすめる部分が多いですから。
つらいどころか、楽しくて仕方がなかったですよ。久保田師匠といっしょに夜中まで発泡スチロールを削り続けたことを、今でも思い出します。クーラーもない教室で、工業用の扇風機回しながらひたすら削り続けていました。
車椅子の開発で高校生の科学技術チャレンジで世界3位に

その車椅子は全国の産業フェアで発表し、メンバーは卒業したので私がリーダーを引き継ぎ、さらに改良を加えました。改良後の作品を高校生科学技術チャレンジ(JSEC) というコンテストに出してみないかと言われ、嬉しかったですね。論文の書き方も教えてもらって、ついでにCGや動画をつくってCDに焼いて、論文につけて送ったんです。
このコンテストで文部科学大臣賞を受賞。翌2005年にアメリカで開催されたインテル国際学生科学技術フェア(ISEF)に日本代表として出場し、グランドアワード3位になりました。ISEFは賞金総額4億円、アメリカで開催される高校生科学賞のオリンピックのようなもので、80カ国1500人のファイナリストが集う大会です。
――すごいですね! 高校生の科学領域の最高峰に駆け上がったのですね。
JSECにしても、他の高校生たちは、スーパー進学校の頭のいい人たちでしたが、私たちは工業高校。偏差値が30くらい違っていたかもしれませんね。
賞をもらうよりうれしかったのが、憧れの人との出会い
でも、私にとって何よりうれしかったのは、このふたつのチャレンジを通して、憧れの方々に出会えたことです。ノーベル賞を受賞した小柴昌俊先生、ロボティクスが専門でもと早稲田大学教授の橋本周司先生。そして、当時のISECの企画の中心だった元朝日新聞の渡邉賢一さん(現一般社団法人元気ジャパン主宰)とは、アメリカで夜通し語り尽くしました。私が通っていた高専で人工知能をやっているときに、「早稲田大学が呼んでいるから来ないか」と言ってくれたのも、ナベケンさんです。奈良から東京に来て友人がひとりもいない中、当時のNPOや内閣官房の活動の末席に呼んでいただいたり、栃木の農園のコミュニティに参加させてもらったり。貴重な体験をたくさんさせていただきました。
――世界がどんどん広がっていきましたね。
高校3年生のその当時、「3年前はひきこもっていたんだなぁ」と思うと、そのギャップに自分でも驚いていました。

不登校時代は自分が社会の荷物だと感じ、何もかもつらかった
――家から出られない当時、何がつらかったでしょうか。
自分は社会の荷物だと思っていたので。親にとっても荷物でした。本当に親には申し訳ない気持ちでいっぱいでした。だから、なにをしてもらうのもつらいし、なにをするのもつらいんですよ。学校に来ていないくせに好きなことをやっている。それに罪悪感を覚えるようになっちゃっている。
そう思うと、何もできない。体も気持ちも動かなくなりました。言葉さえ出なくなって、ただ天井をみつめるだけになりました。
――その頃の学校の存在は絶大なもの、でしたよね。
「義務」だったんですよ。その義務をこなしていないやつに楽しい部活動とか放課後遊んでいる資格などないと。
学校になじめない自分がおかしいのだと思っていました。高校を卒業して、高専で人工知能を研究していたのですが、それも人と話すのが苦手だし、人と仲良くなったところでその関係を維持する事も苦手だし、人間関係疲れたし、申し訳ないという気持ちを抱くのもいやだし。自分にとって都合のいい相手を作ればいいと思ってAIをやったんです。
不登校の頃は、いかに死なないようにするか考えていました。でもそれいいなと。生きる理由を考えなくていい。すごくそれはいいなと思った。
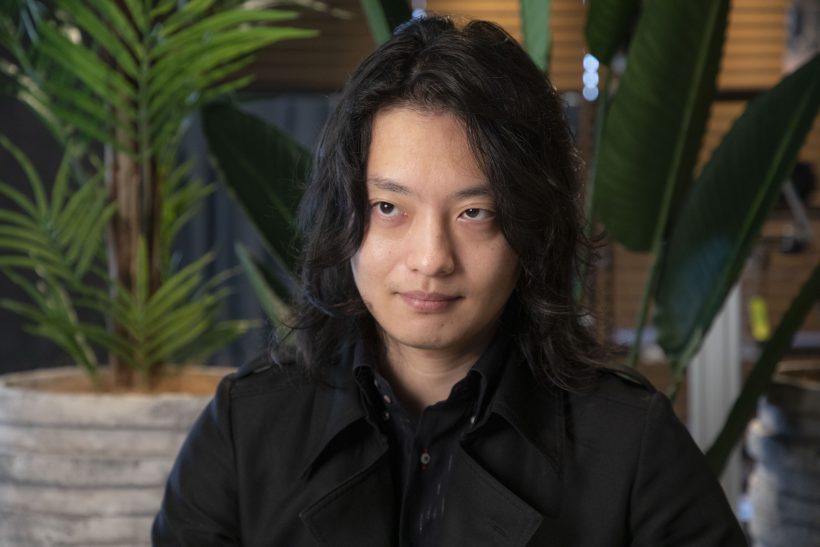
不登校時代、衝動的に命を絶ちそうな自分を感じていた
――自分でも危ないな、と思うときはありましたか?
衝動的に飛び降りてしまうよなところには、近づかないようにしていました。勝手に体が動いて池の前に立っていたこともありました。当時私は、深夜徘徊していたようなんです。気づけば外にいる。あ、俺は死にたがっているなという自覚もありました。父親はそれを警戒して、何メートルかおいてうしろからついて歩いてくれたらしいです。
――そんなことがあった後、大きな賞を受賞し、ご自身で納得し、そして生きる意味も見いだしたのですね。
社会に参加できることは、癒しだと思いました。そして癒しだとすると、それは全部「出会い」がもたらしてくれたのだと。そう考えると人と話したくないからと人工知能をやっていることにも違和感を覚えました。自分を苦しめるのは人なんだけれど、自分を生かしてくれたのも人、憧れを与えてくれたのも人で。
それならば、外に出ることができない人が、社会とつながる装置を作った方がいいんじゃないかと思ったんです。不登校の頃に天井を眺め続けて苦しんだ、あのつらさを次の世代に残したくないなと。そうだ、孤独というストレスをなんとか解消することをやろうと思ったのが17歳のときです。そう思ったら、死にたいと思うことがなくなりました。
不登校の体験から「孤独の解消」をロボット開発のテーマに
――それで、家から出られない人がパイロットになってロボットを動かし、外の世界をロボットとともに見て、外の人たちと交流する、そんなシステムを作ったのですね。そして、そのロボットがOriHime。このOriHimeで、オリィさんは世界的な研究者として絶賛されました。
人は自分の人生の中の失敗から「君はこれをしないほうがいい」とアドバイスをくれるのですが、自分が納得してみるまで、必要性がわからないことが多いでしょう。会社をつくるときも、いろんな人が「俺が失敗したから、こうしたほうがいい」といってくださったのですが、私は、失敗にまず自分が突っ込んでみたいんですよ。

――大人は子どもに失敗させないために、さまざまな警告や「これはやめておけ」という禁止をしたりしますね。
そうですね、でも人に言われるより、自分に納得感があるかどうかってけっこう大事だと思う。
「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」と、ドイツの鉄血宰相と呼ばれたオットー・フォン・ビスマルクは言いますが、私は愚者でいい。まあそれに対する反論かどうか、哲学者のヘーゲルは『我々が歴史から学ぶことは、人間は決して歴史から学ばないということだ」と言っています(笑)。
私はだから、自分の経験に投資するようにしています。今もお金を稼いだら全部自分の経験に変えたい。旅をしてもいいし。最近は、家のガレージに溶接機一式をそろえていろんなものを溶接しています。そうすると金属をくっつけるときやシリコンでフィギュアみたいなのをつくるときにも役立つ。しかも、なんでも1回やるとハードル下がるじゃないですかか。だから、3カ月に一度くらいちょっとずついろんなことやりたいなと思っています。
分身ロボットカフェの経営が今の一番の興味

――重度身体障害の方などがパイロットになり、Orihimeの接客を管理する「分身ロボットカフェDOWNverβ」も、その新しいことのひとつですね。大盛況ですね。
はい、そうです。今はこのカフェができたばかりだから、一番力を入れています。飲食店経営者になってしまったので、お客さんにどうやって楽しんでもらえるか、また、この後どう継続するのか、やりたいこと、やるべきことはたくさんあります。お客さんとして来てくれている子が、ずっとOriHimeを観察して、追いかけている子もいて。夢中になっている子たち見ていると、昔の自分を思い出しますね。
不登校には環境の変化が大事、でも自分が変わろうと思うかどうか
――改めて伺いますが、人は不登校から脱することができるのでしょうか。不登校が「孤独」であるなら、その克服はできるのでしょうか。
環境を変えることはとても大事だと思います。環境によって人って価値観ぜんぜん違ってきますから。ただ、自分が「克服したい」というモチベーションをもてるかどうかですね。変わろうと思わないと変わらない。
私は、不登校時代のあの孤独のつらさを身をもって知って、二度と味わいたくないと思った。そして「孤独の解消」を開発テーマにしました。孤独の解消がテーマでなければ、社交性を勉強しようなんって思わなかったですし。

また、私は以前、自分でできることは自分でやるほうがいい、と思っていました。けれど2019年から分身ロボットカフェをやろうとなったとき、とても自分ひとりではできないことを悟ったんです。完全にキャパオーバーだったんですね。その頃からチームで動くことに興味を持つことができた。30年かかりましたけれど、今はチームプレーの重要性を感じています。そんなふうに、人は変わる。けれど、人から言われても意外に変わらないものです。
「自分育て」もうまくいかない。まして「子育て」は難しい
――親は自分の子どもがすごくひとみしりだとか、不登校で学校にいけなくて社会とは断絶してしまうんだ、それが困るから今この子を変えようという風になってしまうけれど、結局、変わるのは自分でしかないんですよね。
自分って自分が思っている以上にコントロールできないじゃないですか。まして、子育てって「他人育て」ですからね。他人育てがうまくいくはずがなくて、なぜなら自分育てもうまくいかないから。明日なにかやろうとしたことは、自分に対しても人に対しても、破られてきたと思うんです。
それより、まずは保護者の方は、環境を大事にしてあげればいいのではないでしょうか。周囲の環境のあり方を大事にすれば、出会いと憧れが芽生える。その出会いと憧れにどう行き着くか――。そこに、「孤独の解消」のカギがあると思います。
オリィさんの言葉から考えたい、親としてまずできること
子どもが不登校になると、保護者は大きなショックを受け、自分のつらさを受け止めきれないほどになります。けれど、オリィさんの話を聞くと、子どものほうが何倍も、何十倍もつらいことが改めて分かります。しかも、そのつらさの中心は「親に迷惑をかけて申し訳ない」という思い。心配している親の姿を見て、本人のほうがつらくなるなんて――。衝撃を受けます。この子どもの思いを、保護者は忘れないようにしながら、何をしたらいいのか、何をしたら傷を深めるのか、考えていきたいですね。
プロフィール

吉藤オリィ(よしふじ・おりぃ)さん
本名吉藤 健太朗。自身の不登校の体験をもとに、対孤独用分身コミュニケーションロボット「OriHime」を開発。この功績から2012年に「人間力大賞」を受賞。 開発したロボットを多くの人に使ってもらうべく、株式会社オリィ研究所を設立。自身の体験から「ベッドの上にいながら、会いたい人と会い、社会に参加できる未来の実現」を理念に、開発を進めている。ロボットコミュニケーター。趣味は折り紙。2016年、Forbes Asia 30 Under 30 Industry, Manufacturing & Energy部門 選出。近著にミライの武器 「夢中になれる」を見つける授業 (サンクチュアリ出版)。2021年夏、日本橋に、家にいるパイロットがOriHimeを操作して店舗の来訪者に接客する『分身ロボットカフェDAWN』をオープン。
取材・文/三輪 泉 撮影/五十嵐美弥

