4月25日は世界ペンギンの日!
よちよち歩く姿と、愛くるしい表情で親しまれているペンギンたち。4月25日はそんな彼らのことを想い、地球環境について考える「世界ペンギンの日」です。
由来
「世界ペンギンの日」は、南極にあるアメリカの南極基地の隊員たちの発見から始まりました。
彼らの滞在するマクマード基地付近では、毎年同じ時期にアデリーペンギンが姿を見せます。その時期が毎年4月25日前後であったことから、隊員たちがその日を「ペンギンの日」と祝ったことに由来して、現在では世界的にペンギンについて考える日として普及しています。
日本では多くの種類のペンギンが飼育されている
実は、日本は世界でも有数のペンギン飼育国です。世界に存在するペンギンは一般的な分類で18種類、そのうち日本国内で飼育されているのはなんと11種類!
たとえば長崎にある長崎ペンギン水族館には9種類ものペンギンが飼育されており、全国各地でいろいろなペンギンを見ることができます。
参考:TCA東京ECO動物海洋専門学校
:長崎ペンギン水族館
ペンギンの日に関する出来事
ペンギンについてもっと興味を持ってもらおうと、「世界ペンギンの日」にちなんだイベントも数多く開催されています。
和歌山アドベンチャーワールド
和歌山県のアドベンチャーワールドではペンギン飼育エリアの大掃除イベントを開催し、動物や地球に優しい洗剤・掃除用具を使用したクリーニングの様子をライブ中継しました。
ほかにも多くの施設でペンギンのお出迎え、特別解説やパネル展示、体重当てクイズなど興味深いイベントが行われました。
伊勢シーパラダイス
2025年世界ペンギンの日に向けては、三重県の伊勢シーパラダイスで特別バージョンのお散歩を行い、さらに「ペンギン飼育員なりきり体験」を実施予定です。
このほかにもいろいろな施設でペンギンのイベントが予定されていますので、お近くの地域にあればぜひ行ってみてください!
ペンギンの種類と特徴
ペンギンとひとくちにいっても、住む場所から求愛方法、独自の特徴などその生態は実に多種多様です。それぞれのペンギンが持つユニークな生態を紹介します。
コウテイペンギン

ペンギンの中で最も大きく、体長はゆうに1メートルを超えます。
生態と習性
コウテイペンギンは南極に住むペンギンで、-60℃にもなる極寒に耐えながら繁殖を行うペンギンです。
求愛行動の際にはオスが羽を広げておじぎをし、強さや健康さをアピールします。また過酷な寒さに立ち向かうため「ハドル」と呼ばれる群れを形成し密集して暖をとる習性があります。ハドルは外側のペンギンと内側のペンギンが交代することで、群れ全体が均等に温まる仕組みになっています。
ユニークな特徴
メスはシーズンに1つだけ卵を産み、オスは孵化するまでの約2か月間、その卵を両足の上において温めます。
この間もオスたちはハドルを形成して暖をとり、絶食して卵を守り続けるのです。さらに産まれてある程度成長したヒナたちも、ハドルを形成して寒さに耐えながら狩りに出た両親を待ちます。
アデリーペンギン

白黒のツートンカラーに目の周りの白いリングが特徴で、Suicaペンギンのモデルとしても親しまれています。
生態と習性
アデリーペンギンも南極に住んでおり、南極観測基地の近くで見られることもあります。
主な食べ物は性別や年齢で異なり、メスはオキアミ類、オスは魚類を比較的多く食べるという報告例もあります。メスはシーズンに2つの卵を産み、まずはオスが卵を温めます。孵化するまでの約35日間、途中で一度だけオスとメスが交代して食事に行くのです。
ユニークな特徴
海岸近くの高所に巣をつくり産卵するため、オスは巣づくりでメスにアピールします。
巣の材料となる小石を拾い、ときには奪い合い、完成した巣の前で特有の鳴き声を上げてメスを呼ぶのがアデリーペンギンの求愛行動です。
イワトビペンギン

目の上の黄色い飾り羽と、頭の冠羽が特徴的なペンギンです。作品でキャラクター化されることも多く、世界中で親しまれています。
生態と習性
イワトビペンギンは、厳密には南インド洋から南太平洋に生息する「ミナミイワトビペンギン」とチリからアルゼンチン沖に生息する「キタイワトビペンギン」に分かれており、食べ物や狩りの方法も少しずつ異なっています。いずれもカラフルな外見が目を引きますが、やや攻撃的な性格を持っています。
ユニークな特徴
岩場のくぼみや平地に巣をつくって生活し、名前のとおり急な岩場を素早く飛び跳ねて移動します。
ほかのペンギンのヨチヨチ歩きとは違って両足を揃えてピョンピョンと跳ぶ姿から、英語でも「Rock hopper(ロックホッパー)」と呼ばれています。
ジェンツーペンギン

比較的大型のペンギンで、流線型の体形と鮮やかなオレンジ色のくちばしと足が特徴的です。
生態と習性
主にオキアミのほか小魚なども捕食し、水中での狩りも得意なペンギンです。潜水時の最大水深は水深80mにも達し、泳ぐ速度も時速約36kmと、泳ぎが得意なペンギンといえるでしょう。
海中での狩りの際も天敵のシャチやアザラシに気づくと、ものすごい速さで泳いで逃げることで有名です。
ユニークな特徴
ペンギンの中でも好奇心が強いといわれており、水族館ではお客さんに近づいてくることも多いとか。
また穏やかな性格から日本では別名「オンジュンペンギン(温順ペンギン)」という名前も付けられています。
マゼランペンギン

胸に2本の黒い帯が特徴的な、中型のペンギンです。
生態と習性
マゼランペンギンは温暖な気候を好み、アルゼンチンなど南米の海岸に住んでいます。
住みかはなんと巣穴で、砂浜に掘った穴や岩場のすき間などに入り込んで直射日光や天敵から身を守ります。
ユニークな特徴
マゼランペンギンは、夫婦の絆が非常に強いことで知られています。
ほかのペンギン種ではシーズンごとにペアがかわる種も多い中、マゼランペンギンは基本的に毎年同じパートナーと繁殖し、卵の孵化後も協力して子育てを行います。
ペンギンの保護活動と環境問題
ペンギンたちの生息する南極や亜南極は、地球温暖化の影響を大きく受けています。ここではペンギンたちの現状と、保護活動について解説します。
絶滅危惧種としてのペンギン
日本では多くの種類のペンギンが飼育されていますが、その中には絶滅危惧種も少なくありません。日本で最も個体数が多いとされるフンボルトペンギンもそのひとつで、野生下では絶滅の危機に瀕している種です。
そのほかケープペンギンやキタイワトビペンギンなどを含む10種のペンギンも近い将来における野生での絶滅が危惧されており、さらにはその他の3種も準絶滅危惧種に指定されています。
世界中において、ペンギンたちはすでに過酷な状況に追い込まれているのです。
ペンギン保護のための取り組み
国際自然保護連合(IUCN)の調査をうけて、レッドリスト入りしているペンギンを救おうとする取り組みが世界各地で行われています。
生息地の保全や傷ついたペンギンの保護・治療、そして人工繁殖によりその個体数を回復させる活動も盛んです。そしてペンギンにとって大きな影響を及ぼす海洋汚染や地球温暖化など、環境問題への対策も注目されています。
地球温暖化がペンギンに与える影響
環境問題の中でも、地球温暖化はペンギンたちの生存を脅かす深刻な問題です。
地球温暖化は、海氷の減少、海水温の上昇、水質の酸性化を招きます。これらはペンギンの繁殖場所や餌場を奪い、餌となる生物が生存しにくくなるなど、ペンギンに限らず海洋生物全体の生態系バランスを崩す大きな原因となるのです。
多種類のペンギンが見られる施設を紹介
「ペンギンのことをもっと知りたい!」そんなあなたにおすすめしたい、多くの種類のペンギンに出会える施設を紹介します。
旭山動物園
4種のペンギンと出会える北海道・旭川動物園。冬の期間は雪の園内をお散歩するペンギンを見ることもできます。
仙台うみの杜水族館
5種のペンギンと出会える宮城県・仙台うみの杜水族館。ペンギンがカートに乗って登場し、間近で観察できるイベントもあります。
越前松島水族館
3種のペンギンと出会える福井県・越前松島水族館。1日2回のお散歩に加えて、泳ぎを真下から見られる空中水槽が人気です。
名古屋港水族館
4種のペンギンと出会える愛知県・名古屋港水族館。ペンギンたちのエサ代などに使われる「クルッと寄付」でエンペラーペンギンの羽根入りお守りがもらえるなど、ユニークな取り組みも。
海響館
5種類のペンギンと出会える山口県・海響館では、ペンギンの巣作りを観察できます。18種のペンギンの模型や質問コーナーを設けており、ペンギン博士になりたい人にはうってつけの場所です。
長崎ペンギン水族館
日本最多、9種類のペンギンと出会える長崎県・長崎ペンギン水族館。昭和34年、捕鯨船に乗ったペンギンが長崎にやってきたことをきっかけに、長年ペンギンの飼育と研究活動に励んでいます。
世界ペンギンの日はペンギンを愛でながら過ごそう
世界ペンギンの日は、かわいらしい姿で私たちを魅了するペンギンたちに思いを寄せ、彼らが暮らす地球環境について考える大切な日です。
国内では11種ものペンギンが飼育されており、各地の動物園や水族館ではさまざまなイベントも開催されています。この機会に、ペンギンの多様な生態や愛らしい行動を知り、未来のためにできることを一緒に考えてみませんか? ペンギンの魅力に触れることは、地球を守る一歩にもつながります。
こちらの記事もおすすめ
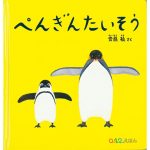
文・構成/HugKum編集部





