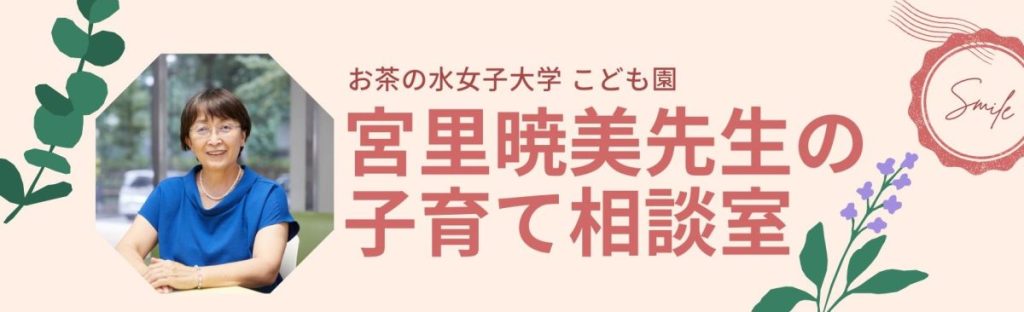
育児情報の多さに困惑……。この時期、本当にやっておいた方がいいことはなんですか?
0歳と2歳の子どもがいます。育児の情報を見ると乳幼児期にやっておいた方がいいことがたくさん書いてありますが、毎日の生活が精いっぱいで、とても全部はできそうにありません。この時期に必ずやっておいた方がいいことはなんでしょうか。できればシンプルに子育てを考えたいです。
① 0歳児は一緒に外に出てさまざまなものに触れる

0歳児の育児は親にとっても初めての体験の連続ですし、子どもは見るものすべてが新鮮。新生児期が終わり、外に出られる時期になったら、抱っこひもやベビーカーなどで外に出てみてください。外に出ると言っても大きな公園に行く必要はなく、自宅のベランダでもOK。風に吹かれたり、家の中とは違う香りを感じたり、それだけでも子どもにとってはよい刺激になりますし、お母さんの気分も変わります。
- 「あそこに犬がいるね。かわいいね!あ!ワンって鳴いたね」
「桜の花が咲いていてきれいね。今度お花見しようね」
「いいにおいがするね~。あの焼き鳥屋さんおいしそう」
家の近くをお散歩しながら、こんな風に話しかけるのもいいですね。近所の方が話しかけてくれることもあるかもしれません。大人にとっては何気ないことですが、0歳児にとっては適度な刺激になり、感性を豊かにするきっかけとなるのです。
②1歳間近になったら「探索する動き」を大切にしよう

0歳児の後半ごろからは、お座りができたり、ずりばいやハイハイをしたりと、行動範囲が広くなっていきます。
そこで見られるようになるのが「探索活動」。ティッシュを箱から出したり、棚に入っているものを全部取り出したり、大人からすると「なんでそんなこと?」と、思えるようなことを集中してやっている姿を見かけるようになります。つい止めたくなるのですが、気持ちに余裕がある時は、ぜひ好きなようにやらせてあげてください。特別なものではなくても、家の中にあるなんでもないものが、子どもにとってのいいおもちゃになります。※誤飲には気をつけましょう。
③歩行が安定したら動き回れる場所に行ってみよう

1歳を過ぎると身体の動きがしっかりとして歩行が安定し、2歳で身体的な動きの発達は完了すると言われています。
この頃は動きが活発になってくるので、公園や児童館など、思いっきり動き回れる場所で遊ばせましょう。まわりにいる人に興味を持ち始める時期でもあるので、子どもに出会えるような子育て広場などの場所に行くのもいいですね。同じくらいの子どもを持つママや児童館のスタッフなど、ママ自身が人と話してリフレッシュすることも大切です。
④イヤイヤ期に必要なのは「適度な距離感」

イヤイヤ期は見方を変えれば「やりたいやりたい期」、自己主張を発揮する成長過程のひとつの時期のことを言います。思い通りにならなくて「イヤだ―!」と泣き叫ぶ子どもを見ていると、大人は困ってしまい、時にはイライラしてしまうこともありますよね。気持ちに余裕がある時は、下記のように対応するのがおすすめです。
- ●気分が変わるきっかけを作る
- 「あっ!すごいトラックが来た!何を運んでいるのかな?」
- 「おいしいおやつを食べようか?」
- ●共感して落ち着くのを待つ
- 「洋服がぬれていやだったのね。気持ち悪いものね」
- 「悲しかったね。いっぱい泣いていいよ!」
イヤイヤ言っているのを見ていると、ついどうにかしてあげようと思ってしまいますが、嫌だ!と言いたい気持ちを受け止めて可能な限り放っておいても大丈夫です。子どもと適度に距離を取り、それでもイライラしてしまう時はパパに選手交代。ママ自身がリフレッシュすることで、また向き合えるようになります。園の先生に相談するのもいいですね。
大変だけどかわいい、それが乳幼児期
一人で抱え込むことなく、一緒に子育てをしているパートナーや友人、近所の児童館の保健師など、さまざまな人に頼りながら、子育てが「大変」ではなく、「楽しい」と思えるように過ごせるといいですね。ママがしっかりリフレッシュして笑顔でいることは、子どもにとって何よりも幸せなこと。「私ばっかり楽しんで子どもに悪い」なんて思わずに、ママが気分転換することも忘れずに。 成長が著しい乳幼児期はあっという間に過ぎ去ります。
宮里先生の新刊も発売!

『お茶の水女子大学こども園の春・夏・秋・冬 子どもも大人もワクワクする保育の提案』
2200円(税込)/小学館
お茶大こども園の現場の保育者が自分で撮った写真(計約400点)とエピソードで日々の保育をレポートしています。0歳児から5歳児クラスの子どもの思い・成長、保育者の子どもへの思い、かかわりなどが伝わってくる1冊。
四季ごとの自然との触れ合い、日常の遊び、保育環境の設定、行事の進め方などまねしたくなる実践例が盛りだくさんです。
あなたにはこちらの記事もおすすめ


記事監修

文京区立お茶の水女子大学こども園園長として園運営に携わり、「つながる保育」を主軸に置いた教育・保育活動を展開。保育の現場や保育者の養成に30年以上にわたり従事。Eテレ「すくすく子育て」などのテレビ番組に出演、「耳をすまして目をこらす」(赤ちゃんとママ社)単著、「はじめてママ&パパの1・2・3歳 イヤイヤ期の育児」(主婦の友社)監修など、著書も多数。
取材・文/本間綾





