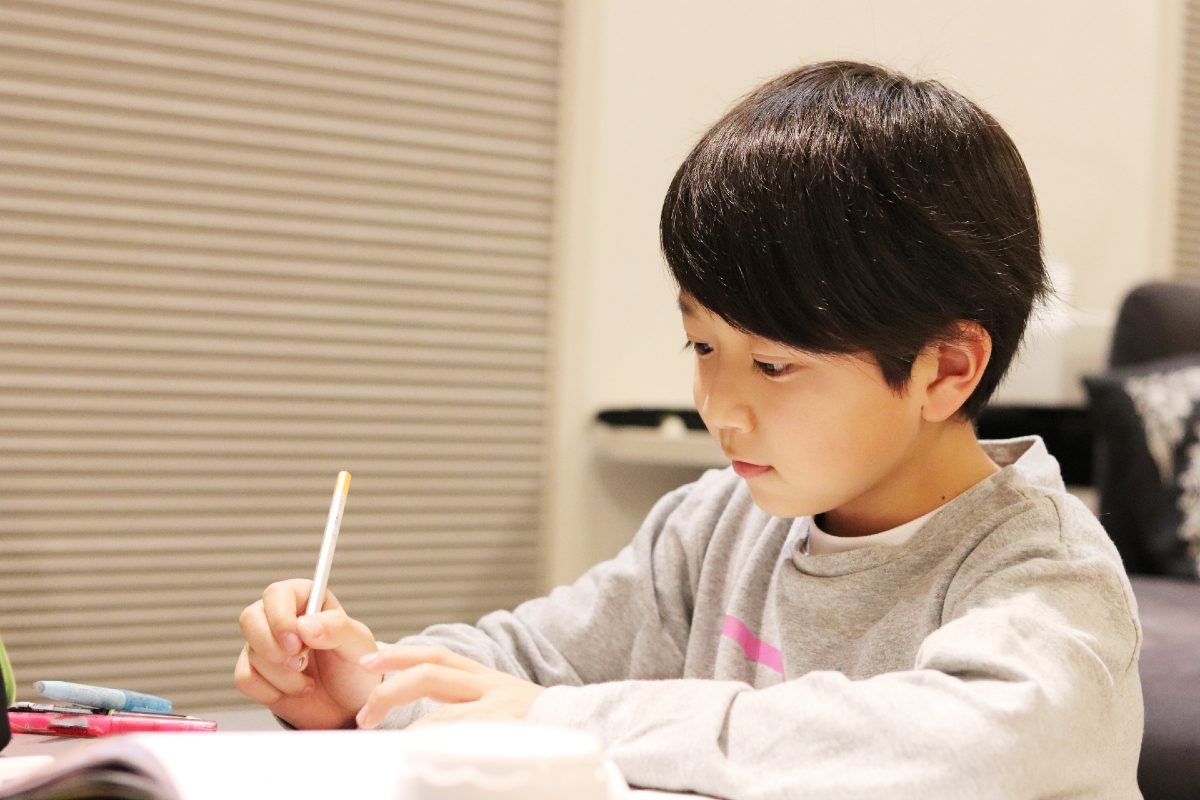メタ認知とは
メタ認知とは、アメリカの心理学者ジョン・H・フラベルの「メタ記憶」という概念を元にできた心理学用語です。自分の考えていること・感じていること・記憶していることなども含めて、物事を客観的にみられる能力といえます。
急激にメタ認知が発達するのは、小学校高学年から中学生の時期です。例えば小学校中学年以下では、子どもは自分の好きなことを自分の理解しているままに話します。相手が話を理解しきれていなくても、話したければそのまま話し続けることもあるでしょう。静かにしていなければいけない時間につい話してしまうといったことも、メタ認知の発達が不十分な場合に起こりやすいことです。
一方、小学校高学年以降は、相手の反応を見ながら理解度に合わせて説明の仕方を変える、といった工夫を行うようになります。今はどうするべき時間かを把握して、ふさわしい行動を取れるようになるのもこの時期です。成長とともに伸びたメタ認知により、相手のことや周りのことを考えて行動できるようになっていきます。
メタ認知は子どもの教育にも重要

子どもの教育を考えるときにもメタ認知は重要です。メタ認知について触れている学習指導要領や、メタ認知の伸び方、メタ認知の成績への影響などを見ていきましょう。
学習指導要領でもメタ認知を重視している
学習指導要領では「育成すべき資質・能力についての基本的な考え方」を示しています。
育成すべき資質・能力は、
「何を知っているか、何ができるか(個別の知識・技能)」
「知っていること・できることをどう使うか(思考力・判断力・表現力等)」
「どのように社会・世界と関わり、より良い人生を送るか(学びに向かう力、人間性等)」
の三つの柱から成ります。
このうちメタ認知を含んでいるのは、三つ目の「どのように社会・世界と関わり、より良い人生を送るか(学びに向かう力、人間性等)」です。
子どもがより良い人生を送るために、計画的に学習に取り組み、自分の感情と向き合い、自分の思考を適切に捉えるために欠かせない要素として、メタ認知に触れています。
子どものメタ認知は学年が上がるにつれて伸びる
メタ認知は、大きく3つの要素に分けられます。
「メタ認知的知識」は、自分の得意・不得意を客観的に理解する能力を指します。「メタ認知的モニタリング」は、計画や見通しを立て、その進捗や結果を評価するプロセスを指します。そして「メタ認知的コントロール」は、現状を改善するための具体的な方法を考え、実行に移す能力を指します。
ベネッセの「小学校高学年の学びに関する調査2019」によると、3種類のメタ認知は、どれも学年が上がるにつれて伸びているそうです。
例えばメタ認知的知識の「自分は何が得意で、何が苦手かをわかっている」という項目は、4年生87.0%・5年生89.9%・6年生91.3%という結果が出ています。
ただしメタ認知的モニタリングやメタ認知的コントロールは、メタ認知的知識と比べるとできている子どもの割合は低い傾向です。
メタ認知は成績にも影響する
同じくベネッセの「小学校高学年の学びに関する調査2019」によると、メタ認知が高いほうが成績・思考力・非認知能力が高いという結果が出ています。
メタ認知が高い群と低い群に分けて、成績の自己評価を上位層・中位層・下位層に分けると、メタ認知が高い群の方が成績上位層の割合が高い結果でした。成績や思考力についても同様に、メタ認知が高い方が上位層の割合が高くなっています。
出典:ベネッセ教育総合研究所|小学校高学年の学びに関する調査2019
メタ認知を伸ばすメリット

メタ認知の高さが影響するのは成績だけではありません。自分の行動や感情のコントロールや、より良い人間関係にもつながります。
ここではメタ認知を伸ばすことで得られるメリットをチェックしましょう。
自律的に行動できるようになる
「21時に寝られるように夕飯を食べたら早めにお風呂に入ろう」「土日は家族で出かけるから平日のうちに必要な勉強をしておこう」「テストで80点以上を目指したいから計画的に勉強しよう」など、自ら考え行動できるようになるのは、メタ認知を伸ばすメリットです。
達成したい目標に向けて、子どもが自発的に取り組めるようになります。
自分の気持ちと向き合えるようになる
怒りや悲しみといった感情が起こったときに、自分の気持ちと向き合えるようになるのもメタ認知を伸ばすメリットです。幼い子どもは怒りや悲しみを感じると、泣いたり暴れたりして発散させることがあります。
徐々にメタ認知が伸びてくると、怒りや悲しみの原因は何かを客観的に理解できるようになるため、感情に任せた行動を取りにくくなるでしょう。自分の気持ちを理解して、次に生かせるようにもなっていきます。
相手を理解して良い関係を築ける
友達や家族など周りの人と良好な関係を築きやすくなるのも、メタ認知を伸ばすメリットといえます。メタ認知の発達が不十分な場合、相手との関係性を自分の視点からしか見られません。
悪気がなくても、自分にとって都合の良いように話を進めたり、相手を傷つける言動をしたりすることもあるでしょう。
メタ認知が伸びると、相手の考えや感情を客観的に理解できるようになります。自分と相手の違いが分かるようになるため、より良い人間関係を構築可能です。
メタ認知を伸ばす取り組み

成績はもちろん、目標を持って行動することや、良好な人間関係にも関係するメタ認知を伸ばすには、何が有効なのでしょうか?
子どものメタ認知を伸ばすために、日常的にできる取り組みを紹介します。
読み聞かせで「〇〇ならどうする?」と聞く
本の読み聞かせをしているなら、メタ認知を伸ばすチャンスです。登場人物の行動に対して「〇〇ならどうする?」と問いかければ、読み聞かせをきっかけに子どもが「自分ならどうするか」と考えることを促せます。
登場人物とは異なる行動や、複数の行動を取れる可能性があることに気付くと、ある物事が起こったときにできることは一つではないと理解できるでしょう。
読み聞かせを通して考えることに慣れていれば、実際にトラブルが発生したときにも、冷静に対処可能です。
努力を具体的に褒める
子どもの努力を具体的に褒めることも、メタ認知を伸ばすことにつながる取り組みの一つです。テストの点数を褒めるなら「頑張ったね!」「〇点ですごい!」ではなく「苦手な計算練習を毎日繰り返しやった成果が出たね」というように褒めます。
具体的な努力を褒めれば、子どもは何がテストの点数に良い影響を与えたのかを理解可能です。今回の例であれば、苦手な部分を繰り返し学習するとテストの点数が良くなる、と理解できます。
その結果「算数のテストでは苦手な計算練習を繰り返しやったから目標を達成できた。他の科目のテストでも苦手なところを繰り返し勉強しよう」と考えられるようになるでしょう。
失敗は分析する
失敗したときに、失敗そのものを怒ったり叱ったりすると、メタ認知は伸びにくくなってしまいます。メタ認知を伸ばすには、なぜ失敗したのかを子どもが自ら分析しやすいよう声掛けをしましょう。
例えばテストで目標を達成できなかったときには「なぜ達成できなかったと思う?」「どうすれば達成できると思う?」というように尋ねます。子どもが「勉強する時間が足りなかった」と答えたら、「どうすれば勉強する時間ができると思う?」というように、分析を深めていきましょう。
失敗の分析を習慣つければ、子どもが自分で対策を考えられるようになっていきます。
計画表を作る
メタ認知を伸ばすには、計画表作りも役立ちます。例えば学習に関する計画表であれば、いつ・どこで・何を・どのくらい学習するかを明記するのが、計画表作りのポイントです。計画表は1週間・1カ月など管理しやすい期間で作成します。
作った計画表はそのままにするのではなく、振り返る時間を設けるのも重要です。計画がうまくいったところは、うまくいった理由を考える習慣をつけます。例えば漢字練習を計画通り毎日できたなら、「練習量がちょうどよかった」といった理由があるはずです。
計画がうまくいかなかったところは、なぜ計画通りに進められなかったのか、計画通りに進めるには何が必要かを考えて見直します。例えば計算練習は計画通りに終わらなかったなら、次の計画表では終わるように工夫が必要です。
例えば「週3日に分けて計算練習に取り組んでいたけれど1日分の量が多いと感じた」のであれば、「1日当たりの量を減らして週5日に分けて取り組む」といった解決策が考えられるでしょう。
親もメタ認知を意識する
子どもは親が何を考えどのように行動しているかを見ています。子どものメタ認知を伸ばすには、親もメタ認知を意識して生活することが有効です。
子どもが学習計画表を作るのと同じように、親は家事や仕事に関する計画表を作ってもよいでしょう。前回の計画表の見直しや、次回の計画表へ何を生かすかといったことを話すことで、子どもの分析力の向上も期待できます。
成功したときには何が良かったかを、失敗したときにはどうすれば成功できたかを日常的に分析することで、親自身のメタ認知が伸びていきます。親のメタ認知が伸びれば、子どもへより効果的な声掛けが可能です。
[まとめ]メタ認知の伸びは子どもの自律の鍵
自分の考えや感じていることを含めた物事を、客観的に捉えられるようになるのがメタ認知です。メタ認知は小学校高学年ごろから伸びていく能力で、教育指導要領でも育成すべき資質・能力とされています。
子どものメタ認知の高さは、成績の高さはもちろん、自律的な行動・感情のコントロール・良好な人間関係などにつながります。
教育においてメタ認知を意識するなら、日常的にできる取り組みから始めると有効です。例えば読み聞かせをするときに「自分ならどうするか?」と子どもが考えられるよう声掛けをしたり、成功したときにはその理由を具体的に伝えたりします。
子どもが自ら考え目標を達成していける力を身に付けるために、メタ認知を伸ばす取り組みが役立ちます。
こちらの記事もおすすめ

構成・文/HugKum編集部