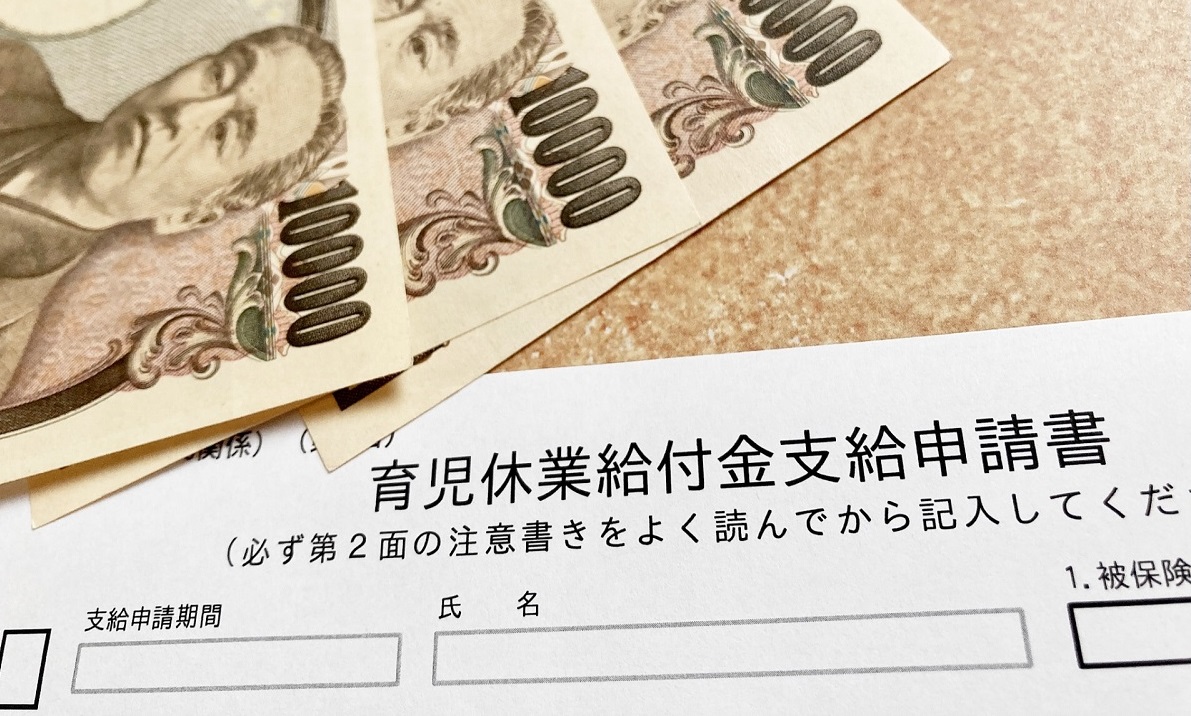育児休業給付金とは?
育児休業給付金は、育児休業を取得中の人に対して雇用保険から支払われる手当金です。受給期間や条件には、さまざまな規定が設けられています。
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
受給できる期間
育児休業は、1歳未満の子どもを養育する労働者が仕事を休める制度です。「育児・介護休業法」で定められており、原則として産後休業が終わってから子どもが1歳になるまでに取得できます。
産後休業は出生日から8週間なので、1歳まで続けて育児休業を取得した場合は、約10カ月分の育児休業給付金を受け取れます。
子どもが保育所に入所できないなどの理由があり、1歳以降も復職できない場合は、1歳6カ月までと2歳までの2回に限り延長することも可能です。
受給の条件
育児休業給付金の受給条件は以下の通りです。
・雇用保険に加入している
・育児休業開始日からさかのぼり、2年間で賃金支払対象日が11日以上または支払対象時間が80時間以上の月が12カ月以上ある
・休業期間中に賃金月額の80%以上の金額が支払われていない
・休業期間中の就業日数が月10日または就業時間が80時間以下である
就業期間については、上の子の育休や本人の病気休業が理由で条件を満たせない場合、4年間までさかのぼってカウントされます。
また前職で雇用保険に加入しており、1日の空白期間もなく入社した人は、転職したばかりでも支給対象となります。
支給額の計算方法
育児休業給付金の支給金額は、どのように算出されるのでしょうか。基本的な計算方法と、税金などの扱いについて紹介します。
賃金を基に1日の金額を計算
育児休業給付金の算出基準は、休業開始前6カ月の賃金です。
産休から続けて育休に入るママの場合は、産休開始前6カ月の賃金を基に計算します。計算に用いる賃金は、残業代や各種手当を含む給与のことで、手取り金額ではありません。
まずは、6カ月間の賃金を合計した金額を180で割り、「休業開始時賃金日額」を求めます。この日額に決まった係数をかけた金額が、1日当たりの支給額です。
係数は、育休の取得期間によって変わります。休業開始から180日までは67%、開始日から181日以降は50%です。
◆育児休業開始日から6ヶ月間
休業開始時の賃金日額 × 支給日数×67%
◆育児休業開始日から6ヶ月経過後
休業開始時の賃金日額 × 支給日数×50%
支給額には上限と下限がある
育児休業給付金の支給額には、上限と下限が設けられています。
令和3年(2021年)8月1日現在、支給額の計算のもとになる「賃金月額」の上限は45万600円、下限は7万7310円と定められています。仮に、自身の月額が、上限を上回る場合は上限額45万600円を、下限を下回る場合は下限額の7万7310円を賃金月額として支給額が算定されます。
上限額と下限額は、毎年8月1日に見直されます。対象になる可能性のある人は、最新の情報をチェックするとよいでしょう。
税金や社会保険料は免除される
育児休業給付金は非課税ですので、所得税も住民税もかかりません。
ただし、住民税は前年の所得に対して課されるため、育休期間中に前年分を納付しなければならないケースがあります。自治体から納付書が届いても慌てずに済むように、お金を残しておくようにしましょう。
また育休中は、健康保険・厚生年金・雇用保険の保険料支払いが免除されます。
育児休業給付金から保険料が引かれることはなく、免除期間中に健康保険が使えなくなったり、将来の年金受給額が減ってしまったりする心配もありません。
支給額を計算してみよう

育児休業給付金の正確な支給額は、申請時に会社が提出する「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」を基に、ハローワークが計算します。
しかしおおよその金額なら、自分でも計算が可能です。計算の手順や便利な計算ツールを紹介します。
自分で計算する方法
まずは直近6カ月分の給与明細を用意し、総支給額を合計します。総支給額があまり変わらない人は、1カ月分を6倍してもよいでしょう。
6カ月の合計金額を180で割ると「休業開始時賃金日額」が分かります。この数字を基にして、以下の順に支給額を計算していきましょう。
1.育休開始から180日までの1日当たりの支給額(a):休業開始時賃金日額×0.67
2.育休開始から180日間の総支給額(b):(a)×180
3.育休開始から181日以降の1日当たりの支給額(c):休業開始時賃金日額×0.5
4.育休開始181日以降に支給される総額(d):(c)×181日以降の休業予定日数
5.育休期間中の総支給額:(b)+(d)
※育休の取得予定が180日未満の人の総支給額は、(a)× 休業予定日数 でOK
育休期間も分かる計算ツール
支給額の目安をもっと簡単に知りたい人は、計算ツールを活用してみましょう。
こちらのツールでは、出産予定日と住んでいる自治体、1カ月の給与を入力するだけで、産休と育休中にもらえるお金がすぐに表示されます。
それぞれの休業開始日と終了日が分かる他、別の画面で支給時期と金額も表示してくれます。1歳までの期間だけでなく、1歳6カ月と2歳まで延長した場合の支給額を計算できるのもポイントです。
いつ頃にいくら振込まれるのかが一目瞭然なので、休業中の家計のやりくりを事前に計画するのに役立つでしょう。
【2022年最新版】産前産後休業・育児休業給付金|期間・金額計算ツール
給与明細から細かく計算できるツール
育休中の1カ月当たりの収入を、休業前と比べながらシミュレーションできるツールもあります。このツールでは給与明細の項目を入力していくと、給与と給付金それぞれの支給額と手取り額が表示されます。
休業中に支払う前年の住民税額を教えてくれる他、シミュレーション結果をCSVに保存して、後で見返すことも可能です。
ただしこのツールで計算できるのは、育休開始から180日までの月額のみです。181日以降の金額を知りたい人は、自分で計算する必要があります。
育休中はどうなる?収入シミュレーション : 子育て支援サイト : 株式会社 日立ハイテク
▼こちらの関連記事も

男性の育児休業給付金もチェック
育児休業は夫婦同時に取得してもよく、給付金もそれぞれに支給されます。パパの育休をうまく活用できれば、ママの負担は多少なりとも軽減されるでしょう。
男性が育休を取得するときに、注意したいポイントを解説します。
男性の育休期間は女性とは異なる
産後8週間経ってから育休が始まるママと違い、パパは子どもが生まれた日から育休を開始できます。
仮にパパが、子どもの誕生から1歳になるまで連続して育休を取れば、約1年間育児休業給付金を受給可能です。1年間は仕事を休まない場合も、パパの育休の開始日が早ければ、その分給付金も早く振り込まれます。
赤ちゃんが生まれた直後の大変な時期に、夫婦同時に仕事を休んだとしても、パパの給付金が早くもらえれば経済的な不安は軽く済むでしょう。
なお、仕事と子育てを両立しやすい環境を作るために、国はさまざまな対策を講じています。2022年の10月には、男性版の産休や育休の分割取得など、新たな制度が導入されることが決まっています。
「パパ・ママ育休プラス」が使える
「パパ・ママ育休プラス」は、共働き夫婦がそれぞれ育休を取るとき、後から取得するほうが、特別な理由なしに子どもが1歳2カ月になるまで休業期間を延長できる制度です。
利用の条件は以下の通りです。
・子どもが1歳になるまでに配偶者が育休を取得している
・子どもが1歳になるまでに申請者が育休を開始予定である
・申請者の育休開始予定日が、配偶者の育休の初日以降である
例えば、ママが育休に入った後、子どもが1歳になるまでにパパが育休を取る場合、パパの育休期間を子どもが1歳2カ月になるまで延長できます。ママの産休中にパパが育休を取り、ママの育休期間を延ばすことも可能です。
もちろん、延長中も育児休業給付金は支給されます。お互いに休業取得期間を相談して、上手な取り方を考えてみるとよいでしょう。
▼関連記事はこちら

育児休業給付金の申請と受け取り方法

育児休業給付金を受け取るためには、育休の申請とは別の手続きが必要です。給付金申請から振込までの手続きの流れと、注意点を見ていきましょう。
受給資格確認手続きが必要
育休を取得したい人は、開始希望日の1カ月前までに会社の担当部署に申請します。ママの場合は、産休と同時に申請するとスムーズです。
育休の詳細が決まったら、会社が用意した給付金の申請書類に必要事項を記入します。
申請には育児中であることを証明する書類(母子健康手帳の写しなど)とマイナンバー、給付金を受け取る口座の番号が必要です。
育休が開始されると、会社がハローワークに対して育児休業給付金の受給資格確認手続きを行います。受給資格が認められると、給付金の支給申請ができるようになります。
「受給資格確認」と「支給申請」は別の手続きですが、同時に行うことも可能です。会社によってやり方が異なるため、詳しくは担当者に直接確認しましょう。
2カ月に1度申請書を提出
育児休業給付金は原則として2カ月ごとに、2カ月分をまとめて申請します。1度に全ての休業期間分を申請できるわけではないため注意しましょう。なお、申請者本人が希望すれば、1カ月単位で申請することは認められています。
受給資格確認後の初回の支給申請が終わると、次回の申請期限と支給予定額が記載された通知が届きます。期限までに、所定の方法で手続きを済ませましょう。
とはいえ、2回目以降も基本的には会社が申請してくれます。手続きといっても会社が用意した書類に署名する程度なので、育児に追われて申請を忘れてしまう心配はほとんどないでしょう。
振込までに時間がかかる場合も
育児休業給付金の申請には、該当する期間の賃金台帳や出勤簿など、休業していたことを証明できる書類が必要です。
従って、月に1度のペースで申請する場合を除き、支給申請書を提出できるのは最短でも育休開始から2カ月後となります。
ハローワークが申請を受け付けてから支給決定までには約2週間、決定から振込までにはさらに約1週間かかります。会社が書類を用意して申請に行くまでの期間を考慮すると、どれほど早くても振込までに3カ月かかると思っておいたほうがよいでしょう。
また、ハローワークへの申請期限は、育休開始日から4カ月目の末日に設定されています。このため会社の対応によっては、振込まで5カ月ほど待たされるケースもあります。
急ぐ人は担当者に早めの手続きを依頼するか、書類を送ってもらい自分で手続きするなどの対策を検討しましょう。
育児休業給付金に関するQ&A
育休中は、予定外の出来事が起こる可能性も十分にあります。育児休業給付金の計算に影響すると考えられる、三つのケースと対処法を見ていきましょう。
育休中に2人目を妊娠した場合
育休に再び赤ちゃんを授かった場合は、職場復帰の時期や出産予定日によってさまざまなパターンが考えられます。
上の子の育休が終わる前に生まれる予定なら、上の子の育休期間は下の子の産前休業開始日または出産日の前日までです。生まれた後は産後休業を経て、下の子の育休を取得することになるでしょう。
上の子の育休期間が終わり、数カ月職場に復帰した後で産休に入る場合は、下の子の出産手当金や育児休業給付金の支給条件は上の子と同じです。
ただし、上の子の育休が明けて間もないため、時短勤務や残業時間減少によって休業開始時賃金日額が上の子のときよりも減る可能性があります。
育休中に働いた場合
育休中に10日以上または80時間以上働いた場合、その期間の育児休業給付金は支給されません。働いた日数や時間は、在職中の会社以外で副業した分も含まれるので注意しましょう。
10日または80時間に満たないときは、受け取った賃金額に応じて以下のように支給額を計算します。
・賃金月額の13%(181日以降は30%)以下:減額なし
・賃金月額の13%(181日以降は30%)以上80%未満:=休業開始時賃金日額×支給日数×80%-賃金額
・賃金月額の80%以上:支給なし
例えば、賃金月額が30万円の人は、育休開始から180日までは3万9000円、181日以降は9万円までなら、賃金をもらっても育児休業給付金の減額はありません。
育休中にボーナスをもらった場合
育休中にボーナス支給日を迎えた場合、賃金とみなされて育児休業給付金が減額や無支給となることを心配する人もいるでしょう。
しかし育児休業給付金は、あくまでも毎月の給与を基に計算します。そのためボーナスが支給されたからといって、該当月の支給額を減らされることはありません。
ただしボーナスの支給条件は、会社によって異なります。業績の悪化を理由に支給されなかったり、育児休業の期間に応じて支給額が減らされたりする可能性はあります。
育児休業給付金額を計算し、安心して出産を
会社から給料が出ない育休期間は、育児休業給付金が頼みの綱です。いくら受け取れるのかを事前に知っているだけでも、気持ちにゆとりが生まれるでしょう。
支給の時期や申請方法についてもある程度押さえておけば、いざというときに落ち着いて対処できます。安心して出産に臨むためにも、ママとパパの支給額を計算し、産後の計画を立てておきましょう。
あなたにはこちらもおすすめ


構成・文/HugKum編集部