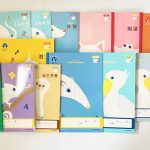ユニバーサルデザインの定義と原則
ユニバーサルデザインには、一般的な定義や原則が設けられています。まずは、どのようなものをユニバーサルデザインと呼ぶのか、定義や原則を紹介しましょう。
誰もが使いやすいデザインを指す
ユニバーサル(universal)は、「万人の」「普遍的な」などの意味を持つ英語です。つまり、ユニバーサルデザインとは、すべての人が使いやすいデザインを意味します。
性別・年齢・国籍・障がいの有無など、個人の性質や状況による違いがあっても、スムーズに使えることを意識したデザインがユニバーサルデザインであるといえるでしょう。
ユニバーサルデザインを意識して建築物や製品を作ることで、それぞれの違いによって起きる問題やトラブルを未然に防げます。
ユニバーサルデザインの7原則
ユニバーサルデザインの7原則は、アメリカの建築家ロナルド・メイスによって提唱されたものです。内容を見てみましょう。
・公平性がある(Equitable use)
・柔軟性がある(Flexibility in use)
・シンプルで直感的(Simple and intuitive use)
・情報が分かりやすい(Perceptible information)
・間違いや危険への許容度が高い(Tolerance for error)
・身体的負担が少ない(Low physical effort)
・適切なサイズとスペース(Size and space for approach and use)
基本的には、7原則を満たしたものがユニバーサルデザインです。誰もが使えるように、さまざまな工夫が施されたデザインといえるでしょう。

色づかいにも配慮
ユニバーサルデザインは、色覚の多様性にも配慮し、色づかいについても配慮されています。
避けるべき組み合わせとしては、「赤と緑」「青と紫」「水色とピンク」など、色相が近く識別しづらい配色が挙げられます。これらは色覚に特性がある人にとって同じ色に見えることがあり、誤認の原因になります。
一方、奨励される組み合わせは、明度や彩度に差があるものや、暖色と寒色を交互に使った配色などです。例えば「濃い青と薄い黄色」や「黒と白」などは識別しやすく、視認性が高まります。
また、色だけに頼らず、形や模様、文字情報を併用することで、より多くの人にとって理解しやすいデザインになります。背景と文字のコントラストを強調することも重要で、同系色の組み合わせは避けるべきです。
こうした配慮が、誰もが安心して利用できる環境づくりにつながります。
出典:「ユニバーサルデザイン」って何だろう?/浜松市
:色のUD「カラーユニバーサルデザイン」とは?|TOPPAN|TOPPAN CREATIVE
ユニバーサルデザインの身近な事例
ユニバーサルデザインは、身近な場所にも使われています。普段見かけることが多い事例を確認しましょう。
段差なくスムーズに乗降できるバス

乗降口や車内の段差をできる限りなくしたバスを、ノンステップバスと呼びます。ノンステップバスは、一般の人だけでなく高齢者や子ども、車椅子の人なども乗降しやすいデザインです。
現在では、日本でもノンステップバスが増えてきています。今後は、バリアフリーの考え方を意識し、さらにノンステップバスが増加していく可能性があります。
しかし、すべてのバスがノンステップバスに切り替わっているわけではないため、まだまだ改革が必要な分野です。
出典:『ノンステップバス』 | バス大図鑑 | いすゞタウン | いすゞ自動車
音が鳴る信号機
音が鳴る信号機は、音響式信号機と呼びます。信号が青になるとメロディや鳥の声が流れ、信号が青になったことを知らせてくれるのです。
視覚に障がいがある人でも、音響式信号機を使えば信号の状況が分かります。誰でも分かりやすいデザインの一種であると考えられるでしょう。
しかし、近くに多くの信号がある場合はどの信号の音なのかを判断することが難しいという問題もあり、あくまでも一部の信号機のみに採用されている仕組みです。
出典:音響式信号機 | 社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合
電車内のフリースペース
一部の電車には、「フリースペース」と呼ばれる座席のない広い空間が設置されています。主に、車椅子やベビーカーが利用しやすいよう考えられています。

優先的に配慮すべき人がいないときには、スーツケースなどの大きな荷物も置けるため、誰でも使いやすいよう考えられたデザインといえるでしょう。
多くの人が利用する電車には、誰もが使いやすいデザインが求められているのです。
シャンプーとリンスのボトル
シャンプーとリンスのボトルは、形が同じです。ぱっと見ただけでは区別しにくいため、多くのシャンプーのボトル側面にはギザギザの突起が付いています。
洗髪中でも間違いにくく、視覚に障がいがある人や文字が読めない人でも区別しやすいデザインです。

もともとシャンプーとリンスのボトルは触っただけで区別ができるものではありませんでしたが、利用者の声を受け、1991年にギザギザの突起が付いたボトルを販売し始めたことがきっかけで業界に広まりました。
ユニバーサルデザインの類語
ユニバーサルデザインには、似たような意味を持つ類語があります。それぞれどのような違いがあるのか、主な類語について確認しましょう。
ノーマライゼーション
ノーマライゼーションは、障がいの有無にかかわらず暮らしやすい社会を目指すことを指す言葉です。
ユニバーサルデザインも、ノーマライゼーションと考え方は似ています。主な違いは、ユニバーサルデザインは、何らかの製品や公共物などのデザインの一種であるということです。
ノーマライゼーションを目指すための取り組みの1つが、ユニバーサルデザインを推進することであるともいえます。
バリアフリーデザイン
バリアフリーは、何らかの障壁(バリア)をなくす、または取り除くための取り組みなどを指す言葉です。
つまり、バリアフリーデザインは、障壁を取り除く目的で作られたデザインを意味します。例えば、介助が必要になった高齢者向けのデザインや、障がいを気にせず使えるようなデザインです。
対して、ユニバーサルデザインは障壁の有無にかかわらず、すべての人が使いやすいデザインを指します。
インクルーシブデザイン
インクルーシブデザインの「inclusive」は「包括的な」という意味を持つ英語です。
包括的とは、多様な立場や背景を持つ人々を広く包み込むことを指します。つまり、ユニバーサルデザインと同じように、多くの人が使えるようなデザインのことをインクルーシブデザインと呼ぶのです。
特に、インクルーシブデザインには「少数派」や「排除されようとしていた人」に焦点を当て、その人たちが望んでいるものを作り上げようとする意図があります。
ユニバーサルデザインが求められる理由と社会的背景

ユニバーサルデザインは、日本でも普及し始めています。すべての人が使えるデザインを心掛けることは望ましいですが、なぜ近年ユニバーサルデザインが求められているのでしょうか? その理由を解説します。
多様な文化的背景を持つ人の増加
日本では、多様な文化的背景を持つ外国人の観光客や移住者が増加しています。2024年6月末の調査では、在留外国人数が358万8,956人と過去最高の人数です。
さまざまな言語や文化を持つ人が増えると、誰にでも分かりやすいデザインが求められる場面も増えてくるでしょう。
例えば、イラストや図で表現されているピクトグラムは、異なる言語を使う外国人であっても分かりやすいデザインの一種といえます。
出典:令和6年6月末現在における在留外国人数について | 出入国在留管理庁
少子高齢化による高齢者の増加
日本では、少子高齢化によって高齢者が増えています。高齢になると介護・介助が必要になる場面が増えてくるため、誰にでも使いやすいデザインを必要とする人も増えるのです。
また、高齢者が介助なしで過ごすためにも、ユニバーサルデザインは役立ちます。すべての人が使いやすいデザインであれば、体力や機能が低下した状態でも使いやすいはずです。
家の中や公共の場が年齢を問わずに過ごしやすい環境であれば、介助が必要な場面も減ってくるでしょう。
身近なユニバーサルデザインを探してみよう

ユニバーサルデザインとは、すべての人が使いやすいデザインのことです。性別・年齢・国籍・身体的な状況などを問わず、どのような人でも使いやすいよう考えられています。身近な例として、電車内のフリースペースや区別しやすいシャンプーとリンスのボトルなどが挙げられるでしょう。
外国人の増加や高齢化の進行などもあり、ユニバーサルデザインは日本でも求められる場面が増えています。
こちらの記事もおすすめ
構成・文/HugKum編集部