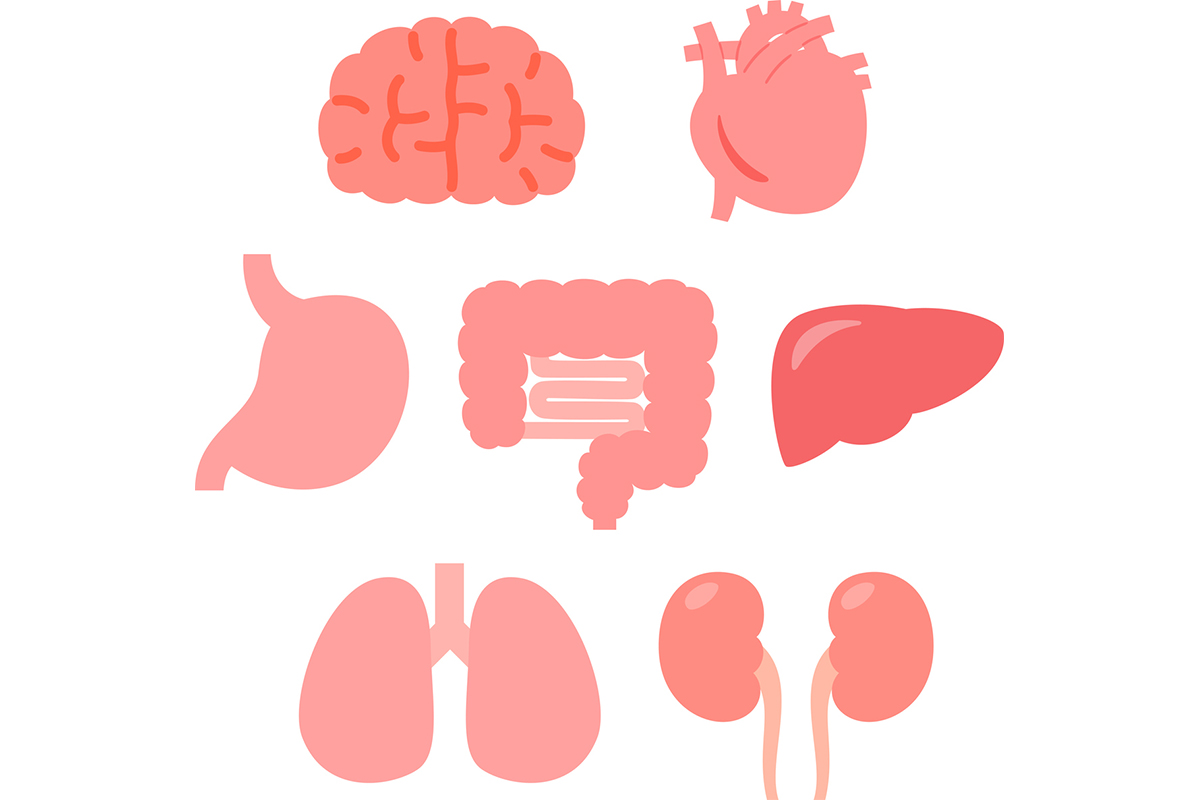器官の基本情報
よく「からだの器官」などと耳にすると思います。でも「器官って、いったい何だろう?」と思ったことはありませんか? そもそも器官とは何なのか、なぜ必要なのか、器官の基本から見てみましょう。
器官とは
「器官」とは、動物や生物のなかでいくつかの組織が集まって、ある機能を持つ部分のこと。人の場合は、心臓、胃、肺、脳などの臓器を指します。
器官の定義
「器官」を辞書で調べると、「多細胞生物において、いくつかの組織が集まって生理機能をもつ部分」などと書かれています。多細胞生物とは、からだが複数の細胞でできた生物のこと。人間もそうですし、猫、犬、牛などの動物も、多くの植物なども多細胞生物です。そして、人間のからだの話をするときに「器官」というと、先ほどご紹介したように臓器を指しますが、植物の場合なら、根、茎、花などの部分を指します。
人間のからだで「消化器官」といえば、消化の働きをもつ内臓をまとめて差し、動物や植物の「生殖器官」というと、生殖機能をもつ部分のことを指します。
なぜ器官は必要なのか?
器官には、それぞれの生物が生きていくために必要な機能があります。私たちは、呼吸して酸素を吸って二酸化炭素を吐いて、食べ物で栄養を取って不要なものは便や尿で排出して、生きているもの。だから、器官にはそんな私たちの命を支える大切な役割があるのです。
主要な器官とその役割
次に、人のからだで主な器官にはどんなものがあるか見てみましょう。それぞれにどんな働きがあるのか、役割ととも解説します。
心臓:体のポンプ
心臓は、私たちの命のためにもっとも大切な器官。胸の中央あたりにある、こぶしより少し大きめのサイズで、大人なら200~300グラム程度です。
心臓にある筋肉「心筋」が収縮することで、ポンプのような役割を担って、血液を全身に送り出し、今度は全身を流れて汚れた血液が戻ってきます。車でいえば、エンジンの役目を担う一番大切な部分です。
心臓が収縮するのは、1分間に60~100回。1日で10万回近くも収縮して、血液を送り出し続けています。そして心臓が止まってしまうと、死に直結することになります。
肺:息をするための器官
心臓の近くで、左右の胸にあるのが肺です。人は「息を吸って吐いて……」という呼吸をしなければ生きていけません。肺は、そんな呼吸をするための器官です。
人が呼吸するのは、生きるためにエネルギーが必要だから。口から食べ物を食べ、それが体内でブドウ糖という栄養になったとき、酸素と結びついてエネルギーが生まれるのです。そのときに酸素が必要となるのです。また、エネルギーが生まれた後には二酸化炭素ができるので、これもからだの外に排出しなければなりません。このように「空気中から酸素をからだの中に取り入れて、からだの中でできた二酸化炭素を外に出す」役割を行っているのが肺です。
左右に2つある肺は、気管と気管支につながり、それが口と鼻につながっています。
腎臓:体の浄水システム
腎臓は腰のあたりに左右に2つある器官で、そら豆のような形をしています。大きさは握りこぶしくらい。腎臓は、老廃物が混じった血液をろ過して、余分な塩分をからだの外に排出する働きがあります。
腎臓でろ過され、きれいになった血液はまたからだを巡り、ろ過されたものは尿となってからだの外に排出されます。また、尿の量を調節して、からだの水分量を一定に保ったり、赤血球をつくるホルモンを分泌したりする役割もあります。
脳:指令を出す中央コンピュータ
脳は、頭にある大切な器官です。重さは体重の2%程度と言われ、1.2~1.6㎏ほどあります。
脳は、「大脳」「小脳」「脳幹」に分けられていて、大脳は物事を考えたりする部分、小脳は手や足を動かすなどの運動をコントロールする部分、脳幹は呼吸などの生命をコントロールする部分です。
また、右側の脳「右脳」と、左側の「左脳」では働きが違い、右脳は音楽や芸術のような感覚的・創造的な思考を、左脳は計算、言語のような論理的な思考を担っています。
体の中での連携:器官同士の協力
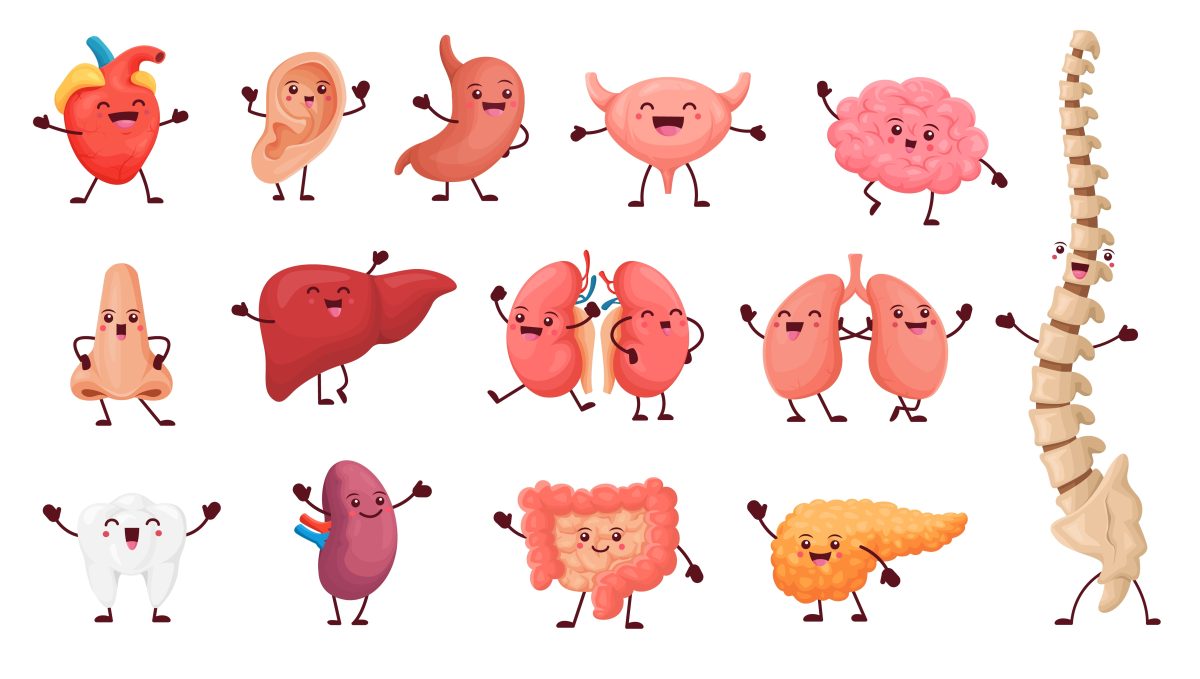
人のからだでは、それぞれの器官が連携してさまざまな働きを担っています。
循環系:心臓と血管の働き
全身にくまなく流れている血管。その血管に流れる血液を送り出しているのが、心臓です。心臓には「動脈」という太くて厚い血管につながっていて、心臓が収縮してポンプのように血液が押し出されます。
そして、血液には栄養素や酸素、白血球、赤血球などが一緒に入っていて、それらをからだの隅々まで届けてくれるのです。
心臓と血管は、2つの器官が連携してそれぞれの役割を果たしているわけです。
消化系:食べ物をエネルギーに変える
私たちが食べ物を口から取り入れると、口から喉、食道を通って、胃、小腸、大腸を経て、最後は肛門から便として排出されます。これが、一連の消化のプロセスで、これらを消化器官と言います。
口では、唾液を分泌して食べ物を砕き、胃では胃液が出て食べ物をドロドロの状態にしていき、小腸では栄養素が吸収され、大腸では水分が吸収されます。それぞれの器官に、それぞれの役割があって、この連携プレーがあって消化ができるのです。
神経系:情報の伝達路線
神経には「抹消神経(まっしょうしんけい)」と「中枢神経(ちゅうすうしんけい)」があります。
抹消神経は、血管と同じように、からだのあちこちまで張り巡らされている神経。中枢神経は、脳や脊髄からなっていて、全身に指令を出す中心的な働きをになう部分です。中枢神経から指令が出ると、それによって抹消神経でからだの隅々まで指令が伝わる仕組みなのです。
器官を健康に保つ:生活との関係

からだの器官は、それぞれでとても大切な役割があるもの。だから、器官を健康に保つことが必要です。
正しい食事:器官の働きをサポート
毎日の食事は私たちのエネルギー源で、からだを作っているもの。だから、ジャンクフードやファストフードばかりに頼る食生活ではなく、栄養バランスのとれた健康的な食事が一番です。とくに、和食は世界で見ても健康的な食事です。お菓子などもたまにはいいですが、基本的にはヘルシーな食事を心がけたいですね。
運動の重要性:器官の機能を活性化
適度な運動を行うことは、からだを健康にキープするためには欠かせません。ストレス発散になってリフレッシュできるため、運動の効果はダブル!ぜひ定期的に運動する習慣を続けていきたいですね。
休息とストレス:体のリカバリーとバランス
運動は毎日頑張りすぎる必要はありません。自分にあった息抜きの方法を見つけていきましょう。現代社会ではだれもがストレスを抱えているものですが、休息でストレスを減らし、メンタル面でも健康的になっていけるといいでしょう。
「器官」の優秀さにびっくり!
「器官」という言葉はよく耳にしたり使ったりしていても、その詳しい意味や内容まで理解している方は少ないかもしれません。でも、この記事でご紹介したように、人の器官はそれぞれに大切な役割があって、しかも他の器官と連携してさまざまな機能を持っていることもおわかりいただけたでしょう。
私たちが毎日元気に暮らせているのは、そんなからだの器官があってこそ。からだの不思議について、あらためて注目してみてはいかがですか?
こちらの記事もおすすめ


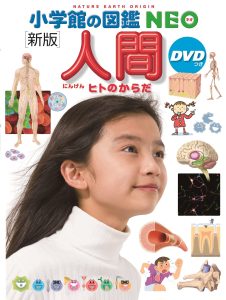
文・構成/HugKum編集部