少年法とは
少年法の定義や目的を解説します。少年法の基礎知識を身に付ければ、この法律に対する見方が少しずつ変わってくるはずです。あわせて諸外国の少年法の歴史と現状を解説します。
少年が起こした事件に対する処分の方法を定めた法律
少年法とは、不法行為を行った少年に対して、成人とは異なる措置を行うことを定めた法律です。少年法では第2条において、20歳に満たない人を「少年」と定義しています(2022年以降、18歳と19歳は「特定少年」。後述)。なお、14歳未満の人に関しては「触法少年」と定義され、逮捕されたり処罰を受けたりすることはありません。
罪を犯した少年に対しては、基本的に懲役刑や罰金刑に代表される「刑罰」ではなく「保護処分」が下されます。具体的には、少年に矯正教育を施して社会復帰を目指す「少年院」に送致される、もしくは保護観察官や保護司が指導や支援を行う「保護観察」を受けることになります。
少年の健全な育成を目的とする法律
少年法の目的は、少年に厳しい刑罰を与えることではなく、教育的なアプローチを通して少年の更生を促すことです。「処罰ではなく保護処分を検討すべき」とする考え方を「保護主義」といいます。
人格的に発展途上である少年は、少年法の下で矯正教育を行うことで、性格や思考が変わっていく可能性(=可塑性)が高いとされています。成人にも可塑性は認められるものの、成長過程にある少年は成人に比べて、より高い可塑性を持つと考えられています。
保護主義の考え方は20世紀初頭のアメリカで生まれました。現在の日本の少年法では、第1条において、少年の健全な育成を図るという趣旨で保護主義的な考え方が示されています。
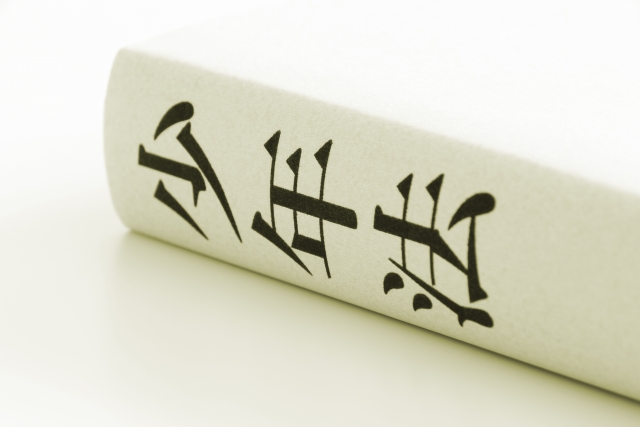
諸外国における少年法
アメリカでは、1899年にイリノイ州において少年裁判所が設立されました。その後1980年代に入ると、「少年にも厳しい処罰を与えるべき」とする批判が噴出します。
ついには特定の少年に対し、成人と同等の処罰を下すと定めた州も次々と現れました。しかしその後のアメリカでは、多くの州で少年として扱う年齢の上限を、17歳未満から18歳未満まで引き上げています。
一方イギリスでは、1908年の「児童法」の成立に伴い少年裁判所が創設され、16歳未満の人を少年として定義しました。その後1933年には、少年として保護の対象となる人の年齢を17歳未満、1991年には18歳未満と定義し直しています。なお、イギリスにおける少年法適用年齢の下限は10歳以上です。
出典:子どものための少年法を!―少年非行と少年法改正|全国青少年教化協議会
:アメリカにおける少年非行の動向と少年司法制度|法務省
:連合王国の少年非行の動向と非行少年処遇|法務省
成人事件と少年事件の違い
罪を犯した少年は、成人と異なるプロセスで処分を受けることになります。成人が起こした事件(成人事件)と少年が起こした事件(少年事件)との扱われ方の違いを解説します。少年法のリアルを知りましょう。
全ての少年事件が家庭裁判所に送致される
少年事件は原則として、全ての事件が警察や検察から家庭裁判所へ送致されます。これは「全件送致主義」と呼ばれ、少年法の第41条と第42条で規定されるルールです。
成人事件の場合、検察官によって起訴された事件に関してのみ刑事裁判が開かれます。不起訴処分となれば裁判は開かれず、その時点で事件は終了となります。
しかし少年事件においては、起訴猶予や不起訴処分に相当する制度が明確に整備されていません。嫌疑なしや嫌疑不十分となった場合には、家庭裁判所への送致は行われないものの、犯罪の事実が疑われる少年事件は全て家庭裁判所に送致されます。

少年事件には保釈制度がない
保釈とは、検察官によって起訴された後に身柄拘束から一時的に自由になれることを指します。「保釈保証金」として一定額を納めることで認められる被告人の権利です。
少年事件には保釈に関する制度がありません。事件が家庭裁判所に送致されても、保釈保証金を納めて保釈を求める制度は、少年事件には適用されません。少年事件では、家庭裁判所に送致された後は「少年鑑別所」に収容されるケースが一般的です。
少年鑑別所に収容されるのを止めるためには、裁判官に鑑別所送致をしないように求めたり、鑑別所送致の取り消しの申し立てを行ったりする必要があります。
審判は非公開
少年事件の審判(罪を犯した少年の処分を決める手続き)は非公開で行われます。これは少年法の第22条で規定されているルールです。
成人事件の刑事裁判はオープンで行われます。事件と無関係な第三者であっても裁判を傍聴できるため、誰がどのような罪を犯したかは広く公開されているといえるでしょう。
一方、少年事件においては基本的に非公開で審判が行われます。更生の可能性がある少年のプライバシーを守るため、このような措置が取られています。少年審判には、少年本人・裁判官・書記官・調査官・少年の保護者・付添人(主に弁護士)が参加可能です。
改正少年法のポイント

少年法は2022年4月に改正が行われています。改正少年法では、18歳と19歳の少年を「特定少年」として位置づけることになりました。特定少年に関する改正少年法のポイントを解説します。
逆送される事件の範囲拡大
逆送とは、家庭裁判所への送致が行われた後に実施される検察官への送致のことです。逆送された事件は刑事裁判によって裁かれます。たとえ少年事件であっても、事件の内容が重大だった場合、少年が16歳以上であれば、逆送されて刑事裁判を受けることになります。
改正少年法では特定少年に該当した場合、逆送される事件の範囲が広がりました。そのため強盗罪や組織的詐欺罪などであっても、逆送される可能性が生まれたのです。この逆送に関する特例は少年法第62条で規定されています。
実名報道の一部解禁
特定少年については実名報道される可能性が出てきています。
18歳未満の少年の場合、法を犯した時点で少年法の定める「少年」に該当する場合には、たとえその後成人して刑事裁判を受けることになったとしても、報道において実名が公表されることはありません。このルールは少年法の第61条で規定されています。
改正少年法では、逆送されて刑事裁判を受けることになった特定少年については、第68条の規定により報道内容を制限しないとしました。なお、特定少年が刑事裁判にかけられた場合でも、略式命令の手続きが取られた場合には、実名報道が行われないことがあります。
特定少年は罪の重さを重視して処分される
特定少年に関しては、犯した罪の重さを考慮して処分内容が決められるようになりました。
18歳未満の少年において、処分内容を決める際に重視されるのは「再犯の可能性」です。犯した罪の重さをそのまま処分内容に反映させるのではなく、少年本人の性格・犯罪を犯すに至った成育歴・家庭環境などを考慮し、再び非行に走る可能性を考慮して処分内容を決定するのです。
改正少年法では、特定少年については罪の重さで処分内容を決定することになりました。このルールは少年法の第64条に規定されています。

特定少年は〝ぐ犯少年〟の規定から除外される
ぐ犯少年とは、将来的に犯罪を犯す可能性が高いと判断された少年のことです。例えば家出を繰り返していたり、犯罪に関わっている人物との交流があったりする場合、ぐ犯少年と見なされることがあります。
18歳未満の少年の場合、ぐ犯少年に該当する少年は、たとえ今犯罪を犯していなくても、家庭裁判所による審判の対象となる可能性があります。これは少年法の第3条で規定されるルールです。
改正少年法では、特定少年の場合、たとえ犯罪を犯す可能性が濃厚であっても、ぐ犯少年としては扱わないことになりました。このルールは少年法の第65条で規定されています。
特定少年は成人と同等の刑罰が科される可能性がある
特定少年については、成人と同レベルの刑罰が下される可能性が生まれています。
これまでの少年法では、逆送されて刑事罰が確定した少年には、「懲役◯年以上◯年以下」といった不定期刑を科すこと(不定期刑制度)を規定(第52条)していました。改正少年法では、特定少年が刑事裁判で有罪となった場合、成人と同様に「懲役◯年」のような有期刑が科される可能性があると、第67条に定められています。たとえ刑期中に特定少年が明らかに更生したとしても、刑期が短縮されることはありません。
またこれまでの少年法では、逆送されて刑事罰が下される少年に対して、刑期の上限(短期10年、長期15年)が定められていました。改正少年法では、特定少年に関しては少年法が定める刑期の上限を適用しないとしています。死刑が言い渡される可能性さえあるのです。
少年法は社会に必要な法律
改正少年法の内容から分かるように、日本の少年法は厳罰化の流れの中にあるといえるでしょう。少年への厳罰を求める声が高まっていることや、諸外国の少年法適用年齢が18歳未満であることから、今後も少年法の厳罰化が進む可能性はあります。
しかし、少年法は罪を犯してしまった少年を非行から守るのが目的の法律です。「厳罰化が少年の再犯を防ぐ最良の方法とはいえない」と指摘する声もあります。今こそ少年法の意義を再確認する必要があるといえるでしょう。
こちらの記事もおすすめ
構成・文/HugKum編集部







