ファイナンシャルプランナーが子育て中のパパママに必須な「お金」の話を、絵本を例にとりながらわかりやすく解説していくリレー連載。最終回の第12回は有名な絵本、「手ぶくろを買いに」を通して、登場人物の思いからお金の役割について考えます。子どもと一緒に絵本を読むことで、お金の原点を学ぶことができます。
お金の役割を登場人物の思いから考える一冊
今回ご紹介する絵本『手ぶくろを買いに』は、児童文学者である新美南吉が20歳の時に創作した作品です。
『手ぶくろを買いに』
作/新見南吉 絵/どいかや(あすなろ書房)
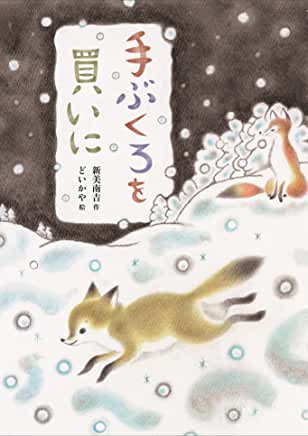
物語のあらすじ
ある寒い冬の朝、生まれてはじめての雪を知った子ぎつね。母ぎつねは、子ぎつねの手にしもやけができてはかわいそうだからと、母手ぶくろを買ってやろうと思います。そして暗い夜、子ぎつねの片手をかわいい人間の子どもの手に変えて、二つの白銅貨をにぎらせるのです。
一人で町に行った子ぎつねは、ぼうし屋さんでまちがった方の人間の手を出してしまいます。お店の人に、木の葉で買いにきたと思われましたが、白銅貨はカチ合わせてチンチンとよい音がするほんとうのお金でした。そこでぼうし屋さんは、子ども用の手ぶくろを子ぎつねの手に持たせます。
まちがえた手を出し、きつねだとばれてしまっても手袋を売ってくれた人間を、子ぎつねと母ぎつねはどう思うのでしょうか…。

子ぎつねと母ぎつねの人間への思いのちがい
この物語では、登場人物によってそれぞれの経験による思いの違いがあることがわかります。
子ぎつねは「人間はやさしい」と思う経験をした
子ぎつねは、はじめてぼうし屋さんとやり取りをしたことで「人間は怖くない」と思います。また、親子の会話を聞いたことで人間もきつねの自分と同じだと感じて「人間はやさしい」との思いになったのではないでしょうか。
母ぎつねは、過去のいやな経験から「人間は怖い」との思いをもっているので、子ぎつね一人で町に行かせます。しかしきつねの手を出しても手ぶくろを買えた子ぎつねの言葉から「人間はいいものかしら」とつぶやき、人間に対する考えに変化が出てきたようです。
お金はどのような役割を果たしたでしょうか?
ぼうし屋さんは、きつねの手を見て「木の葉のお金」を持ってきたのだろうと思っていました。だから手ぶくろを売らないという選択もあったかもしれません。でも、子ぎつねの手から差し出されたのは、本物のお金でした。本物のお金だったからこそ、問題なく手ぶくろと交換したのでしょう。
交換するというお金の役割を知る
お金が「交換する」という役割を持っていることから、この物語が成り立っています。もし、偽物のお金だったらぼうし屋さんが困りますよね。手間をかけて作った手ぶくろが「木の葉のお金」という価値のないものとは交換できないはずです。本物のお金を持ってきたということが、たとえきつねでも信じようという気持ちを持つ助けになったのでしょう。
はじめてのお買い物を経験する意味
子ぎつねにとって初めてお金をもってお店に行く経験でしたが、入り口であいさつをしてから欲しいものを伝えて、お金を渡して手ぶくろを受け取ってお礼もしています。母ぎつねも心配しながら帰りを待っていますね。物語の展開は初めてのお買い物と同じです。初めてのお買い物はハプニングもありますが、心を大きく成長させてくれます。

お金を使うことは相手とのコミュニケーション
長く愛される物語から学ぶこと

新美南吉記念館のホームページによると、『手ぶくろを買いに』は1933年(昭和8年)の作品です。作者の新美南吉は幼くして母を亡くし、養子に出されるなど寂しい子ども時代を送っていたそうです。今とは時代も生活環境も違う中で生まれたこの作品が、現在でも多くの読者に愛されています。
物語は、母ぎつねの「人間はいいものかしら」で終わっています。この作品は、登場人物の思いに焦点を当てた物語として、小学校の国語でも取り上げられることがあります。立場や経験で各々の持つ思いは違っていても、それぞれの思いを実現させるために「お金」を使い、きつねの親子と人間をつなげることができたのではないでしょうか。
お金を使うことは相手とコミュニケーションをとることでもあります。買い物をするときには、相手と言葉を交わし、「ありがとう」と言いあったりします。このコミュニケーションの積み重ねをすることで、物語の子ぎつねのように、先入観にとらわれずに、前向きな考え方ができるようになるのではないでしょうか。
ぜひ子どもと一緒にゆっくりと読んで、お金がつないだきつねの親子と人間の思いについて、感想を言い合ってみてください。
執筆者プロフィール
安藤真寿
キッズ・マネー・ステーション認定講師/CFP®認定/1級FP技能士
小学校教諭一種免許状/高等学校免許状(商業)/学校図書館司書教諭
特別支援教育支援員からファイナンシャルプランナーになる。小学校や中学校で学校生活をサポートする仕事から多数の児童生徒たちとかかわっていた。お金について”progress”(前進)をモットーにわかりやすく伝えていきます。
記事監修

「見えないお金」が増えている現代社会の子供たち。物やお金の大切さを知り「自立する力」を持つようにという想いで設立。全国に約160名在籍する認定講師が自治体や学校などを中心に、お金教育・キャリア教育の授業や講演を行う。2018年までに1100件以上の講座実績を持つ。
連載バックナンバーはこちら

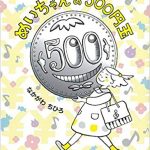
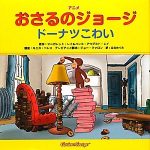

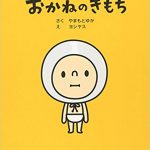
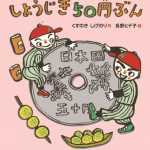
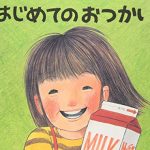


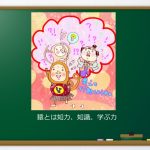

文・構成/HugKum編集部





